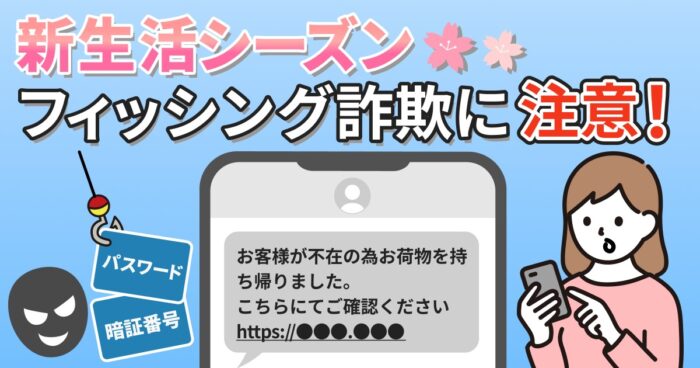「特集」 イスラエル ガザ侵攻1カ月 パレスチナ統治どうなるのか

錦田 愛子
慶應義塾大学教授
ハマース(ハマス)らパレスチナ武装勢力がイスラエルに侵入し、キブツ(集団農場)などに対する奇襲攻撃から11月7日で1カ月がたった。240人以上とされるイスラエル人の人質は、開戦から3週目に計4人が解放されたきりで、残りの人々については本稿執筆時点では依然、消息も明らかにされていない。イスラエル国内では人質の家族から安否を案じる声が高まり、ネタニヤフ政権への支持率はついに3割を切った。地上部隊がガザ地区に入り、駐留展開するようになってからも、人質救出の報せは届かない。
他方でガザ地区では、衝突直後から開始された激しい空爆と地上部隊の攻撃により、6日の時点で死者の数が1万人を超えた。これまでのイスラエルとガザの諸勢力との戦闘で出た最多の死者数は2014年の50日間におよぶ戦闘での2231人で、これをはるかに上回る規模の犠牲者がすでに出ている。戦闘開始以降、完全封鎖下に置かれたガザ地区では、水も食糧も不足し、衛生状況の悪化が懸念されている。複数の病院が燃料不足で機能停止し、このままでは攻撃による直接の負傷者以外の間でも犠牲者が増大する恐れがある。
戦闘が長期化の様相を呈するなか、本稿ではこの衝突がそもそもなぜ始まったのか、パレスチナ、イスラエル双方はこの戦闘により何を得ようとしているのか、改めてその根源に立ち返り考えてみたい。また、今回の戦闘はこれまでと比べてどのような特徴をもつのか、戦闘終結後の解決策を巡る議論についても触れる。
ハマースの奇襲の背景
多くの人々にとって、今回のハマースら武装勢力による攻撃は、平穏な日常を脅かし突如始まったテロ攻撃と映っているかもしれない。イスラーム過激派思想をもつハマースが勢力拡大や支持の回復を狙って起こした軍事作戦で、ガザ地区の市民に対する報復攻撃での被害を度外視した自滅的な攻撃と評価する向きもあるだろう。しかし実際にそうなのか。一般にテロ攻撃は、実行する側から見れば、世間から無視され続けてきた積年の社会経済的な問題や、鬱屈(うっくつ)した思いが背景にある場合が多い。15年にフランスやベルギーで起きた「イスラーム国」信奉者によるテロも、長年それらの国に住む移民の若者が差別や経済格差に苦しみ、居場所を求めて組織に加わり起こしたものだった。個々の苦しみを他人に向けた暴力という形で表現することは決して肯定され得ないが、そうした問題の再発を防ぐには、より根源的な差別や経済格差への取り組みが必要となる。
今回のハマースの攻撃についても同様の性格が指摘される。ガザ地区では06年のハマース政権の成立に始まり、翌年から本格的に開始された封鎖政策で、住民の生活がイスラエル政府による厳しい制約の下におかれてきた。食糧や医薬品、攻撃で壊された家を建て直すための鉄骨やコンクリートなど、生活に欠かせない物資の搬入も、軍事転用への懸念から制限される。東京23区の半分ほどの広さの土地に閉じ込められ、失業率は5割を超えるとされるなか、希望を抱けないガザ地区の若者の間では自殺率が急上昇しつつあった。イスラーム教では自殺は神から授かった大切な身体を傷つけることであり、大きなタブーとされる。それを破るほどの絶望がガザには蔓延(まんえん)していたことになる。
イスラエル側でハマースによる襲撃を許した背景には、軍の治安対策に関する慢心が指摘される。17年続く封鎖はガザ地区とイスラエルの関係をある意味で安定したものとし、管理体制は万全と考えられていた。攻撃の数週間前にはガザ地区との境界線の早期警戒システムで使用する観測気球の故障が報告されていたが、ただちに修理や交換はされなかった。これまでガザ地区からの攻撃は、ロケット弾の攻撃や少数の戦闘員の潜入に限られており、イスラエル国内の治安への大きな脅威とはならないという過去の経験に基づく先入観が生まれてしまっていたのだろう。
双方が求めるものは何か
これまでに例を見ない多くの犠牲者を出したイスラエルは、現在、01年9月11日に起きた中枢同時テロ後の米国と似た国民心理にあるといえる。存在が脅かされるような恐怖感から、過剰な暴力の行使が世論の中で正当化されやすい状態である。アルカーイダの指導者ビンラーディンを発見できないもどかしさの中で、アフガニスタンを攻撃しタリバン政権を崩壊させた米国と、ハマース幹部を発見できずにガザ地区を壊滅に追いやるまで攻撃するイスラエルは、合わせ鏡のような相似関係にあるようにみえる。
ネタニヤフ首相は今回の攻撃で、ハマースの軍事力とともに統治能力も破壊すると明言している。ガザ地区内の軍事拠点を破壊し、武装部門の指導者を殺害することはもちろんだが、今後のガザ地区における統治をハマースに委ねるつもりもない、という意図がそこからはうかがわれる。しかしハマースは04年に連続して起きた指導者暗殺攻撃以来、指導部をガザ地区内と国外とに分けて配置し、ハニーヤやマシュアル、マルズークなど政治部門の主要な幹部はカタールに滞在している。彼らを暗殺できない限り、ハマースを組織として壊滅させることは不可能だ。
また今回は、ハマースら武装勢力の側により多くのイスラエル人の人質が取られており、彼らを無事奪還することが至上命題と考えられる。イスラエルはハマースをテロリストと位置付けているため、「テロリストとは交渉しない」という一般的な慣行に従うなら、ハマース側とはできない。武装勢力の要求には応じず、地上軍のトンネル部隊の投入により、実力行使で人質を解放できれば最善だが、攻撃開始1カ月がたっても、まだほとんど成果は出ていない。
パレスチナ武装勢力の側では、今回の攻撃を開始した当初より、一定数の人質を取り、交渉のカードとして使うことを狙っていた様子がうかがわれる。よく訓練され統制のとれた奇襲攻撃から、人質を取ってすぐにガザ地区内に退却したこと、人質のもつ携帯電話など位置情報が伝わるおそれのある通信機器をすぐに回線遮断していることなどからも、これらが計画的な動きだったと考えられる。誤算があったとすれば、想定外に多くの人質を捕獲し過ぎたという点かもしれない。
かつてイスラエル軍がガザ地区に地上侵攻してきた際に、捕虜とした兵士1人に対して、イスラエル政府は5年かけて交渉し、千人以上のパレスチナ人政治囚を交換条件として釈放した。現在、イスラエルの獄中にいるパレスチナ政治囚は約5千人とされており、単純計算でいえば5人の人質があれば全員の釈放を望める状態といえる。240人以上というのは明らかに多すぎる人数であり、そのことで逆にイスラエル政府を激高させ、交渉が困難な状態を導いてしまっている。
ハマース側は、イスラエル軍による攻撃ですでに60人以上の人質が死亡したと主張している。真偽は不明だが、これだけの規模の爆撃が繰り返されれば、戦闘員からそれほど遠くない場所に拘束されていると考えられる人質の身に危険が及ぶことも、十分考えられるだろう。
しかし人質が死傷したとなれば、国際世論が強く反発しハマース側がこれまで以上の非難を受けることは必定だ。兵站(へいたん)や物資の補充もできず、兵糧攻めにあうパレスチナ武装勢力が多数の人質を抱え続けることは大きな負担であり、高いリスクとなることを意味する。
ガザ戦後統治巡る議論
イスラエル軍の報道官は7日、ガザ地区北部の軍事拠点を制圧したと発表し、翌日にはハマースが北部の支配権を失ったと述べた。イスラエル側の攻撃の過程での死者は39人で、まだ比較的少数にとどまっている。地上部隊の展開が始まってから、ここまではイスラエル軍の攻撃が順調に展開しているようにもみえる。まだ多くの民間人が残っていたガザ地区北部からは、イスラエルが一時的に攻撃の手を緩めた間に5万人が南部に向けて移動したとも報道されている。国際社会の注目が高いことから、パレスチナ側もイスラエル側もこうした人道的配慮は熱心にアピールしている。
9日に米政府は、イスラエル軍が地上侵攻を強めるガザ北部で民間人避難のため1日4時間の戦闘休止時間を設け、北部から南部への「人道回廊」が2カ所設置されると表明した。軍は今回の一時休止を「戦術的、局所的」なものとしている。
こうして一定の戦果らしきものが提示できてくれば、イスラエル政府としても報復攻撃の成果を強調し、人質交渉に応じやすくなる。だが今後、パレスチナ武装勢力側があっさりと降伏するとも考え難く、中期的な戦闘の見通しはいまだ不透明だ。
一方でさまざまな主体の間で模索が始まっているのが、長期的な戦闘終結後のガザ地区を巡る統治の在り方に関する議論だ。5日にパレスチナ自治区のラーマッラーを訪問したブリンケン米国務長官は、自治政府のアッバース議長と会談し、ガザの統治を自治政府が「全面的に引き受ける」という合意を得たとする。だが、アッバース議長率いるファタハ政府は元々ガザ地区では支持が低く、どこまで実効力のある統治ができるか不明だ。
イスラエルとしてはむしろ、一定期間は軍をこのまま駐留させ、ハマースら武装勢力が再び勢力を盛り返さないよう、直接管理下に置く方が安心感は高い。ネタニヤフ首相は6日、そうした部隊の無期限駐留の可能性に言及している。とはいえ長期駐留となるとイスラエルにとってコストは高く、より長期的な解決策として別の選択肢を模索せざるを得なくなるだろう。
慶應義塾大学教授 錦田 愛子(にしきだ・あいこ) 1977年広島県生まれ。東京大学法学部卒業。2007年総合研究大学院大学文化科学研究科博士課程修了(文学博士)。東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所准教授、ヘブライ大学トルーマン研究所客員研究員、慶應義塾大学准教授などを経て23年から現職。16年大同生命地域研究奨励賞受賞。主な著書に「ディアスポラのパレスチナ人」(有信堂高文社)。
(Kyodo Weekly 2023年11月20日号より転載)