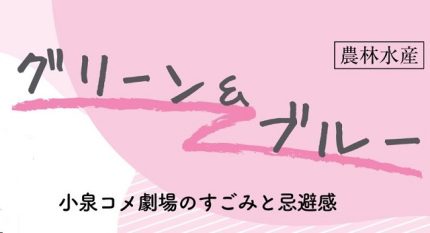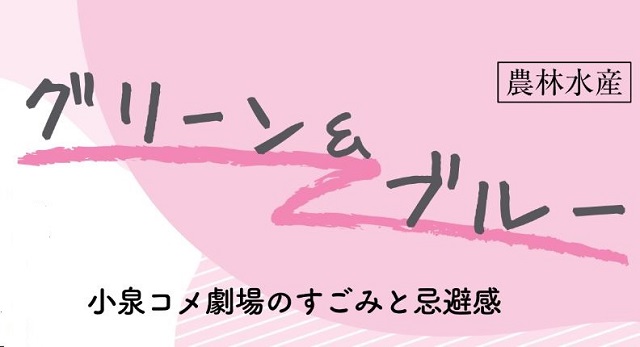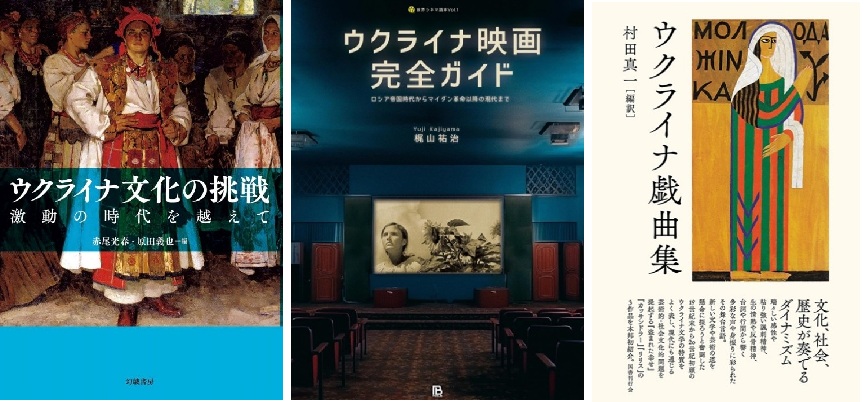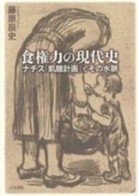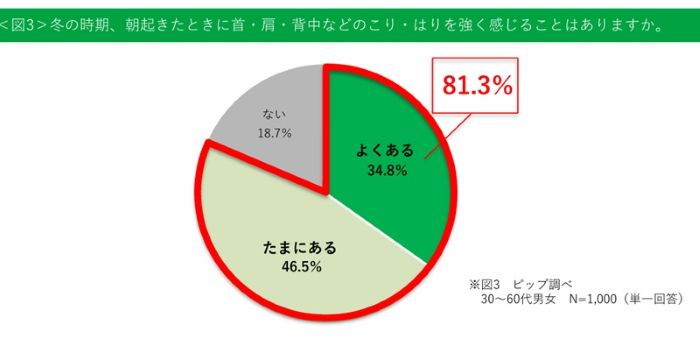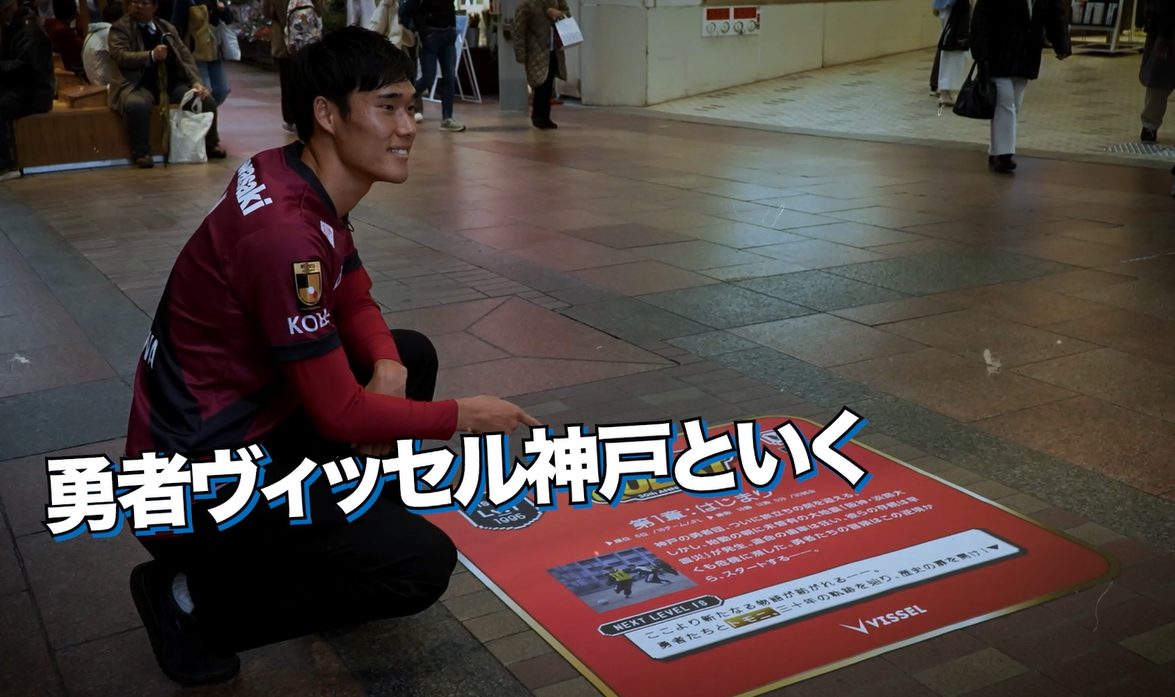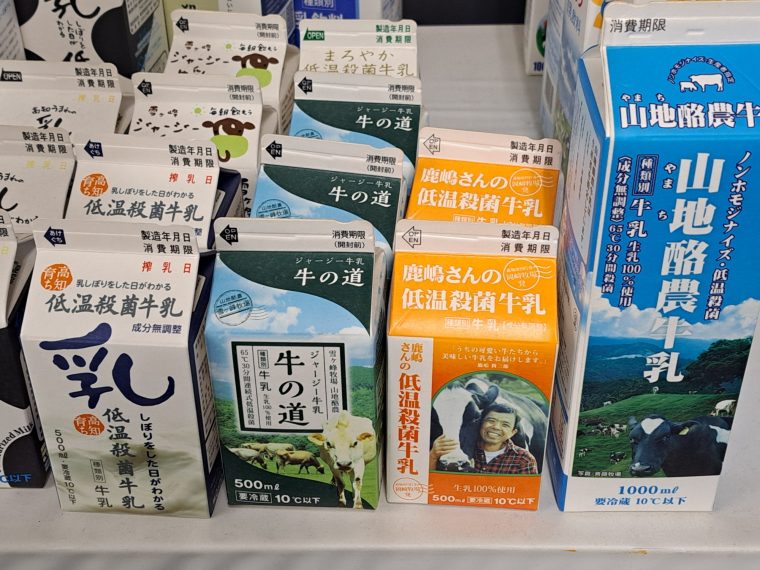小泉コメ劇場のすごみと忌避感 小視曽四郎 農政ジャーナリスト 連載「グリーン&ブルー」
前農相の失言で米高騰への世間の反発が高まったところへ忽然(こつぜん)と登場した小泉進次郎新農相。親子2代の劇場型政治か「やることなすこと度肝をぬく」とは、この1カ月の農相の動きだ。組織・団体に忖度(そんたく)しないが就任の条件はともかく政府備蓄米放出で早速、随意契約とはびっくり。しかも5キロ2千円、備蓄米を全放出し緊急輸入、「聖域なくあらゆることを考える」、「(需給は)じゃぶじゃぶにしていかなきゃいけない」など、まるで儲(もう)けを狙って米を抱える業者に脅しをかけるかのようなパフォーマンスの連続。約70年続く米の作況指数の公表も廃止とは、驚きのあまり息をのむ人も。わずかの期間に、従来、考えられないことを次々と実行する「小泉コメ劇場」のすごみには思わず口をあんぐりだ。この劇場的効果か、農林水産省調査の6月中旬の全国のスーパーで販売の米の平均価格(5キロ)が4カ月ぶりに3千円台に。しかも一時は低迷続きの内閣支持率も数ポイント上昇。「米価対策は参院選の争点」とがぜん、米対策を重くみる与党首脳の全面支援を受けての強気がのぞく。
しかし、劇場型政治もやがて国民は慣れ、その異常さに気づく時がくる。なぜ、「米離れを防ぐため」とか「緊急事態だから」とかの理由だけで大凶作や大災害の時とされていた備蓄米の放出どころか、価格調整のため、本来の一般競争入札ではなく、公平性に疑問のある随意契約で実施できるのか。高騰が理由なら逆に暴落時にも備蓄米として買い上げもできたのではないか。価格は市場原理で決め、そのために単年度で需給を均衡させるとの狙いから生産調整を生産現場に求め、政府自らは流通に介入しないとしてきたのに、今回は介入しまくりだ。さまざまな規定や従来方針を完全に無視したことの責任はどうなのか。
特に生産調整に苦労を強いる農家に対し、「ミニマムアクセス(MA=最低輸入量)米」(約77万トン)のうち売買同時入札(10万トン)のみが主食用とされてきたが、小泉氏はMA米全体や、必要によってはすぐに緊急輸入を表明した。1993年の大凶作時こそ緊急輸入したが、今回、凶作でもないのに対応方針に問題はないのか。
この間、マスコミは米高騰の犯人捜しと人気農相の追っかけ報道を繰り広げ「小泉劇場」の来客増に貢献したが、本来、農相はより本質的な原因の追究に努めるべきだ。確かに流通関係全7万事業者への調査などは実施中だが、現行米政策のベースは四半世紀前の方針転換にある。この間の政策の影響など根本的な検証と反省が必要だろう。東北地方のJA(農業協同組合)元幹部は小泉農相の言動を見て「総理大臣になっては困る人だ」と感じたという。実行力は示したが、その強引さは話し合いを重視する農家には忌避感を与えている。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.26からの転載】