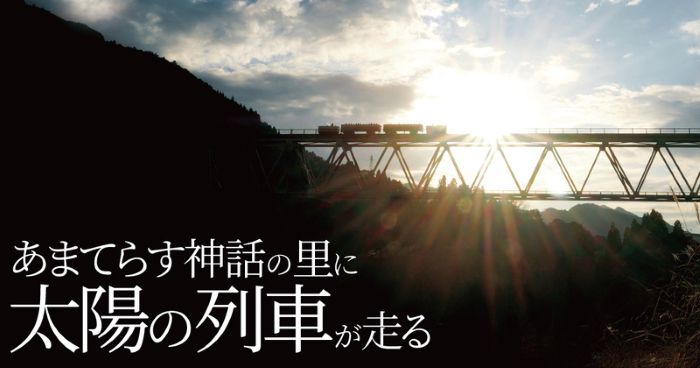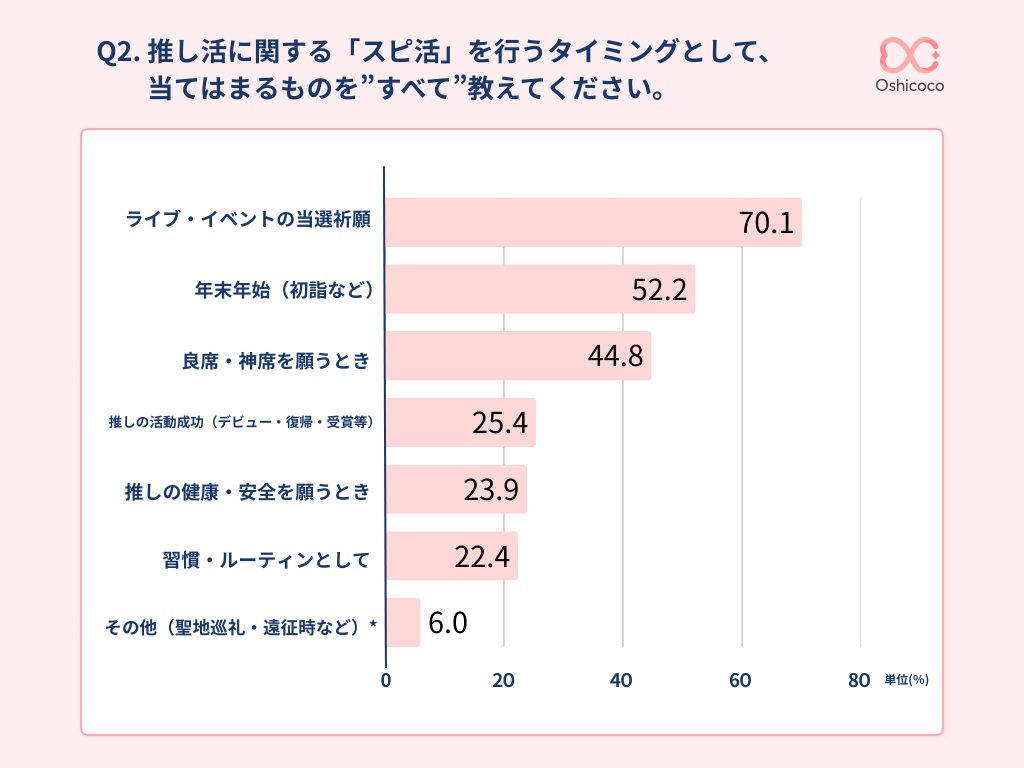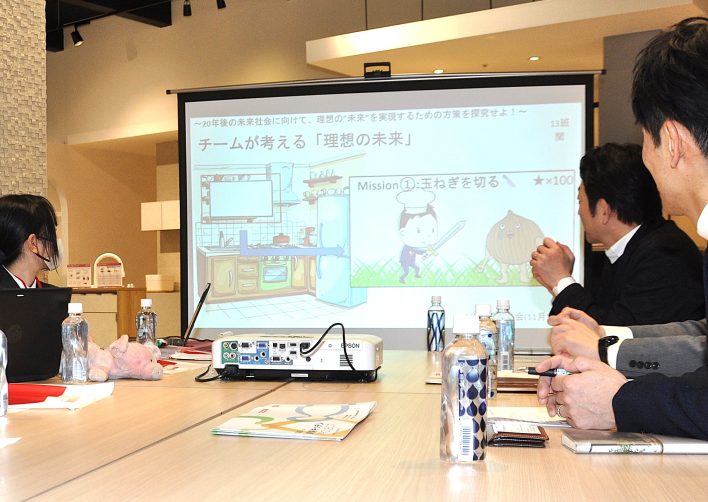「キャロ活」今昔 畑中三応子 食文化研究家 連載「口福の源」
ひと昔前まで、ニンジンは子どもに嫌われる野菜の筆頭だった。理由は小さく刻んでハンバーグのタネに混ぜてもすぐ分かるニンジン臭さ、のはずだったが、今はフルーツ感覚でサラダや洋菓子でも食べるようになった。ニンジンに何が起こったのか?
潮目を変えたのが、1990年代前半からジュース原料に使われたことだ。甘みの強い品種を臭みを出さない新方式で搾った100%ジュースが大ヒットし、すっきり爽やかで甘い野菜へのイメージチェンジに成功した。
近年、人気が高いのが、キャロットラペ。ラペはフランス語で「すりおろす」という意味で、酢と油のドレッシングであえるだけの簡単なサラダだ。フランスでは家庭料理の定番で、カフェやビストロの定番オードブルでもある。
おいしく作るコツはたった一つ、おろし器で千切りにすることだ。表面がザラザラになり、包丁でスパッと断ち切るより味がしみやすくなる。ドレッシングにオレンジやレモンの果汁、砂糖を少し加えると、さらに食べやすい。あえる前に塩もみして水気をキュッと搾れば、冷蔵庫で4、5日保存できて常備菜にもなる。スナック菓子のように、食べ出すと止まらない。
食べ比べや手作りを楽しむ「キャロ活」なる言葉が生まれ、目下ブームなのがキャロットケーキである。すりおろしたニンジンをたっぷり生地に混ぜたケーキで、ニンジンの水分や食物繊維のおかげでもっちりジューシーな独特の食感になる。
砂糖が貴重品だった中世ヨーロッパでニンジンを甘味料として使ったのがはじまりで、砂糖が配給制になった第2次大戦中のイギリスで広く作られたそうだ。
決まったレシピはなく、店や作る人によって形もさまざまだが、シナモンやクローブなどのスパイスを強めにきかせること、バターではなく植物油を使うこと、上に濃厚なクリームをトッピングすることが多い。一般的なケーキよりも甘みが控えめなので罪悪感なく食べられ、地味な茶色で〝映えない〟ところがキャロ活女子には魅力らしい。
ニンジンには東洋種と西洋種がある。原産地はアフガニスタン周辺とされ、日本へは江戸初期に細長い東洋種が、明治初期にオレンジ色で太く短い西洋種が、2度にわたって伝来した。甘みに富んで肉質が柔らかい東洋種は煮物に適していたが、戦後は栽培しやすく、洋食に適した西洋種が主流になった。
まだ砂糖が手に入りづらかった終戦の翌年、「主婦之友」で「主食にもなるクリスマス菓子」と題し、すりおろしたニンジンを配給の雑穀粉に混ぜたレシピが紹介されたことがある。使ったのは、優しい甘さの東洋種だったろう。食べるものがなく栄養失調で亡くなる人が多かった時期だ。それでも祝い菓子を作ろうという気持ちと、主食にもなるという言葉に泣けた。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.18らの転載】