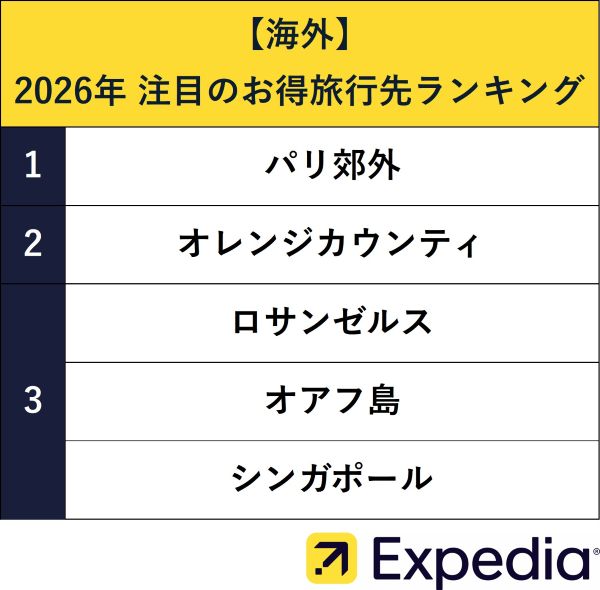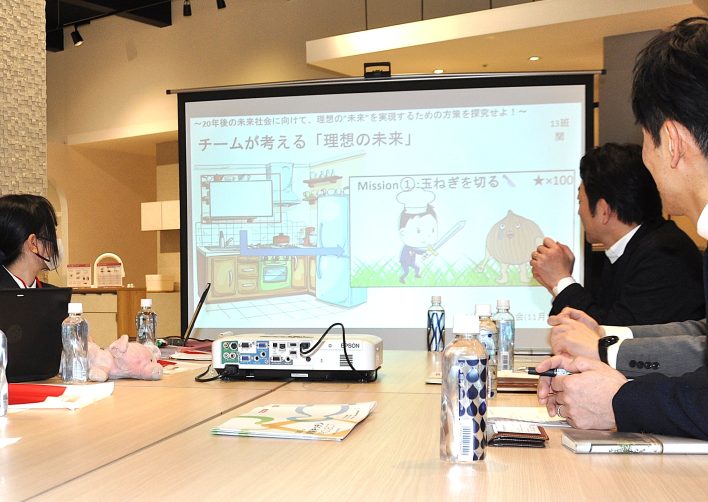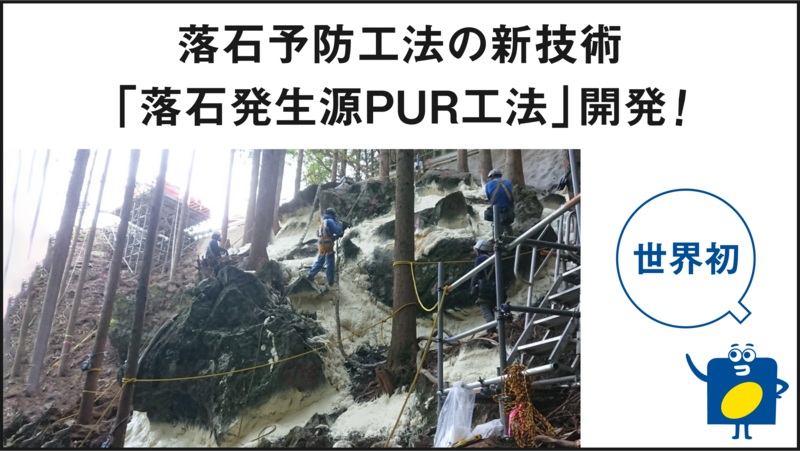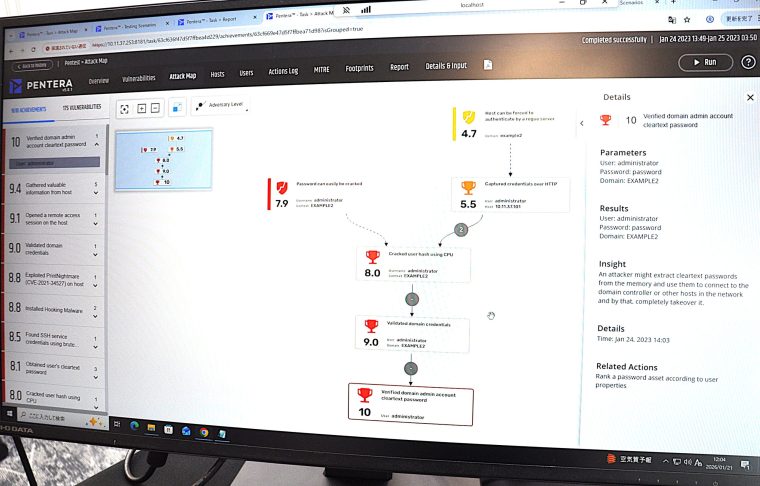「特集」イケア効果ない石破政権 心理面から政界考察 野党は「暗黙の横並び」 「展開見えない」がいい?

本田 雅俊
政治行政アナリスト
うなずける不人気
令和7(2025)年度予算案の衆院審議がヤマ場を迎え、与野党の駆け引きが激しさを増している。石破茂首相が初の日米首脳会談を無難に終えてホッとできたのも束(つか)の間、永田町では依然として「3月退陣説」や「6月政変説」が燻(くすぶ)る。
政権が不安定なのは、少数与党であることに加え、石破首相が不人気だからだ。他人の3割が自分を「好意的」、4割が「無関心」、3割が「非好意的」に見るというが、多少は下がったとはいえ、2月の共同通信社の世論調査でも石破内閣を「支持しない」、つまり「非好意的」はまだ4割を超える。
支持されない最大の理由は「経済政策に期待が持てない」(31・5%)だが、背景にはもっと大きな理由が考えられる。相手に何かを伝えようとする時、表情などの「視覚情報」が55%、声音などの「聴覚情報」が38%を占めるのに対し、「言葉」そのものは7%に過ぎないとされる。この法則に基づけば、残念ながら石破首相が国民に好印象を与えることは難しい。マナーの欠如やだらしなさは、この難易度をさらに高くする。
永田町ではまだ「石破降ろし」は始まっていないが、国会で演説や答弁を終えても、身内のはずの与党席からでさえ拍手はまばらだという。それは、石破内閣を心の底から〝自前の政権〟であると思っている自民党議員が皆無に等しいからだ。自分で手間をかけて作ったものには特別な愛着が湧くことを「イケア効果」と呼ぶが、石破内閣にそうした思いを抱いている者はほとんどいないのだ。
しばしば石破首相は、田中角栄元首相の名言「握った手の数しか票は出ない」を引用する。しかし、当の石破氏は永田町で多くの議員と胸襟を開いて交流してきたわけではない。「面倒見が悪い」「自分だけいい格好をする」と言われるゆえんだ。とりわけ永田町には「持ちつ持たれつ」「貸し借り」の慣習が強く残っており、面倒見が悪ければ、鎌倉時代の「御恩と奉公」の関係にも似た「返報性の原理」は働かない。
かつての石破氏に対する国民的な人気の根底には、冷や飯を食みながらも政権に堂々とモノを申す姿勢への判官びいきがあった。だが、首相に就任すると、仏頂面で「しんどい」「寝る時間がほとんどない」「誰も褒めてくれない」などと愚痴やため息を漏らす。いくら途中から作り笑いを浮かべて愛想よく振る舞おうとしても、負の「初頭効果」はそう簡単に払拭できるものではない。
確かに政治家は他人に褒めてもらいたい承認欲求が人一倍強い〝種族〟だが、苦労や頑張りを自慢気に語る石破首相に「辟易(へきえき)する」(自民三役経験者)人は少なくない。子どもは褒められれば期待に応えて伸びようとする(ピグマリオン効果と呼ばれる)。もしも石破氏が自分自身にこれを期待しているのであれば、異常な物価高にあえぐ国民に「甘えるな」「ふざけるな」と怒鳴られるだろう。
たとえ第一印象が悪くても、話してみると「意外にいい人だ」と思うことは珍しくない。否定的な印象が途中で好意的に転じるほうが最終的な評価として残りやすい「ゲインロス効果」だ。小渕恵三氏は首相就任時に「冷めたピザ」と揶揄(やゆ)されたが、人柄の良さも手伝って、後半の評価は大きく高まった。石破首相にこの可能性がないわけではないが、現時点で大逆転の材料は見つからない。「今の彼が素の石破茂」(閣僚経験者)だからだ。
国民民主の刷り込み成功
昨年10月の衆院選で国民民主党は議席を4倍に増やし、一躍「時の党」となった。勝因としてSNS(交流サイト)を駆使した選挙戦術などが挙げられるが、「手取り増」といった分かりやすいメッセージも大成功を収めた。最初に打ち出された情報が人々の後々の判断に影響を与えることは多く(アンカリング効果)、「年収103万円」や「178万円の壁」といった数字は見事に国民の脳裏に刷り込まれて「基準値」となっている。
国民民主の勢いはとどまるところを知らず、世論調査によっては立憲民主党を支持率で上回る。2月9日の横浜市議補選でも議席を奪い取り、鼻息はすこぶる荒い。参院選の1人区にもどんどん単独候補を立てている。人は売れ筋商品に弱かったり、人だかりの店に吸い寄せられたりしやすい。同様に、参院選に向け、国民民主の人気がさらなる人気を呼ぶ「バンドワゴン効果」が高まることを他党は強く警戒する。
昨年の衆院選で立憲民主は50議席増やしたものの、比例区は合計1156万票で前回とほぼ同じであった。「あれでは『昔の名前で出ています』だ」(ベテラン地方議員)と呆(あき)れられるように、執行部には新鮮味も感じられず、支持率は伸び悩む。民主党政権時代の失政がまだまだ人々の記憶から薄れていないこともある。2009年の衆院選で民主党(当時)は比例区で合計3千万票近くを獲得したが、その半数以上がそっぽを向いたままだ。
維新の会も国民民主にお株を奪われた感があり、勢いに陰りが見られる。「や(野)党」でも「よ(与)党」でもなく、「ゆ党」として右顧左眄(うこさべん)した印象が持たれたり、自らを「第2自民党」と評したりしたことがマイナスに働いた。
さらに、国民民主の「年収の壁」に比べ、教育費の無償化はやや曖昧性を伴う。社会保険料の「1人当たり6万円引き下げ」は分かりやすいが、「バナナの叩(たた)き売り」「二番煎じ」の感は拭えない。人は損得勘定で動きやすいが、利益を得る喜びよりも、損をする苦痛のほうが2倍以上強いという。それならば、今は思い切った物価高対策のほうが国民に支持されよう。
一方、自民党の強さの秘訣(ひけつ)の一つは、長年にわたって権力を握り続けてきたことだ。だが、政策の継続性を裏返せば、それはまさに硬直性にほかならない。「政治とカネ」の問題のみならず、続けてきたから安易にやめられない「コンコルド効果」により、時代に見合った新たな政策を打ち出せないことも、国民の「自民党離れ」を引き起こしている。
個々の議員が有権者との接点を広げる活動を新型コロナ流行前の水準にまで戻せていないことも、自民の党勢衰退の一因だろう。SNSの時代でも、やはり握手の数を増やさなければ、本当の意味での「単純接触効果」は生まれない。さらに、高齢化の進展や地域コミュニティーの崩壊といった大きな社会変化に対応できなければ、自民党にとっても「適者生存の法則」は人ごとでなくなる。
かつての自民党は唯一の国民政党として、圧倒的に支持された。有権者の多くは周りの人と同じ投票行動を取って安心感を得たし、経済の安定成長はこの安心を確信に変えてきた。反復投票を好む日本人の国民性も、自民党の長期政権を支えた。
しかし、経済の停滞や物価高、社会の閉塞感などによって今や老舗政党は振るわず、逆に〝ベンチャー政党〟が脚光を浴びる。人は既製品に欠乏感を抱く時に新製品が発売されるとドーパミン(快感や意欲、運動機能などに関係する神経伝達物質)が分泌され、興味を向けるというが、それはそのまま昨今の政党にも当てはまるようだ。
神経戦の佳境はこれから
昨年の衆院選後、石破首相は野党各党に「熟議の国会」を呼びかけ、予算案や法案の修正に柔軟な姿勢を見せてきた。政策によって交渉する野党を使い分けたり、野党の分断を図ったりする巧みさから、司令塔の森山裕幹事長を「まるで鵜匠(うしょう)だ」(自民元議員)と評する者もいる。自公政権を少数与党に追い込みながら「大山鳴動してネズミ一匹」に終われば野党は「無能」「無力」の誹(そし)りを免れず、森山幹事長は腰を低くしながらもその心理を見事に逆手に取っている。
国民民主や維新にとり、自民党との交渉打ち切りと絶縁は、本心では最も避けたい結末だ。だから最初に過大な要求を突きつけた後、本命の要求を受け入れやすくする「ドア・イン・ザ・フェイス」の手法も取られるし、たとえテーブルを蹴って出て行ってもまたすぐに戻ってくる。
両党だけではない。むしろ存在感が著しく薄くなった公明党のほうが強い危機感を持つ。斉藤鉄夫代表の「連立離脱」発言はその表れだ。「下駄の雪」と皮肉られながら自民党と連立を組んできた公明党だが、かつて800万を超えていた比例票は、昨年はついに600万を割り込んだ。
政治改革などを巡り、これから与野党間のせめぎ合いはさらに激化する。夏に参院選、さらにその前には東京都議選が控えているため、各党は合意と独自性発揮のバランスに苦慮する。チキンレースよろしく、安易に譲歩したりすれば、支持層から見放されるからだ。
のみならず、国民民主と維新はそれぞれ相手の出方にも細心の注意を払っており、それは「囚人のジレンマ」に似る。一党だけが政府与党案に賛成すれば、「政権にすり寄った」として来たる選挙で票を大幅に減らしかねないから「暗黙の横並び」が意識されているのだ。
実績のアピール合戦も激しくなる。事実ではない「偽の記憶」を集団で共有する「マンデラ効果」を挙げるまでもなく、多くの人々によって信じられていることでも「フェイク(偽)」は少なくない。たとえ嘘(うそ)でなくても、表現を巧みに変えることによる「フレーミング効果」は随所に散りばめられている。「あと半分」か「まだ半分」か、「達成率70%」か「未達成率30%」かといった表現の違いによっても印象は大きく異なるのだ。そうした視点から政党や候補者のチラシを見るのも面白いかもしれない。
もっとも、国民民主も維新も、本心ではそれぞれの要求が一瀉千里(いっしゃせんり)に実現することを必ずしも強くは望んでいないという。「主張し続けること自体が存在意義」(野党国対)であり、要求が簡単に実現してしまえば国民の支持と期待が瞬く間に萎(しぼ)むため、しばらくは旗印として掲げておきたいのだ。国民も現状維持か野党案かの二者択一ではなく、ひとまずその中間あたりで納得しやすい。「年収の壁」の見直しでいえば、150万円あたりの落としどころが「松竹梅の法則」(三つの選択肢から多くの人が真ん中を選ぶとされる心理傾向)にも合致する。
参院選の獲得議席目標について石破首相は早々に「非改選議席と合わせて自公両党で過半数」と明言した。これだと改選125議席のうち与党で50議席以上獲得すればよく、「かなり低いハードル」(全国紙デスク)になるが、これすら難しいとの見方もある。大規模災害や戦争はあってはならないが、「そのような状況にでもならなければ政権に強い追い風が吹かない」(自民中堅)との悲観論もある。「吊(つ)り橋効果」は政治の世界でも見られるのだ。
しかし、多くの国民は現在の少数与党体制と「熟議の国会」を肯定している。石破首相が自信満々でふんぞり返る姿よりも、低姿勢で国会論戦に臨む光景を歓迎しているのだ。人は物事が完結するよりも途中段階のものに興味を引かれるという。テレビ番組が面白いところで「続きはCMの後で」と中断するのは、視聴者が「ツァイガルニク効果」で関心を高めるからだ。参院選までまだ数カ月あるし、衆参同日選挙の可能性もゼロではないが、多くの国民はまだまだ「展開の見えない政治」に興味をそそられるようだ。
政治行政アナリスト 本田 雅俊(ほんだ・まさとし) 1967年生まれ。慶應義塾大学卒。内閣官房副長官秘書などを務めた後、98年慶應義塾大学大学院博士課程修了。武蔵野女子大学(現武蔵野大学)助教授、米ジョージタウン大学客員准教授、政策研究大学院大学准教授などを経て現在、金城大学客員教授。主な著書に「総理の辞め方」など。b-dotにコラム「政眼鏡」を連載中。