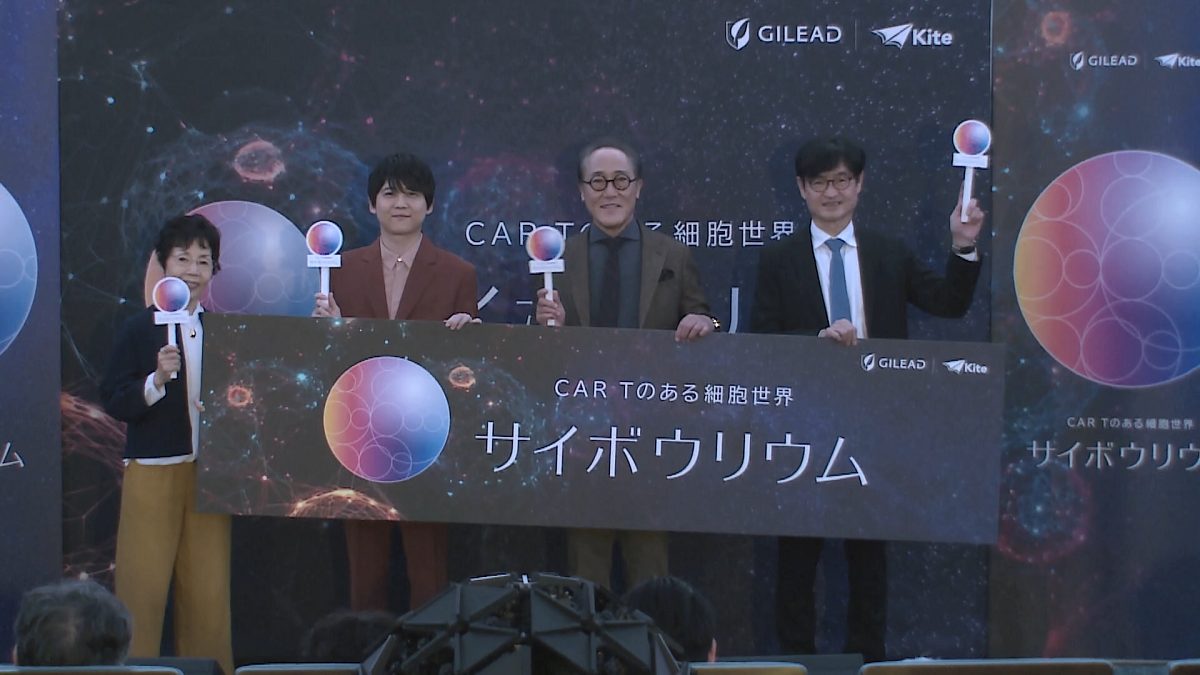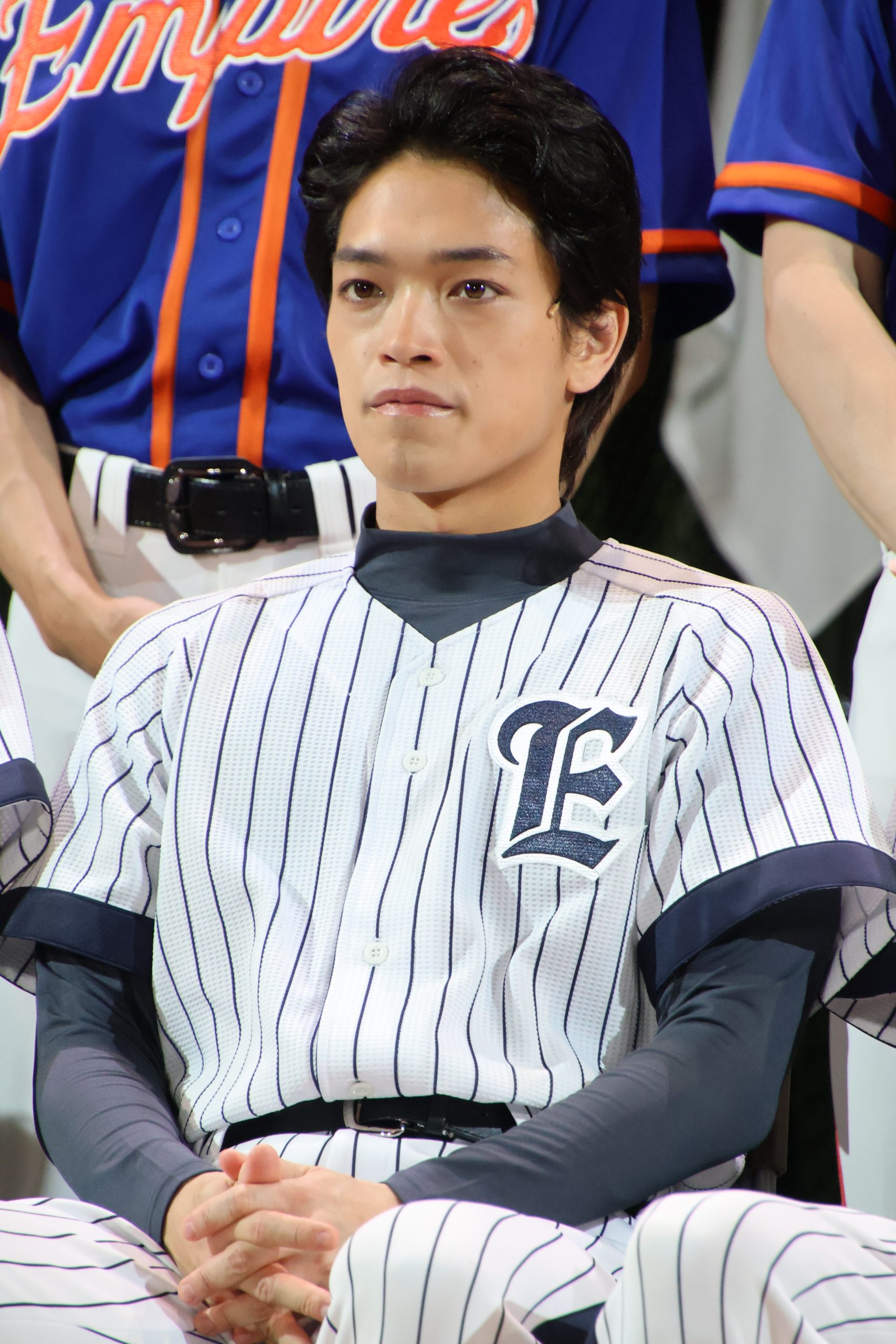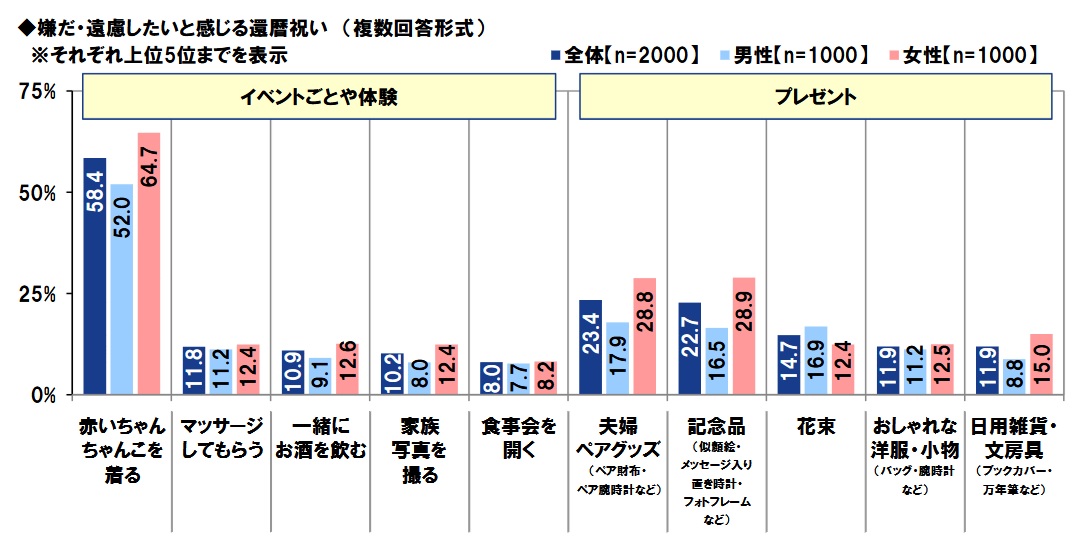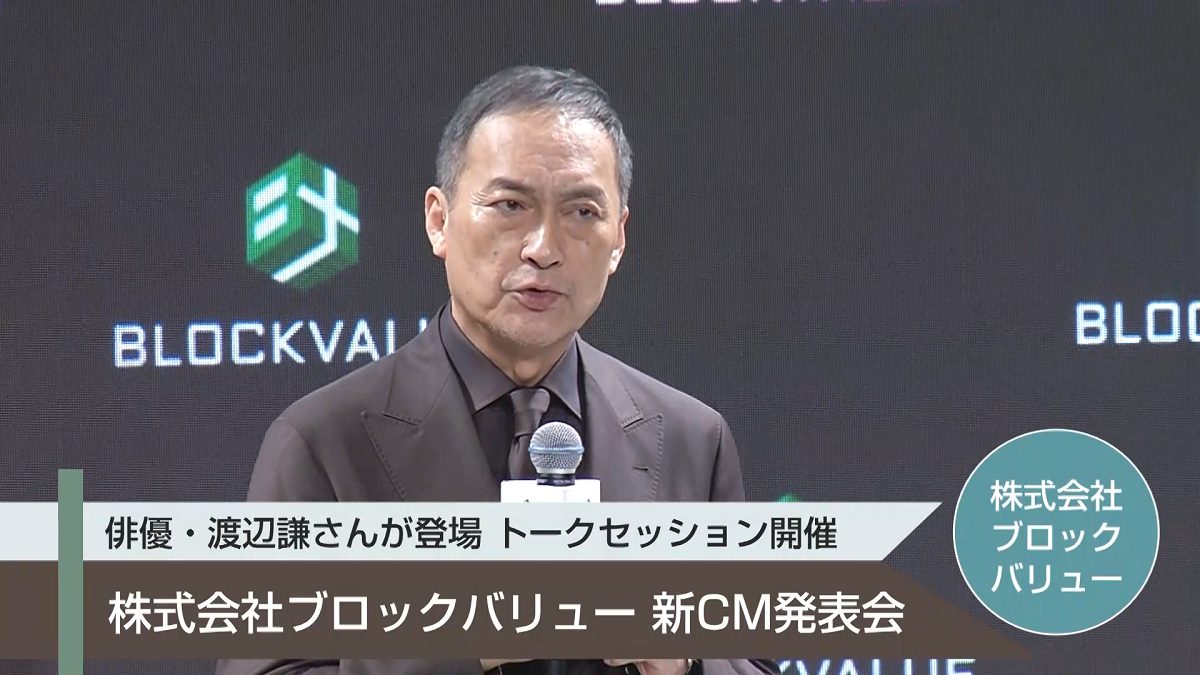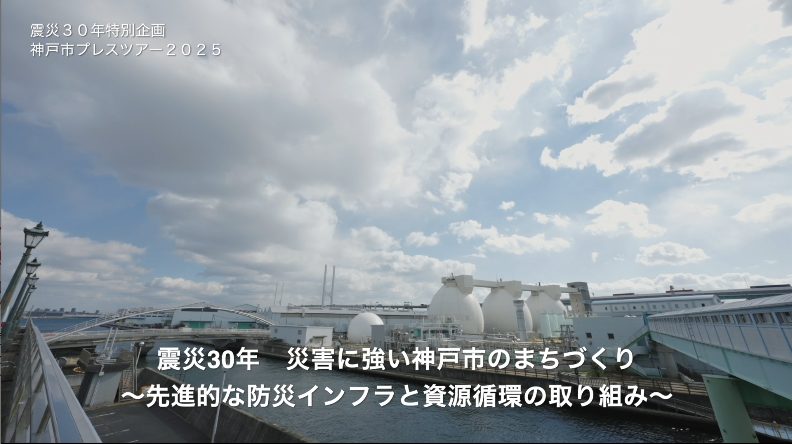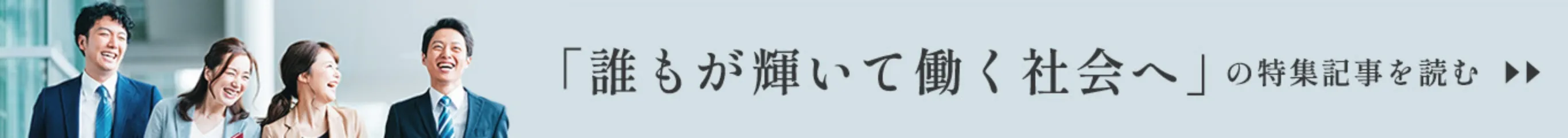被災者に援助が届かない理由は 【舟越美夏✕リアルワールド】
東南アジアに住んでいた頃、雨が好きだった。雨の匂いがする風が吹き始めたと思うと、大粒の雨が落ちてくる。強烈な日差しで熱を帯びていた通りが冷やされ、ほっと一息ついたものだ。
しかし、3月末にマグニチュード7・7の地震に見舞われたミャンマー中部の人々にとって、雨は非情だ。雨季は6月からなのに、震源地とその周辺は4月上旬に激しい風雨に見舞われた。古都マンダレーでは地震で傾いたビルが倒壊した。多くの市民が戸外で寝泊まりをしているが、雨風をしのげるテントがある人は少数に過ぎない。そもそもテントはおろか、何もかもが足りない。食料、清潔な水、医薬品、トイレ。倒壊した建物の下には遺体が埋まったままだ。本格的に雨季が始まれば、コレラやマラリアなどが蔓延(まんえん)する可能性がある。世界保健機関(WHO)はミャンマーに最高レベルの緊急事態を宣言した。

僧侶ら11人が死亡した震源地ザガインの寺院=提供写真
「今は、個人が寄付してくれる水や食料で生き延びている。軍事政権の支援はもちろん、外国支援の食料など見たことがない」。マンダレーで避難生活を送る37歳のタイ・ザーさんは言う。そう語るのは、彼だけではない。
軍事政権は市民の命を後回しにすることを、市民は経験から知っている。2008年5月に南部を襲ったサイクロンは、14万人の死者・行方不明者を出したが、被災者を支援したのは、僧侶や市民だった。軍事政権は国際援助団体や報道機関が混乱をもたらすと考え、被災の実態が国内外に知られないようにすることに熱心だった。
今回の地震では、軍政トップのミンアウンフライン総司令官は、地震が発生した翌日に国際社会に支援を呼びかけた。首都ネピドーで省庁や軍事施設に大きな被害が出たことが背景にある。しかしその後、「国内外の団体は当局と調整しなければならない」と発表し、援助物資の詳細と届け先、ボランティアの人数と出身地まで細かく登録することを義務付けた。「搾取されないように援助物資を届けるため」「政府の支援活動が妨害されないため」などを理由としたが、実際には民主派などの抵抗勢力に援助物資が渡ることを危惧しての措置だと、市民は知っている。
「これが物資を届ける障害になっている。軍事政権の懐に支援物資の一部が入るはずだ」と地元ジャーナリストは推測する。
小規模の支援グループは当局の目をかいくぐり被災者に物資を届けている。だがいつまで続けられるか分からない。震源地ザガインは軍が新たな検問所を設置し、以前にも増して支援者が入りにくくなっているという。
援助活動が進まない中で、軍事政権は被災地周辺への空爆を続け、さらには総選挙の12月実施を発表した。軍政に正統性を与えることになる総選挙には、岩屋毅外相が「深刻な懸念」を表明し、明確なシグナルを送っている。日本は災害で豊富な経験があるだけでなく、ミャンマーと戦前から深い関係を持ち、アジアの安定を望む国でもあるのだ。できることが多いはずだ。
ベンガル湾の熱帯低気圧が、暴風雨をもたらす季節が近づいている。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No. 18からの転載】

舟越美夏(ふなこし・みか)/1989年上智大学ロシア語学科卒。元共同通信社記者。アジアや旧ソ連、アフリカ、中東などを舞台に、紛争の犠牲者のほか、加害者や傍観者にも焦点を当てた記事を書いている。