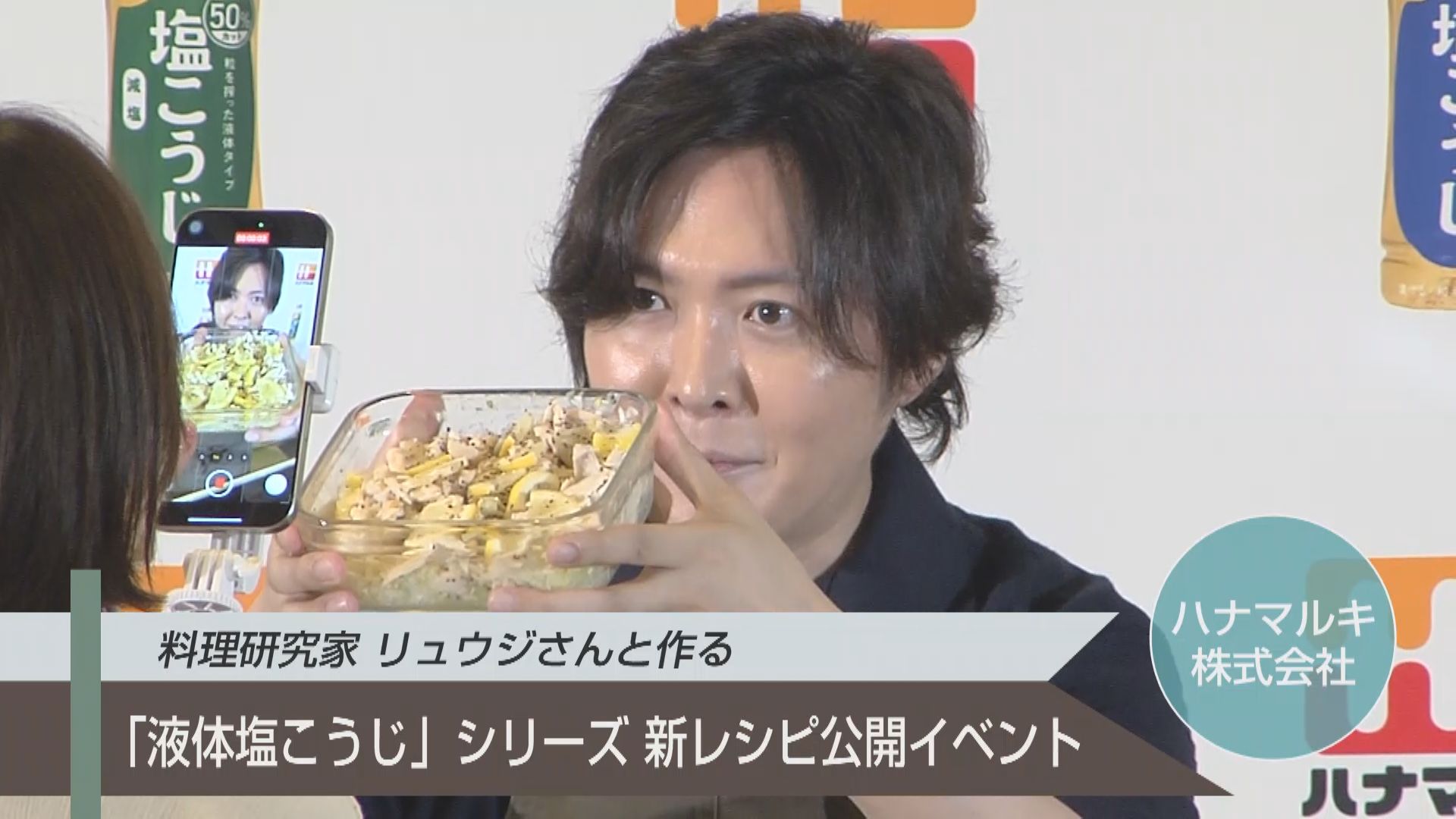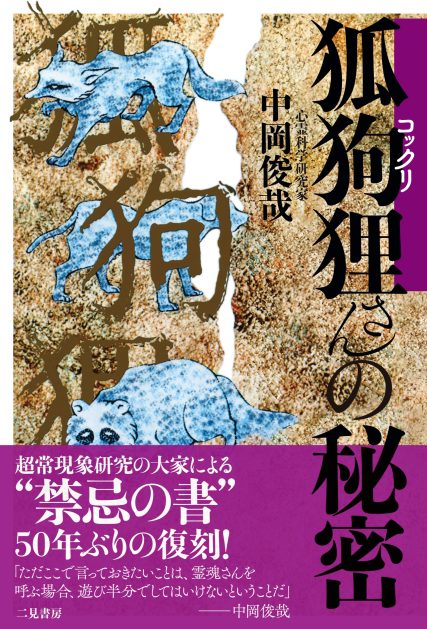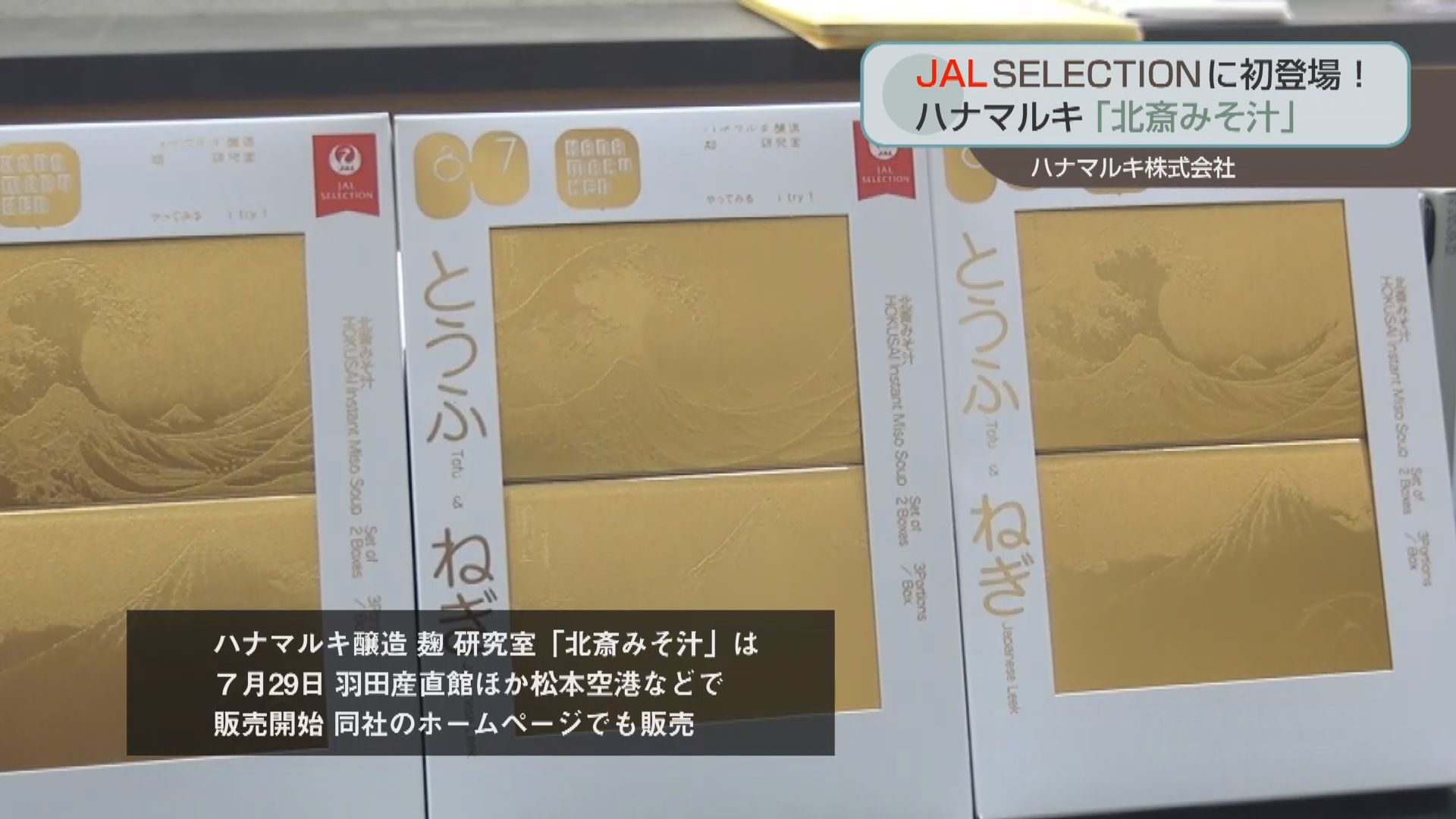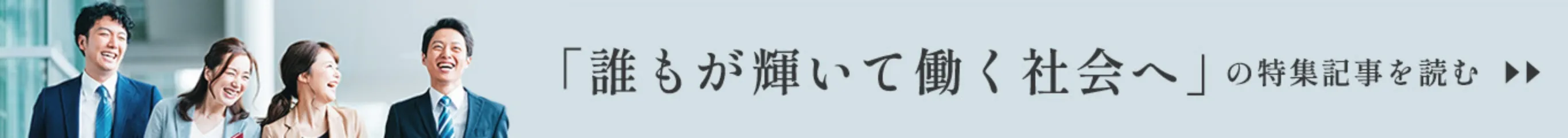「特集」 自民党の大惨敗 政権継続には「何でもあり」 参院選前に解散も

後藤 謙次
政治ジャーナリスト
元プロ野球の野村克也監督が残した名言が思い浮かぶ。
「負けに不思議の負けなし」
与党自民党の大惨敗に終わった第50回衆院選のことだ。自民党には負けの要素が全てそろっていた。中でも「詫(わ)びる」と「ブレる」は敗北に直結する最悪の要因だ。「詫びる」は言うまでもなく旧安倍派を中心に拡大した政治資金パーティーをめぐる「裏金問題」。衆院選公示日(10月15日)に首相石破茂が発した第一声も「お詫び」からだった。
「『政治とカネ』の問題が二度と起きないよう、深い反省の下に選挙に臨む」
ところがお詫びの後に、「今後どうする」という具体的な対応策がなかった。むしろ最終盤になって非公認とした候補者が支部長を務める小選挙区支部に公認候補と同額の2千万円が振り込まれていたことが発覚した。
さらに石破の発言のブレも大きかった。自民党総裁選の論戦では、「衆院解散は予算委員会を開催して国民に対して判断材料を提供してから」との考えを繰り返してきた。ところが、総裁に就任すると予算委を開かないどころか、首相指名選挙前日の〝首相内定者〟の段階で解散を予告、選挙日程まで明示した。
敗戦処理への準備
10月27日の投開票の結果は自民党に無残な結果を突き付けた。公示前の247議席から56議席減の191議席。友党の公明党も32議席から24議席に激減した。投票日直前まで「自公で過半数(233)を割ることはないだろう」と語っていた石破の思いは木っ端みじんに打ち砕かれた。
これに対して立憲民主党は98議席から50議席増の148議席に躍進。国民民主党は4倍増の28議席。しかも国民は比例代表の候補者が足らずに3議席をみすみす失うという想定を超える勝利を収めた。
もっとも自民党はかなり早い段階で負けを覚悟して〝敗戦処理〟の手を打っていた。選挙戦が終盤を迎えた10月21日午後9時過ぎ、石破以下選挙を仕切る最高幹部が自民党本部に集結した。副総裁菅義偉、幹事長森山裕、選対委員長小泉進次郎、参院議員会長関口昌一、そしてただひとり政治家ではないが陰の司令塔とも言える事務総長元宿仁が顔をそろえた。
接戦区のテコ入れが表向きのテーマだったが、より重要なのは選挙後の状況分析と対処方針の策定だった。与党内の問題では「公明党の発信力が増す」との認識を共有した。結果として公明党も後退したが連立政権内の比重はより高くなったと言っていい。ただ公明党の代表に就任早々の石井啓一が落選して、国土交通相の職にあった斉藤鉄夫が代表に交代。自公関係も未知の領域に突入した。
党内状況をめぐっては石破と総裁の座を争った前経済安全保障担当相の高市早苗の動向が話題に上った。出席者の共通認識は「選挙後は高市さんの影響力は低下する」(党幹部)というものだった。
確かに高市が頼みとした旧安倍派の衆院議員は公示前の59人から20人に激減、かつての最大派閥は第5派閥に転落した。しかも旧安倍派再興のカギを握る安倍派5人衆のうち自民公認で当選したのは元官房長官の松野博一のみ。高木毅は落選。残る萩生田光一、西村康稔、世耕弘成は非公認で当選を果たしたが、復党への道は遠い。国民世論の厳しい視線があり森山は萩生田らを自民党への復党ではなく統一会派への入会にとどめた。萩生田らが高市と組んで「石破降ろし」を仕掛けられる状況にはない。むろん高市自身はポスト石破への意欲を失っていないとみるべきだろう。森山は高市の不穏な動きを封じるため選挙戦の最終盤で石破と高市の街頭演説でのそろい踏みを要請した。しかし、高市は遊説日程を理由に申し出を断った。問わず語りの「反主流派宣言」とも言えた。
最高幹部会議でより重要なテーマは、与党過半数割れに備え、自民党と政策的に近い国民民主党の取り込みにあった。筆者はたまたまこの日の午前中に森山にインタビューした。そこでの森山の答えはその後の展開を強く示唆した。
「政策がしっかり一致していれば、どこの政党とも連立を組んだり、政策ごとに連携したりするやり方はあります」
森山はこの中で立憲民主党との大連立に関しても「大連立も悪いことではありません」と述べ、選択肢の中にあるとの考えを示したのだった。つまりその考えの根底にあったのはどんな状況になっても「自民党政権の継続」。平たく言えばそのためなら「何でもあり」だった。
比較第1党へのこだわり
負けを覚悟したとはいえ選挙情勢は投開票日が近づくにつれて悪化の一途をたどった。新聞各紙にも「自公過半数割れ」の見出しが躍った。さらに投開票日27日になると、比較第1党が「自民ではなく立民」との情報が流れ、自民党内に衝撃が走った。この時点で石破は周辺にはこう語っていた。
「比較第1党なら辞めない」
投票が続く中で石破と森山はテレビ・ラジオの選挙特番で責任論や進退に触れる話は一切しないことを申し合わせた。現に石破が口にしたのは続投への意欲だった。
「われわれが掲げた政策の実現に向けて最大限努力していかないといけない」
森山も与党過半数割れが確定後、28日未明に「微力を尽くし、責任を果たしていきたい」と述べ、辞任を否定した。これにより新聞各紙は与党過半数割れを大きく報じる一方で責任論への言及は限定的だった。29日付朝刊になると、「連立の枠組み拡大」を軸に紙面が展開され、総選挙で躍進した国民民主党と自公との部分連合問題が前面に躍り出てきた。
森山は既に国民との幹事長、国対委員長会談を31日午前10時から開催することで合意を取り付けていた。この合意は特別国会での首相指名選挙を睨(にら)んで自民党内の造反を牽制(けんせい)する狙いがあった。「政権維持」はだれも反対できないからだ。これと軌を一にするように国民代表の玉木雄一郎が首相指名選挙では決選投票になっても国民民主党は「玉木雄一郎と書く」と繰り返した。間接的に石破続投を容認するのと同義語だった。
その一方で森山は無所属当選者を自民党との統一会派入りの働き掛けを進め、旧安倍派の3人と旧二階派の平沢勝栄、さらに無所属で当選した広瀬建(大分2区)、三反園訓(鹿児島2区)の6人が衆院会派の「自民党・無所属の会」に入会した。これにより自民党の実質的な国会内勢力は197人。それでも公明党の24人を加えても221人で、過半数には12人足らない「少数与党政権」がほぼ確定的になった。
この議席の溝を埋めるのが国民との部分連合と言えた。森山はより安定的な政権運営を目指すため政調会長同士による常設的な協議機関の設置を申し入れたが、国民側が「個別の政策テーマごとの協議」を求め、緩い連携を主張して自民も受け入れざるを得なかった。
代表野田の逡巡
一方、立憲民主党は大幅に議席を増やしながらがむしゃらに野田政権の樹立に向かうことには抑制的だった。立民のスローガンは「政権交代が最大の政治改革」。その目的に向かって動いていたのは長老格の小沢一郎だった。「取れる時に取らなければならない」。小沢は31年前に結党以来、初めて自民党を下野させて7党1会派による細川護熙連立政権を樹立した立役者。小沢にはその成功体験があった。しかし、野田佳彦は違った。信頼する党幹部にこう語っている。
「比較第1党なら泥(どろ)をかぶっても、傷だらけになろうとも政権を取りに行った」
立場は違っても野田も石破同様に「比較第1党の重み」を強く意識している点では一致していた。さらに野田を躊躇(ちゅうちょ)させたのが参院の現状だ。参院の過半数は125。これに対して立民は39議席に過ぎない。他の野党をかき集めたとしても「ねじれ国会」という厳しい現実が待ち構える。野田の基本戦略は来年7月の参院選で議席の挽回を図った上で次の衆院選で堂々たる政権交代を狙っていると見るべきだろう。
ただ石破も不安定な国民民主党との部分連合がそれほど長く続くとは思っていない。自民党内には早くも「国民との連携は来年2月まで」(党幹部)との見方がある。この時期は2025年度予算案が衆院を通過するタイミングだ。ここで予算の年度内成立が確定すれば、政界は一気に参院の選挙モードに入るからだ。国民も自民の補完勢力の印象が強まれば参院選での存在感発揮は難しくなる。必然的に自民党に対して厳しい条件を突きつける野党にならざるを得なくなるのは目にみえている。
必然の衆院解散
これに対して野党側がまとまればいつでも内閣不信任案が可決される状況は変わらない。しかも石破の選択肢も限られている。少数与党政権という脆弱(ぜいじゃく)な政権基盤を強化するには自公連立の枠拡大か総選挙での議席挽回の二つに一つ。連立強化で政権を安定させた例には小渕恵三政権があるが、この時は野中広務、古賀誠ら練達の士がそろい、竹下登ら指南役も健在だった。それに比べて今の人材が枯渇した自民党では不可能に近い。ならば解散権の行使しかない。
特別国会での首相指名選挙は石破の続投を確定させるものだが核心は石破が引き続き解散権を手にすることにある。早ければ25年予算が成立した直後の4月から要警戒ゾーンに入り、7月の衆参同日選挙に向けて大きな流れが生まれると見るだろう。79年の大平正芳と福田赳夫が衆院本会議場で首相指名選挙を争った「40日抗争」は翌年、大平の急死を経て衆参同日選挙の自民圧勝で終止符を打った。
ただし石破が解散権を行使できるための環境を整えられるかどうか。内閣支持率の引き上げが最優先の条件だ。しかし、国民民主の言いなりになれば、党内からの造反の「むしろ旗」が上がる。大乱世はまだ入り口に立ったばかりだ。(敬称略)
政治ジャーナリスト 後藤 謙次(ごとう・けんじ)1949年東京生まれ。共同通信社客員論説委員、白鷗大学名誉教授。73年共同通信社入社。政治部長、論説副委員長、編集局長を経て2007年退社。退社後はTBSテレビ「news23」のキャスター、テレビ朝日「報道ステーション」などのコメンテーターを務める。日本記者クラブ賞、第72回菊池寛賞を受賞。
(Kyodo Weekly 2024年11月18日号より転載)