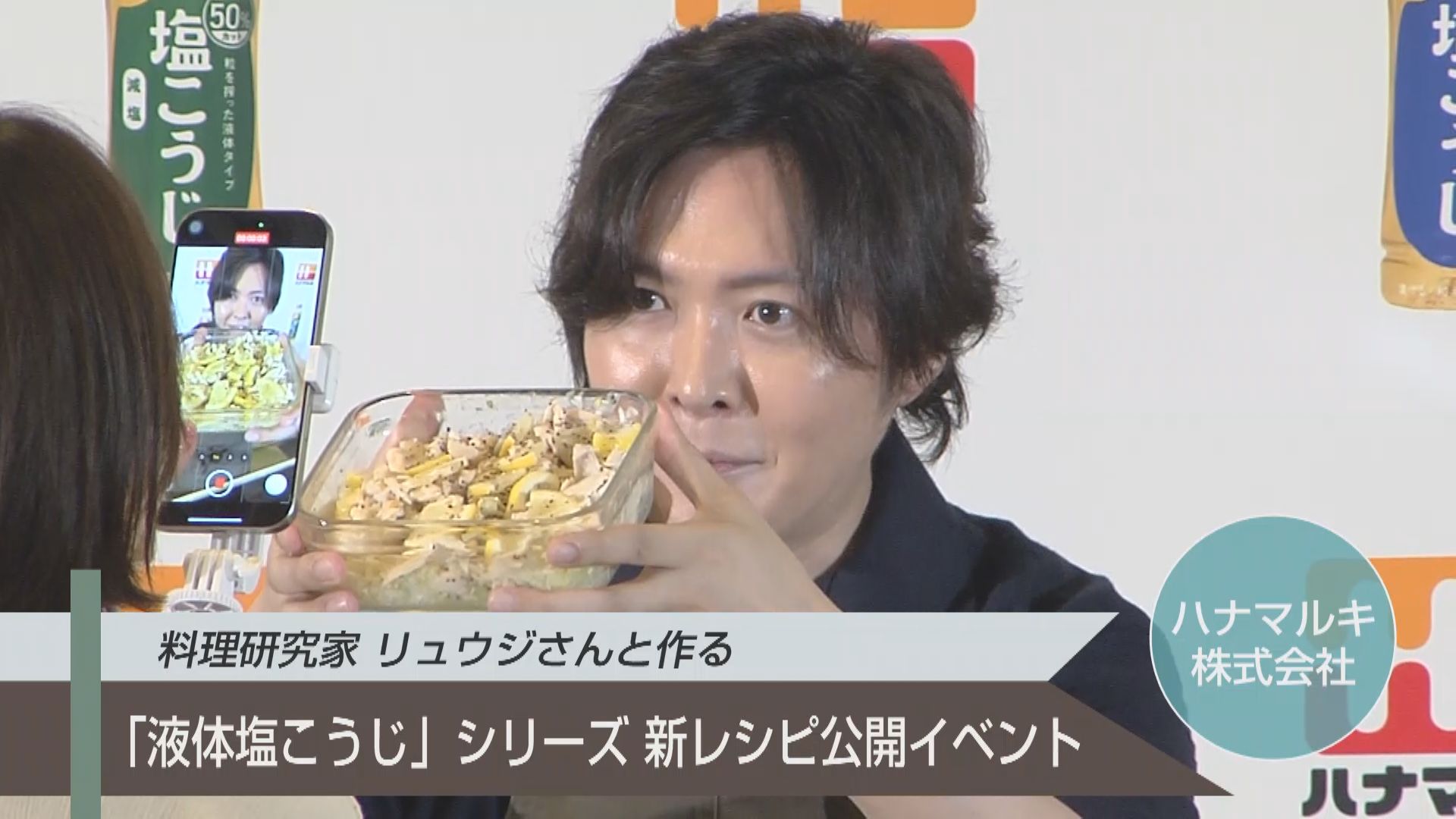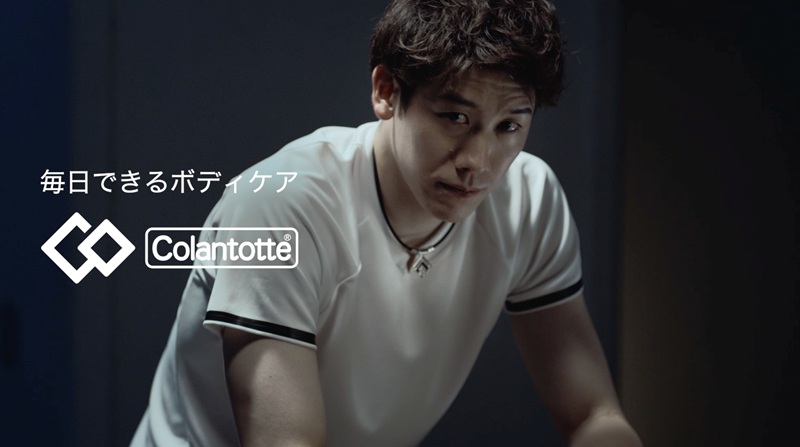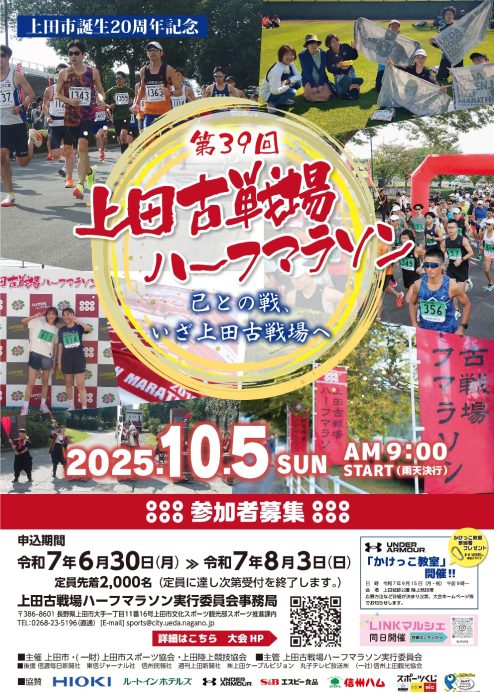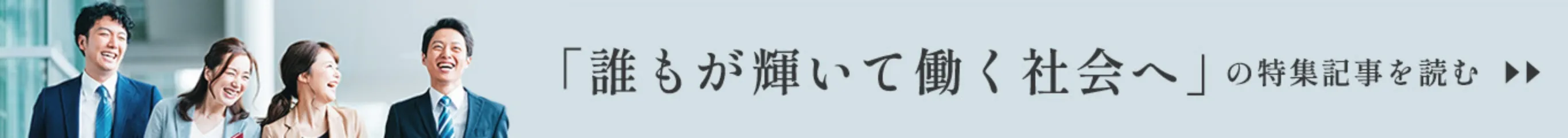「特集」 男子バレーに注目 パリ五輪 飛び出せ海外 大会は曲がり角

生島淳
スポーツジャーナリスト
4年に一度の夏を楽しみにし始めたのは、小学校の時だ。1976年のモントリオール・オリンピック、早起きして女子バレーボールの決勝、日本対ソ連の試合を見た。日本の完勝、笑顔の金メダルだった。
それ以来、オリンピックを現地で見ることは私にとっての目標であり、それは96年のアトランタ大会で実現する。それから夏冬合わせて7度、現地に足を運んだが、2024年のいま、こう思うに至るようになった。
オリンピックは新しい局面に入ったな。
「怪物」大会
もっとハッキリ書けば、1896年の第1回アテネ大会から128年がたち、大会としての旬、ピークを過ぎてしまったと思う。
立候補都市の激減している実情は、国際オリンピック委員会(IOC)にとって頭痛の種になっていたが、コロナ禍で行われた3年前の東京オリンピックは異常な大会だったと言わざるを得ない。無観客。「熱狂なきオリンピック」はオリンピックの在り方を問い、日本では大会後に談合問題が白日の下にさらされた(その余波はいまだに続いている)。
日本がオリンピックに臨む体制には変化が見られる。日本オリンピック委員会(JOC)は1952年のヘルシンキ大会以来、選手団の主将を置いてきたが、主将個人にかかるプレッシャーや、イベントへの参加など負担の重さが指摘され、主将を廃止することを決めた。
選手団の主将は名誉職のようなものであり、スポンサー企業やメディア向けの「顔」としての役割が大きかった。実態に即さない制度の廃止は好ましい。
そしてメディアも報道姿勢を見直す時が来ている。JOCはパリ大会の金メダルの獲得目標を20個としているが、メディアがそれに乗る必要もない。たとえば陸上のように決勝に進出するだけでも大きな価値を持つ競技もある。メダルという数ではなく、「実」を探る姿勢がこれからは必要だ。もっとも、オリンピックという大会は「怪物」だから、一つ一つの競技を吟味するのが難しいのは分かってはいるのだが…。
個人的にはオリンピックが曲がり角に来ている以上、今後、日本人も向き合い方を変えていかなければならないとは思う。
一方で、競技について分析していくと、今後の日本のスポーツの在り方の指針を示す競技が見られるのがうれしい。
半世紀ぶりのメダルか
今大会、私が最も注目しているのは男子バレーボールだ。現在、世界ランキング2位。男子のオリンピックでのメダル獲得は、72年のミュンヘン大会の金メダルまでさかのぼらなければならない。
バレーボールがオリンピックの正式競技に採用されたのは1964年の東京大会から。70年代まではソ連、東ドイツ、ポーランドといった社会主義国家と日本、韓国といった東アジアの国々のスポーツだった。しかし、80年代からはアメリカやブラジル、そしてオランダ、イタリアなどが強豪国として台頭してきた。
つまり、80年代を境に資本主義国家にもバレーボールの強化体制が広がり、それと同時に日本男子は国際競争力を失っていったのである。日本国内では毎年のように国際大会が開かれ、男性アイドルが場内演出、テレビの宣伝に起用されて盛り上がりを見せていたが、競技力についてはオリンピックの出場権を獲得するのも難しくなっていた。
その要因の一つに、70年代の栄光があったがために、海外のコーチングの導入が遅れたことが挙げられる。95年まで、男子日本代表の監督はミュンヘンの金メダルチームの関係者で占められていた。
最先端の海外のコーチングを十全に取り入れるようになったのは、2017年からだったと私は見る。フランス出身のフィリップ・ブランをコーチに招聘(しょうへい)し、風向きが変わり始めた(後に21年から監督に就任)。しかし、ブラン監督によれば、日本を指導することは簡単なことではなかったという。
「コーチに就任してから、選手たちと何度か面接を行いました。私が選手たちに求めるプレーはどんなものか、丁寧に説明をしたんです。選手たちも『はい』と返事をしてくれました。ところが、うまくいかない。2度目に面接をした時も同じ要求を繰り返したのですが、まったく変化が見られない。3度目になって、私は作戦を変更しました」
ブラン監督は説明するのをやめた。その代わり、選手たちがどんなことを求められているのか、自分の口から説明してほしいと言い放った。
「あの時の、何人かの選手の表情をあなたに見せたかった。目を見開いて、口を開ける選手、固まってしまった選手もいました。それまで選手たちは『はい』と返事するだけで、何も理解しないでプレーしていたんですよ。おそらく、高校、大学でコーチから意見を求められた経験がなかったのではないですか?日本の指導者はいい返事をする若者を育てるのは得意なようです」
「日本的」を変革
皮肉のきいたブラン監督の見立ては、日本で生まれ育った人間には耳が痛い。しかし、この「説明を求める面談」を終えてから、チームに変化が見られた。監督のコンセプトを理解し、それを積極的に実践する選手が出始めた。そして前回の東京大会では準々決勝に進出し、復活を印象づけた。
その中心になっているのが、石川祐希、高橋藍(らん)の2人だ。石川と高橋はイタリアでもプレーし、技術の幅を広げ、世界のトッププレーヤーへと成長した。また、パリ・オリンピックに先立って行われていたネーションズリーグでは2位に入ったが(国際大会では47年ぶりのメダル獲得)、試合によっては相手に手の内を明かさず、石川、高橋を温存する試合さえあった。それでも世界の列強と戦えるようになったのは、選手層が分厚くなったからに他ならない。
ブラン監督は、チームづくりの「肝」となる部分についてこう話す。
「日本は年功序列社会ですよね。しかし、バレーボールの世界ではそれは通用しません。先輩にチームのことを任せ、後輩は自分のことに集中しているような態度は許されないのです。チームの中心であるにもかかわらず、組織のことに無関心だとしたら、それは責任の放棄です」
年齢に関係なく、組織に責任を負う。そのために年齢に関係なく話し合える風土をつくる。それが監督をはじめとしたマネージメントスタッフ、選手たちの仕事である。
こうした発想はラグビー日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ(HC)のチームづくりの発想にも似ている。ジョーンズHCは常々、こう話している。
「チームの構成員が、全員を理解しなければなりません。日本人同士、外国人同士でグループを形成するようでは真のコミュニケーションは生まれません。お互いのことをよく知ることで、目指すラグビーが実現できるのです」
バレーボール男子も、相互理解が深まったなかでオリンピックを迎える。7月1日時点の世界ランキングはポーランドに次いで2位。プールステージではアメリカ、アルゼンチン、ドイツと対戦するが、1位通過をすれば、準々決勝での組み合わせが優位になる。特にアメリカは油断ならない相手。この一戦を見れば、日本がどれだけの高みを目指せるのか見えてくるに違いない。
海外に飛び出す選手
バレーボール男子は海外の最先端のコーチングを取り入れて成功したが、日本から海外に飛び出して成功している選手たちもいる。
前回の東京大会、スケートボードの男子ストリートで優勝した堀米雄斗は1999年生まれ。ティーンエージャーの時から活躍していたこともあり、高校を卒業してからはスケートボードの本場、アメリカに拠点を移す資金力があった。当初は英語が思ったように話せず、孤独な時間も多かったようだが、アメリカで成功を収め、東京オリンピックでも金メダルを獲得した。
アーバンスポーツの場合、日本とアメリカではマーケットの規模が違う。最初から「本場」を目指したことが成長を促したのである。
ただし、東京大会から3年しか経過していないのに、堀米がパリ大会の出場を決めたのは、6月23日の最終予選だった。東京オリンピックの後は、周りの競技レベルが飛躍的に向上し、板を縦横無尽に扱う年下の選手が台頭、堀米が劣勢に立たされていた。新興スポーツはそれだけ進化のスピードが速く、これまでの文脈では捉えきれない。
そして今後、堀米のように世界のトップを目指す選手であればあるほど、海外へ拠点を移すことが当たり前になるだろう。
女子やり投げで金メダル獲得を射程に捉えている北口榛花(はるか)は、誰に命令されたわけでもなく、自分でチェコ人コーチにメールを出して門下に加わった。チェコに本拠地を構えてヨーロッパを転戦してきたことで、北口にとってパリで試合することは「日常」に近いものがあるだろう。
また、5月には男子100メートルのサニブラウンがオリンピック参加標準記録を突破する9秒99を出し、女子3000メートルでは田中希実(のぞみ)が日本記録をマークしたが、2人が記録を出した大会は世界の一線級がそろうダイヤモンドリーグのオスロ大会だった。
未来への指針
陸上では自分よりも速い選手がレースで先行すると、それに「同期」することで楽に走ることができる。サニブラウン、田中は国内では自分より速い選手と一緒に走ることはまれだが、海外では引っ張ってもらえる立場となる。つまり、日本を拠点にするよりも、海外拠点の方が成長を促せる可能性が広がる。
果たしてパリ・オリンピックでは、どういった環境でトレーニングを進めてきた選手たちが活躍するだろうか。パリ・オリンピックではその流れを読み解いていきたいが、それは日本のスポーツ界の未来への指針ともなるのではないか。
スポーツジャーナリスト 生島 淳(いくしま・じゅん) 1967年宮城県気仙沼市生まれ。早稲田大学卒業後、博報堂に入社。勤務しながら執筆を始め、1999年に独立。ラグビーW杯、五輪ともに7度の取材経験を誇る一方、歌舞伎、講談など伝統芸能の原稿も手がける。著書は最新刊「箱根駅伝に魅せられて」(角川新書)、「ラグビー日本代表ヘッドコーチ エディー・ジョーンズとの対話 コーチングとは『信じること』」(文藝春秋)など。
(Kyodo Weekly 2024年7月22日号より転載)