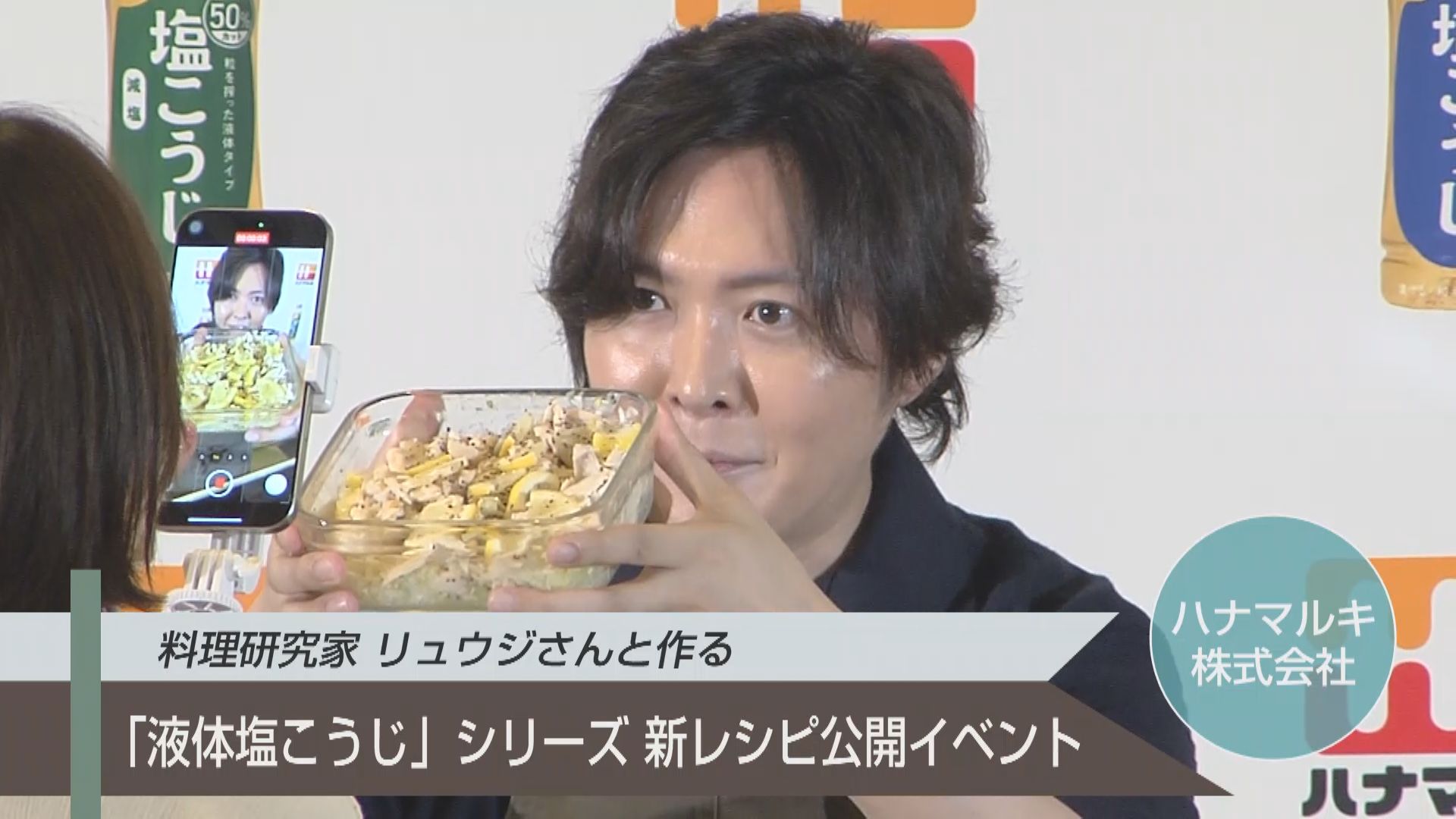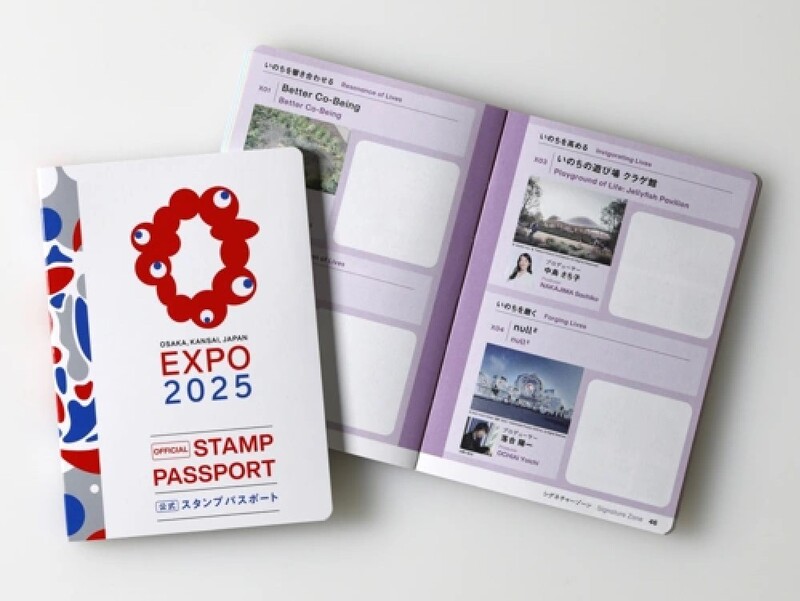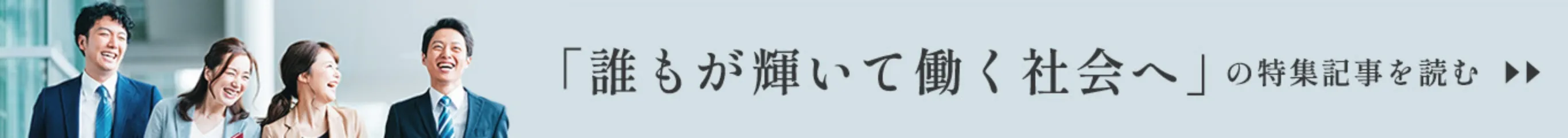「特集」ハリスvsトランプ 女性・黒人・アジア系大統領誕生なるか 分厚いガラスの天井

海野 素央
明治大学政治経済学部教授
筆者は、バラク・オバマ氏(以下、初出以降敬称および官職名略)が米国史上初の黒人大統領に当選した2008年大統領選以来10年以上、研究の一環として民主党候補の選対にボランティアとして参加し、内情を観察してきた。その経験や研究を基に、民主党大統領候補のカマラ・ハリス副大統領が初の女性・黒人・アジア系大統領として勝利する道筋を、大胆に予想する。

選挙集会でハリス氏と記念撮影する筆者(右)=2019年8月、米西部ネバダ州ラスベガス
共和党大統領候補ドナルド・トランプ前大統領の暗殺未遂、民主党大統領候補だった現職ジョー・バイデン大統領の撤退という劇的な展開を経て「ハリス対トランプ」の対決構図が固まった。
「検事」対「犯罪者」
今後、最大のポイントになるのが9月10日に予定されるテレビ討論会だろう。注目点は、元検察官のハリスが、議会襲撃事件など四つの事件で起訴されたトランプの「犯罪」を厳しく追及し「無実ではない人間」として提示できるかである。ハリスはさらに、トランプが開いていた不動産セミナー「トランプ大学」の授業料詐欺疑惑や元作家の女性に対する性的暴行事件も取り上げ、「重罪犯」「詐欺師」「性的暴行者」と責める。トランプが任命した判事3人を含む連邦最高裁がトランプに免責特権を与えた件も批判するだろう。
これらの「犯罪」を柱にしたディベート戦略は、民主党支持者、民主党寄りの無党派層および反トランプの共和党穏健派にエネルギーを与える。英誌エコノミストと調査会社ユーガブの全米共同世論調査(8月11~13日実施)によれば、全体で56%がトランプを「腐敗」と結び付けた。世論調査で定評がある米キニピアック大学の激戦州ペンシルベニア州の有権者に限定した調査結果(同月14日発表)も見てみよう。同州は選挙人が19で、激戦7州において最も選挙人が多い。すでに大統領職を1期務めたトランプについて「大統領として効果的に職務を務める性格か」と質問したところ、46%が「はい」、53%が「いいえ」と回答し、「はい」が「いいえ」を7ポイント下回った。「トランプは正直か」という質問に関しては、37%が「はい」、60%が「いいえ」と答え、こちらは「はい」が「いいえ」に対して23ポイントも低かった。同州の有権者の過半数が、トランプは大統領としての資質に欠けるとみているのだ。
トランプのリーダーシップスキルに関しては、50%が「ある」、49%が「ない」と回答し拮抗(きっこう)した。ただし、女性は9ポイント、黒人は56ポイント、「ない」が「ある」を上回った。米国は女性が男性よりも登録有権者数が多い。他方、ハリスのリーダーシップスキルは「ある」が48%、「ない」が47%でこちらもほぼ同等だったが、女性は「ある」が12ポイント、黒人は68ポイント高かった。
18~34歳の若者は両氏のリーダーシップスキルをどのように捉えているのか。同調査では、トランプに対して若者の53%、ハリスに対して57%が「ある」と回答し、ハリスが4ポイントリードした。
ハリスが討論会でトランプの「犯罪」を取り上げる一方、トランプはバイデンの次男ハンターが薬物依存症を隠して銃を購入し有罪評決を言い渡された件を持ち出す。その時ハリスはどう人間性を見せながらトランプに反論できるのか。薬物依存症の家族を持つ人々に同情を示し、彼らに寄り添うメッセージを送るのではないだろうか。しかし、それでもトランプは9月から始まるハンターの脱税の裁判を取り出して切り返す公算が大きい。米国民は脱税には厳しい目を向ける傾向がある。
そこでハリスはこう再反論することもできる。「あなたの一族が経営するトランプ・オーガニゼーションの最高財務責任者アレン・ワイセルバーグは脱税で禁錮5月の実刑判決を言い渡されて収監された」―と。
ハリスはトランプに「重罪犯」のイメージを植え付け、彼女が支持を得たいと願っている女性、黒人および若者に対してトランプの大統領としての「資質」に一層の疑問を持たせることが極めて重要だ。討論会で、ハリスが自分を「正義の擁護者」、トランプを「腐敗した重罪犯」に描ければ、討論会以降の選挙戦をかなり有利に進められる。
イスラエルーハマス戦争
テレビ討論会におけるもう一つの注目点は「イスラエル―ハマス戦争」である。ハリスは相性を重視して、ミネソタ州のティム・ウォルズ知事を副大統領候補に選択し、最有力候補と目されていたペンシルベニア州のジョシュ・シャピロ知事を外したと言われている。アラブ系の人口が多い激戦州ミシガンでの勝利を強く望むハリスは、ユダヤ系のシャピロが障害になると考えたのかもしれない。
前で紹介したエコノミストとユーガブの調査では、「イスラエルとパレスチナのどちらに同情するか」との質問に、若者(18~29歳)の16%がイスラエル、21%が同等、37%がパレスチナと回答し、パレスチナがイスラエルを21ポイントも上回った。「ハリスはイスラエルとパレスチナの衝突に関して、どちらにより同情的か」と尋ねたところ、イスラエルとパレスチナが共に16%であったのに対して、最も多かったのは42%の「分からない」であった。選挙の勝敗の鍵を握る若者には、ハリスのイスラエルとパレスチナに対する態度が明確になっていないのだ。
一方バイデンに関しては、若者の40%が「あまりにもイスラエル寄り」と回答した。若者とアラブ系の票獲得を目指すハリスは、そのために討論会でパレスチナに寄り添ったメッセージを発信することが不可欠だ。
ハリスの強みは、一体どこにあるのだろうか。今回の米大統領選挙でバイデンとトランプ双方を嫌う人々を「ダブルヘイター」と呼び、選挙の行方を不透明なものにした。彼らは変化を望んでいた。ハリスは「変化の代理人」として、彼らのニーズに合致したのだ。
多様性の体現者
ハリスは、彼女自身が人種の多様性を体現している点も強みだろう。オバマは黒人男性とみられているが、ハリスは黒人であり、アジア系女性でもあり、オバマよりも多様性の要素を持っている。選挙戦においては、黒人、アジア系および女性の票の獲得が可能である。
さらに、ハリスに対する支持者の熱意は最大の強みである。日本では理解しにくいが、この熱意が多くの有権者を陣営に呼び込み、選挙が「祭り」の領域に入っていくのだ。ハリスとウォルズは、「喜び」「寛大」および「親切」という言葉を使い始めた。憎悪や恐怖で分断されたトランプ政権には「戻らない」という決意の象徴として使用している。ウォルズは、トランプやJ・D・バンス副大統領候補が、人々の喜びを奪おうとしていると有権者に訴えている。ハリス陣営は、「ハリス対トランプ」を「陽対陰」ないし「明対暗」という対立構図に置き換えて、混沌(こんとん)とした1期目のトランプ政権にうんざりしている有権者、特に若者を陣営に引き寄せようとしており、それは目下のところ成功しているとみてよい。
オバマ元選対が加勢
上記に加えて、ハリスが雇ったオバマ選対の幹部であった3人も、ハリスの強みになる可能性がある。2008年オバマ選対で選対本部長を務めたデイビッド・プラフ氏が、上級顧問としてハリス陣営に入った。プラウフは、早速、自身のX(旧ツイッター)に、トランプを「高齢・奇妙・臆病者・重罪犯・不適任」と投稿した。12年オバマ陣営の選対副本部長であったステファニー・カッター氏も、上級顧問として加わった。さらに、08年と12年に激戦州を担当したミッチ・スチュワート氏は、激戦州のアドバイザーとして採用された。以下で、彼らの選挙戦略を説明しよう。
第1に、08年と12年の大統領選挙と同様、激戦州でフォーメーションを組む。例えば、中西部ウィスコンシン州(選挙人10)、ミシガン州(同15)、東部ペンシルベニア州(同19)の3州を最重点州に置き、仮にウィスコンシン州ないしミシガン州を落とした場合、黒人の人口割合が高い南部ジョージア州(同16)の勝利で補足する。「3+1(スリー・プラス・ワン)」が可能になる。
第2に、戸別訪問を中心にした地上戦に力を入れる。ハリス陣営によれば、8月7日にミシガン州デトロイトで行った選挙集会では、約1100人がボランティア運動員として署名した。陣営はネバダ州でバイデン撤退から3週間で1万人以上のボランティア運動員をリクルート。彼らは戸別訪問や電話による支持要請、ポスター設置などを行う。選対の力は、ボランティアの運動員数と関係がある。
激戦7州で選対事務所数が最多なのはネバダ州の13だが、現在12あるアリゾナ州の選対数を今後、6増設して18にする予定だ。選対やボランティアの支持者宅が戸別訪問の拠点になる。
第3に、「異文化連合軍」を組んで、連合軍のメンバーの票の組み合わせで勝利を目指す。ハリス陣営の激戦州の責任者ダン・カニエン氏も、08年にオバマ陣営に参加した人物だが、彼は連合軍のメンバーに、まず黒人とアジア系、次に女性、続いてヒスパニック(中南米系)と若者を挙げた。このほか、20年にバイデンに投票しなかったが、共和党の過激主義に強い不快感を抱き、以後、中間選挙や地方選で同党に投票していない有権者と、今回の大統領選挙でどの候補に投票をするのか決めかねている7%の有権者(7月30日時点)も、陣営に引き入れる対象となっている。
白人女性のヒラリー・クリントン元国務長官が破れなかった「ガラスの天井」。それよりもはるかに分厚い天井を、ハリスは破ることができるだろうか。
明治大学政治経済学部教授 海野 素央(うんの・もとお) 1960年静岡市生まれ。米国際大学(現アライアント国際大学)博士課程修了。専門は異文化間コミュニケーション論。過去の米大統領選で民主党のオバマ、クリントン、バイデン各候補の陣営に入り激戦州で戸別訪問や電話による支持要請といった「地上戦」に従事しながら研究。「オバマ再選の内幕」「トヨタ公聴会から学ぶ異文化コミュニケーション」(いずれも同友館)など著書多数。
(Kyodo Weekly 2024年9月2日号より転載)
編集部からのお知らせ
新着情報
あわせて読みたい



自動車リサイクル促進センター