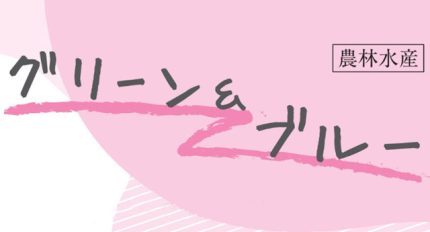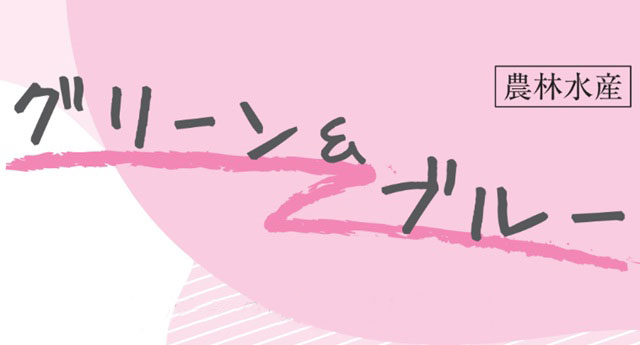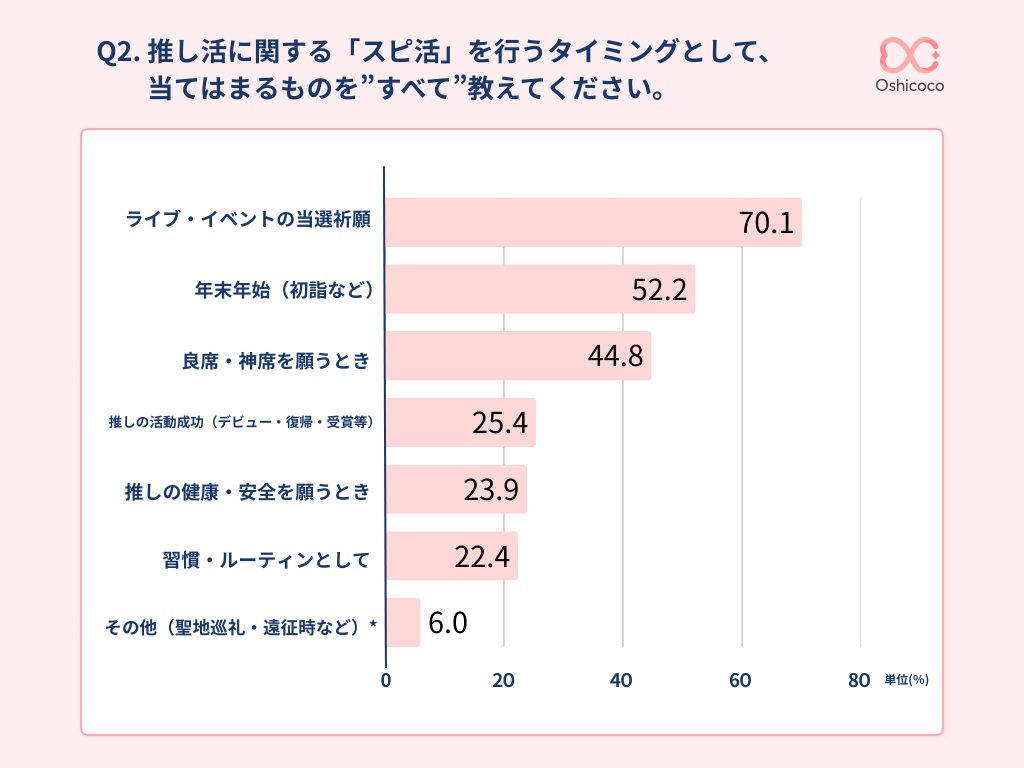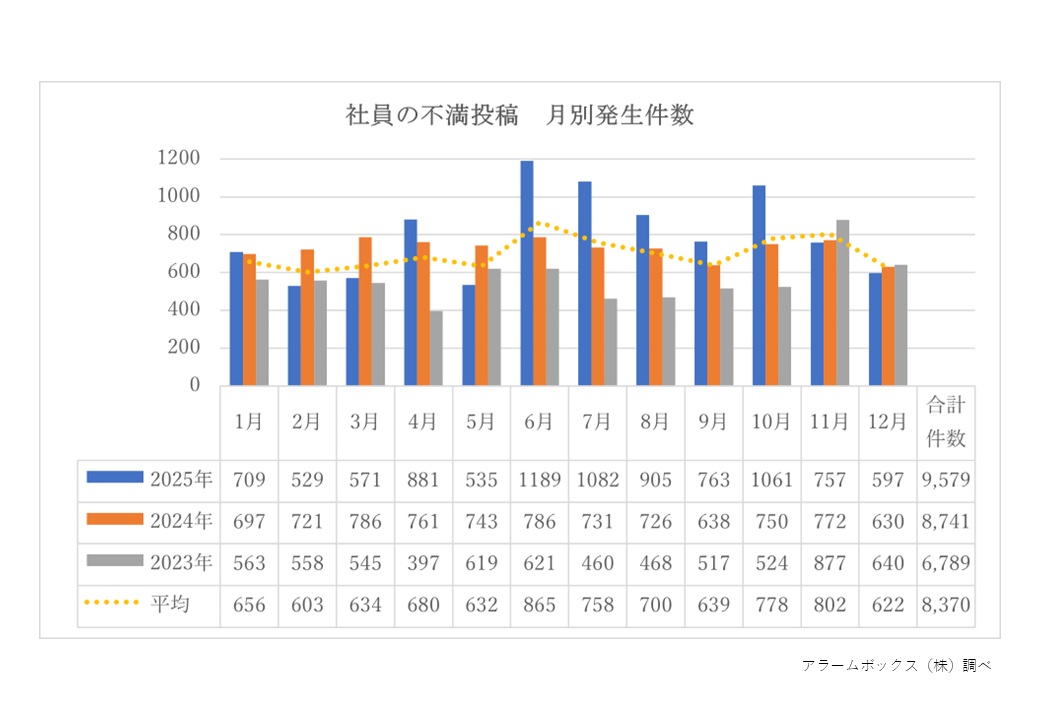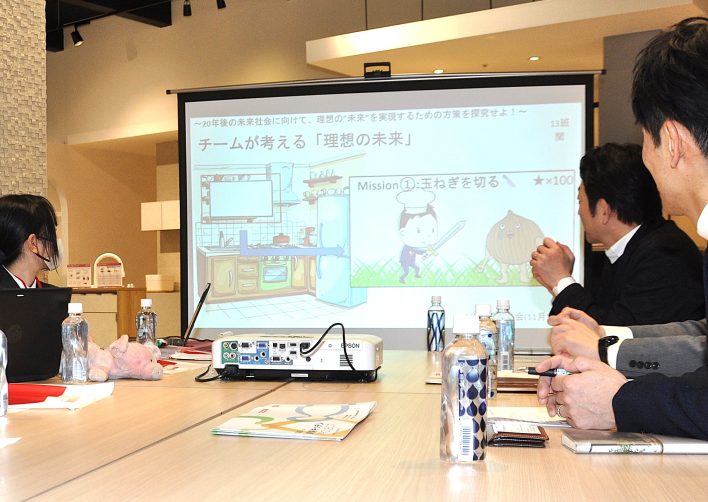「丸干し屋のままでいいのか」 中川めぐみ ウオー代表取締役 連載「グリーン&ブルー」
「自分たちを丸干し屋として捉えたままでいいのか、ずっと考えています」。そう話してくださったのは、鹿児島県・阿久根市で水産加工業を営む下園薩男(しもぞのさつお)商店の3代目、下園正博さんだ。
1939年創業の歴史を持つ同社は、ウルメイワシの加工・販売を主軸としてきたが、漁獲量の減少や丸干しを食べる生活者の減少などが要因で、この40年ほど厳しい状態が続いていた。
父である2代目は息子に家業を継がせる気はなかったし、正博さん自身も大学に入る頃までは継ぐ気はなかったという。しかし在学中に将来を考えた際、“自分にしかできないことをしたい”と、家業を継ぐことを決意。IT企業や水産系商社で経験を積んだ後、30歳で下園薩男商店に入社した。
正博さんがまず取り組んだのは、IT企業などの経験を生かした社内のDX化。そして新商品の開発だ。これまでにアプローチできていない女性や若者といった層に好まれる商品をと、2年ほどをかけて完成させたのが「旅する丸干し」という、イワシの丸干しをオイルに漬けた瓶詰だった。ボンタンやトマトガーリックなどこれまでの丸干しからは想像できない味付けに、鮮やかでポップなパッケージ。都心のデパートや雑貨屋などでも取り扱いは増え、農林水産大臣賞も受賞した。
他にも小さなお子さん向けに「はらぺこイワシ。」という焼きウルメ丸干しのおやつを開発。幼少期にほのかな苦味や渋みを経験してもらうことで味覚を育てようという商品で、近隣のこども園では給食として採用されている。
この商品ができたのは、実は先代たちのおかげでもある。50年ほど前、丸干しイワシの競合から差別化するため、地元の漁業者と相談して朝方4〜6時にイワシを獲ってもらうことにした。そうするとイワシの胃が空っぽで、苦味が少なく美味(おい)しい丸干しにできるという。これを正博さんがコンセプトからデザインし直し、ヒット商品につなげた。
こうして聞くと下園薩男商店は順風満帆にみえるだろう。しかし現在も漁獲量の減少や生活者の趣向変化は進み続けており、丸干しだけで事業を続けるのでは頭打ちになるという。そこで冒頭の「自分たちは丸干し屋のままでいいのか」という問いだ。
正博さんは既に「イワシビル」という〝カフェ・雑貨店・ホステル〟からなる複合施設などを企画運営し、加工・販売の枠を超えた新たなコミュニケーションの形にチャレンジしている。例えば地域をロードバイクで走るインバウンドの方が休憩や宿泊でふらりと立ち寄り、たまたま食べたイワシの丸干しに感動するといった出会いが生まれているそうだ。
厳しい状況がこの先も続く水産業界で、私たちは自分自身を何屋として捉え、変化・進化していくのか。正博さんから問い続ける大切さを学ばせていただいた。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.41からの転載】