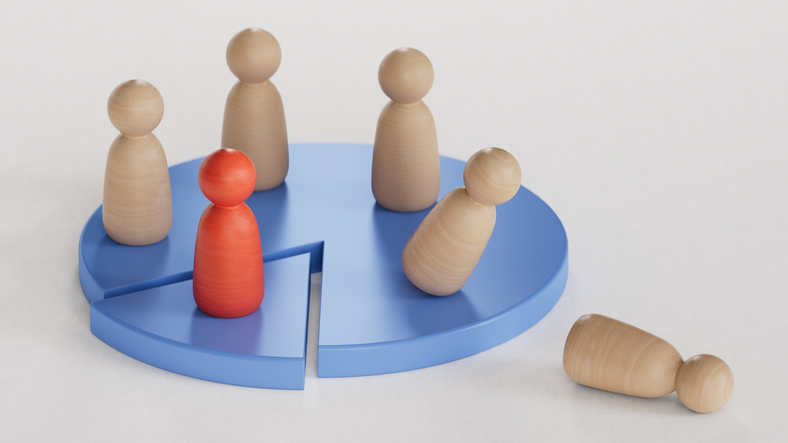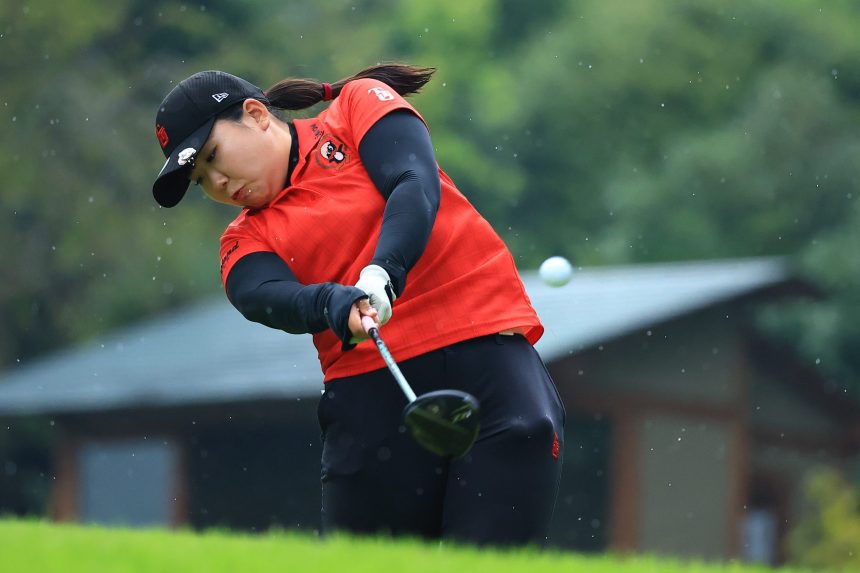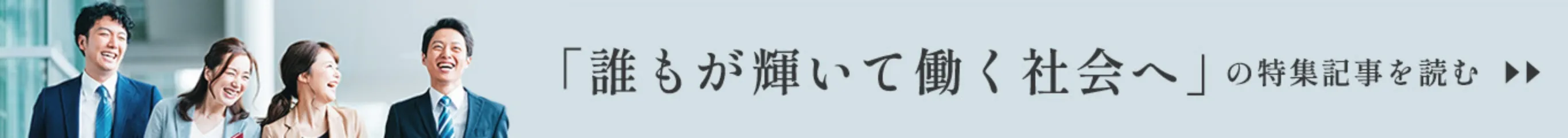「特集」宇宙の始まり 物質誕生前に迫る ナノヘルツ重力波 パルサー使い観測

浅田 秀樹
弘前大学教授
2021年の年の瀬、米航空宇宙局(NASA)がジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)を打ち上げ、観測を開始した。世界の天文観測を約30年間けん引してきたハッブル宇宙望遠鏡(HST)の後継機であり、NASAが得意とする宇宙(地球の大気圏の外側)から行う天文観測における旗艦である。JWSTにより圧倒的に高解像度の天体画像が得られ、従来の望遠鏡では見えなかった遠方の暗い天体の観測が期待されている。
いざ観測が始まってみると、通説に反して、宇宙初期に巨大な銀河が既に存在していることが衝撃を与えた。宇宙初期での天体形成にはかなり時間がかかるため、生まれたての銀河は小さくて軽いはずだと信じられていた。宇宙初期の重い銀河が次々と発見されたことに、天文学者は頭を抱えている。
銀河の中心には巨大ブラックホールが潜んでいて、銀河同士が合体する際、巨大ブラックホールの連星からとてつもなく長い重力波(じゅうりょくは)(ナノヘルツ重力波と呼ぼう)が放出されるはずだ。ナノヘルツ重力波の観測が、宇宙初期を探る上で重要なツールとなる。しかし、ナノヘルツ重力波の観測は、以下に述べる通り困難な挑戦で完全には成功していない。それでも、昨年6月、その観測的証拠を複数の国際研究グループが同時に発表し、大変注目されている。これらについて、本稿で紹介しよう。
見えすぎて困った
今年の夏も全国的に猛暑で湿度が高かった。この湿度とは、地球の大気に含まれる水分のことである。大気には水分子が存在するため、光は完全には透過できない。大気中の水分は雲を形成し日光を遮る。大気中の水分の密度のむらによって日光が屈折する現象が、虹である。大気中の水分は光を吸収・散乱するため天文観測の大敵だ。よって、地上の望遠鏡を用いて撮影される天体の像はぼやけてしまう。
結局、人類は宇宙空間に望遠鏡を打ち上げて、宇宙から観測することにした。代表的な宇宙望遠鏡がHSTである。1990年にNASAが打ち上げ、その後、スペースシャトルによって運ばれた機材を用いた宇宙飛行士の船外活動により、望遠鏡のアップデートまでも行われ、長い期間、宇宙観測を先導してきた。NASAが2021年に打ち上げたJWSTによってついに主役交代となった。
JWSTの望遠鏡の面積はHSTの約7倍もあり、光をたくさん集めることができるため、これまで暗くて観測できなかった遠くの銀河さえ見ることが可能となった。実際、見えたのだ。しかし見つかり過ぎたことが天文学者を大いに悩ませている。
光は光速(秒速約30万キロ)で進むため、遠くの天体からの光が地球に届くまでにはとても時間がかかる。100億光年離れた天体からの光が地球に届くには、100億年かかる。つまり、その天体を今観測しても、現在の姿ではなく100億年前の姿を見ることになる。JWSTが見つけた宇宙の始まりの頃の重い銀河の存在を説明することが難問なのだ。
宇宙誕生時に天体は存在しない。そもそも宇宙の始まりの時点には物質さえ存在せず、ビッグバンと呼ばれる宇宙初期に、物質の源である軽い元素が誕生した。その後、それらの物質が集まり、惑星、恒星、銀河などの天体の階層構造がつくられた。JWSTが発見した銀河は、宇宙誕生後わずか3億年と若いにも関わらず、大きく成長(非常に重い)した点が厄介なのだ。
近年の天文観測によって、銀河の中心には巨大ブラックホールが生息していることが明らかになった。JWSTが発見した銀河にも巨大ブラックホールが住んでいるはずだ。銀河同士が衝突・合体する際、それらの中心にある巨大ブラックホール同士も合体するだろう。ただし、正面衝突する確率は極めてゼロに近く、近づいて連星をなした後に時間をかけて合体すると考えられている。
しかしながら、ブラックホールは光らない天体のため、巨大ブラックホールの連星はJWSTでも直接見ることは不可能。ここで登場するのが「重力波」である。重力波は15年に初検出され、その成果は17年のノーベル物理学賞に選ばれたほど、科学界にインパクトを与えた。重力波はアインシュタインの一般相対性理論の産物である。
時空のゆがみ
アインシュタインは、重力とは質量などによって周りの時間や空間が曲がる現象だと看破した。空間の曲がりは、水平に張ったゴムシートにボールを置けば、シートがたわむようなものだと思ってもらえば、ここでの話には十分である。時間の曲がりをイメージすることは難しいが、重力の強さで時間の進み方が違ってくると思ってもらえばいいだろう。極端な場合がブラックホールだ。ブラックホールのへり(ホライズンと呼ばれる)では、遠方から測定すれば時間がまったく進まず、観測不可能となる。だから、ホライズンからの光がわれわれに届くことがない。結果、ブラックホールは真っ黒(ブラック)なのだ。
さて、ゴムシートに1個のボールを静かに置けばシートのたわみ具合は時間的に変化しない。しかし、ゴムシートに2個のボールを投げ込んだ状況ではたわみ具合が時間的に変動する。同様に、ブラックホール2個が互いの周りを公転すれば、その周りの時間や空間の曲がりが時間的に変化し、それが遠方に伝わっていく。これが重力波の正体である。米国のLIGO(ライゴ)重力波検出器が15年に重力波の初検出に成功し、その後、欧州のVirgo(ヴィルゴ)も成功した。現在、日本のKAGRA(カグラ)重力波検出器も参加した国際共同観測体制(それぞれの頭文字を取ってLVKコンソーシアムと呼ぶ)で観測が進んでいる。ただし、KAGRAは岐阜県飛騨市神岡の地下にあり、今年1月の能登半島地震で被災し現在修復中。地元NPOからの義援金がKAGRAに贈られるなど、LVK共同観測へのKAGRAの早い復帰が望まれている。
ナノヘルツ重力波の証拠
さて、LVKのような大型重力波検出器は、数キロの大きさがある。この検出器は重力波による時間・空間の伸び縮みを精密に測る目的で建造されている。レーザーと呼ばれる特殊な光を検出器の中を数百回も往復させることで、重力波による微弱な変動を検知する。詳細は省略するが、この地上にある大型重力波検出器を用いて測定できる重力波の長さ(波長)は、100から1千キロ程度である。この波長の重力波を生み出す代表例が、ブラックホール2個からなる連星である。そのブラックホールの質量は、太陽質量の10から100倍くらいのものが該当する。実際、2015年に初検出された重力波の発生源は、こうしたブラックホール連星だと解釈されている。
長さ1千キロは、宇宙ではかなり短い。もっと長い重力波は存在するのだろうか。そして、存在するならどうやって検出すればよいか。昨年6月、複数の国際観測チームが、ナノヘルツ重力波の証拠を公表し、大きな話題となった。チームのうち、ナノグラブが老舗で代表格である。ナノヘルツは単位時間当たりの振動の回数を表し、1ナノヘルツは、1回振動するのに30年間かかるような、超ゆっくりした振動のこと。重力波は光の速さで伝わるため、1ナノヘルツの重力波の波長は30光年にもなる。太陽系から一番近い恒星はアルファケンタウロスで、われわれから約4光年もの距離にある。つまり「近い恒星までの距離より長い波を測定した」というのが彼らの主張だ。先に述べた通り、LVKのような地上の大型重力波検出器は「大型」とはいえ数キロの大きさしかないので、そんなに長い波長を測定することは到底不可能である。まるで10センチの定規を用いて月までの距離を測ろうとするようなものだからだ。
自然界最強の「物差し」
それでは、どうやって星までの距離に匹敵するような波長の重力波を測定できたのかを説明しよう。彼らは、とても正確かつとても長い「物差し」を使用したのである。自然界に存在する最も正確な時計が「パルサー」とよばれる天体である。この天体は、規則正しく電波を放出し、その周期の正確さは、人間が作り上げた原子時計をも上回っている。多数のパルサーが、われわれの銀河系に分布していて、天文学者が定期的にそのパルサーからの電波を測定している。
パルサーから電波が規則正しく届くはずが、重力波が通過すると、時間と空間が伸び縮みするため、電波の到着時間に乱れが生じる。いつも規則正しく運行する電車(例えば山手線)が悪天候などのため、到着時間が不規則になってしまうのと似ている。
観測するパルサーは、われわれから数十〜数千光年の距離にあるため、原理的には、その距離より短い重力波の影響が全て含まれる。しかし、人類は数千年も観測を継続するわけにはいかない。複数ある観測チームの中でも古参のナノグラブチームは、およそ20年間の観測データの蓄積がある。従って、彼らは、数光年程度の長い波長の重力波を検出することが可能だ。実際、彼らを含む五つのチームが別々の観測装置を用いてパルサーを継続的に観測し、ナノヘルツ重力波の証拠を昨年6月に発表した。
サイエンスの世界において、「再現性」は重要である。ある研究グループが新発見を主張しても、他の研究者が独立に調べて再現できなければ、その新発見は科学的知見として認定されない。この点で、複数のチームが別々の装置を用いて同様の現象を見いだしたので、ナノヘルツ重力波の証拠は「とても強い」と考えられている。しかし、まだ統計的な信頼度が十分ではないため、「証明」ではなく「証拠」というソフトな言い回しが発表で用いられた。現在、四つのチームが合同で観測・解析を行うために「国際パルサータイミングアレイ」のコンソーシアムを立ち上げ、鋭意活動している。2、3年後には、よりはっきりした結果が公表されるらしい。
始まりの始まり
観測された(らしい)ナノヘルツ重力波はどこから来たのか? 実は研究者の間で意見が割れている。すでに述べた通り、巨大なブラックホールの連星から発生したとする学説が有力である。一方、宇宙の始めに物質の源である元素が誕生したのがビッグバンである。しかし、そのビッグバンの前に何があったのか、観測的証拠は得られていない。宇宙が急膨張したとする「インフレーション理論」が有力な仮説であり、その理論もまた、超長波長の重力波の存在を予言する。ひょっとしたら、ナノヘルツ重力波の観測によって、ビッグバン以前の、つまり物質さえ存在しなかった宇宙の姿をのぞけるかもしれない。一体どんな景色をわれわれは見ることができるのだろうか。今後の進展が楽しみだ。
弘前大学 教授 浅田 秀樹(あさだ・ひでき) 1968年京都市生まれ。京都大学理学部卒。大阪大学理学研究科博士後期課程修了、博士(理学)。現在、弘前大学・大学院理工学研究科教授、宇宙物理学研究センター長。専門は、一般相対性理論および理論宇宙物理学。著書は最新刊「宇宙はいかに始まったのか ナノヘルツ重力波と宇宙誕生の物理学」(講談社)、「三体問題 天才たちを悩ませた400年の未解決問題」(講談社)など。
(Kyodo Weekly 2024年9月9日号より転載)