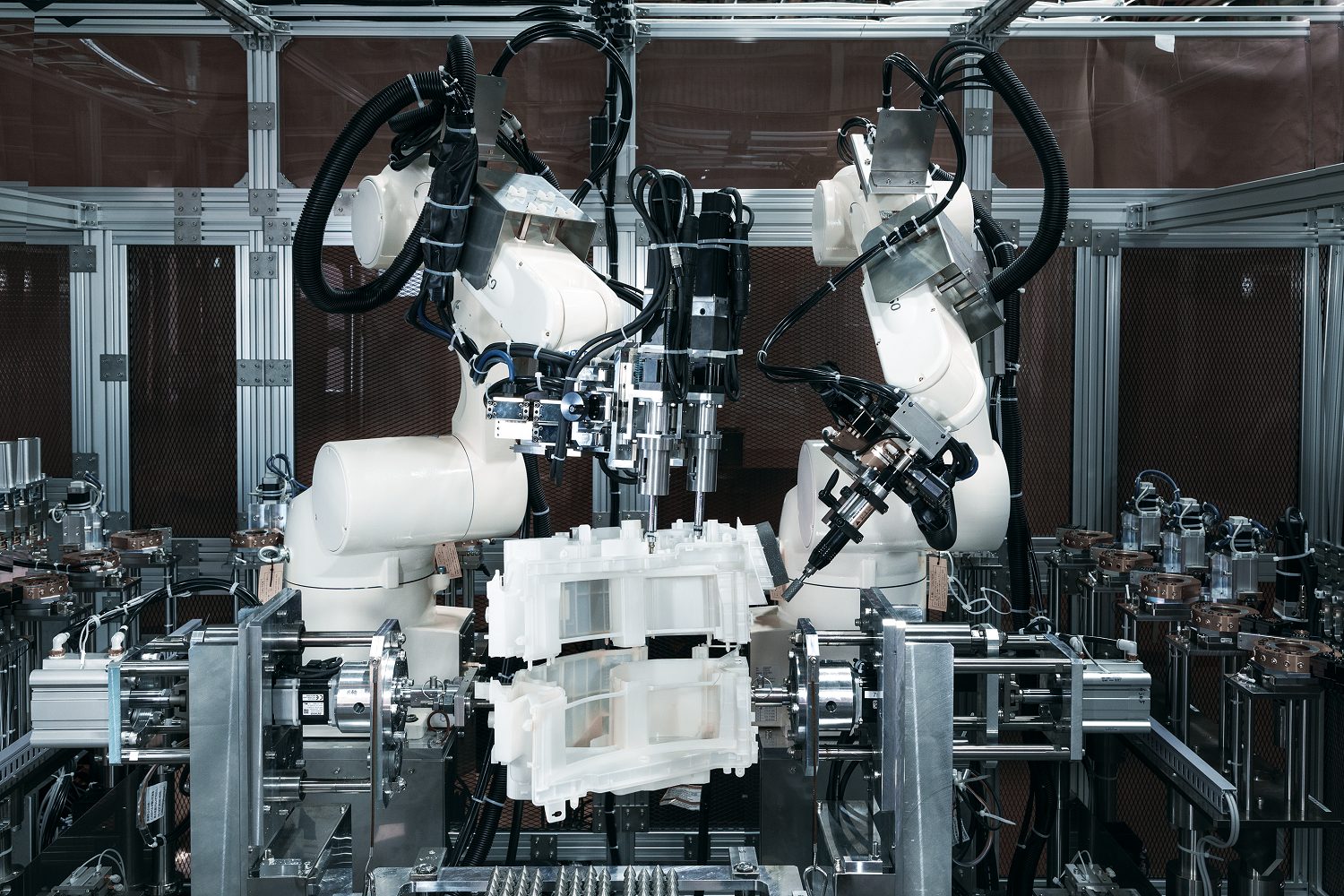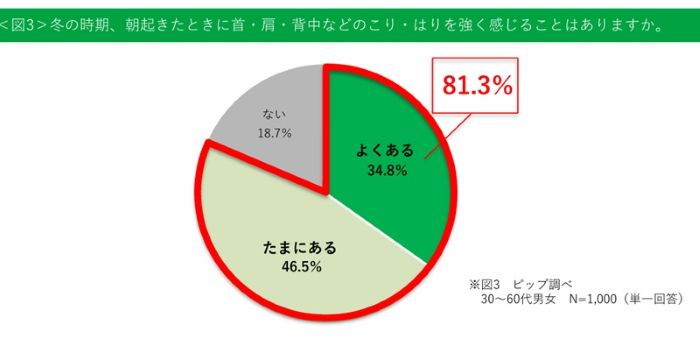ウクライナ文化からの「挑戦」 【沼野恭子✕リアルワールド】
まもなく、ロシアがウクライナに全面侵攻を始めてから丸4年になる。この間、日本ではウクライナに関する報道が格段に増え、それにともない、一見ウクライナ理解も進んだように見える。しかし、大部分は戦況や政局に関する情報で、残念ながら、ウクライナの言語・文化・芸術についての本格的な紹介が格段に増えたとは言い難い。
そもそも日本にはウクライナ語やウクライナ文化を専門とする研究者が少ないのでやむを得ないのだが(19世紀の国民的詩人タラス・シェフチェンコの詩集は以前から日本語訳が出ているが)、ウクライナ文化こそがウクライナ人の拠って立つところであり、ウクライナの人々が現在戦いつづけている理由がまさに自らのアイデンティティーを守るためであることを思えば、ウクライナ文化の内実こそもっと深く知りたい。
そんな中、ウクライナ文化に関する良書がいろいろ出版されるようになってきた。特に注目されるのは、赤尾光春・原田義也両氏の編による論集『ウクライナ文化の挑戦』(幻戯書房、2025)だ。20人を超えるウクライナの作家や研究者、日本の研究者やジャーナリストが、ウクライナ文化の諸領域について多角的に論じている。侵略のイデオロギーである「ロシア世界(ルースキー・ミール)」の実態、ウクライナ語が抑圧されてきた歴史、多言語使用状況の変遷。そしてウクライナの歌、美術、文学、映画の豊かさが鮮やかに描きだされている。その多彩で自由な躍動は、タイトルの示すとおり、「文化」の仮面をかぶって侵略してくる教条的なイデオロギーに対する、ウクライナ文化からの「挑戦」に他ならない。長くソ連の文化圏に組み込まれてきたウクライナが、その文化の独自性をきわだたせるためにロシア文化との差異化を図っている実情も浮き彫りにされている。
この論集で、オレフ・センツォフとセルゲイ・ロズニツァというウクライナの才能あるふたりの映画監督に焦点を絞った梶山祐治氏は、『ウクライナ映画 完全ガイド』(パブリブ、2024)を上梓(じょうし)しており、そこではウクライナ映画全般について詳述している。大変な労作である。
他にも、村田真一氏の編訳で『ウクライナ戯曲集』(国書刊行会、2025)が刊行されたことは記憶に新しい。収録された3編の作品のうちの一つ、20世紀初頭のウクライナの未来派詩人ミハイリ・セメンコの幻想的な詩劇「リリス」が近く上演されるという(劇団「街の星座」による公演。1月22〜25日、東京、サブテレニアン)。
これらの著作が、今後日本で、ウクライナ文化独自の魅力を本格的に研究・翻訳・紹介していくための端緒となることを願わずにいられない。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.3からの転載】

沼野恭子(ぬまの・きょうこ)/ 1957年東京都生まれ。東京外国語大学名誉教授、ロシア文学研究者、翻訳家。著書に「ロシア万華鏡」「ロシア文学の食卓」など。