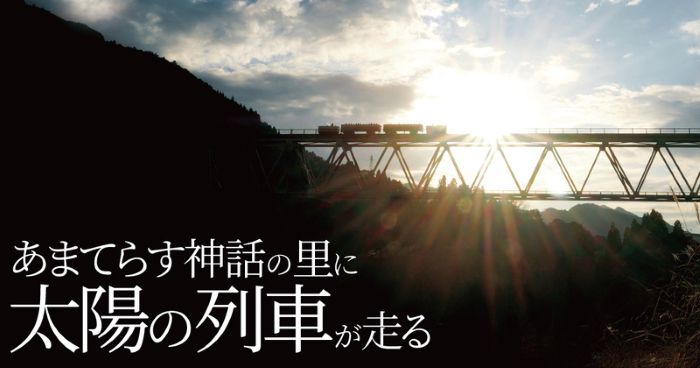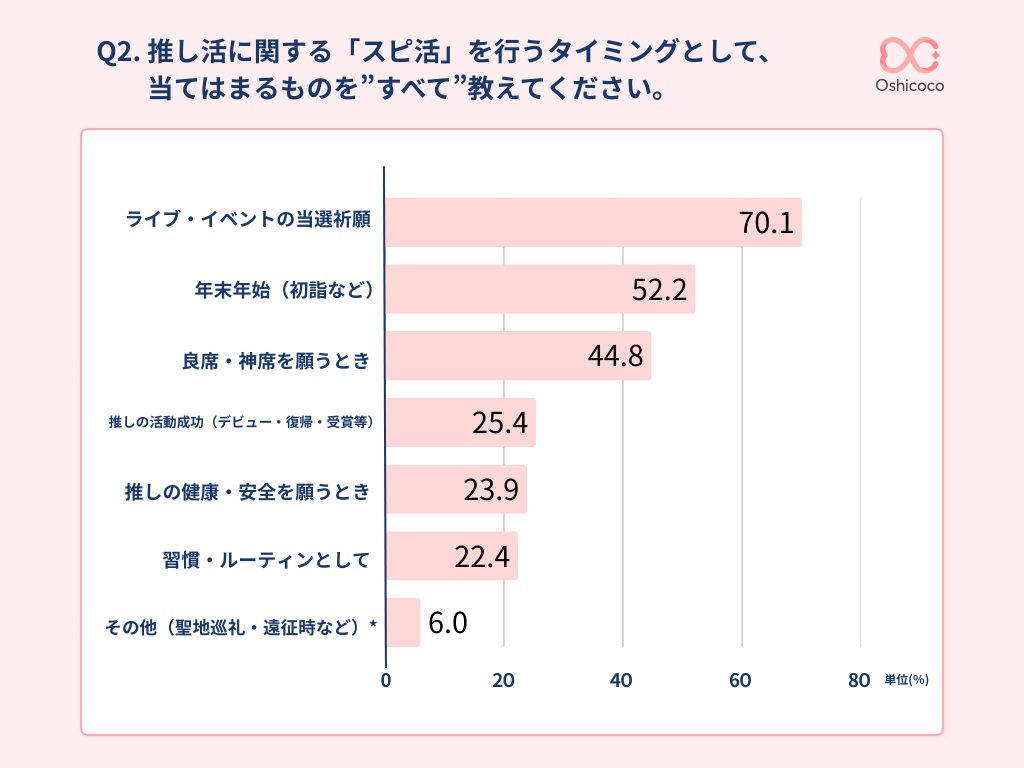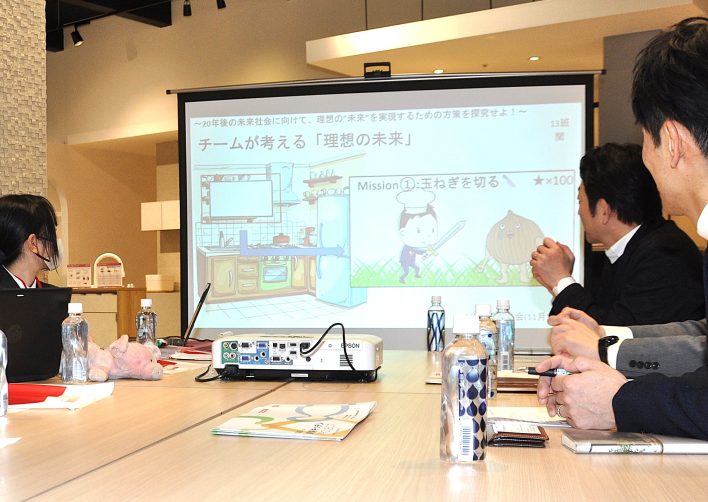決戦食レシピ 畑中三応子 食文化研究家 連載「口福の源」
戦後80年となるこの夏、関連ドラマをいくつか見たが、そこで再現される戦時中の食卓はみな〝おいしそうすぎ〟に思えた。実際はどうだったのか、戦争末期の『婦人之友』『婦人倶楽部』『主婦之友』の料理記事を読んでみた。
婦人雑誌は明治と大正時代に2回の創刊ブームがあって女性の生活や考え方に大きな影響を与えたが、戦局の悪化で大半が休刊・廃刊に追い込まれ、敗戦まで残ったのはこの3誌だけだった。1937年に日中戦争が始まってからのレシピは節米と代用食が中心になったが、44年と45年の食料不足は過酷を極め、ほとんど生きのびるためのサバイバル食と化して「決戦食」という呼び名も生まれた。
「家庭で調味料を自給しませう」(婦人之友45年5月号)は、塩の代用に海水を使ったり、野生の果実から酢を作ったりのアイデア集。現代人は1日約10グラムの塩を摂(と)っているのに対し、配給量は5人家族の場合1人当たり月に40グラムで、あまりにも少なかった。醤油(しょうゆ)は1日1人大さじ1杯強、味噌(みそ)は約20グラムの配給があったが、今と違ってほとんど醤油と味噌で味付けしたから、やはり絶対的に足りない。こうして料理からは味がなくなっていった。
「野菜不足を克服する春の野草の食べ方」(婦人倶楽部44年4月号)は、道端の野草のレシピを紹介。この頃になると最低限の栄養を確保するため、野草だけでなく、それまで捨てていた野菜の根や茎、葉、皮、種子、はては魚の骨や頭、ひれ、茶がらなどの利用が盛んに提唱された。食品ロスは限りなくゼロに近かったろう。
そのままでは食べづらい廃棄物は、消化吸収率が高く、貯蔵でき、軽くて運搬しやすいことから、乾燥させて粉末にする方法が編み出された。45年になると雑穀や大豆粉に劣化した煮干しの粉などを混ぜた「食用粉」なるものがコメの代わりに配給され、すいとんの材料になったそうだ。
「非常食と戦時栄養食の工夫と作り方」(主婦之友44年5月号)で、陸軍大佐の栄養学者・川島四郎が「食物というものは、煮たり焼いたりしなければ食べられないといふような考え方は、もうこの決戦下に通用しなくなっています」として、高野豆腐や切り干し大根、干し椎茸(しいたけ)をそのまま食べるよう勧め、「永く噛(か)みしめていると、また格別な風味」とうまいことを書いている。戦争中は軍人が婦人雑誌で料理指導をし、料理研究家も国策に沿ったレシピを考案するようになっていた。
これらはほんの一例。3誌は少しでもよりよく食べるための工夫を発信し続けたが、当時のレシピを読んでいると戦争は食文化も破壊することを痛感する。日本の食が戦前の水準に戻るには長い時間がかかった。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.34からの転載】