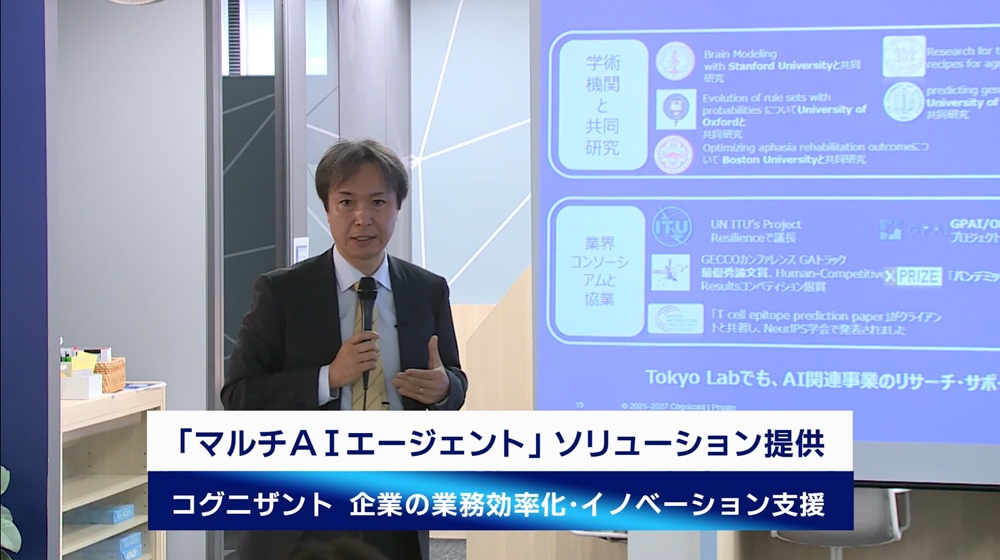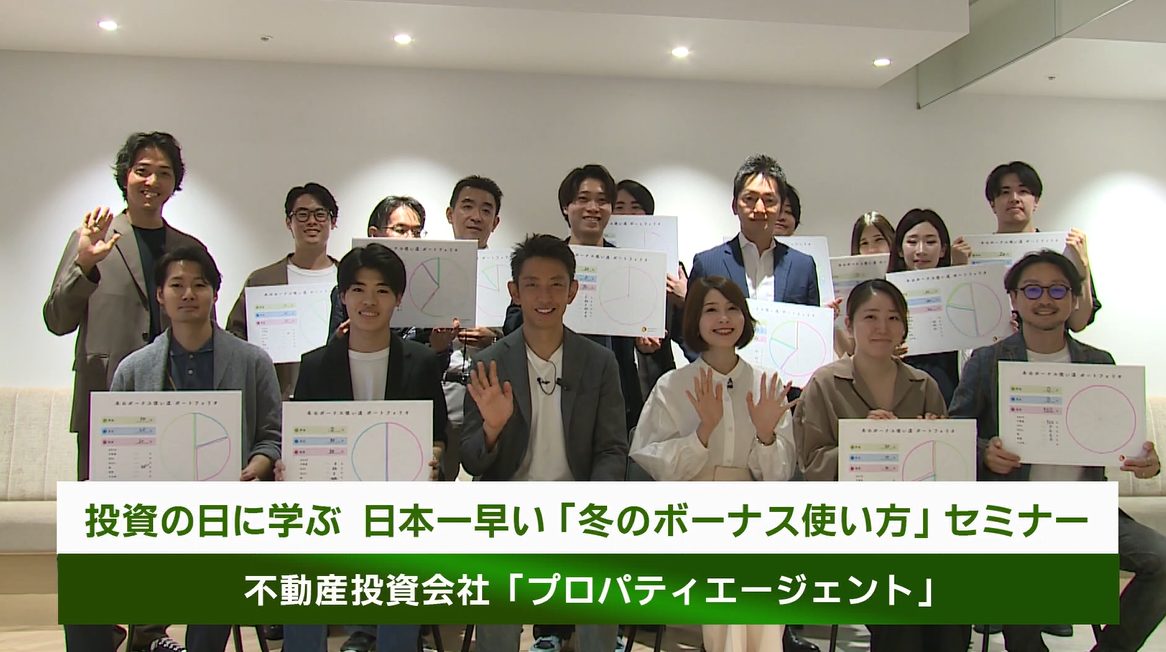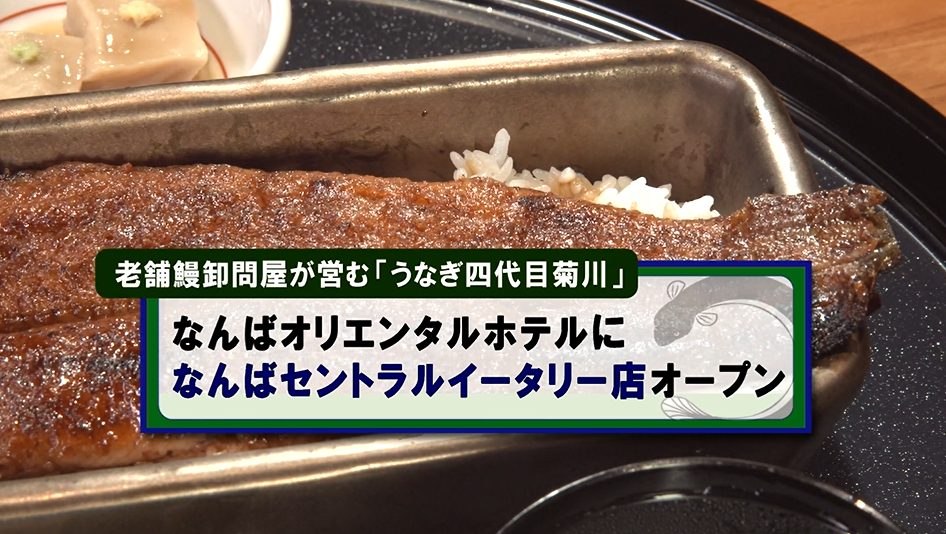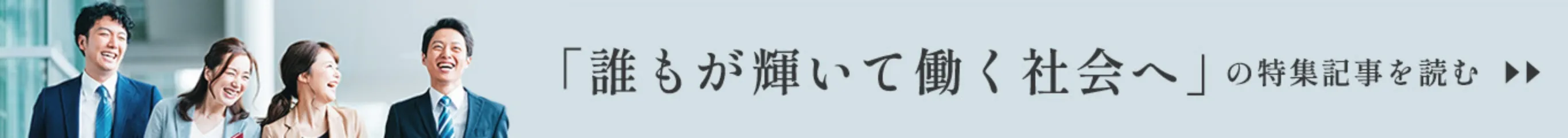アフガンで出会った恐るべき関西のおばちゃんたち 【舟越美夏✕リアルワールド】
旅の醍醐味(だいごみ)の一つは、日常の枠からはみ出た印象深い人に巡り会い、自分の小ささを感じることだ。先日、アフガニスタンで出会った日本女性2人が、そんな方々だった。
90歳の西垣敬子さん(兵庫県宝塚市在住)と78歳の中道貞子さん(京都府宇治市在住)。2人は長年、アフガンで教育分野を中心に、女性と子どもの支援活動を続けてきた。

西垣さん(左)と中道さん(右)=カブール、筆者撮影
「私たち、関西のおばちゃんよ。飴(あめ)ちゃんも持ってるし」。さらりと言うが、活動の対象地域もスタイルもそれぞれ違う、恐るべき行動力の「一匹狼(おおかみ)」たちだ。
西垣さんは、普通の主婦だったが40代で神戸大学に入学し、仏教美術史を専攻。50代半ばで英国に、82歳でイランに語学留学した。1993年、アフガニスタン大使館による写真展で衝撃を受けた。翌年に内戦下の同国に単独で入り、国内避難民キャンプを視察した。以来、孤児院への教育資材や大学の女子寮建設など多岐にわたる支援を続けた。
50回近い訪問の中で、西部の古都ヘラートの細密画に出会った。ヘラート大学細密画学科の教授と交流を深め、2021年には日本で初めて「ヘラート派細密画展」を宝塚市で開催した。細密画科の女子学生は現在「女子教育禁止」政策により自宅で勉強を続けている。西垣さんは今回、彼女たちと会い、作品を日本に持ち帰った。
中道さんは「生き物に学ぶ生物教育」をライフワークにする理科教師だ。1971年から奈良女子大学付属中等教育学校で教壇に立ち、副校長を務めていた2002年8月、女性教育支援の調査団メンバーとして首都カブールを訪れた。「先生、細胞って美しいんですね」。日本の顕微鏡をのぞいた高校生の言葉に感動した。中部バーミヤン州チャプダラ村で、私財を投じて建設した学校校舎は2005年に完成した。以来、学校運営の支援を続けている。
チャプダラ校訪問に同行させてもらった。白いスカーフ姿の女子生徒が歓迎の花束や刺繍(ししゅう)作品を抱えて並んでいる。1年生から9年生まで男女約3百人が在籍するが、7年生以上の女子66人は登校できない。中道さんは各教室を回り、教師から要望や問題点を聞き、顕微鏡を贈呈した。「しっかり勉強してね。ずっと見守っていますよ」。中道さんを見つめる少女たちの目は真剣だった。
再会の涙と発見に満ちた2週間の旅。帰国後、すぐに2人は次のプロジェクトに取り組んだ。西垣さんはヘラート派細密画展の準備に、中道さんは旅の詳細な記録をまとめ、ザンビアで開かれる女性と教育に関するセミナーでの発表準備に入った。
「参りました」と呟(つぶや)いていたら、中道さんから「大好きなアフガン女性よ」とウェブサイトのリンクが届いた。教育を届けるNGO(非政府組織)を30年前に設立し、粘り強い活動を続けてきた医師サケナ・ヤクービさんの講演だ。「俺たちにも教育と仕事の機会を」と迫る武装した若者たちを受け入れ、頼もしい味方に育てたエピソードは圧巻だった。
「教育は人を変える。愛情と思いやり、信頼と誠実さがあれば目標を達成できる」。結びの言葉で、壁を乗り越え歩き続ける西垣さんと中道さんが浮かんだ。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No. 38からの転載】

ふなこし・みか 1989年上智大学ロシア語学科卒。元共同通信社記者。アジアや旧ソ連、アフリカ、中東などを舞台に、紛争の犠牲者のほか、加害者や傍観者にも焦点を当てた記事を書いている。