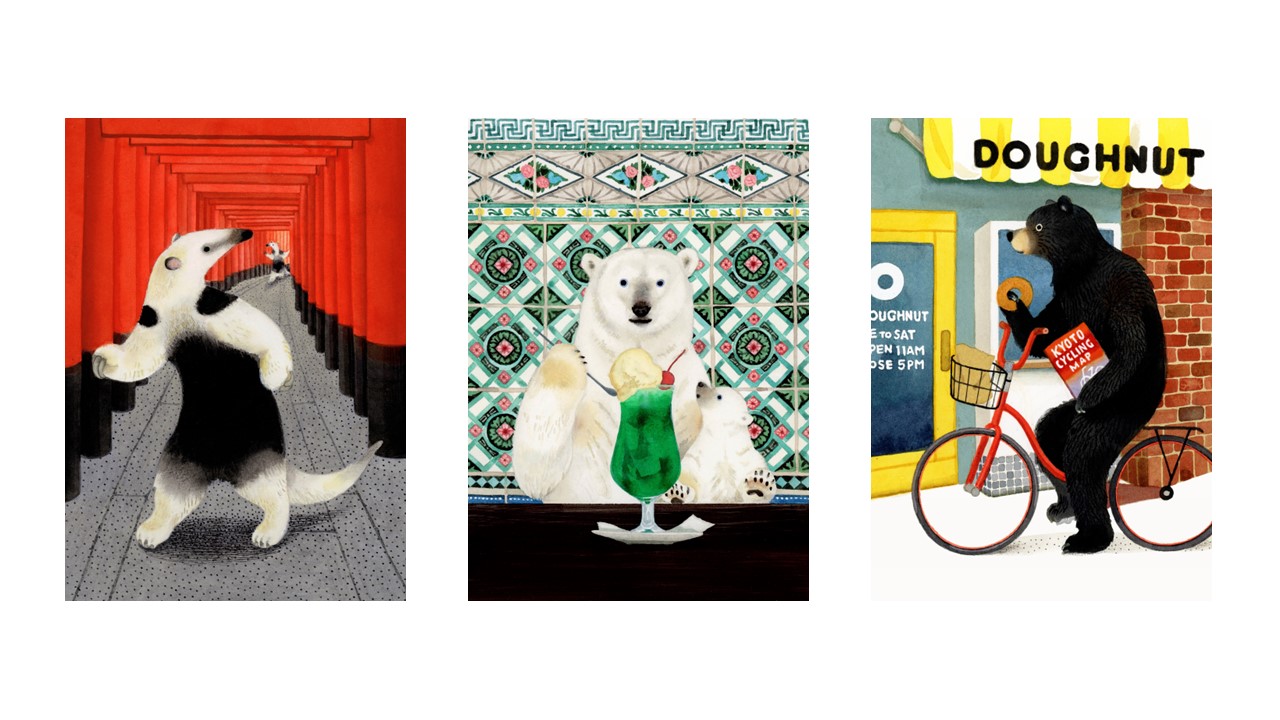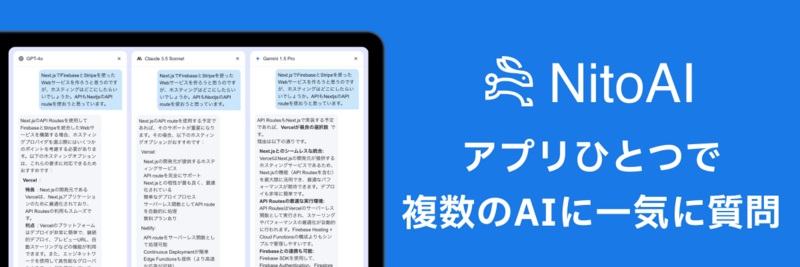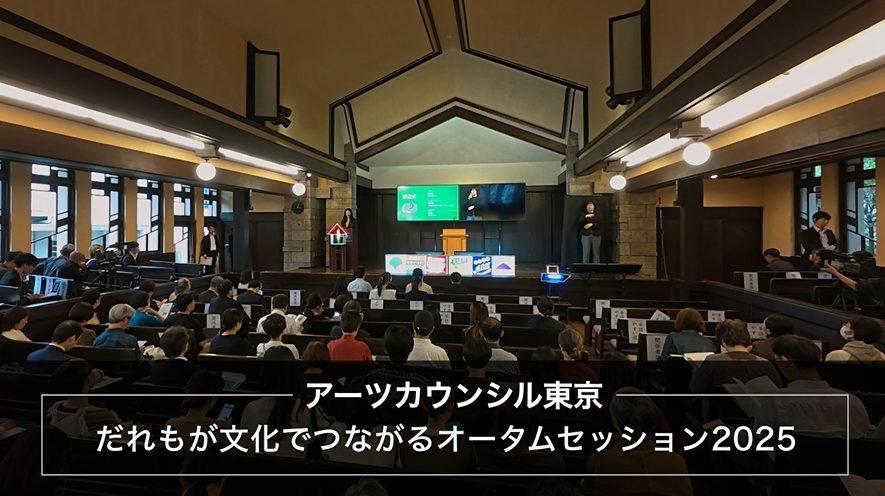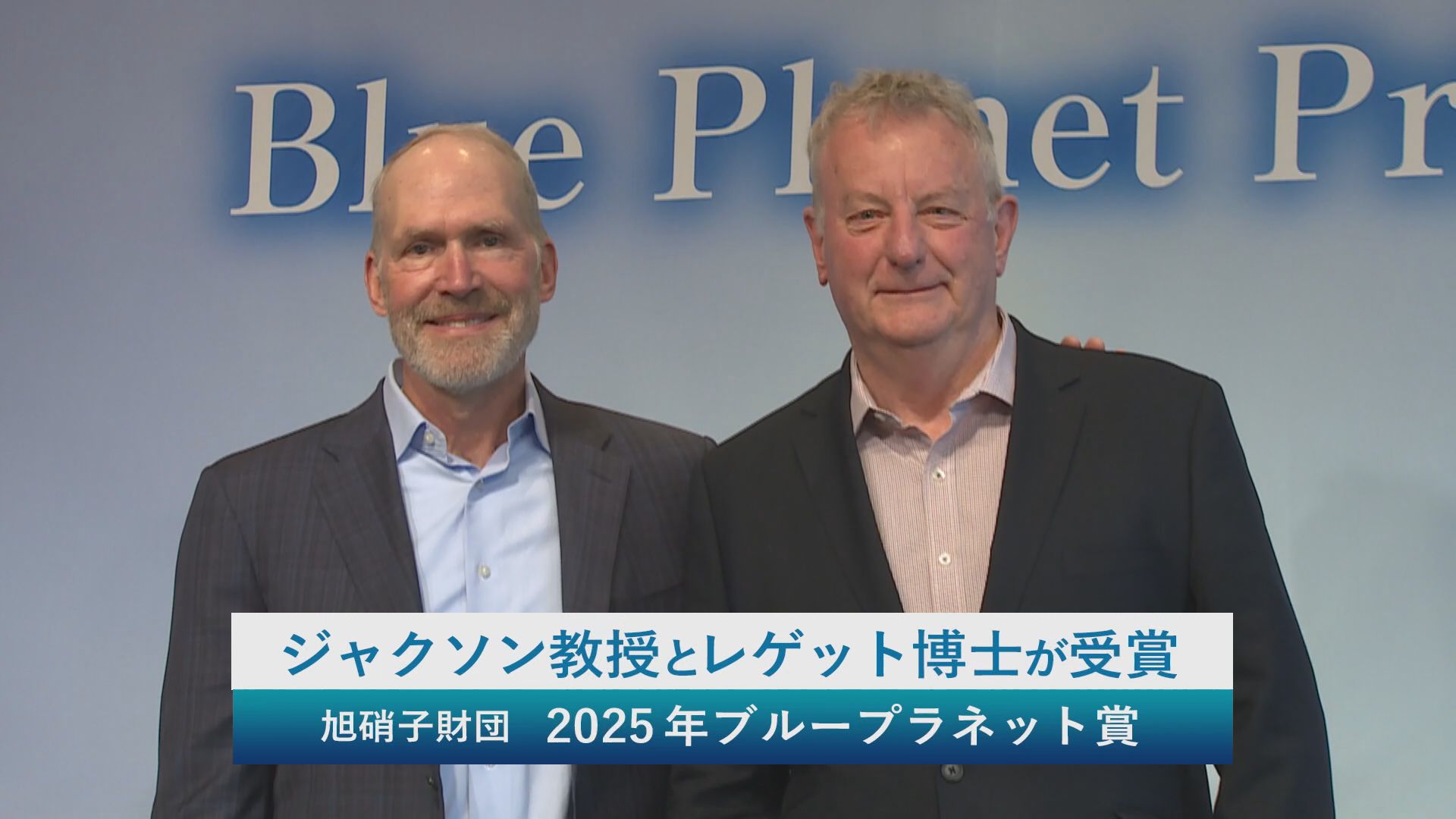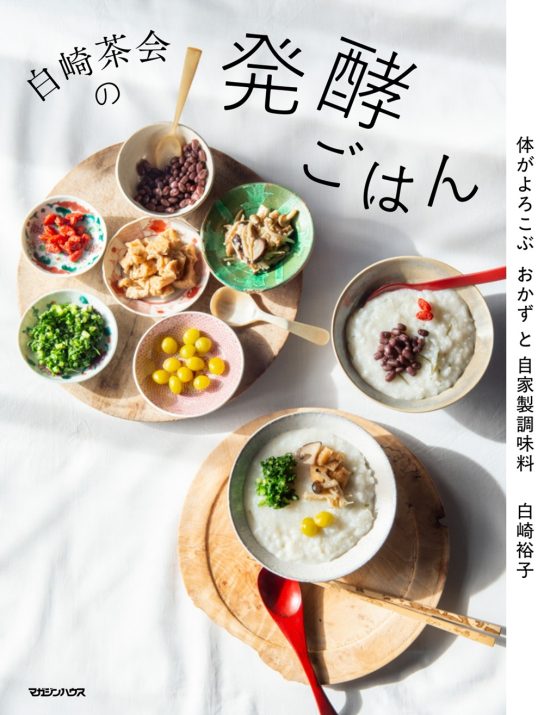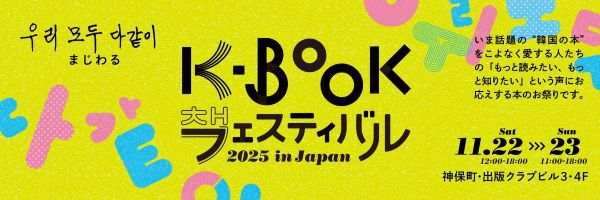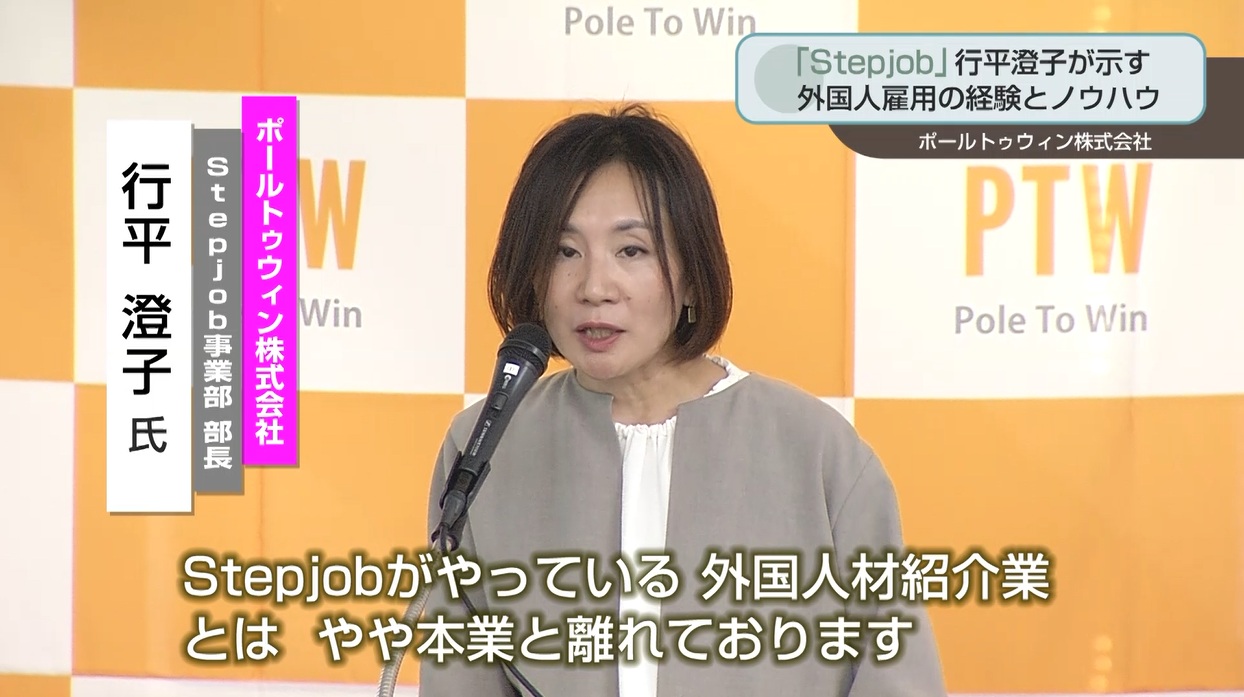「特集」 攻防「AI対AI」 激変する採用現場 公平性への懸念も 「人間中心」は不変

平 和博
桜美林大学教授
就職戦線が、大きく変化している。〝台風の目〟は、生成AI(人工知能)の台頭だ。応募者たちはエントリーシート(ES)の作成や推敲(すいこう)にAIを使うようになり、企業側もAI採用選考システムで迎え撃つ。「AI対AI」の攻防が繰り広げられている。AIの浸透は、採用ばかりではない。人事評価や業務の代替まで、労働市場全体に大きなインパクトを及ぼす。そしてAI利用には、根深い懸念が影を落とす。
2800件超の自動応募
「朝食を終えるまでに、私は全米の12の異なる業種に応募していた」。米テクノロジーニュースサイト「404メディア」のライター、ジェイソン・ケーブラー氏は、10月10日付の記事で、そんな体験を紹介した。
ケーブラー氏が使ったのは、オープンソースで公開されているソフト「自動求人応募AIホーク」だ。生成AIと連動させて、ビジネス用ソーシャルメディア「リンクトイン」に掲載された求人に、次々と自動で応募をしてくれるソフトだという。記事の中では「2843件の応募をした」という他のユーザーの声も紹介している。
生成AIは、人間のような自然な文章を、自動的に、瞬時に、膨大に作り出せる。それを求人応募に最適化させたのが「AIホーク」だ。「2843件」という数字は、生成AIによる求人応募の洪水が起きていることを示す。
ソフト開発の背景には、企業側の採用選考自動化の広がりがあるという。企業側もまた、AIを使っている。求職者のAIが自動応募をし、企業側のAIが自動選考をする。株式の自動取引のような風景が、労働市場に広がる。
インターネットの普及とともに1990年代から企業のオンライン採用が広がった。AIの台頭はその規模の拡大と自動化を後押しした。米国の雇用機会均等委員会(EEOC)委員長、シャーロット・バロウズ氏は2023年1月の公聴会で、雇用主の約83%、世界のトップ企業「フォーチュン500」の99%が、採用プロセスで何らかの自動化ツールを使用している、との推計を示した。
生成AIにはオープンAIの「チャットGPT」やマイクロソフトの「コパイロット」、グーグルの「ジェミニ」、アンスロピックの「クロード」などがある。いずれも基本機能は無料で利用できる。
それらの生成AIに「就活用のESを作成して」と命令し、自分のプロフィールなどの基本情報を貼り付けて、「学生時代に力を入れたこと」「自己PR」「志望動機」などを項目別に整理するよう条件付けをすると、数秒で文案が画面に示される。
あらかじめ用意された設問に答えるだけで、ESの自動作成や添削をするサービスも、ネット上にある。

チャットGPTの画面
3人に1人が就活に利用
日本の就職戦線にも、生成AIは着実に浸透している。就職情報のマイナビが6月に公表した「2025年卒大学生活動実態調査(5月)」によると、「就職活動の場面で生成AIを使ったことがある」との回答はほぼ3人に1人(37・2%)。前年の同様の設問では18・4%だった。
用途別(複数回答)では、「ESの推敲」が最も多く56・6%、「ESの作成」41・7%、「自己分析」(28・8%)、「業界研究」(25・2%)と続いた。生成AIを面接官に見立てた「面接対策」も17・8%に上っている。
生成AI利用の理由は「自身のアウトプットを改善・改良」が57・3%、次いで「作業時間の短縮」が53・9%だった。
企業はどうか。ソフトバンクは17年から、新卒採用選考のES評価に、IBMのAI「ワトソン」を導入。評価にかかる時間を75%削減したという。また、20年からは、動画面接の評価にもAIを導入している。
ただ、マイナビが7月に公開した「2025年卒企業新卒採用活動調査」によると、日本企業の採用におけるAI利用は一部にとどまっている。「AIを活用した採用活動の補助ツールの利用」は、「導入していない」が92・6%に上った。利用ケースでは「適性検査の評価検討」が3・8%で最も多く、「募集要項の内容検討」が2・5%で、「ESの評価検討」(1・2%)、「面接内容の評価検討」(1・1%)と続いた。
また、学生が就職活動で生成AIを利用することについては、「積極的に活用してほしい」(5・0%)、「使い方を慎重に検討した上で活用してほしい」(52・7%)と肯定的な回答が目立つ一方、「利用しない方がよい」も19・6%に上った。
日本の生成AI利用は、AI先進国の米国や中国に比べて低調だ。総務省の24年版情報通信白書の個人向けアンケートでは、生成AIの「利用経験あり」との回答は中国が56・3%、米国が46・3%、英国39・8%、ドイツ34・6%に対して、日本は9・1%だった。
企業向けアンケートでは、「業務で使用中」との回答が、米国で84・7%、中国が84・4%、ドイツが72・7%だったのに対して、日本は46・8%だった。
女性差別を「学習」
アマゾンが進めていたAI人材採用システムの開発が、「女性差別」を解消できずに中止となった。ロイター通信は18年にそんなニュースを報じた。
アマゾンは14年からAIで履歴書を審査するためのシステム開発を始めた。だがソフトウエア開発などの技術職で、女性の評価が低くなる不具合が発覚。原因は学習データだった。
AIは過去の膨大なデータを学習し、そこから特徴を見つけてモデル化する。このモデルに基づいて新たに入力されたデータの評価や予測などの作業を行う。学習データにバイアス(差別・偏見)が含まれていれば、出力結果にもバイアスが入り込む。しかも単に反復するだけでなく、それを増幅させてしまうリスクもある。
アマゾンは過去10年にわたる履歴書をAIに学習させた。その大半が男性からのもので、採用された技術職も大半が男性だった。するとAIは、採用に適した人材は「男性」だと判断し、履歴書に「女性」という言葉があると評価を下げていた。
プロファイリングに懸念
AI人材採用システムに期待されるのは作業の効率化だ。だがそれ以上に、正確性、公平性、透明性が要求される。
日本において、採用へのAI活用に影を落とすのが、19年に明らかになった「リクナビ事件」だ。
就職情報サイト「リクナビ」を運営していたリクルートキャリアが、就活生の同意を得ずに、AIを使って内定辞退率を算出し、企業に提供していたことが問題となった。個人情報保護委員会は、個人情報保護法違反があったとして、同社に2度にわたる是正勧告を実施。厚生労働省も職業安定法違反があったとして行政指導を行っている。
個人情報とAIの不用意な利用が、混乱と不信を引き起こした事件として記憶される。
このようなAIを使った個人情報の分析「プロファイリング」は、国際的にも懸念が指摘される。
欧州連合(EU)で今年5月に成立した世界初の包括的な規制法「AI法」では、採用選考、人事評価のAIシステムは「ハイリスクAI」に分類され、「リスク管理」「学習データの品質確保」「透明性確保」「正確性確保」「人間による監視」などが義務付けられている。
米国でもEEOCが23年、採用・昇進へのAI利用に関するガイダンス(指針)を発表。ニューヨーク州では昨年7月、採用や昇進評価にAIを使用する場合、通知や差別防止のための監査を義務付ける州法を施行した。コロラド州、イリノイ州でも同様の規制を含む州法が成立している。イリノイ、メリーランド両州にはAI動画面接を規制する州法もある。
さらに米人権団体「電子フロンティア財団(EFF)」が19年、AI動画面接ツールを提供する「ハイアービュー」について、正確性やバイアスの問題を指摘し、連邦取引委員会(FTC)に申し立てを行った。同社は21年、ツールから顔画像の分析機能を削除すると発表した。同社を巡っては22年にイリノイ州でも集団訴訟が起こされている。
22年にはEEOCが、オンライン学習サービスの「iチューターグループ」のAI採用ソフトが高齢の求職者を違法に排除したとしてニューヨークの連邦地裁に提訴。翌年、求職者らに計36万5千ドル(1ドル150円換算で約5500万円)を支払うことで和解した。
正当な評価どう保障
採用選考だけではない。日本IBMは19年、同社のAI「ワトソン」を、賃金査定に導入することを発表。これに対して同社労組は20年、査定項目の開示などを求めて東京都労働委員会に申し立てを行った。この労使紛争は今年8月、査定項目などを会社側が開示する、との内容で和解した。
AIは、労働市場全体にもインパクトを及ぼす。オープンAIは23年3月、ペンシルベニア大学との共同研究で、生成AIの労働市場への影響調査を公表している。調査では、米国の約80%の労働者は、少なくとも仕事の10%に影響を受け、19%の労働者は影響の割合が仕事の50%に上る可能性があるとした。AIが人間の仕事を置き換えていくということだ。
だが、AI時代にあっても、雇用と労働の中心は人間だ。求められているのは、すべての人が差別や偏見なく正当に評価され、やりがいのある仕事に取り組める社会だ。それをどう保障していくのかが問われている。
桜美林大学教授 平 和博(たいら・かずひろ) 1962年生まれ。早稲田大学卒。86年、朝日新聞社入社。社会部、シリコンバレー駐在、編集委員、IT専門記者などを担当。2019年4月から現職。日本ファクトチェックセンター運営委員。科学技術振興機構 社会技術研究開発センタープログラムアドバイザー。著書に「チャットGPT vs. 人類」(文春新書)、「悪のAI論」「信じてはいけない」(いずれも朝日新書)など。
(Kyodo Weekly 2024年11月4日号より転載)