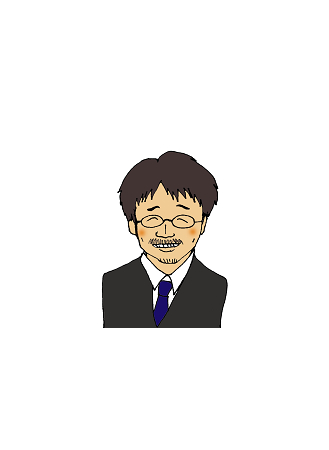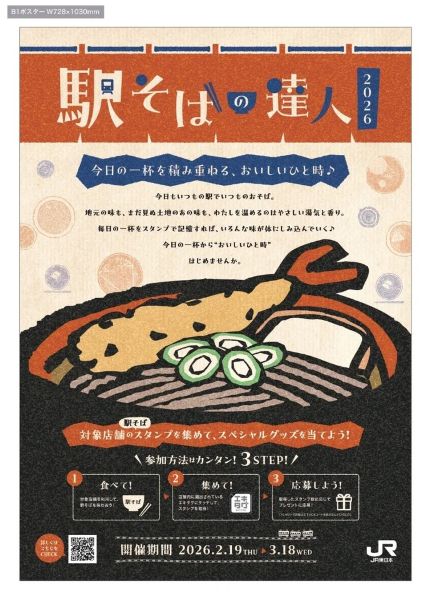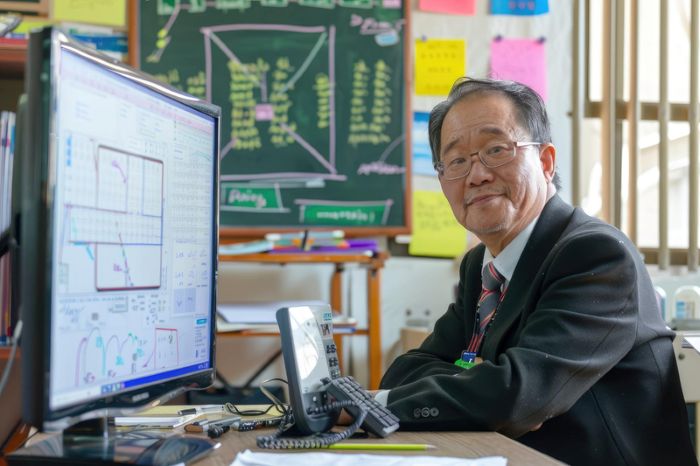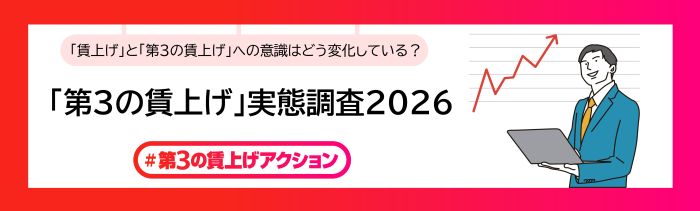「語り継ぐ」ことと「理想の防災教育」について
~防災を自分事として考えるようにする3つのアドバイス~
2025年5月8日
尾西食品株式会社
報道関係各位
~防災を自分事として考えるようにする3つのアドバイス~
「語り継ぐ」ことと「理想の防災教育」について
防災学習アドバイザー・コラボレーター 諏訪清二先生
尾西食品株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長 市川伸介 ※以下、尾西食品)は、防災食・備蓄のリーディングカンパニーとして、 ”アルファ米”をはじめとする非常食を製造・販売。 専門家のアドバイス、被災者の声を通して日常の防災意識を高める活動を進め、2021 年3月より、公式サイトにて防災コラムの発信をしております。今回は、兵庫県立大学(大学院減災復興政策研究科)客員教授で兵庫県立舞子高校環境防災科の初代科長を務められた諏訪清二先生に震災を「語り継ぐ」ことと「理想の防災教育」について伺いました。
〜防災教育の始まり〜
――全国初の専門学科 兵庫県立舞子高校環境防災科立ち上げの経緯背景について
防災科ができた背景としては大きく2つの要因がありました。1つは阪神・淡路大震災の後、従来型の避難訓練だけでは命を守れないと県も意識し、「命の大切さ」や「助け合い」などを学ぶ新たな防災教育を始めたこと。もう1つは高校の多様化路線で、行ける学校ではなく行きたい学校に行く、行きたい学校を作るという流れです。スポーツや音楽といった新しい学科が高校にできた同じ枠組みと新たな防災教育という観点から、防災環境科の設立に繋がりました。
2002年の4月に開設されましたが、準備期間も含めて決して順調ではありませんでした。私も含め所詮防災に関しては素人ですから、外部講師、つまり「本物と出会わせる授業」を意識しました。「震災体験した人や救援活動をした人(消防・警察・自衛隊)の話を聞く」「大学の先生とフィールドワークに行き、実際に見る」ということです。
また、グループ討議やプレゼンテーションをさせるといった実地訓練(アクティブラーニング)を多く取り入れました。何も無い状態から始め、正直手探り状態でしたが、結果としては「主体的・対話的で深い学び」ができていたと思っています。
――印象に残っている授業
授業に震災当時西市民病院のレスキュー隊長をしていた神戸消防の方が来てくれた時です。ご自身が救援に当たった際の体験を語りながら、「一人だけ助けられなかったことが悔しい」と泣き出したのです。実は後から分かったことなのですが、生徒の中に、お母さんをその西市民病院で亡くした女子生徒がいたのでした。その生徒は中学校の先生に勧められて舞子高校に入学したものの、母を殺した地震の話ばかり聞かされるのが辛く退学を考えていた矢先に、母のことを涙まで流して一生懸命助けてくれようとしていた人がいたことを知り、防災の勉強を続けようと思ったとのことです。このように、誰もが本気で相手をしてくれ、本物の授業ができて、私自身もとても勉強になりました。
〜語り継ぐことの大切さ〜
――子どもたちが語り継ぐことの意味
舞子高校には「語り継ぐ」というタイトルの体験記があります。これは、小学校2年生で震災を体験した子どもが高校を卒業する際に、自分の体験を書き残したいと言ったのがきっかけで始まりました。今でも3年生は卒業時に災害体験を書き記す活動が続いています。
「災害の記憶は30年限界説」と発信しているマスコミも多くいますが、それは直接体験した人が社会の中に過半数を切って、語れる人が日増しに減っていき、伝承されていかないことを限界と言いたいのでしょう。阪神・淡路大震災当時の語り部は50~60代が中心でしたので、30年経てばその人たちは段々と語ることができなくなります。その頃の大人は子どもたちに語らせなかったし、子どもたちも語ってはいけないと遠慮していました。でも今の子どもたちが語れば、これから30~40年も語り続けることができるのです。「人から聞いた話を分かったように語っては駄目だ」という大人がいるのも事実です。もちろん自分の体験を語るのは体験者しかできません。
でも「語り継ぐ」を「語り」と「継ぐ」に分けて考えれば、『誰かの震災体験の「語り」を聞いて、それを他の人に「継ぐ」』ということであれば、誰にでもできると思っています。「語り継ぐ」というのは、自分の体験でも、誰かの体験でも良いのです。それを語り、自分の感想を付け加えて継いでいくことなのです。
実際、東日本大震災の被災地では震災について語っている子どもたちは、阪神・淡路大震災の時より多いのです。それは語る子どもたちを支えている大人の存在が大きいと思います。人数自体は、まだまだ少ないですが、それでも神戸とは断然多いのです。舞子高校で行っている「語り継ぐ」取組みはそうした思いから始め、今でも続いているのです。
――「語り継ぐ」意味とは
私は2つの意味があると思っています。1つは「社会的な意味を持つ語り」です。
「多くの人が下敷きになって亡くなったから耐震が必要だ」とか、「水が出なくて困ったからお風呂の水は溜めておく」といった話は、それを聞いて実行したら社会の防災力は上がります。このような語りは「社会的な意味」を持ちます。
ただこれだけでは人の心には響かないのです。知識や教訓だけの一方的な語りは伝わらないし、結果として「防災嫌い」を作ってしまっているのではないでしょうか。いくら知識だけ詰め込んでも行動に移さなければ何の役にも立たないのです。
行動に移すために大切なのが、もう1つの「語り継ぐ」意味である「個人的な意味を持つ語り」だと思っています。
「個人的な意味を持つ語り」は往々にして内容が整理されていないものです。何故かと言うと、今日語ったことは「あれは実は本音じゃなかった」と思って明日には作り変える。語っては変わり、また語る。その繰り返しなのです。語り部のその戸惑いが、聞き手の防災と向き合う原動力になるのだと思っています。
大切なことは災害時の良い部分だけでなく、悪い部分もしっかり語り継ぐことだと思うのです。例えば阪神・淡路大震災ではたくさんの服を送ってもらっているのですが、8割が使い物にならなかった。東日本でも状況は変わっていません。しかしその事実は善意という言葉に隠れてしまい、表に出てこないのです。でもこの話を聞いた子どもたちは古着でなく、新しい服を送ろうと思うだろうし、もっと他に必要なものは何かを考えるかもしれません。
「社会的な意味を持つ語り」も、「個人的な意味を持つ語り」もどちらも大切です。また、「人のための語り」も「自分のため語り」も大切です。その内容が「防災教育的な語り」であって良いし、「心のケア的な語り」であっても良いのです。「強さと弱さ」「優しさと醜さ」「成功も失敗も」といったもの全ての事柄を聞く側の発達年齢に応じながら、しっかりと伝えていくことが「語り継ぐ」際には大事なのです。
〜防災教育で大切にしたいこと〜
――防災を如何に「自分事として考えられるようにする」のか。3つの大切なポイント
防災教育では体験者の声を聞くだけで良いのです。 教育となると先生が「今日はこんな話を聞きました、だからこうしましょう」などと言ってしまうのですか、そんなことは言わなくていいのです。
よく防災は「自分事として考えることが大事だ」と言われていますが、「自分事として考える」とは果たしてどういうことでしょうか。実は言っている人達も良く分かっていない。その方法論がないことが多いのです。「自分事として考えなさい」と言ってそうしてくれたら、これ程楽な教育はありません。価値の存在だけを伝えて「自分事として考えなさい」という授業は無意味で、方法論を示して授業をすべきだと思っています。
私が考える「自分事として考えさせる」方法は3つあります。
1つ目は「結論だけでなくプロセスを教える」ことです。防災教育では結論を教えることが多く、「助け合いは大切」とか、「人に喜ばれる支援をしましょう」とかまとめるのではなく、現実を受け止められる範囲ギリギリかちょっと超えたものを子どもたちに預けて、あとは子どもたちに自分で考えさせるのです。例えば「震災の時に下敷きになって亡くなった人がいる」と伝えれば、「耐震の家にしましょう」とまで言わずとも、子どもたちはプロセスや事実を聞いたら、自分で考えられるのです。
2つ目は「同世代からの語りを伝える」ことです。例えば当時小学生だった人が自分の体験を今の小学生に、「あれから自分がどうやって生きてきたか」と語ったら伝わりやすいのです。高校生には当時の高校生が、消防学校の若手には当時の消防活動にあたった人が語れば自分事にしやすいのだと思います。
3つ目は「夢と防災を結びつける」ことです。以前熊本の益城町の小学校で5年生の女の子が将来の夢をお花屋さんになることだと話してくれたので、「それって地震の時に役立つの?」と聞くと返事に困ってしまいました。でも、その子は長い避難所生活を体験していて、「避難所では何かするとすぐ怒られるのに、周りはうるさいし」、「殺風景で臭いがひどかった」と話をしてくれていたので「もし将来、避難所にあなたが育てた花を持って行ったらどうですか?」と問いかけたらニコッと笑って「それならできます」と答えてくれたのです。これが、自分の夢と防災が繋がるということだと思います。
防災は社会そのものであり、夢も社会と関係します。同じ社会を通して防災と夢は繋がっているのです。大人たちの価値を押し付けるのではなく、どうしたら子どもたちが自分事にしやすいかを考えてあげるのが防災教育においては大切だと思っています。
――非常食について
災害時ほど美味しいものを食べたいものですから、一番良いのは避難所に行かない生活をすることです。地震で壊れない家に食料や水があるという状態が良いと思います。避難所で行政が配る食事は当てにしない方が良いです。
「非常食はこうあるべきだ」ではなく、「日常食と同じものが非常食」と言えるような暮らし方をすれば良いのです。避難が必要な人は、できるだけ美味しい非常食を持出袋に用意しましょう。できれば毎日、非常持出袋から出しても食べられるような美味しいものを入れておきたいものです。災害時こそ美味しいものが食べられるのが一番良いし、美味しいものが食べられないと、やはり元気が出ないですよね。
――理想の防災教育とは
理想は学校の教科にすることだと思います。防災を勉強した子は比較的行動に繋がります。例えば防災の授業の前後にアンケートをすると、学ぶ前に比べて行動の部分は全部上がります。教えるとやるし、教えないとやらない。だから学ぶ場は作るべきだと思っています。知識を持っていても行動に移せるかどうかは、人間力にかかっています。災害対策のハード面は目に見えて解かりやすいですが、人間が生き延びるためには行動するというソフト面もとても大事で、防災教育は社会の防災力を高めるうえで確かな方法と言えるのではないでしょうか。
WEBはこちら https://www.onisifoods.co.jp/manage/article_edit.php?no=27
■兵庫県立舞子高等学校
語り継ぐ https://www.hyogo-c.ed.jp/~maiko-hs/kanbo_2024.html
https://www.instagram.com/kataritugu_kanbo/
■尾西食品株式会社
・事業内容:長期保存食の製造と販売
・所 在 地:〒108-0073東京都三田3-4-2いちご聖坂ビル3階
・URL:https://www.onisifoods.co.jp/
・お問い合わせ:https://www.onisifoods.co.jp/inquiry/
編集部からのお知らせ
新着情報
あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター