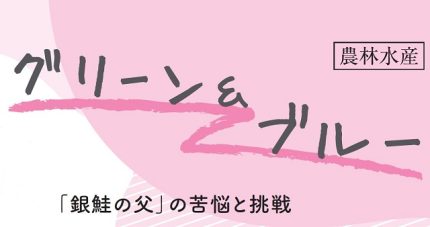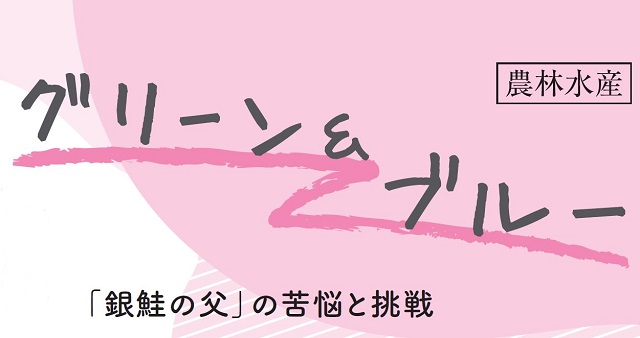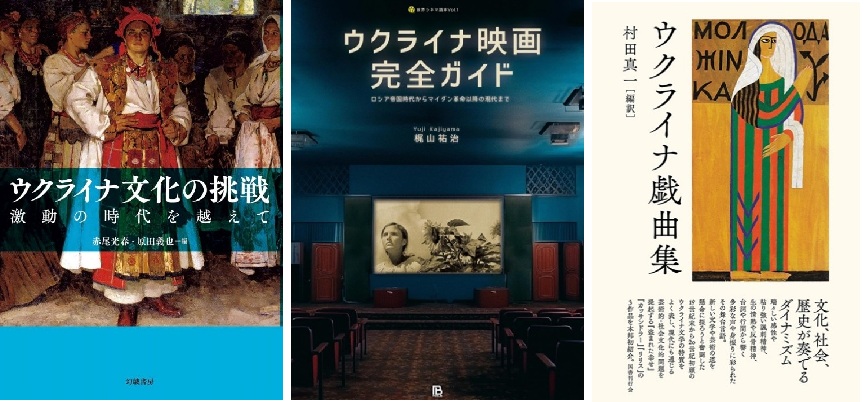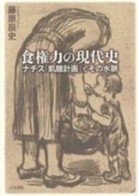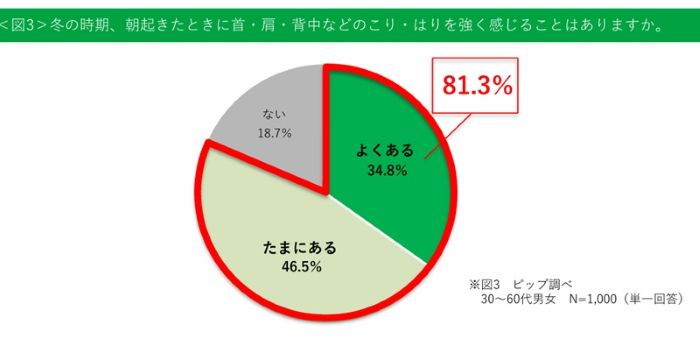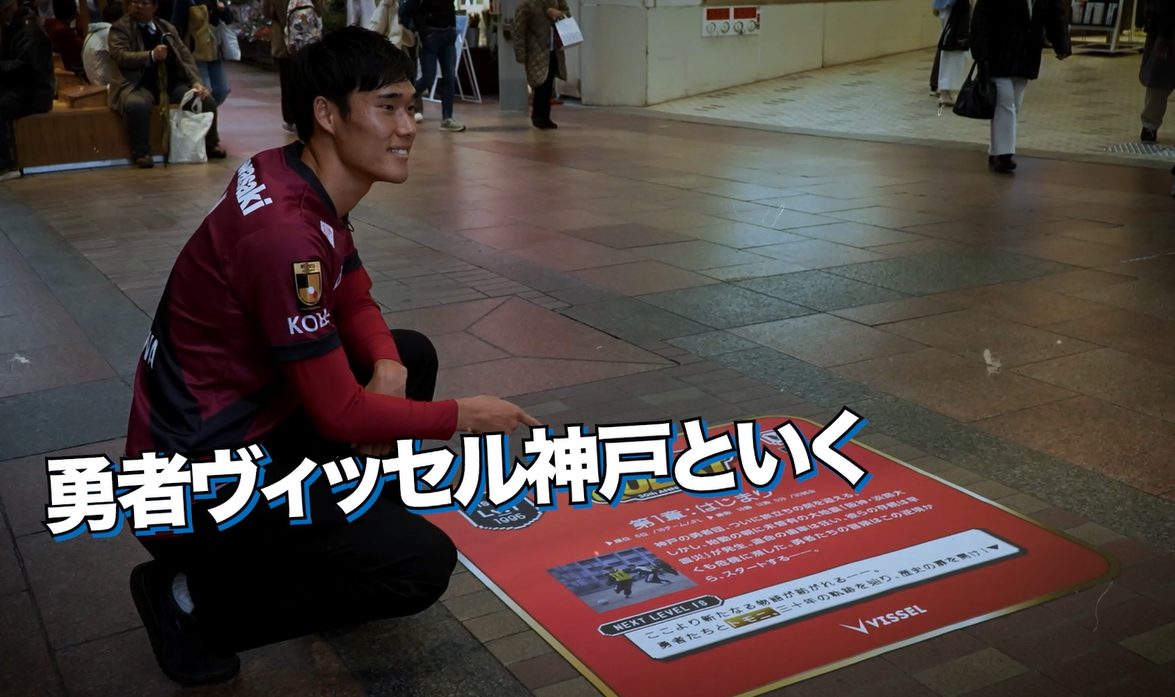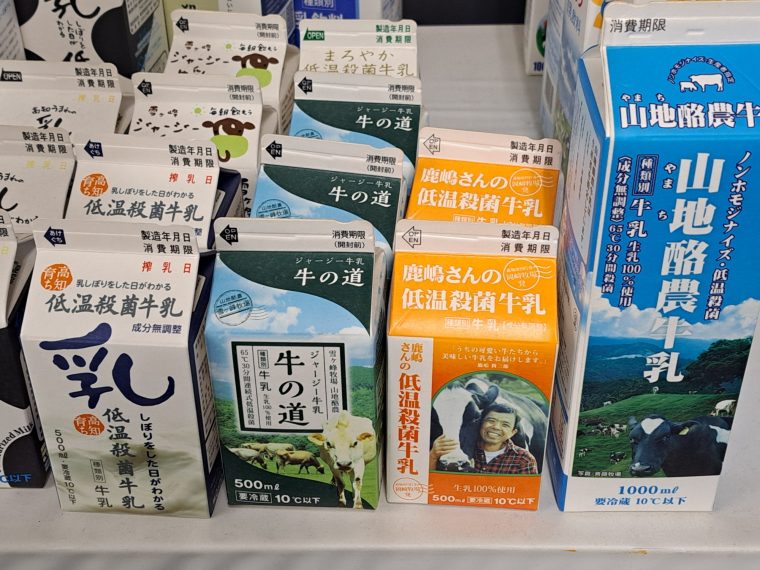「銀鮭の父」の苦悩と挑戦 中川めぐみ ウオー代表取締役 連載「グリーン&ブルー」
日本の食卓に欠かせない食材、鮭。全国各地のスーパーで当たり前のように年中販売されていますが、実は安定して食べられるようになったのは、ここ30年ほどなのをご存じですか? その背景には「銀鮭の父」の苦悩と挑戦の日々がありました。
舞台は宮城県。成長に3〜5年かかり、秋・冬に収穫される天然の“秋鮭”が一般的だった昭和50(1975)年ごろに、わずか6〜8カ月で稚魚から成魚に成長し、春・夏に収穫できる“銀鮭”の試験養殖が、県北部の志津川町(現・南三陸町)で行われていました。
その噂(うわさ)を聞き付けて銀鮭の養殖・安定供給を事業化したいと考えたのが、宮城県・女川町の漁師である鈴木欣一郎さん。後に「銀鮭の父」と呼ばれる人物です。
秋鮭に比べて圧倒的な成長スピードを誇る銀鮭の養殖事業は、業界でもさぞ歓迎されたかと思いましたが、事実は真逆だったそう。
まず試験場でも技術が完成していなかった銀鮭養殖を、いきなり事業として始めようとする鈴木さんに、試験場担当者たちの風当たりは強く、3度足を運んでもノウハウを教えてもらうことはできなかったと言います。
諦められない鈴木さんは試験場へ通い、技術を目で学んだそう。そこから稚魚やエサの開発に取り組み、本格的に養殖をスタートするのに約2年を費やしました。
「これでやっと養殖事業が始められる」。そう思った鈴木さんですが、次に待ち受けていた試練は、漁協や周囲の漁師たちからの大反対でした。
当時の宮城県は牡蠣(かき)やワカメの漁場が中心。銀鮭のエサやフンが他の魚介類に与える悪影響を懸念し、周囲の協力が得られないどころか、漁協を通しての販売も受け入れてもらえませんでした。
しかし、ここでも鈴木さんは諦めません。「漁協が売ってくれないなら、自分で直接売ってみせる」と、水揚げした銀鮭を片っ端から箱に詰め、市場へ出荷したのです。それまで春や夏に鮭が入ることがなかったので、市場の仲買い人たちはびっくり。東京・築地で驚くほどの高値が付いたという。
そんな状況を見て、女川町の漁師たちも徐々にまねをするように。鈴木さんの親戚から始まり、大手の水産業者までが目をつけ、今では県内だけで約60社が銀鮭の養殖を行っているそうです。
こうして養殖された銀鮭は全国へ広まり、今ではお店でも家庭でも、いつでも美味(おい)しい鮭が年中食べられるように。鈴木さんはそんな世の中をつくり出した、まさに「銀鮭の父」と言えるでしょう。
この話を聞かせてくださったのは、「銀鮭の父」のお孫さん。彼もまた祖父に似たのか、ITを活用したスマート漁業や海外輸出、資源管理にもいち早く取り組み、苦悩しながらも着実に成果をあげています。
「銀鮭の父」と、その孫。世代を超えた挑戦が私たちの食卓を彩ってくださる事実に、感謝しかありません。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.30からの転載】