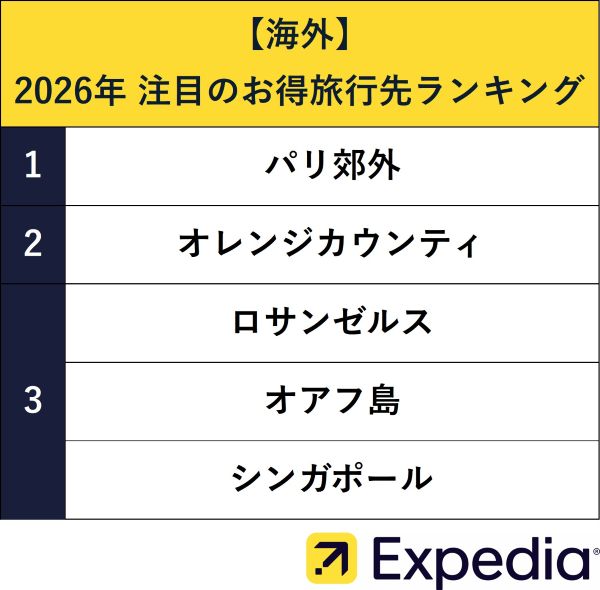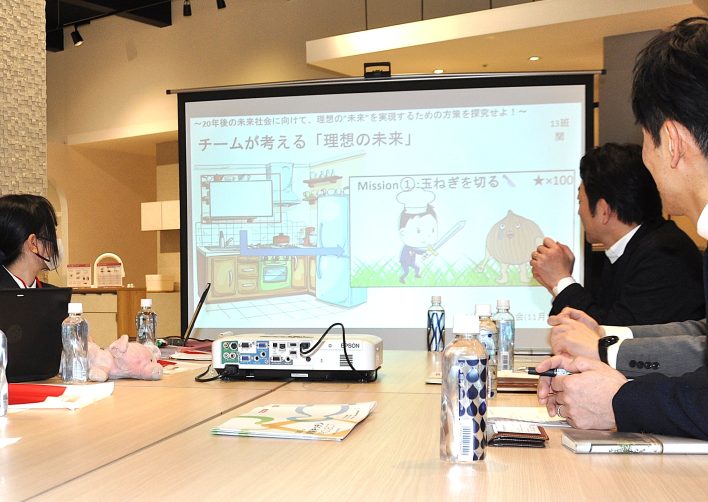「持続的な管理」を利用の条件に 赤堀楠雄 林材ライター 連載「グリーン&ブルー」
最近、ナラやタモ、センといった国産広葉樹の需要が増加している。背景には世界的に良質な資源が減少していることに加え、円安で外国産広葉樹の輸入コストが上昇していることがある。
広葉樹の主なユーザーは製紙業界と家具・木工業界である。このうちの家具・木工業界が国産広葉樹に熱い視線を注いでいる。
国内の広葉樹資源は量がまとまりにくく、小規模な木工房では以前から使われていたが、大手家具メーカーでは外国産材を使うのが主流だった。ところが、海外からの調達が難しくなる中、国産広葉樹にシフトする動きが規模の大小を問わず急速に広まっている。さらにウイスキー樽(たる)の需要も急増していて、樽材になるミズナラの価格が上昇し続けている。
こうした需要サイドの動きに対し、林業界では歓迎するムードもあるものの、急増する需要に対して資源の持続的な管理が追いつかず、森が劣化することを心配する声も上がっている。
7月5、6日に北海道大学の雨龍研究林(幌加内町)で行われた白樺(しらかば)プロジェクトの森林ツアーに参加した。同プロジェクトは2019年にスタート。従来、あまり使われてこなかった白樺に注目し、幹だけではなく樹皮や枝葉、樹液も含めすべて使い切ることを目指している。「ずっと使える」ようにと、資源の育成にも力を入れている。
ツアーでは、ササ地が多く、地表を覆うササにさえぎられて種が発芽しづらい北海道で森がどうやってつくられるかを学んだ。
「倒木更新」とは、寿命が尽き、あるいは落雷や風害などの天災で倒れた木の上に場所を得た種が発芽し、次世代の木が育つことを言う。倒木がササを抑え込む効果で新たな命が育まれる。ササ地を人為的に掻(か)き起こし、種が発芽しやすい環境を整える方法もある。森はインスタントにつくられるわけではなく、早送りもできない。
需要が急増する中で広葉樹の生産量は増えていて、国内にも案外資源があるじゃないかと受け止める向きもある。だが、それは国産広葉樹が注目されてこなかった、つまり利用されてこなかった間に育まれた資源があるだけで、利用と育成のバランスを取りながら森を管理できるかどうかは、これからの大きな課題だ。
「資源があるから使う」のではなく「資源が持続的に管理されているから使う」という姿勢で森と付き合わないと、森は簡単に劣化してしまう。木はわれわれの暮らしを豊かにしてくれる。だからこそ、森が健全に維持されているかどうかに関心を持ちたい。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.28からの転載】