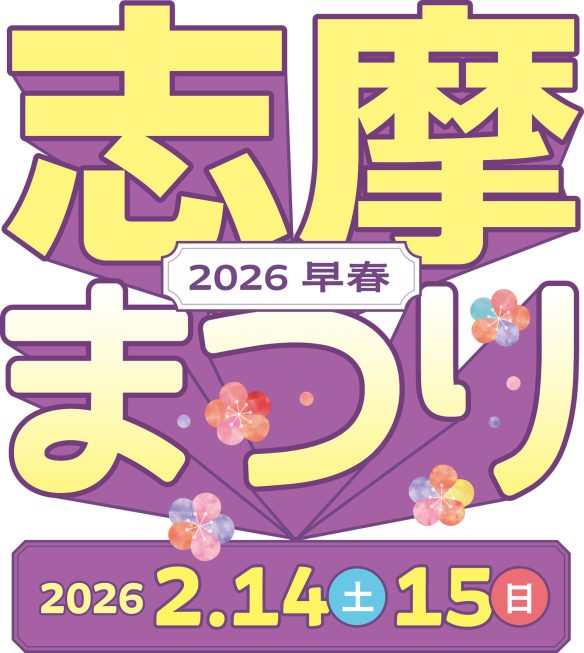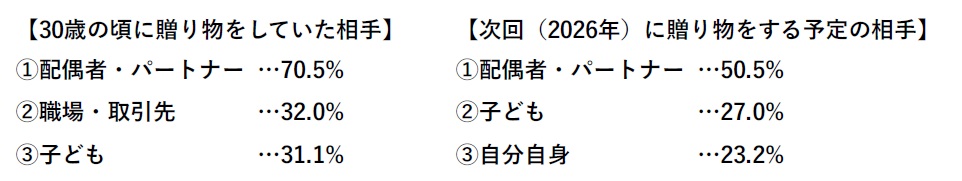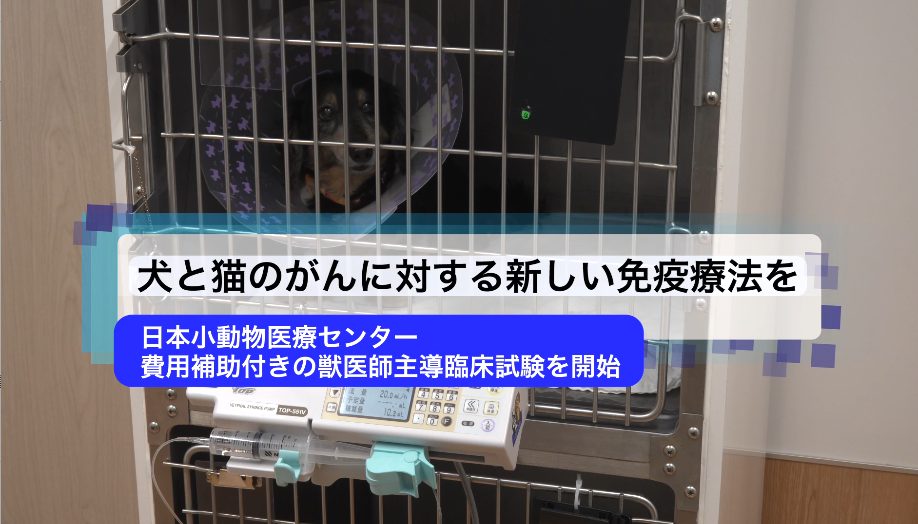そこにクリスチャン宰相はいなかった 【政眼鏡(せいがんきょう)-本田雅俊の政治コラム】
たった1枚の写真だが、多くの人に、ある種の“希望”を抱かせた。ローマ教皇の葬儀がサンピエトロ大聖堂で執り行われた際、米国のトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が膝をつき合わせて会談する光景だ。ロシア側の出方にもよるが、この電撃会談によってわずかながらも国際政治が前進しようとしている。
ローマ教皇フランシスコが13億人を擁するカトリック教会の最高指導者であったのみならず、国際社会全体にも極めて大きな影響力を持っていたことは誰もが知る。だから葬儀には宗派を超え、160もの国や組織が代表を派遣し、多くの首脳や王族も参列した。米国などは現職大統領のみならず、バイデン前大統領も参列した。
国葬級の葬儀では必ずといっても過言でないほど“弔問外交”が繰り広げられる。厳かな葬儀の前後であるし、時間も限られているが、各国の首脳同士が顔を合わせ、握手を交わすだけでも意義はすこぶる大きい。トランプ、ゼレンスキー両大統領の会談もわずか15分程度であったが、その成果は計り知れない。
しかし、せっかくの機会であったにもかかわらず、またわが国では15年ぶりのクリスチャン宰相であるにもかかわらず、バチカンに石破茂首相の姿はなかった。日本からは岩屋毅外相が派遣されたが、“格下”の感は拭えない。首相の参列見送りを批判したマスコミは少なかったが、スケジュール的に著しく困難だったわけでもない。
葬儀は日本時間の4月26日16時から始まった。もはやアガサ・クリスティー的な思考が求められるが、羽田からローマまでの飛行時間は約13時間であるため、25日のみどりの式典の後に政府専用機で出発すれば、各国首脳と立ち話程度はできた。石破首相は、26日はメーデー中央大会に顔を見せたものの、「果たしてそちらを優先すべきだったのか」(閣僚経験者)といった冷ややかな見方が強い。
石破首相は27日からベトナムとフィリピンを訪れることになっていた。よほどのことがない限り、ドタキャンや急な日程変更は外交マナー上、避けなければならないが、バチカンでの葬儀を終え、ローマから直行すれば、ハノイのノイバイ空港にはほぼ予定通りに着けた。“強行軍”のようにも見えるが、2月初旬にトランプ大統領に会いに行ったときほどではない。
もちろん、たとえローマに飛んでいたとしても、各国首脳とはほんの短時間の会談になっただろうし、社交と英語が必ずしも得意でない石破首相が国際舞台で蚊帳の外に置かれたかもしれない。だが、それでも日本の首相としてのプレゼンス(存在)は極めて重要だった。学校でも、おとなしい生徒と単なる欠席者とは大きく異なる。
自民党幹事長経験者の一人はかつて「どんな会議でも、そこに最初から最後まで居ること、座っていることが政治の基本。ずっと居れば、いざ発言するとき、どんなに当選回数が少なくてもみんな聞く耳を持ってくれるものだ」と語ったことがある。この指摘は首脳外交にもそのまま当てはまるかもしれないが、どうも石破首相の考え方は違うようだ。
スケジュールと航路を何とかやり繰りすれば、世界の首脳が集まるローマに駆けつけることができたはずだが、石破首相はこれを選択しなかった。物理的な可能性よりも、まさに意思の問題だったといえる。それどころか、「首相の葬儀参列の選択肢が官邸で真剣に検討された形跡がない」(自民中堅)ことが事実だとするならば、石破外交なるものに大いなる不安とあきれを感じる者は多い。
知日派として知られた米国のアーミテージ元国務副長官と国際政治学者のジョセフ・ナイ氏が最近、相次いで死去した。彼らが最前線で活躍していたとき、わが国に対してしばしば「ショー・ザ・フラッグ(旗幟を鮮明に)」「ブーツ・オン・ザ・グラウンド(部隊への参加を)」などとげきを飛ばした。米国の国益のためでもあったが、わが国を“世界の孤児”にさせないことも大きな目的であった。
“軍事オタク”と称されるだけあって、石破首相は安全保障問題や軍事問題には一家言持っており、それはそれで結構なことである。だが、それよりも前に重要なのは、日本の首相のひるまない外交そのもののはずだ。石破首相が世界の動きに活眼を開いて行動しなければ、わが国はトランプ大統領にだけ気を遣う“世界の孤児”になりかねないのではないか。
【筆者略歴】
本田雅俊(ほんだ・まさとし) 政治行政アナリスト・金城大学客員教授。1967年富山県生まれ。内閣官房副長官秘書などを経て、慶大院修了(法学博士)。武蔵野女子大助教授、米ジョージタウン大客員准教授、政策研究大学院大准教授などを経て現職。主な著書に「総理の辞め方」「元総理の晩節」「現代日本の政治と行政」など。
編集部からのお知らせ
新着情報
あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター