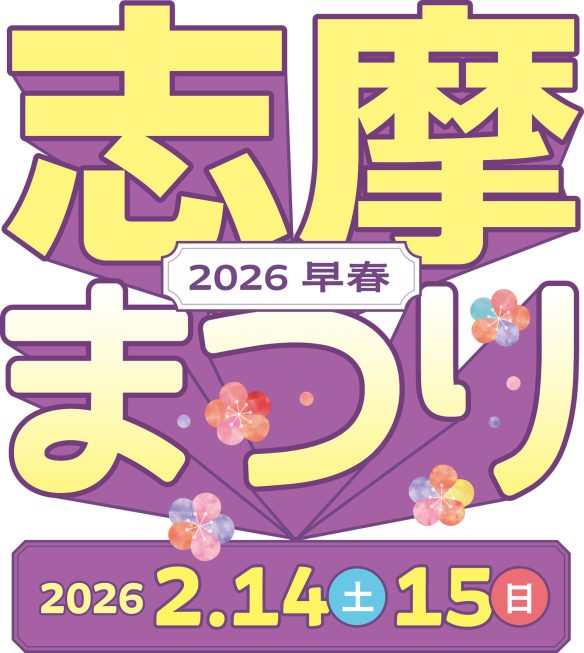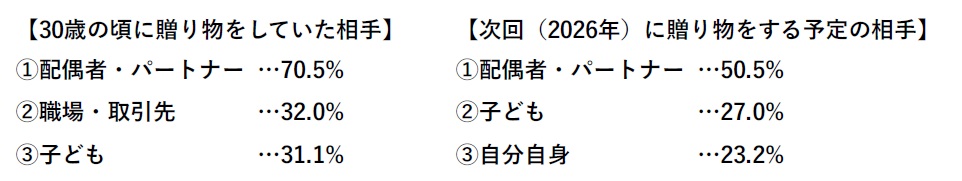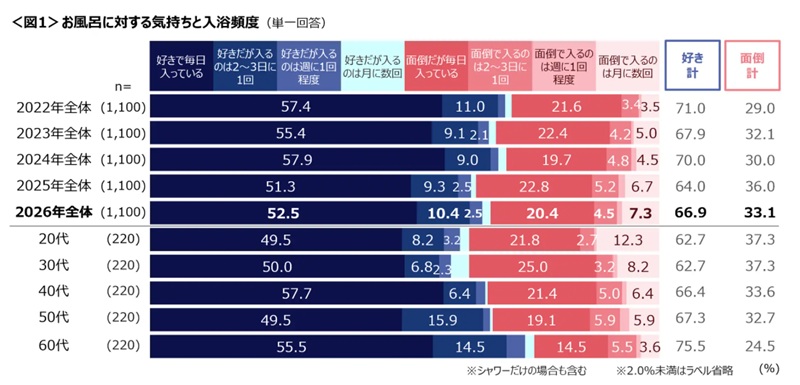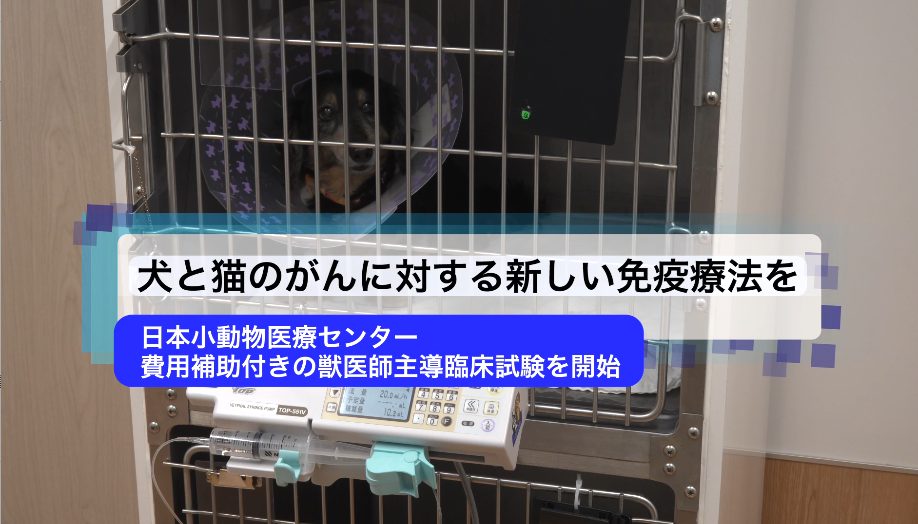長野にジェンダー平等を 松本で信濃毎日新聞、共同通信社がシンポジウム

「男は仕事、女は家庭」など社会的・文化的につくられた性差(ジェンダー)の問題を考えるシンポジウム「信州からジェンダー平等を2025 ともにあたらしく」が9月21日、長野県松本市の信毎メディアガーデンで開かれた。家庭や職場、地域の中のジェンダー課題を多角的に掘り下げ好評だった信濃毎日新聞の連載企画「ともにあたらしく」(2025年1~6月掲載)の取材班5人が、取材で得た知見を報告したほか、松本市副市長、ジェンダー研究の専門家、地元企業経営者らが、長野県のジェンダー平等実現に向けた取り組みや課題を議論した。
信濃毎日新聞社と共同通信社の主催。オンラインも含め約300人が参加した。協賛はAirbnb(エアビーアンドビー)▽井村屋グループ▽キッコーマン▽共栄火災海上保険▽信州ハム▽東京農業大学▽八十二銀行・長野銀行。
連載企画の取材班は計5人で女性記者3人、男性記者2人。これまで「当たり前」とされてきた性別役割分担や夫婦同姓の問題を取材した小西和香記者は「結婚したらほとんどの女性が姓を変える、家事は女性がやるなど、当たり前とされてきたことが“当たり前ではない”ということを具体的な数字や事例で伝えたかった。ジェンダーの課題には税制をはじめとした構造・制度における男女の不平等が隠れている。一人一人の意識だけでなく不平等な構造・制度を変えていくことも重要だ」と話した。
沖縄県で相次ぐ米兵の性暴力問題を記事にした岩安良祐記者は、沖縄に足を運んで夜のバー・クラブで話を聞いた性暴力に対する米兵の反応や米軍が定める公共での飲酒時間のルールを守らず深夜まで飲酒する米兵の実態を報告。
「米兵は午前2時半ごろまで公共の場で飲酒しており、相次ぐ性暴力の問題を受けて定めた米軍のルールは形骸化している」と指摘し「沖縄の人からは何度も沖縄はアメリカや政府になめられていると聞いたが、その一端を垣間見た気がした」と述べた。
重なる差別に苦しんだ被差別部落の女性や長野県佐久市出身の女性史研究家・もろさわようこさん(1925~2024年)を取材した河原千春記者は「ジェンダー不平等は一人一人の思いやりでは絶対に解決しない。ジェンダーの不平等が歴史的にどのようにつくられてきたのかをデータや解説で示したいと思った」と語った。また記事を書く上で「DV(ドメスティック・バイオレンス。配偶者や恋人など親密な関係にある又はあった者から振るわれる暴力)や性暴力など暴力と性をめぐる問題を興味本位で報道しないよう慎重に取材を進め、記事が取材対象者にとって二次加害にならないよう表現一つ一つに心を砕いた」と話した。
新聞報道の新しい試みとして、例えばセクハラ被害の実態を正確に伝えるため被害の詳細に触れた記事など連載企画の一部に「気分が悪くなる可能性もあるので無理に読み進めないでください」と注意喚起の断りを記載した取り組みも紹介した。
このような報道の新しい在り方を打ち出せたのは「もろさわようこさんの言葉があったからだ」として、同氏の言葉「自己解体しないで言葉だけ新しいものを求めても、ちっとも歴史は動かない。一人一人が自分を新しくしていく時が、歴史が新しくなる時だ」を読み上げた。
家族をめぐるジェンダーの課題を担当し二つの家族を取材した青木信之記者は取材をきっかけに夫婦げんかが起こってしまったことなどを振り返り「家族を巡るジェンダーを取材することはこうしたあつれきが生まれるぐらい重い課題であり、記事にすることは責任を伴う」と指摘。
「それぞれの家族の息苦しさやしんどさの向こう側には“男(女)はこうあるべき”というジェンダーの規範意識がある。連載はその規範意識を問うものであったが、一歩間違うと取材相手の人生を否定することになってしまうと心配だった。さまざまなジェンダーの規範に染まっている現実の家族の営みは一部を切り取って語れるほどシンプル(単純)ではない。取材相手一人一人の人生を尊重して取材を進めた」と話した。
身体の性と性自認が異なるトランスジェンダーを公表した長野県民の人生や「性別は男と女のみ」とする大統領令を出したトランプ政権下の米国を取材した野村阿悠子記者は「ニューヨークとロサンゼルスでの取材では、性別も年齢も政治信条もルーツも聞かないことがアメリカのマナーと取材相手に言われ、聞けなかった。これがいいことなのか悪いことなのか、私の中では答えは出ていないが、アメリカはそうなっていた」と現地の現状を報告した。
また現在取材している長野県中野市で2023年に起きた4人殺害事件の裁判の進行に触れ、「本家の農家の長男の生き方」を求められた被告の生い立ちと「長男を長男らしく育てなければいけない」という両親のプレッシャーが少しずつ明らかになって「被告が自分らしく生きるということができない状況が浮かび上がってきた」と事件の背景を説明。ジェンダーの問題は身近な日常だけでなく「社会を震撼させるような大事件の根深いところにもある」と語った。

取材班の報告の前に行われた、共同通信社の山脇絵里子・編集局次長が進行役を務めたディスカッションでは、上智大の三浦まり教授ら識者6人が長野県のジェンダー平等に向けた問題提起や各自の取り組みを発表。冒頭あいさつした長野県の阿部守一知事は、県の人口減少対策の一つとして「女性や若者から選ばれる働きやすく暮らしやすい長野県をつくることが大きなテーマになっている」として、研究者らの「地域からジェンダー平等研究会」が2022年から毎年発表している男女平等度を示す「都道府県別版ジェンダー・ギャップ指数」の順位を30年に全分野(政治・行政・教育・経済)で上位10位以内を目指す県の方針などを説明した。
このジェンダー・ギャップ指数の算定に携わる上智大の三浦教授は「四年制大学の進学率やフルタイム賃金の指数の数値からは、長野は女性がトップに就きにくい県に見える」と分析、「この点を改善するには目標となるロールモデルをメディアが発信することが必要」などと指摘した。
発信すべきロールモデルは必ずしも「組織で出世した人や社会的な成功を手にしたキラキラ女子」ではなくてもよく、むしろ「格好悪く弱さもさらけ出して周囲の力を借り自分の限界に挑戦しながら小さなことを変えている“等身大の女性たち”」がふさわしいとして、その生き方と肉声を伝えるメディアの役割に期待した。

ロールモデルに関しては長野県立大大学院の渡邉さやか准教授が「学部生から気軽に相談できる人がいないと言われたり、20代前半のカップルから子育てや長野に住むべきかなどの相談を受けたりすることが多い」と述べ、「若い人は身近に相談できるロールモデルがいないという実感がある」として、ジェンダー平等に取り組む多くの身近なロールモデルを連載で紹介した信濃毎日新聞の取り組みを評価した。
長野県上田市に本社がある古本ネット売買のバリューブックス代表取締役・鳥居希さんは、男性に偏る役員構成を改善した取り組みや、変化する会社の課題に合わせて3年ごとに課題解決にふさわしい人を代表に選ぶルールを作ったことなどを紹介。「24年7月から代表になった私の課題はジェンダーギャップの解消」と述べた。
今年4月に女性管理職が3割になった長野県松本市の伊佐治裕子副市長は、市職員対象のアンケート結果を説明しながら「30%になると女性上司が当たり前の組織になった。当初の女性管理職は背中を丸めて私なんかでいいのかというふうに見えたが、いまは女性管理職が生き生きしている」と組織の変化を口にした。
一方、3~4年の短期間で女性管理職を増やしたことから「女性管理職側の不安、男性職員側の不満」が出ていることも紹介した上で「このような本音が出てきたことで組織が変わっていく土台ができた」と前向きに受け止める姿勢を示し「職員の感情が出てきた今こそ、研修の機会をきちんと設ける、男女とも働きやすい環境をつくる、男性の長時間労働をなくすこと」に取り組んでいく、とした。
地域のジェンダーギャップ解消に取り組むWill Lab(ウィルラボ、東京都台東区)の小安美和代表取締役は国や自治体、企業はもちろん、身近な地域の自治会などでもジェンダー平等の推進が必要と強調。
課題解決にふさわしい代表を選ぶバリューブックスの取り組みは、地域でジェンダー平等を推進する上で参考になるとして、自治会に求められる役割を見直すことで、現在男性ばかりの自治会長職の門戸が女性に広がる可能性を指摘した。
ジェンダー平等推進のワークショップなどを開いている国際NGOプラン・インターナショナル アドボカシーオフィサーの澤柳孝浩さんは、これからの男性の生き方を巡り「いままでは働いていかに稼ぐかということが男性の存在意義とされてきたが、これからは幅広い生き方を男性自身が認め、周囲の友人らに共感を広げていく。これまでと違った生き方が格好良いとみられることが大事だ」と述べ、ジェンダー平等社会に生きる男性のロールモデルを構築する重要性に言及した。
ただ、そのような選択が難しい周囲からは「反論もありうるし、なかなかすぐに共感は広がらない」とも述べ、新しい男性ロールモデルへの共感の輪を少しずつでも広げていく地道な取り組みの大切さを強調した。
シンポジウムの動画はYouTubeで視聴できる。
編集部からのお知らせ
新着情報
あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター