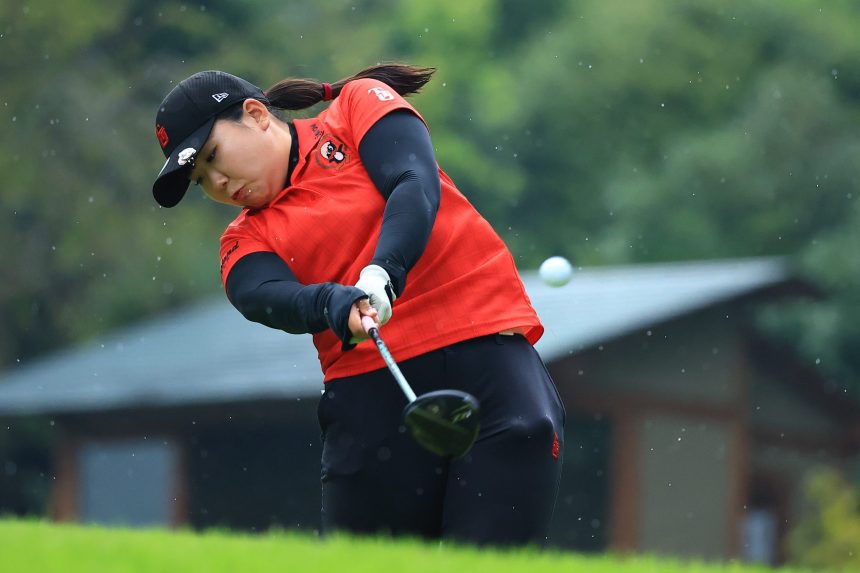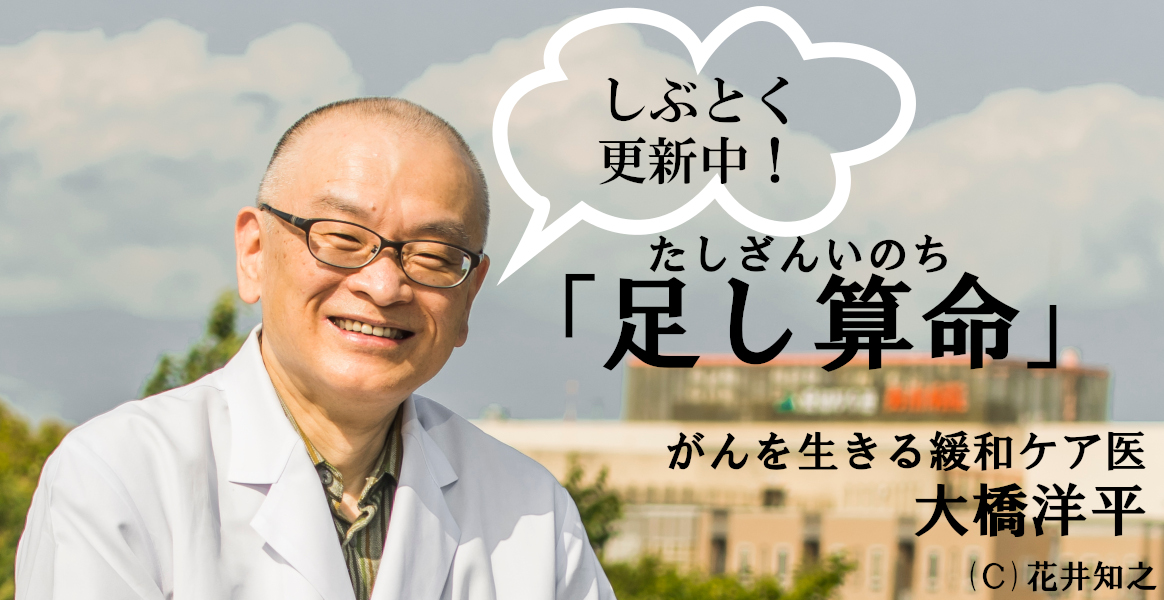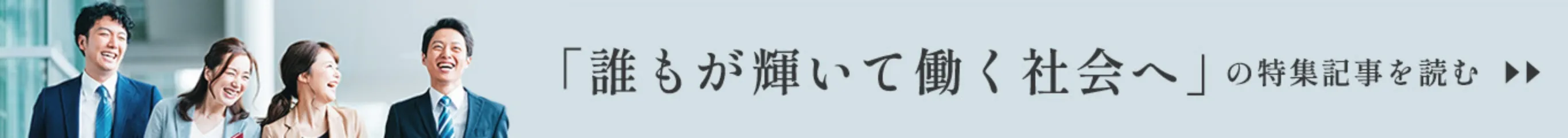「特集」誕生 オタク首相 自民総裁選大逆転 石破丸待つ荒波 自らビジョン語れ

本田 雅俊
政治行政アナリスト
やりすぎ人事
自民党総裁選での勝利を経て、10月1日、石破茂氏が第102代内閣総理大臣に就任した。だが、「総力結集」とは裏腹に、石破首相はあからさまな“勝ち組”偏重の人事を行った。決選投票で支援してくれた菅義偉前首相を副総裁に迎え、その息のかかった議員たちも入閣させた。旧岸田派議員の重用も目立つ。人事で最もやせ我慢を強いられるはずの“身内”だが、総裁選における推薦人の中から6人も閣僚に起用された。
一方、〝石破嫌い〟で有名な麻生太郎前副総裁は体よく党最高顧問に祭り上げられ、茂木敏充前幹事長や河野太郎前デジタル相は無役に追いやられた。逆に高市早苗、小林鷹之の前・元経済安全保障担当相は意地を見せて政権入りを固辞し、新しい総理総裁の求心力に冷や水を浴びせた。旧安倍派からの入閣者がゼロだったことに加え、故安倍晋三元首相を「国賊」とののしった村上誠一郎氏の総務相起用は、いたずらに“負け組”の保守派をいら立たせる。さすがに「どう考えても石破さんの人事はやりすぎだ」(閣僚経験者)といった辛辣(しんらつ)な意見も出はじめている。
石破氏が幹事長などを歴任し、過去に4回も総裁選に挑みながら、これほど総理総裁の椅子が遠かったのにはそれなりの理由がある。離党の“前科”があることもその一つだが、“オタク体質”も影響してきた。読書や鉄道、軍事にはのめり込むが、群れをなすのは苦手だし、好まない。かつて一緒に「石破政権」を夢見た議員たちも、いつの間にか離れていった。
もともと石破氏は安倍氏のように仲間や味方が多いわけではなく、岸田文雄前首相のように敵が少ないわけでもない。総裁選の1回目投票ではわずか46票の議員票しか得られず、党員・党友票でも高市氏を下回った。今回の人事で党内の不満のマグマは確実に大きくなる。
長らく冷や飯を食わされ、党内外に太いパイプを持たない石破首相が、森山裕氏に救いを求めたのは当然だ。「森山幹事長」に異論を唱える者は少ない。もっとも、石破氏は菅副総裁も頼りにしているようだが、森山幹事長ほど信頼を置けるかは不明だ。菅氏の悲願はあくまでも早期の「小泉進次郎政権」の樹立だからだ。
決選投票で逆転できたためだろう、石破首相は旧派閥の影響力低下に雀躍(じゃくやく)する。しかし、「組織としての派閥」はほぼ存在しないものの、特定の人や思想を慕う「精神としての派閥」は今後も残るし、今回、総裁候補を推した各集団が「派閥らしきもの」に変容していく可能性もある。来たる衆院選が終われば、旧安倍派の面々も息を吹き返す。
そもそも自民党政権は「派閥連合政権」といわれてきたように、内閣でも国会でも党でも、原則として各派閥から人が送り出され、それが連帯責任、ひいては「割れない自民党」の素地となった。派閥なきガバナンスは、石破首相が思っているほど簡単ではない。
大逆転の決定打
いつの時代でも、政権発足直後の首相の最大の心配はスキャンダル報道だ。13人の初入閣組の“身体検査”は行われただろうが、遺漏は避けられない。極めて異例ながら、石破氏が首相就任前に「解散」を予告し、早期の衆院選を断行する理由の一つも、ここにある。だが、たとえ当面は乗り切れたとしても、挙党体制を組まなかった、組めなかった石破流人事がもたらしたツケは、倒閣運動に発展しかねない大きな火種としてくすぶる。
総裁選の決選投票で石破氏が大逆転勝利を収められたのは、「長い政治経験から期待された安心感があった」(三役経験者)ことが大きい。石破氏は在職38年の大ベテラン議員で、不遇の時代はあったものの、それなりのポストを務めてきたし、知識も豊富だ。石破氏の保守中道路線に親近感を抱く者もいれば、決選投票前の“最後の演説”に心を動かされた者もいる。
だが、“決定打”は岸田氏が放った。決選投票における石破、高市両氏の議員票の差はわずか16票。岸田氏、そしてまだ影響力の及ぶ旧岸田派は石破氏に票を投じ、当選に導いたといわれる。閣僚に起用しながら、岸田氏がこれほど高市氏を嫌っていたことは驚きであった。
長い政治経験の割に、石破首相は閣僚として外交や財政、経済の分野を担ったことはない。そのため、「石破氏は経済に弱いのではないか」などと危ぶむ企業経営者もいる。総裁選の候補者討論会を通じても、「石破外交」や「石破経済」を期待する声は皆無だった。
さすがに“安保オタク”といわれるだけあって、安全保障や自衛隊の話は枚挙にいとまがない。総裁選でも「アジア版NATO(北大西洋条約機構)」の創設に意欲を示したり、日米地位協定の見直しを訴えたりした。だが、外交そのものについての発言は実に乏しい。このままでは、これからの首脳会談は単に「いかつい顔のつくり笑い」(野党中堅)だけで終わることになりかねない。
見えないビジョン
石破氏は総裁選で金融所得課税や法人増税に言及したが、発言を修正したり、トーンダウンさせたりした。岸田政権の経済政策や成長戦略を踏襲すると言ったり、「危機に強い経済」を提唱したりもしたが、歴代首相の「所得倍増論」や「増税なき財政再建」「アベノミクス」といった骨太の政策に見劣りしない経済・財政政策は、まだ石破氏の口からは聞こえてこない。
もちろん、財務官僚あたりに任せておけば、“立派な政策”は用意される。しかし、まずは首相自らが経綸(けいりん)(国家を治めととのえる策)を示し、どのようにその方向に進めるのかを明言すべきではないか。5回も総裁選に挑戦したのであれば、そうしたビジョンはあってしかるべきだ。それができなければ、「経済無策」「経済音痴」の誹(そし)りは免れない。石破政権の発足に、すでにマーケットは戸惑いを見せている。
石破氏が首相になれたのが偶然ではなく、必然だとするならば、それは裏金事件に代表される「政治とカネ」の問題に終止符を打つためだろう。世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の実態解明も時代の要請のはずだ。だが、ロッキード事件後の三木武夫首相(当時)と同じ轍(てつ)を踏むのを恐れてか、それとも辛苦の末につかんだ政権を手放したくないためか、石破首相の態度は煮え切らず、歯切れも悪い。
岸田首相が何に政治生命を懸けようとしていたのかは、最後まで理解されなかった。だからこそ、石破首相は単にスローガンを唱えるのではなく、また細かい政策でもなく、さらに評論家的な物言いでもなく、政治改革を含めた、この2、3年の具体的な目標と処方箋を明確に語る必要がある。レガシー(政治的遺産)は結果として残るのではなく、まずは最初に目標として掲げるべきだろう。
新政権が発足すると、ご祝儀相場も手伝って、支持率は高めに出る。「お手並み拝見」の期待値が反映され、今回も50%前後を記録した。とはいえ、政権を見る国民の“賞味期限”はかなり短い。石破首相が「勇気と真心で真実を語る」のも大事だが、ビジョンと処方箋で将来を語らなければ、年が改まる頃には、いやその前にも、国民は愛想をつかすかもしれない。
誠心誠意が〝豹変〟
首相になれば、追い風が吹いているうちに衆院選を断行したいと思って当然だ。実際、石破首相は早期の解散に踏み切る。10月27日投開票であれば、参院岩手補選の不戦敗も目立たない。来年夏には参院選も待っており、もしも二つの国政選挙を無事に乗り切ることができれば、石破首相はまさに「黄金の3年間」を手に入れられる。それまではさしずめ「仮免許」といったところだろう。
総裁選の討論会で、一刻も早い解散を主張した小泉氏に対し、石破氏は首をかしげ、その前に十分な論戦があるべきだと“正論”を吐いた。森山幹事長の意向や外交日程への配慮、11月5日の米大統領選後の風向きの変化などを危惧したのかもしれないが、早くも持論を引っ込めた石破首相に驚愕(きょうがく)した国民は多い。それを“ブレ”だと捉える者もいれば、“豹変(ひょうへん)”だと呆(あき)れる者もいる。少なくとも「誠心誠意」「逃げないで挑戦」といった言葉からはほど遠く、国民の納得も共感も得られていない。
立憲民主党の野田佳彦代表は重箱の隅をつつくタイプではなく、正々堂々と議論する雄弁家だ。論戦相手としては手ごわいが、自民党支持層にも意外にファンは多い。党内では現実路線を歩み、石破首相とは議論がかみ合いやすい。片や党内左派、片や党内右派と距離がある点でも似ているし、2人とも酒とタバコをこよなく愛する。
議論好き、討論上手の2人の党首が、くしくもほぼ同じ時期に登場したことは、何かしらの縁かもしれない。お互いがお互いを、そしてわが国の議会政治が2人を必要としたと、将来、歴史が記録するのではないかと期待した識者もいる。しかし、石破首相の早々の方向転換で丁々発止の論戦は先送りにされ、よき好敵手関係にもひびが入る。
衆院選では、自民党は単独過半数の233議席以上の獲得を目指す。「岸田では戦えない」と言って新しい「選挙のカオ」が求められた以上、この目標をクリアできなければ石破首相の求心力はいっきに低下する。総裁選の決選投票で石破氏は189票の議員票を得たが、衆院選で善戦できなければ、支持は瞬く間に離れる。もともと多くは強い支持者ではないのだ。
来るか「終わりの始まり」
だが、立民の野田代表も今回の衆院選で政権を獲得できるとは思っていない。むしろ「天王山」は来夏の参院選だ。衆院選に比べ、国民は参院選で政権に灸(きゅう)を据えやすいし、野党共闘も進めやすい。野田氏を全面支援する小沢一郎氏も、まずは「参院を制する者は天下を制する」戦略に焦点を当てているようだ。
石破政権はまだ発足したばかりで、来年の参院選の行方は見通せない。とはいえ、今回の人事、そして打ち出されない経綸や姿勢の“ブレ”にかんがみれば、かなり厳しくなることが予想される。高市氏や小林氏、茂木氏らは、表面上は「新政権に協力」と言いつつも、内心は「窮地に追い込まれることを手ぐすねを引いて待っている」(自民中堅)らしい。
しかし、石破政権の運命を決めるのは、主権者である国民だ。国政選挙の結果もさることながら、世論調査での内閣支持率、さらにいえば国民が石破首相をどう思うかが大きなバロメーターとなる。国民の多くが石破首相の発言や答弁に誠実さではなく、重苦しいねちっこさや詭弁(きべん)を感じ、テレビ画面から目をそむけたくなれば、それは政権の「終わりの始まり」の兆候にほかならない。
政治行政アナリスト 本田 雅俊(ほんだ・まさとし) 1967年生まれ。慶應義塾大学卒。内閣官房副長官秘書などを務めた後、98年慶應義塾大学大学院博士課程修了。武蔵野女子大学(現武蔵野大学)助教授、米ジョージタウン大学客員准教授、政策研究大学院大学准教授などを経て現在、金城大学客員教授。主な著書に「総理の辞め方」など。b-dotにコラム「政眼鏡」を連載中。
(Kyodo Weekly 2024年10月14日号より転載)
編集部からのお知らせ
新着情報
あわせて読みたい



自動車リサイクル促進センター