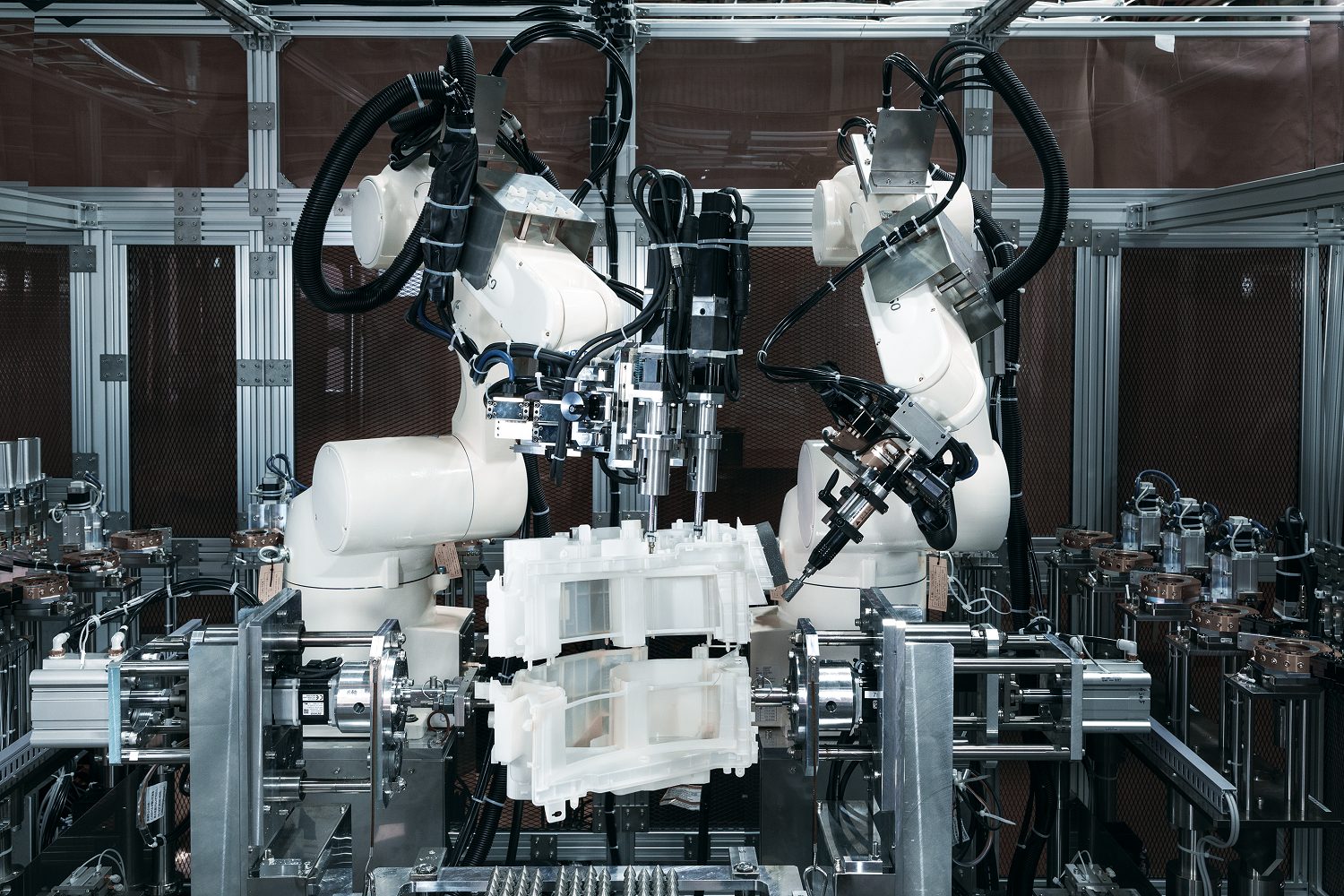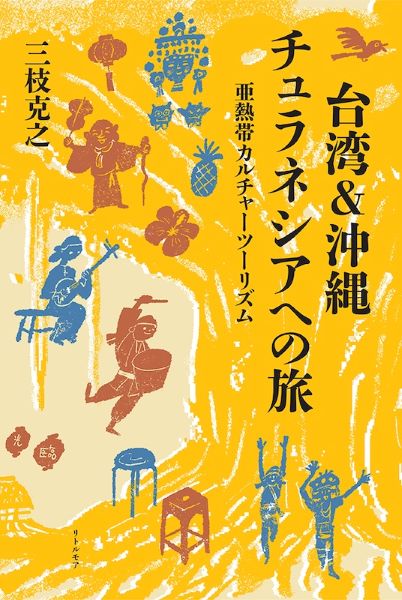青山貴洋監督「問診シーンが最大の課題に」日曜劇場『19番目のカルテ』【インタビュー】
体の不調を感じていても、何科を受診すべきか分からない…。そんな悩みを抱える人は少なくない。そうした現代の医療課題に向き合う存在が「総合診療医」だ。日曜劇場「19番目のカルテ」(TBS系)は、まさにその最前線で患者と向き合う医師たちの姿を描いた物語。富士屋カツヒトの連載漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』(ゼノンコミックス/コアミックス)を基に、「コウノドリ」シリーズ(TBS系)を手がけた坪田文が脚本を担当している。医療ドラマならではの手術シーンなどはないが、日常に潜む痛みやモヤモヤに真正面から向き合うことで、診察室での医師と患者のやり取りが持つ大切さを提示する。青山貴洋監督が語る“問診のリアル”とドラマの役割とは。

(C)TBSスパークル/TBS(撮影:加藤春日)
総合診療医の役割は、「痛みの原因が分からない」「何科を受診すればいいのか分からない」患者を受け止めること。青山監督は取材の中で、患者のわずかな所作や表情から医師が情報を読み取り、診断の糸口を探るプロセスに強い感銘を受けたという。
中でも青山監督が強く印象に残っているのが、医療監修を務める生坂政臣医師の言葉だった。「患者に“ひょう依する”感覚で寄り添う」という言葉に触れたことで、「ただ人と人がしゃべっているだけに見えがちな問診シーンに、どのような演出的工夫を加えられるか」が最大の課題になったと振り返る。
「患者さんが診察室に入ってくる時の歩き方、目の動き、座るかどうか。そういった動作の一つ一つに、実はその人の“痛みの正体”が表れているんです」と青山監督。
演出としては、黒い背景の中で医師と患者が“心の対話”を行うような構成を取り入れた。徐々にその視界が広がり、患者の生活や背景が見えてくる演出には、「見えていなかった患者の世界が、対話によって徐々に明らかになる」という生坂医師の言葉が大きなヒントになっているという。
問診シーンの撮影では、連続ドラマとしては異例のリハーサルを重ねた。「診察室に入ってくる瞬間から問診は始まっている」という生坂医師の言葉を受けて、細かな所作まで丁寧に描く演出が取り入れられた。
例えば、第1話で登場した、仲里依紗演じる黒岩百々のエピソード。「線維筋痛症の患者さんは物に触れる時、皮膚がむき出しになっているような痛みを感じる。だからドアを開ける瞬間やいすに座る動作にも、細心の注意を払っているという話が印象的でした」。
青山監督自身も、線維筋痛症の当事者に取材を行い、症状や日常生活での困難を理解するよう努めた。「ちょうど知人にも同じ病気の方がいたので、仲さんの演技の参考になるよう、撮影現場に来てもらって痛みの程度やしぐさについて確認しました」。
また、「心を閉ざしている人ほど、すぐには座らない」とも教わったという。たくさんの病院を渡り歩き、診断がつかないまま不信感を抱えてきた患者は、医師に心を開くことが難しい。そのため演出でも「座る」タイミングや距離感の変化に細心の注意を払い、「患者さんの心が少し緩んできたな」と思える瞬間を丁寧に映し出している。
主人公の徳重晃を演じる松本潤とも演技について綿密に話し合い、「患者の話を最後まで聞く」など、生坂医師の診療姿勢を演技に落とし込んでいった。

(C)TBSスパークル/TBS(撮影:加藤春日)