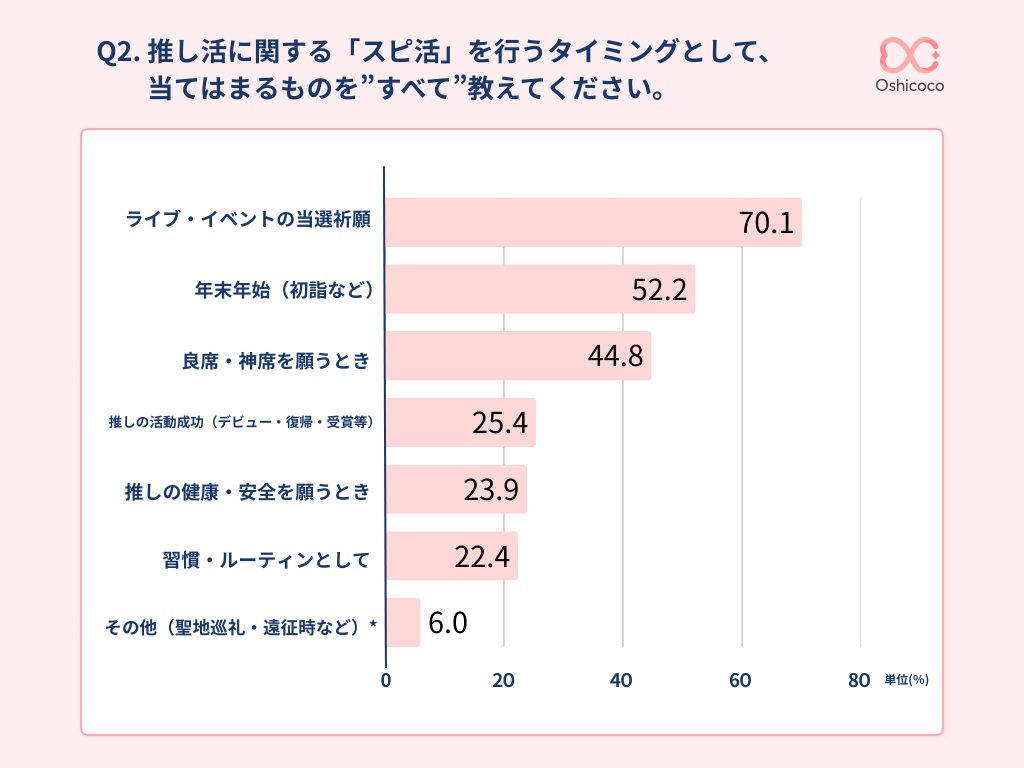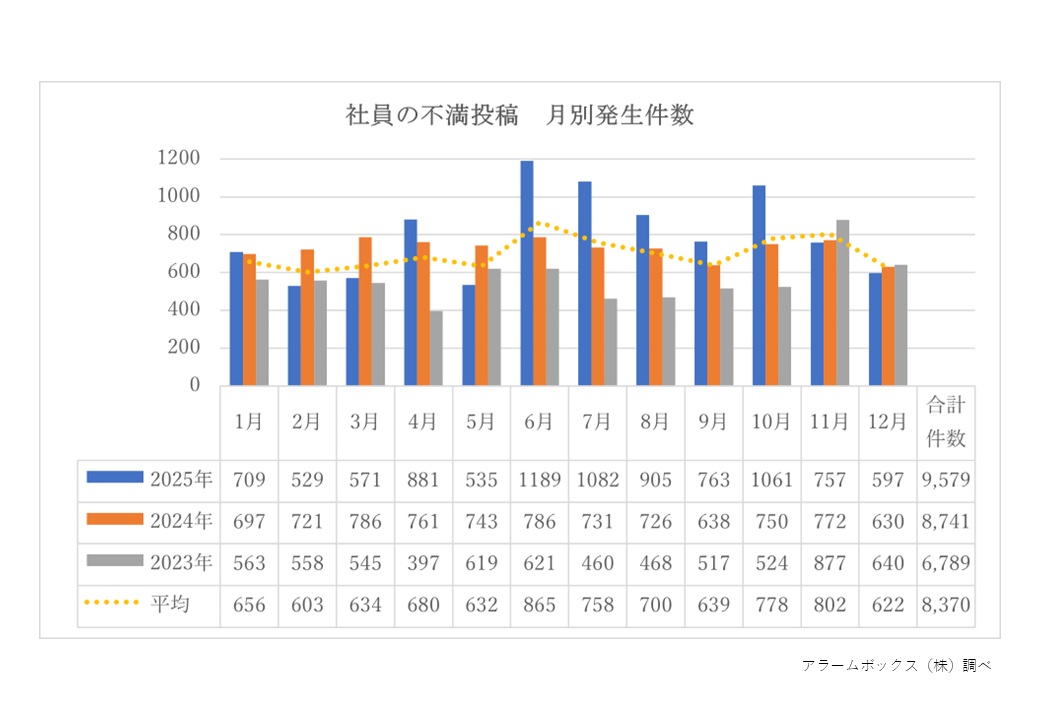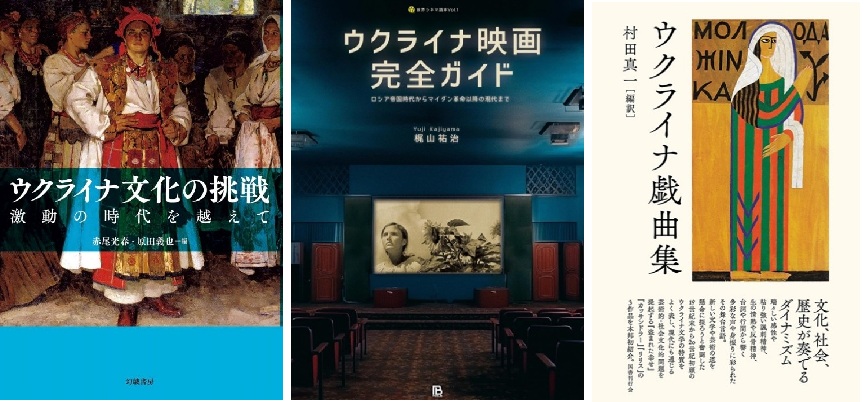コラム「旅作家 小林希の島日和」 日本の精神文化をつなぐ祭り
太陽がギラギラと照りつける7月13日、大分県の保戸(ほと)島へ向かった。3度目の渡島(ととう)だが、今回は特別だ。昨年、公益財団法人日本離島センターが都内で開催する「全国の島々が集まる祭典 アイランダー2024」というイベントへ行った時、保戸島のブースで島の方から「保戸島夏祭り」に来ないかとお誘いを受けた。
保戸島は、津久見(つくみ)市の港から定期船で25分、豊後水道に位置する。周囲約4キロと小さいが、鉄筋コンクリート造りの2、3階建て民家が港から山腹にかけて、ぎゅっと、みっちり建ち並ぶ。外観がカラフルに彩られ、初めて訪れた時はイタリアのアマルフィで見た街並みに似ていると思った。
これは、保戸島が明治中ごろ以降、マグロの遠洋漁業基地として隆盛し、島民のほとんどの男性が漁に出て稼いだ結果、競うように立派な家を建てたからだという。
夏祭りの正式名称は、「保戸島加茂神社神幸祭」。京都・上賀茂神社の分霊を祀(まつ)る加茂神社は、島の鎮守神として崇敬されてきた。12日から宮司と佐伯(さいき)神楽直川保存会が来島し、神事と神楽奉納を行う。
13日の午前便の船に乗り、保戸島に着いた。港には祭りを彩る旗が風にたなびき、御旅所(おたびしょ)が設置されていた。午後に御旅所で神楽が奉納され、小さな子どもたちが次々と神楽師に抱っこされ、大泣きする場面は微(ほほ)笑ましかった。子どもが無事にすくすくと育ちますようにという、祓(はら)いの意味があるのだろう。
初めて見た「湯立神楽」は、神楽師が煮立った釜の湯に、束になったササの葉を突っ込んで、頭上に持ち上げてから観衆のもとへ行く。バッサバッサとササの葉もろとも飛沫(ひまつ)を浴び、無病息災の祓いを受ける。
加茂神社は、山頂付近に鎮座するが、祭りの際は神輿(みこし)に神を移し、港の御旅所に置かれる。その後、男たちが担いで島内を巡幸し、海へ入る。神輿は地面に着けてはならない。終盤、ふたたび急な勾配の山を上り、神社に神様をお戻しする。
『自然と神道文化(1)―海・山・川―』(神道文化会)という本に、民俗学者の宮本常一を師とする記録映像作家の姫田忠義による項「まつりの初源を考える」がある。そこに、「人は何をもって自分の命を支え、養ってきたか。何を食べて生きてきたか。それが、まつりあるいは精神文化を考える場合の起点になる」と記されていた。
祭りを通して、自然や先人に感謝する心を次世代へと託している。また、来年も見に行こう。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.30からの転載】
KOBAYASHI Nozomi 1982年生まれ。出版社を退社し2011年末から世界放浪の旅を始め、14年作家デビュー。香川県の離島「広島」で住民たちと「島プロジェクト」を立ち上げ、古民家を再生しゲストハウスをつくるなど、島の活性化にも取り組む。19年日本旅客船協会の船旅アンバサダー、22年島の宝観光連盟の島旅アンバサダー、本州四国連絡高速道路会社主催のせとうちアンバサダー。新刊「もっと!週末海外」(ワニブックス)など著書多数。