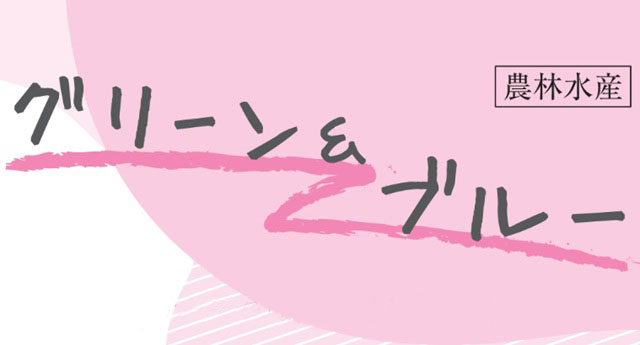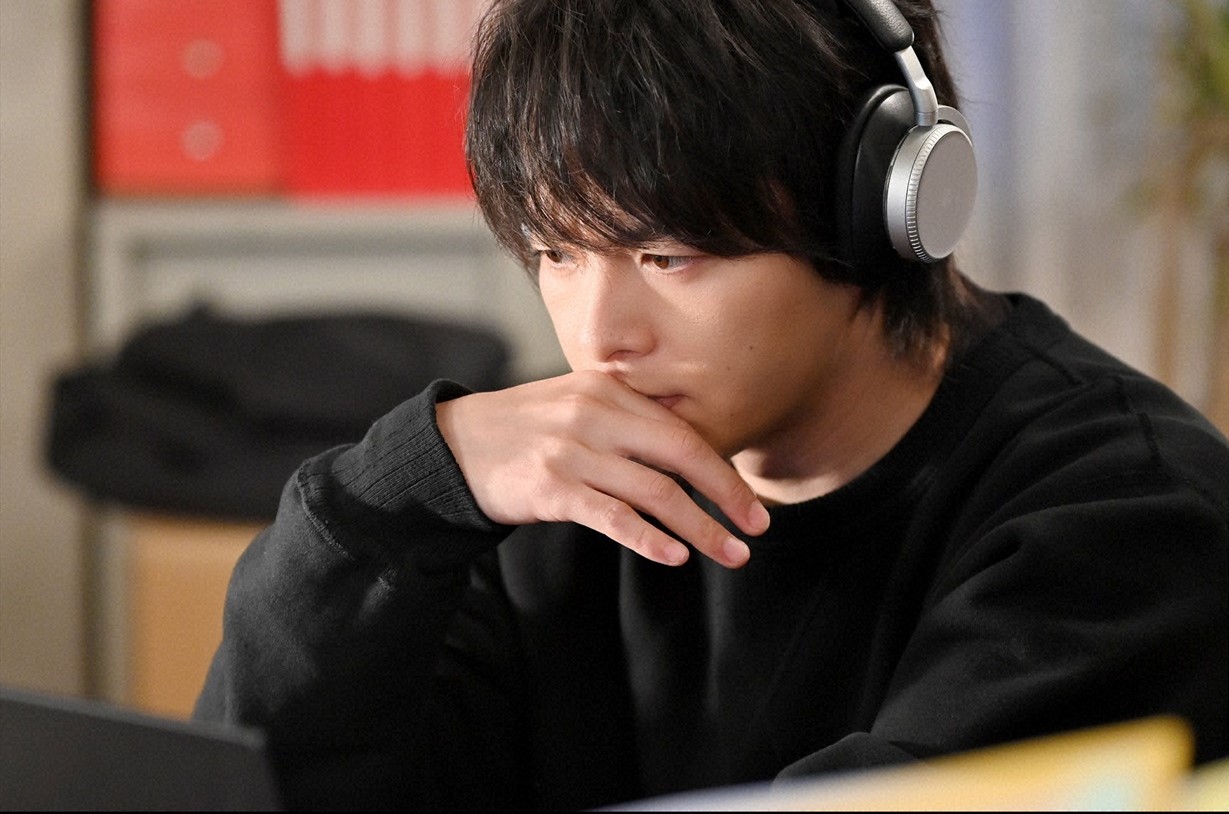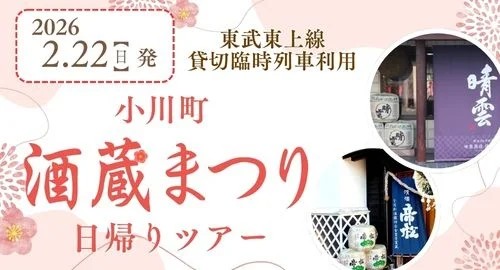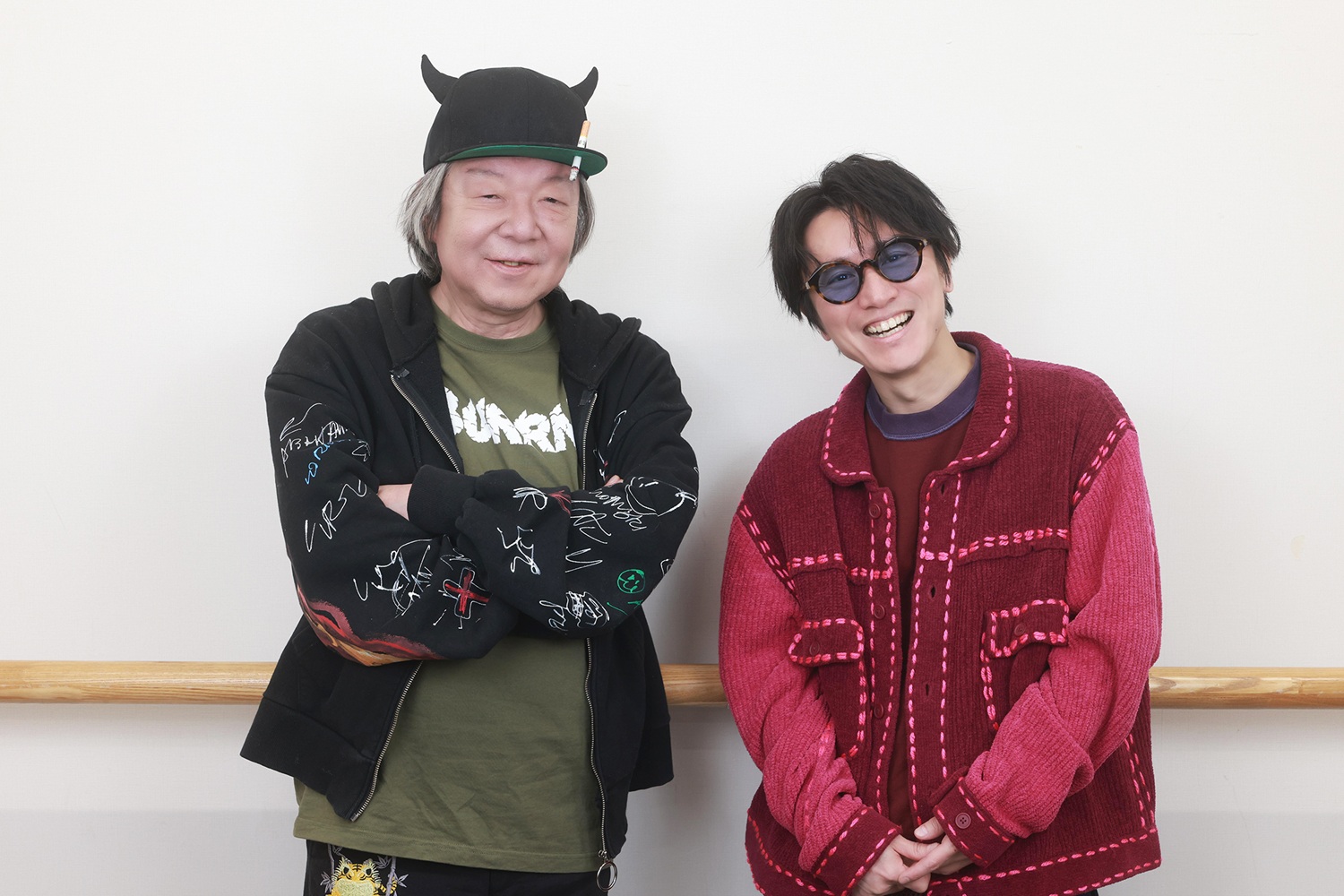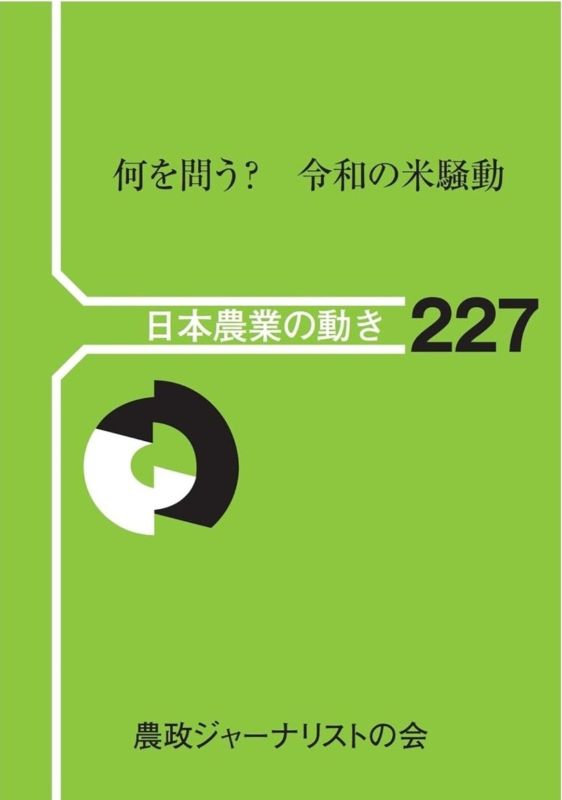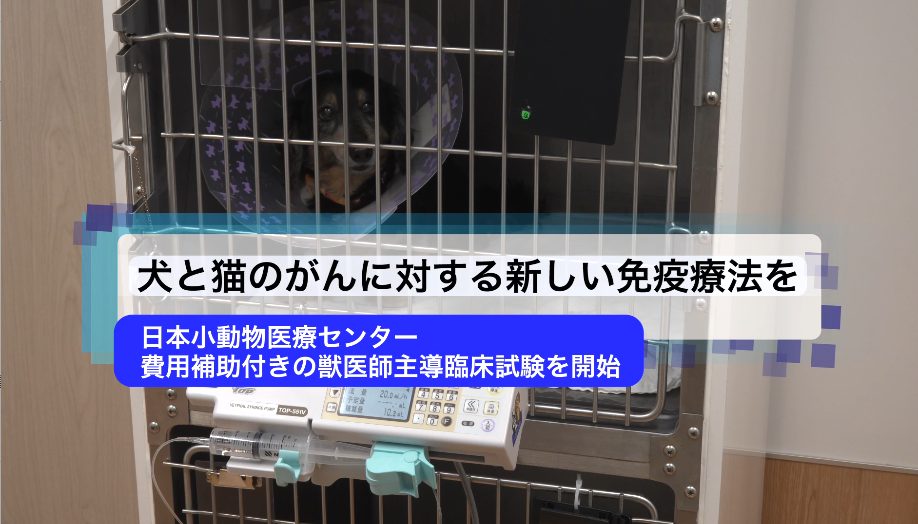日韓比較から見えるコメの魅力 青山浩子 新潟食料農業大学教授 連載「グリーン&ブルー」
似て非なる国といわれる日韓。農業にもこの言葉が当てはまる。両国とも小規模農家が多く、後継者不足などが課題だ。一方、コメをめぐる事情は対照的だ。日本はコメ不足に直面し、増産にかじを切ろうとしている。韓国は生産過剰で米価が低迷し、政府が買い入れすることで米価安定に乗り出そうとしている。両国のコメ事情から、日本のコメの強みが見えてきた。
今年9月、韓国の農業関係者が日本穀物検定協会を訪ねた。同協会は国産および輸入の穀物や飼料、食品の検査を行う第三者機関だ。コメの産地や銘柄ごとに「特A」、「A」などのランクづけを行う機関としても知られている。ランキングは毎年メディアで発表され、消費者の認知度やコメの売れ行きにも影響を及ぼすため、各産地はさらに上を目指そうと品質向上に躍起になる。韓国には客観的な尺度でランキングする仕組みがない。「コメの品質向上のためにも、穀検のようなランキング制度が必要だ」という声もある。
日本でランキングが始まった1971年は、生産調整が本格化した年だ。なぜ韓国で同様の仕組みがないのか。関係者と話して分かったことは、比較的短期間に消費量が減り、生産過剰を前提とする体制を作れずに来たということだ。日本も韓国も1人当たりの消費量は50キロ台だ。日本は100キロを下回って55キロになるまでに40年以上かかった。
韓国はわずか24年で同じ量が減った。日本ではここ数年、高温が続き、コメの収穫量や品質が低下し、2023年産米は特に顕著だった。これが〝令和の米騒動〟につながったため、産地からは「品質検査が厳しすぎる」という意見も出ているほど。それでも、品質に磨きをかけ、各地が競い合ったからこそ、日本産米ブランドが確立できた。
コメの加工品でも日韓で異なる。日本政策投資銀行によると、日本の米加工品の市場規模(出荷額ベース)は約1.2兆円(2020年)で、日本酒など酒類と米菓・もち類が全体の8割を占める。特に日本酒の輸出は伸びる一方だ。コメの品種や土地条件、作り手のこだわりなどを際立たせることでワインのような幅広い価格帯を設定できると期待されている。
これに対し、同じ年の韓国の加工品市場は約8630億円で、米菓・もち類とパックご飯で半分以上を占める。マッコリや焼酎など酒類も有名だが、高付加価値の加工品として認知されておらず、価値の高い酒類の開発を課題にしている。
コメは過剰になっても、足りなくなっても、批判の対象となりやすい。しかし、産地が切磋琢磨(せっさたくま)してよりおいしいコメを世に出す仕組みや、日本酒をはじめとする付加価値の高い加工品などが日本のコメ産業を支えてきた。この強みを生かした上で、担い手が減る中、どう増産するかという課題に向きあうことが必要だ。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.40からの転載】
編集部からのお知らせ
新着情報
あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター