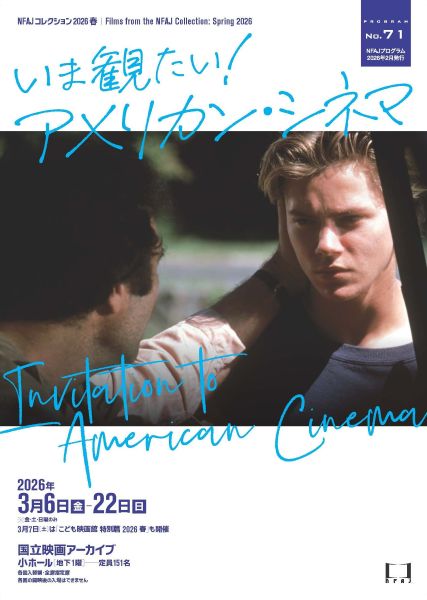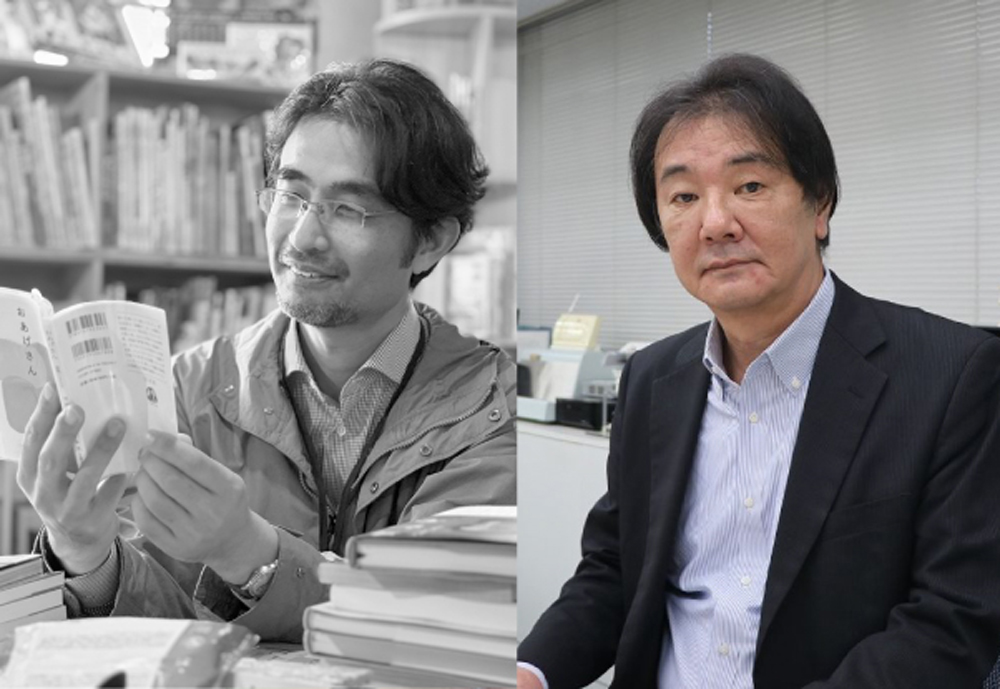ケルト伝承が日本で変貌-妖精「デュラハン」蘇る死者へ
2025/09/17 14:00
大阪公立大学
早稲田大学
ケルト伝承が日本のファンタジー系ビデオゲームで変貌 妖精「デュラハン」、蘇る死者へ
詳しくは、早稲田大学ウェブサイトをご確認ください。
<ポイント>
◇アイルランド民話の首なし妖精「デュラハン」が、日本のゲーム作品とその関連資料でアンデッドの怪物へ変化した経緯を、豊富な図像分析、文献調査、事例研究を通じて解明。
◇日本のファンタジー作品に登場する多くの怪物が西洋産のゲームを経由して伝来したのに対し、デュラハンは1980〜1990年代のケルト・ブームを通じて翻訳から直接導入された点が特徴で、誤訳や解釈のずれが異文化の再想像・再創造の契機となり、独自の文化的ハイブリッド※1なキャラクターの定型を形成。
◇日本で再創造されたデュラハン像は、韓国や中国のゲーム・小説に取り入れられるなど、国際的に影響を及ぼした。
<概要>
大阪公立大学大学院文学研究科のエスカンド・ジェシ准教授(研究当時、早稲田大学高等研究所講師)は、アイルランド民話において「首なしの死を告げる妖精」として知られる「デュラハン」が、日本のファンタジー系ビデオゲームと関連資料のファンタジー事典においては、ゾンビのようなアンデッドや蘇る死者のモンスターへと変容した過程を民俗学と情報メディア学を横断して明らかにしました。
多くの怪物が西洋TRPG※2を通じて受容された一方で、デュラハンは1980~1990年代のケルト・ブームを通じて翻訳から直接日本のファンタジー作品に導入されました。アイルランドの詩人W. B.イェイツ(1865~1939)の著作とその邦訳に見られる誤解を起点として、ファンタジー事典や初期国産RPGが像を定着させました。このように誕生した日本独自の「アンデッド・デュラハン」は、後に韓国や中国の作品へも広がり、文化的ハイブリッド化の仕組みを理解する上で大きな意義を持ちます。
本研究成果は2025年8月3日に国際学術誌「Games and Culture」(オンライン版)に公開されました。
<研究者からのコメント>
異文化に根を張った現代日本ファンタジーが、モチーフの本来の文化圏でも人気を博しているのは、それらの文化圏では発想し得ない再想像を提示しているからだと思われます。意図的な転覆であれ、不本意な曲解の結果であれ、歴史的意識に縛られない日本の創作者たちは、世界の伝承と想像の世界をまたがって奇抜なアイデアを提供しています。日本のコンテンツが世界的に流行している現状を踏まえると、その学術的探究は喫緊の課題であると言えます。
<研究の背景>
日本のファンタジー作品には、ゴーレムやグールなど、海外の神話や民話に由来するモンスターが多数登場してきました。これらは1980~1990年代に西洋TRPGやビデオゲームを仲介に受容され、日本独自の文脈で再解釈されました。その結果、起源が海外にあるにもかかわらず無国籍化し、日本文化の一部として定着しました。本研究者はこれを「文化的ハイブリッド化」として研究し、本来の歴史的背景から切り離され、無国籍的な「ファンタジー世界の存在」と化したモチーフ群にまつわる日本ファンタジーのジャンルの一つを、「データベース・ファンタジー」と提唱しています。
<研究の内容>
アイルランド民俗において「首なしの死を告げる妖精」として知られるデュラハン、その流入経路は多くの外国モチーフと異なり、西洋TRPGを介さず、1980〜1990年代のケルト・ブームを通じてイェイツの著作翻訳から直接導入された点に特徴があります。日本におけるケルト神話・妖精伝承の翻訳に大きく貢献した井村 君江氏は、イェイツの著作を訳す際に、「phantoms」(幻影)と「ghosts」(生気)を単に「幽霊」と訳しました。この解釈は、初期のファンタジー事典やビデオゲームに取り入れられていきます。
本研究では、1985~2019年に発売された日本のゲーム作品に登場するデュラハンを分析し、この誤訳が拡張され、デュラハンを妖精ではなくアンデッドとみなす日本独自の再創造が確立していったことを論証しました。さらに日本産のファンタジー事典がこの像を定着させ、以後のゲームやファン言説を通じて大規模に拡散した経緯を証明しました。
この過程は、ゲームと関連のテクストが文化的仲介者として果たす役割を示す好例です。デュラハンは、日本ファンタジー固有のジャンル的慣習に適応し、輸入文化市場や美学の要請に応じて再編される傾向を示しています。同時に、誤訳や解釈のずれが必ずしも誤謬に留まらず、創造的再想像の契機となることも明らかになりました。こうした日本に生まれたハイブリッド化は、さらに、韓国ゲーム『マビノギ』や小説『月光彫刻師』など、他地域の作品に影響を及ぼし、逆に中国の『ゼンレスゾーンゼロ』のように独自の再解釈を誘発するなど、さまざまなメディアを通じ、国境を越えて展開しています。
以上の知見は、民俗学とゲーム研究の接点を照らし出します。前者にとっては正統的伝承と現代的再想像の境界を問い直す視座を、後者にとってはゲームを文化翻訳と流通の主体として捉える視点を提供します。結論として、デュラハンの日本的再創造は、ポップカルチャーにおける輸入モチーフが受動的に消費されるのではなく、地域的嗜好やメディア制作上の都合に応じて能動的に再編され、さらには国際的文化循環の一部となることを端的に示しています。このようにアンデッドとして定着したデュラハンは、単なる誤訳の産物ではなく、ゲーム文化が創造しうる新しい神話の象徴であるといえます。
<期待される効果・今後の展開>
本研究成果は、民俗学・翻訳研究・ゲーム研究などの既存分野の架橋に貢献するだけでなく、グローバル化時代における文化の「翻訳」と「再編成」の具体例を提示するものです。
社会的には、本研究は二つの意義を持ちます。第一に、ゲームや漫画、アニメといった大衆文化が国際的な文化交流において重要な役割を果たしていることを示し、日本発ポップカルチャーの影響力を具体的事例で裏付けました。これは、コンテンツ産業政策や文化外交の観点からも注目される成果です。第二に、翻訳や受容の過程で生じる誤解や誤訳が、必ずしも負の側面にとどまらず、むしろ創造的な再解釈の契機となりうることを示した点です。これにより、国際的な文化摩擦に対して柔軟かつ建設的に理解するための学術的知見を提供します。しかし、デュラハンはそうではありませんが、実際、異文化の宗教に起源のあるモチーフの日本ファンタジー作品における再想像は、すでに何回もこのような摩擦を起こしてきました。本研究は、日本のコンテンツ業界において、異文化を理解し、それを受容したうえで創作・商業活動を行う手がかりにもなりえます。
以上のように、本研究は学術的には比較文化・メディア研究の新たな知見を提供し、社会的には日本発ポップカルチャーの国際的理解や活用に資する成果を持つものです。
本研究はアンデッドとしてのデュラハン像に注目しましたが、デュラハンには「騎士」や「人外女性」のような他の日本独自の定型も存在するため、今後は包括的な分析が必要です。とくに女性の人外キャラクターに関しては、RPG系ゲームでは倒すべきモンスターとしてしばしば登場する一方、漫画やアニメでは人間に友好的な「人外キャラクター」として描かれる場合もあります。過去の研究では、暫定的に「人外もの」と提唱したジャンルにおいて、このようなキャラクターが現代日本社会についてより自由に語るための手法となっていると指摘してきましたが、デュラハンを用いた事例についても今後調査を続ける必要があります。
<資金情報>
本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業 研究活動スタート支援「現代日本ファンタジーにおける文化の盗用研究」の研究助成を受けて行われました。
<用語解説>
※1 文化的ハイブリッド:異なる文化的背景をもつ要素が交差・融合した結果として生じる、新たな文化的形態。
※2 TRPG:テーブルトークロールプレイングゲーム。参加者が会話で物語を共同的に進める形式のゲーム。ボードゲームと即興演技を組みあわせたものとも説明できる。1970年代のアメリカにホビーとして生まれ、1980年代の後半から1990年代の前半の間に日本において一時的にブームを起こした。
<掲載誌情報>
【発表雑誌】Games and Culture
【論 文 名】The Dullahan, From Fairy to Undead Tracing the Cultural Hybridization of Irish Folklore in Japanese Games and Their Paratexts
【著 者】Jessy Escande
【掲載URL】https://doi.org/10.1177/15554120251362923
編集部からのお知らせ
新着情報
あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター