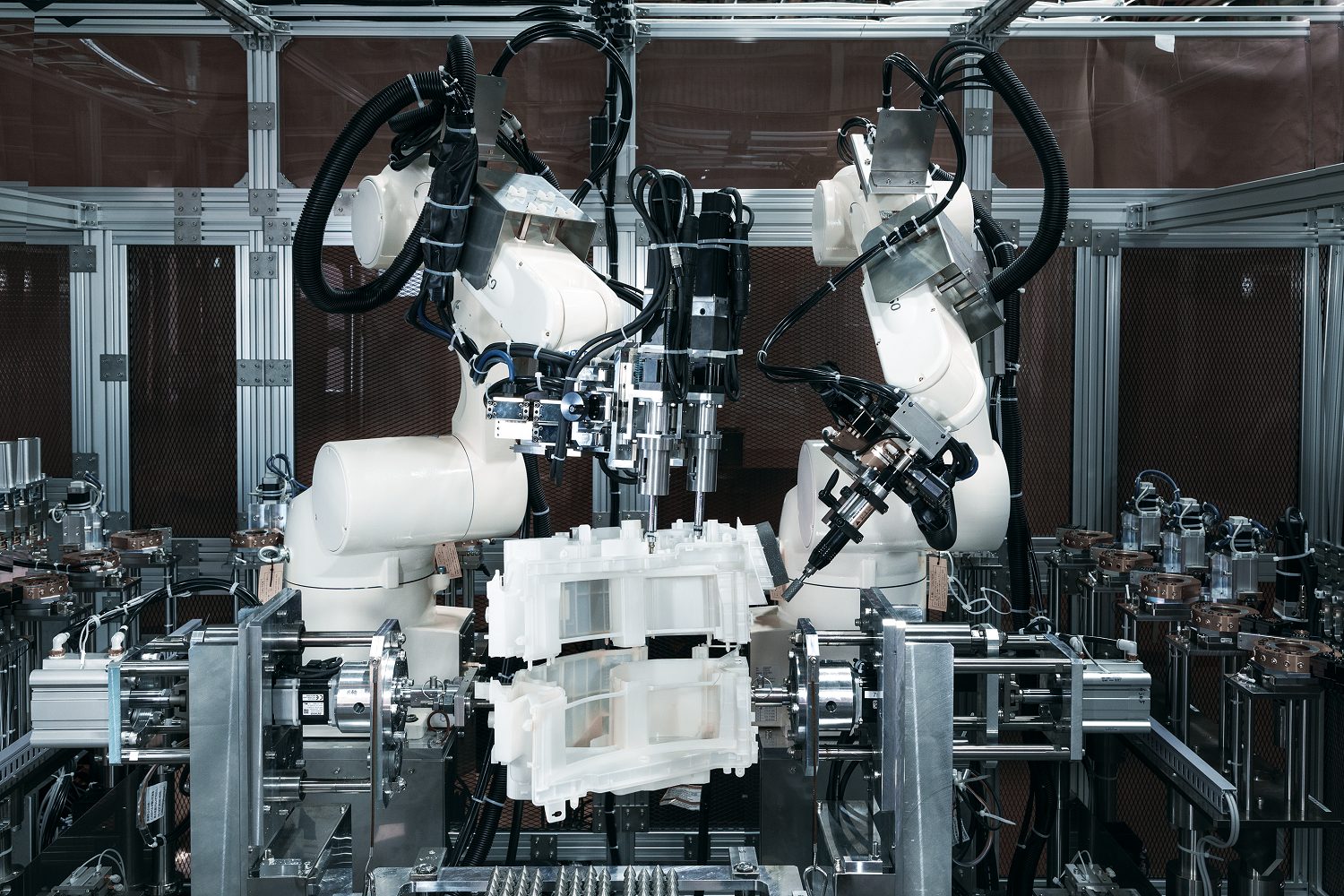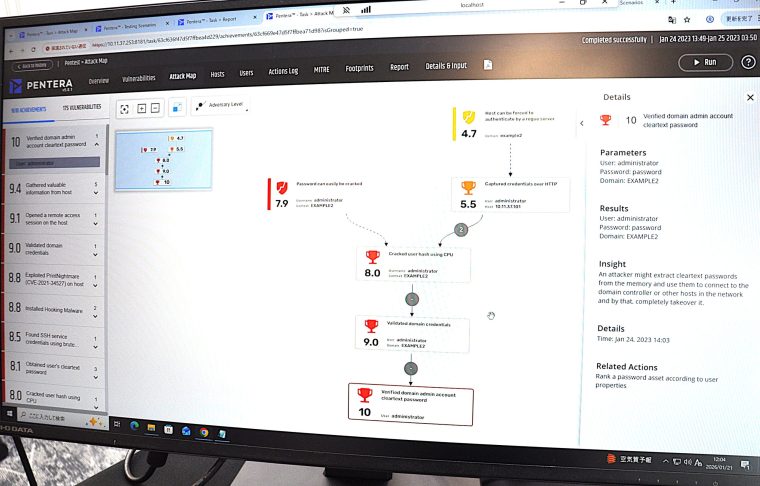広瀬すず「この女性たちの化学反応は一体何なんだという、すごく不思議な感覚になります」『遠い山なみの光』【インタビュー】
ノーベル文学賞受賞作家カズオ・イシグロが自身の出生地・長崎を舞台に執筆した長編小説デビュー作を、石川慶監督が映画化したヒューマンミステリー『遠い山なみの光』が9月5日から全国公開された。1950年代の長崎に暮らす主人公の悦子をはじめ、悦子が出会った謎多き佐知子(二階堂ふみ)、80年代のイギリスで暮らす悦子(吉田羊)が登場する本作で、長崎時代の悦子を演じた広瀬すずに話を聞いた。(*ネタバレに該当する内容があります)

広瀬すず (C)エンタメOVO
-初めて脚本を読んだ時の印象として、「不穏でホラーのように感じた」と聞きました。どの辺りにそれを感じましたか。
佐知子さんの存在もそうですし、せりふのやり取りも、独特のリズム感というか、核心をつくのではなく、かみ合っていないようにも思える。そういうところが何かぞわぞわするというか、ふわふわとした感覚があって、これは何が正解なんだろうと思いました。でも、こうしてプロモーションをしていると、人それぞれに答えがある作品だという気がしてきています。(石川慶)監督のインタビューなどを聞いていると、あえて明確な答えを求めない作品なのだと思いますし、それが良いのだと時間がたった今は思いますが、演じる際にはとても難しい脚本でした。
-1980年代の悦子を演じた吉田羊さんの姿に胸が痛んだと語っていましたが、50年代の悦子をどのように演じようと思いましたか。
これもあくまでも自分が感じたことですけど、50年代の悦子さんとして、戦争が残した傷や痛みや怒りを表現するというよりも、そういうことがあったからこそ、未来に向かって自分のやりたいことや希望に満ちあふれた女性だったのではないかと捉えました。体の中に新しい命もある中、止まるのではなく進むという選択肢を選んだ女性として演じたつもりです。でも、時間がたてばたつほど、その傷が大きな穴のように広がっていくような、体の中にどんどんにじんでいくような体験だったようにも思えて。彼女の記憶が分裂していくのは、無意識にすごく嫌なことを忘れようとしたからではないかと思います。それは、想像しきれない痛みが体内に残っているからだと思う場面や言葉や表情が多くて。でもその痛みは多分80年代の悦子さんにしか感じられない痛みで、それが自分が演じた50年代の悦子さんとは別人のように見えました。80年代の悦子さんにとって、40年代や50年代の記憶や景色がどんなものになっているのかと想像させられるシーンが多かったです。
-緒方悦子というキャラクターをどのように捉えましたか。
同じ役を羊さんと2人で演じ分けたこともそうですが、1人で完結できる役ではなかったので、ある意味、最初に脚本を読んだ時の感覚に忠実に、切実な悦子さんをピュアに演じました。そこに佐知子さんや80年代の悦子さんの色が入ってくると、顔が重なってくるというか、(悦子の娘の)ニキも含めて、4人で1人の女性みたいに思えたので、いろいろと足して割ったような感覚になるといいと思い、できるだけ素直に演じようと思いました。
-悦子と佐知子の関係性をどのように考えましたか。
撮影時は、佐知子さんは佐知子さんとして見ていましたが、完成作を見ると、悦子さんが自分の嫌な記憶を全部佐知子さんに移しているような気もして…。だから、どちらも悦子さんのような気もするし、どちらも佐知子さんのような気もする。それも悦子さんがイギリスに行ってから、あの記憶も自分だったんだと確信している表情にしか見えなくなってきて、ああなるほどと。では、佐知子さんとは一体誰だったんだ、あれも自分の逃げたかった記憶だったんだと素直に受け止めることができたけど、それに気付いた悦子さんはすごくゾッとしたと思うんです。だからこそ、佐知子さんは別人ではないと自覚した自分によみがえってくる感情や景色や痛みがあると、80年代の羊さんが演じる悦子さんを見て感じました。