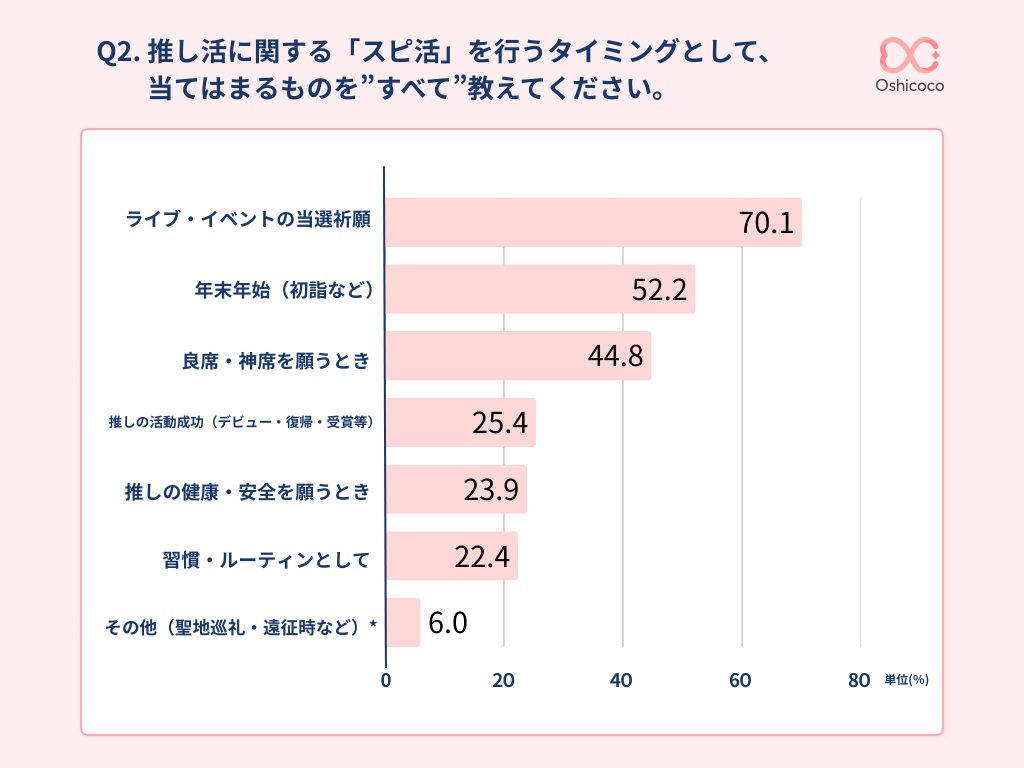「特集」自律兵器規制議論の課題 開発進展、現実が先行 ガザで攻撃支援にAI使用 難しい「軍/民」の境界

佐藤丙午
拓殖大学国際学部教授
自律型兵器の規制
特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)では、2013年以降、自律型致死兵器システム(LAWS)に関する問題を議題としてきた(3年間の非政府専門家会議を経て、16年の締約国会合で政府専門家会合=GGE=の立ち上げが合意された)。19年には11項目の指導原則(Guiding Principles)に合意している。その後、コロナ期間中も会合は続き、24年以降は3年間の予定でGGEを継続し、法的措置を含む対応措置の議論を行っている。
この問題では、議論の舞台はCCWに限られてはいない。オランダと韓国は「軍事領域における責任あるAI利用(REAIM)」を立ち上げ、23年と24年にそれぞれ国際会議を開催し、国連に最終報告書を提出する予定とされる。国連においても、グテレス事務総長が23年に「新平和のための課題」を発表し、26年までに人工知能(AI)を利用した兵器システムに関する法的措置の実現を求めている。
自律型兵器システムの規制については、実は事態の進展の成否が判断しにくい状況が続いている。米国では、12年には国防総省指令3000・08を発表し、司令官の意図を正確に反映しない無人兵器の運用を禁止している。この指令はトランプ大統領のもとで、時限措置から恒常措置へと格上げされた。CCWで合意した指導原則は、新兵器システムを含め、全ての兵器システムは人道法(ジュネーブ諸条約と二つの議定書を中心に、全ての関係条約の意味)に準拠したものであることについて、ロシアや中国を含めて合意したものである。
25年3月3日から8日にかけて実施されたCCW‒GGE‒LAWSにおいても、武力行使に関わる事態における人道法の重要性を議論の基本とし、その対応措置として、禁止と規制の2トラック・アプローチ(日米を含め、多くの国が共同提案者になっている)に対する支持も強力なものとなっている。

国連欧州本部ビル。自律型致死兵器システム(LAWS)の政府専門家会議が開かれた=3月3日、スイス・ジュネーブ(筆者提供)
しかし同時に、戦闘手段の知能化や無人化は進展している。ガザ戦争ではイスラエルがAIを利用した攻撃支援システムを利用したと報じられ、「ラベンダー」や「ゴスペル」、さらには「Whereʼs Daddy」などのシステムの存在が知られるようになった。これらシステムは、攻撃目標の選定と、攻撃対象者の位置特定にAIを利用するものとされている。
論点多数、合意難しく
自律型兵器システムの規制の現状、あるいは、禁止や規制の実現より先に兵器システムの開発が進んでいるのか、など、この問題には多くの疑問が存在する。さらに、韓国などでは、無人化部隊の実現を目標として掲げ、日本でも自衛隊によるAIの利用促進が規定されており、LAWSの前提となる兵器システムの無人化推進は、この2国に限らず、多くの国が追求している。この現状から、国際社会では人道法との関係につき、懸念の声が上がっているのである。
兵器システムは、段階的に開発や実戦化が進む。実は兵器システムの自律化には、複数の出発点が存在する。無人化技術の軍事利用は、観測や監視などの領域で、現在民生分野でも一般的に利用されている技術の利用などから始まった。製造業で活用されるロボットなどは、無人化技術の代表的な事例である。もちろんそこには、スピンオフかスピンオンかなどの論点は存在する。CCWの議論でも時々取り上げられる、対人および対戦車地雷は、動きに反応するセンサーを利用した、無人兵器の一種と解釈することもできる。
つまり、兵器システムの無人化は、近年の現象ではなく、実際には既に多くの兵器システムで進められている。例えば、多くの海軍で採用されている近接艦船防護システムは、接近するミサイルなどの攻撃に対して、最終段階での防護を自動的に行うものだが、このような自動兵器は他の軍種でも採用は進んでいる。LAWSではないかと指摘されるイスラエルの「ハロップ」も、司令官の意図を最終的に反映できるシステムが採用されている。つまり、これらは完全な自律型兵器システムではない。
CCWでの議論では、さらに多くの論点が存在し、コンセンサスによる合意形成には困難も指摘されている。論点としては、自動(automation)兵器と自律化(autonomous)兵器の差、防御兵器における自律化の許容度(攻撃的兵器ではなく防御目的なので、人道法の趣旨に反さない)、致死性の定義(自律型兵器ではなく、自律型致死兵器であることの意味。人道法で規定されるのは、相手の死ではなく、不必要な苦痛であることをどう規定するか)、自律型兵器システムが単体の兵器ではなく複数の機能が統合されて成立する性格があることに起因する課題、人間の関与の定義とその実質的内容など、多くの点が連続的に議論されている。
これらの議論の結果により、各国の兵器開発の方向性が規定される。しかしその半面、各国の兵器開発の現状を、規制の議論に反映させようとする動きも存在する。国際的な合意は、規範的に無謬(むびゅう)の結論が合意されるのではなく、各国の利益を反映した内容でない限り合意形成は難しい。
軍事、民事の線引き
兵器システムが攻撃に至る過程には複数の段階が想定される。それゆえ、CCW‒GGE‒LAWSなどでは、それらを一体として特別なシステムとして規制や禁止の対象にするのか、それともそれぞれの段階での兵器システムの無人化や知能化について、人道法に直接関係する部分だけ議論の対象とするのかが一つの論点となっている。
19年の指導原則に合意した当時、CCWでは兵器のライフサイクルと、攻撃に至る段階を分解した「キル・チェーン」(情報収集から標的特定、目標確認、目標の破壊・殺害、破壊・殺害の評価などに至る一連の行動)が参照されたが、今日も国際社会はこの枠組みを基本として議論を進めている。
兵器のライフサイクルは、兵器の構想から破棄に至るまでの段階を想定し、それぞれの段階で人道法規範を反映させる最適な方法を検討したものである。「キル・チェーン」では、監視から攻撃後の評価に至る攻撃の各局面において、AIの活用などがもたらすリスクが検討された。
先に述べた一体化論は、この問題と深く関係する。軍が行う情報収集は、平時と有事に限らず各種プラットフォームが広範に実施している。人工衛星による情報収集もこれに含まれる。そして攻撃に至る段階として、敵を探索・捕捉し、攻撃目標を特定して、攻撃する。この過程でAIが利用され、情報分析や攻撃目標の特定などで活用される。
攻撃対象は、軍事目標によって規定されるため、軍事固有の問題は、分析のために使用される情報と、攻撃目標のアイデンティティー(形状や特質)になる。このように考えると、攻撃に至る直前の段階まで、民生分野に極めて「近い」技術が使用されていることが分かる。つまり、そこに軍事と民事の境界はなく、技術の使用者がどのような目的をもって技術を使用するかだけが問題となる。
ここで、軍事固有の問題は、攻撃段階において、どのような手段で敵を攻撃するか、という点に絞られる。致死性を巡る問題はここに関係する。攻撃目標を殺害、あるいは破壊するのが最も一般的な攻撃方法であるが、新興技術などを活用することで相手を無力化するなどの方法も検討されている。いわゆるサイバー攻撃による相手システムの混乱や、AIなどによる偽情報の拡散は、この一形態である。そうなると、人道法で規定される「不必要な苦痛」の問題を回避できる可能性がある。
現存する自動兵器や自律兵器は、完全無人化に至っておらず、人間の関与が可能な状態になっている。イスラエルの滞空兵器のハロップや韓国のセントリー兵器のSGR‒A1などは、無人モードと同時にマニュアルモードが備わっており、人間の関与が担保されている。しかし、UUV(海中ドローン)など、いったん起動した後に人間の関与がなく索敵・攻撃することが必要となる兵器の研究開発が進められている。このため、完全自律型兵器システムの完成は近いと見なされており、その上で人道法の担保を必要とするのであれば、研究開発、調達、運用の、ライフサイクルのどこかで規制をかけることが適切なのか議論されている。
このように、無人兵器システムを巡る状況は、現実と将来に対する見通し、現在の法的規範と、技術開発によって不適合となる法的措置などが混在している状況にあるのである。
議論の見通し立たず
CCWや国連では、現在の法的規範を基本として、不足部分を新たな禁止または規制措置で補足しようとしている。しかし、技術開発の状況や、ウクライナやガザ戦争で見えた「新しい戦争」を考えると、国際社会が禁止や規制ではなく、開発促進を図る方向に向くのは、歴史的に見ても自然なことなのかもしれない。ただ軍備管理・軍縮では、規制することに対する戦略的な必要性が認識される時、各種措置の実現が可能になる。
これまで国際社会は、この問題において倫理面の議論を中核としてきた。他の方法論が見つかるのであれば、それを重視することは不思議なことではない。ロシアが主張するように、不拡散は一つの方法論なのかもしれないが、これはグローバルサウス諸国にとっては受け入れられない方法論だろう。
残念ながら、明確に見通しが立たないまま、議論は続いていくのであろう。
拓殖大学国際学部教授 佐藤 丙午(さとう・へいご) 1966年岡山県生まれ。拓殖大学国際学部教授、海外事情研究所所長。99年、一橋大学(博士)。93年より防衛庁防衛研究所助手、主任研究官を経て、2006年より拓殖大学海外事情研究所。13年より国際学部、23年より海外事情研究所所長。専門は国際関係論、安全保障論、アメリカ政治外交。
(Kyodo Weekly 2025年3月17日号より転載)