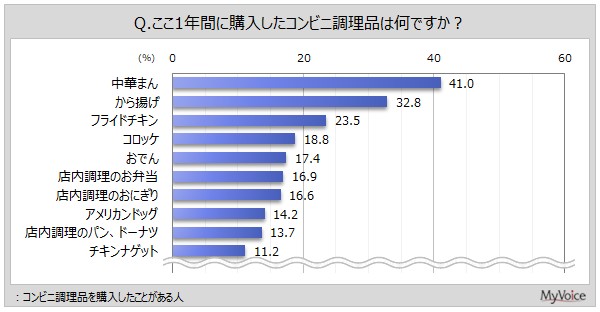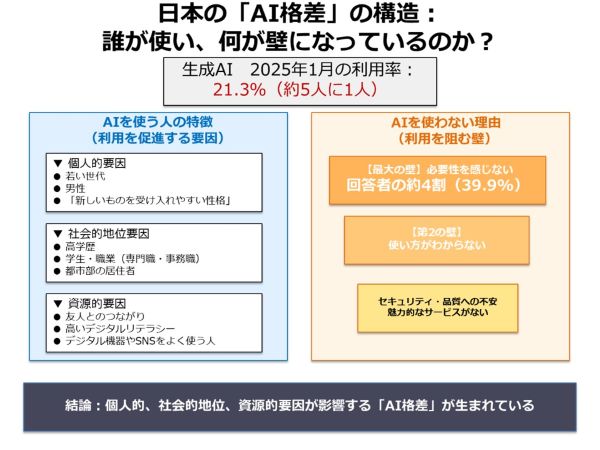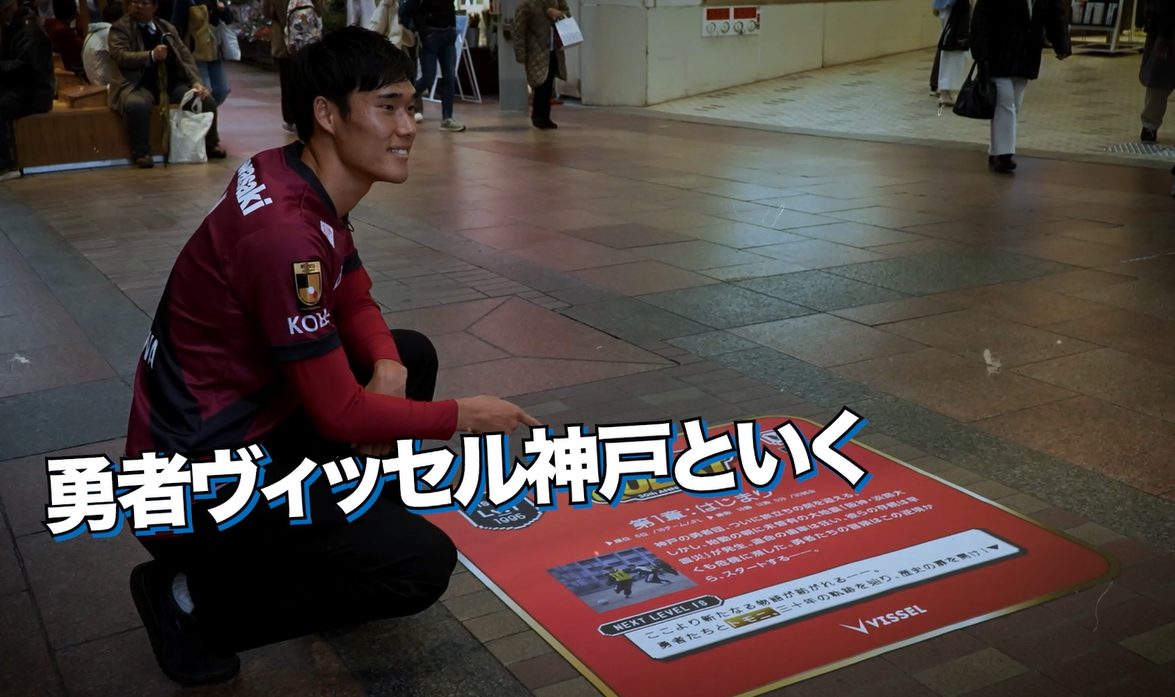9月1日「防災の日」に知っておきたい通信の進化 サイエンスアーツが進める“災害対応DX”

9月1日は「防災の日」。102年前に関東大震災が発生したこの日に合わせ、巨大地震を想定した総合防災訓練が各地で実施された。災害時にさまざまな場面で必要になってくるのが迅速で確実な情報共有。なかでも命や安全に直結する救助・医療現場では不可欠だ。サイエンスアーツ(東京)は、災害時の通信インフラを革新する同社の3つの取り組みを発表している。その核となるのが、ライブコミュニケーションプラットフォーム「Buddycom(バディコム)」。 Buddycomは、スマートフォンやタブレットにアプリをインストールしてトランシーバーや無線機のように使用できるサービスだ。
大阪府茨木市消防本部では、全国の消防本部として初めてBuddycomを主連絡手段として正式採用した。同市は山間部が多い地形のため、一部で消防救急デジタル無線の不感地域が多くあり、消防指令室と消防隊・救急隊での情報共有が困難な状態が続いていた。しかし導入後は不感地域でも安定した通信が可能となり、音声の即時録音・再生や、位置情報による隊員の把握、さらには映像を通じた状況確認といったリアルタイムかつ多角的な情報伝達も実現。災害対応の迅速化と安全性の向上に大きく貢献している。
また、神奈川県海老名市消防本部は、全国の消防本部では初めて、通信インフラが遮断されやすい大規模災害時でも有効な衛星通信「Starlink(スターリンク)」を活用したBuddycomの運用を開始した。現場の担当者は、能登への災害派遣での経験から「災害時に通信が絶たれる恐れがある」という危機感が高まったことが今回の導入のきっかけとなったと話す。Starlinkの採用は、災害協定を結ぶ県外市町村との広域連携も可能にし、消防行政における通信の在り方を大きく変える一歩となりそうだ。 Buddycom とStarlinkの組み合わせは、迅速で確実な対応が求められる消防・医療現場での情報共有を次のステージに引き上げたと言えよう。

それが確認できそうな実証実験が、9月5日・6日に青森県で行われる。内閣府主催の「令和7年度大規模地震時医療活動訓練」である。日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(M9.1、最大震度6強)を想定しており、広域災害に対応する医療体制の検証と強化が目的だ。県の災害派遣医療チーム(DMAT)訓練では、固定回線と携帯電話網が断絶したことを想定し、Buddycomと Starlink を活用した実証試験が行われる。両者を組み合わせることで、病院・調整本部・救護拠点間の多方向通信を確立。災害時の医療現場における情報共有のスピードと精度を大幅に高めることが期待されている。
通信が命を守る時代において、サイエンスアーツ社の取り組みは、災害時における「情報の断絶」を防ぐための新たなモデルケースとなっている。BuddycomとStarlinkの連携は、自治体・医療機関・消防機関にとって不可欠なインフラとなりつつあり、国家レベルで考えていかなければならない大きなテーマになりそうだ。