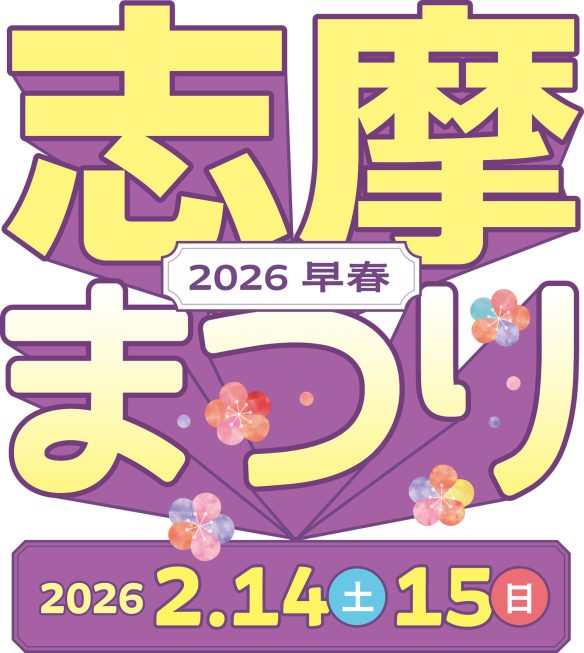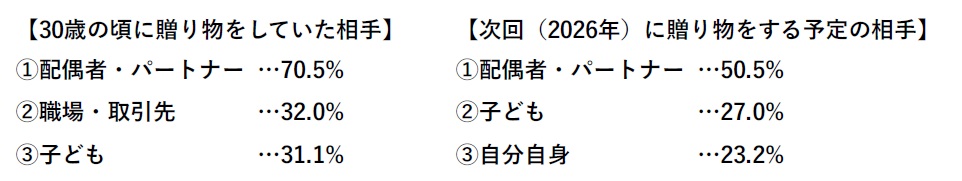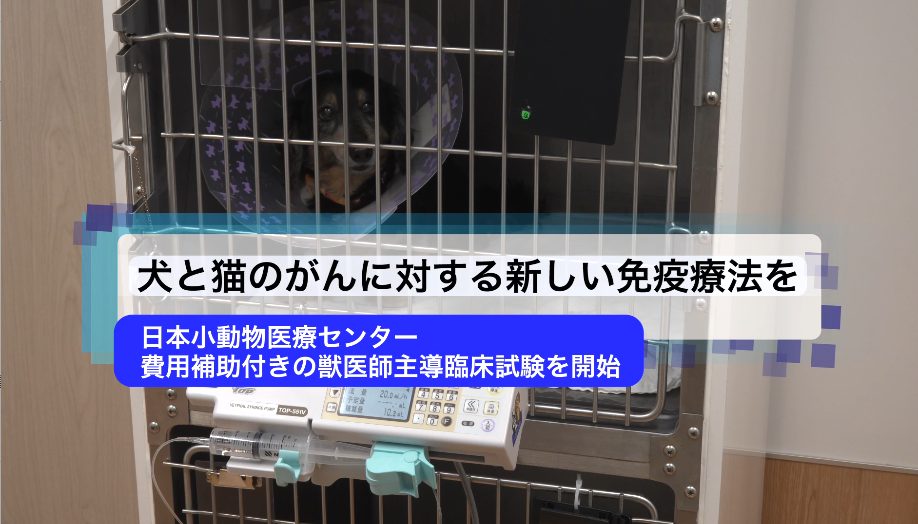「特集」国際刑事裁判所(ICC)と政治化 ―国際機構は政治的であらざるべきか

越智萌
立命館大学国際関係研究科 准教授
はじめに
強い者による犯罪の責任を追及しようとするとき、巨悪と闘う刑事司法の試みは頻繁に強大な圧力にさらされてきた。イソップ寓話(ぐうわ)「おおかみときつねとさる」(ヨゼフ・ラダ『きつねとおおかみ』=1971年)では、裁判官に指名された猿が、狐と狼の報復を恐れ、被害者である羊に罪を着せる。裁判と力との関係のままならなさは、司法制度の歴史にまとわりついてきた問題である。マフィアや暴力団による犯罪の取り締まりのため、歴史上多くの捜査官が殉職し、裁判官が脅迫されてきた。世界的な規模での刑事司法の取り組みとその反発の例として位置づけられるのが、近年の国際刑事裁判所(ICC)に対する米国による制裁措置であろう。
2025年2月6日、米国第2次トランプ政権は、「ICCへの制裁の実施」という大統領令を発した。制裁の理由として米政権は「ICCが米国と緊密な同盟国であるイスラエルを標的とした、不正で、根拠のない行動を行っている」ことをあげている。20年、第1次トランプ政権下で行われた最初のICC制裁実施の際、ポンペオ国務長官(当時)は、ICCを「法的機関を装った、責任を取らない政治的機関」と呼んだ。ICCの活動を「政治的」と呼ぶ動きは広まっている。25年4月、ICC逮捕状の対象となったイスラエルのネタニヤフ首相の訪問を受け入れたハンガリーのオルバーン首相は、ICCが「政治的」になったことを理由に、ICCからの脱退を推し進めるとした。
ICCは、近年批判されるように、政治的なのであろうか。政治的であるとして、それは悪いことなのだろうか。本稿では、国際機構が政治的であるべきではないという議論を振り返った上で、ICCのこれまでの活動における政治性について検討し、ICCはどうすればいいのかについて私見を述べたい。
国際機構の脱政治化
マリーケ・ルイス、ルシル・マルテンス『なぜ国際組織は政治を嫌うのか』(21年)は、国際機構が自らの内部における政治性を最小化し、隠し、さらには消し去るような「政治的」プロセスに着目した。彼らは、国際機構が自らは政治の外にあり、非政治的であると見せる政治的なプロセスを「脱政治化」と定義して、どのような脱政治化の実践がとられてきたか、そしてそれらがどのような意味を持つかについて分析した。この研究によれば、国連などの実践では、専門性を主張し技術的な解決策を示すことや、批判ではなく情報提供という形式で解決策を「おすすめ」することなどで中立性を表そうとすること、時間を浪費して忘却をもたらす、といった戦略がとられている。また、脱政治化は国際機構を機能主義的に理解する立場に親和的で、正当性を独占することができるだけではなく、責任逃れをすることに直結していると分析されている。この研究の重要な点の一つは、こうした国際機構の脱政治化の実践の背後に、またはその結果として、政治的であることが悪いことのように位置づけられているということに気づかされる点である。ルイスとマルテンスはこれを、「政治性の烙印(らくいん)」と呼ぶ。
確かに、国際機構、特に国際公務員で構成されるその事務局は、政治性を排した官僚機関として構想された。国際連盟を設置する際、事務局の構想を請け負ったのは、イギリスの政治家であるエリック・ドラモンド伯爵である。マックス・ウェーバーの官僚論を前提に、ドラモンドは、国際平和のために、各国の間を取り持つ事務を行う国際公務員は、どの国からも独立し、非政治的で、効率的でなければならない、という「連盟マインド」を持つ人であるべきだとした。ドラモンドは、国際連盟の初代事務局長となり、この思想は現代の国際機構の脱政治化を推進する思想的土台となっていると思われる。
しかし、果たして国際機構が政治性を持つことは、常に望ましくないことなのだろうか。またそれは、国際機構により、または国際機構の機関により異なる可能性はないだろうか。
ICCは脱政治化しているか
ICC検察局公認のオンライン議論プラットフォームであるICC Forumでは、25年6月から半年の期間、「どのような方法で、どの程度、ICCは政治的な機関であるのか?」という問題について議論が進んでいる。その中で、米国インディアナ大学デビッド・ボスコ教授は、ICCは活動開始当初より政治性が少なくなっており、それは問題であると主張する。
ボスコ教授は、ICCにおける政治性のレベルを四つに分類する。まず、「非政治的な裁判所」とは、政治的考慮を完全に避ける。次に、「実践主義的な裁判所」とは、国家による支援の程度や訴追の成功可能性など、限られた範囲で政治的状況を考慮する。第3に、「戦略的な裁判所」は、関係国との良好な関係を維持するため、それらの国の国益を訴追戦略に含むといった、より広い目的で政治的考慮を行う。最後に、「捕らえられた裁判所」とは、特定国の利益のために活動する。この分類に従えば、ICCは「戦略的な裁判所」から「非政治的な裁判所」に変化したと主張する。
確かにICCは、活動開始当初は、超大国が関わる事件に「首を突っ込む」ことを避けてきた。ICC活動初期の00年代の事件は、締約国が自国内で起きた事件について自ら捜査を依頼したものばかりであった。また、イラクにおける多国籍軍のメンバーである英国人兵士による殺人と拷問の事案について、当時の主任検察官であったルイス・モレノ=オカンポは、「重大性が十分でない」として捜査を開始しなかったことが批判された。しかし、第2代主任検察官のファトゥ・ベンソーダに代わった10年代以降は、検察官の職権での捜査開始の事例が増えている。また、第3代主任検察官のカリム・カーン氏になったあと、ロシア・ウクライナ戦争といった国家間の武力紛争が生じ、紛争継続中の事案について捜査し逮捕状を請求するといった実践が見られるようになった。
被害者や目撃者からの通報がある場合や締約国からの付託がある場合、捜査を継続する十分に合理的な理由がないなどの事情がない限り、ICC検察官は捜査を行うことが法定されている。また犯罪を疑いに足る合理的な根拠がある場合でその他の事情がない場合には、逮捕状を請求して特定事件について訴追活動に移ることが裁判所規程上期待されている。その意味では、通報や付託があり、証拠が集まった段階では、逮捕状を請求することが「非政治的」な行動なのであり、逆に、大国や友好国の顔色を窺(うかが)って訴追に踏み切らないことは、「戦略的」な行動だととらえられるのである。
ICCはどうすればいいのか
「捕らわれた裁判所」は言語道断であるとして、「非政治的」でも「戦略的」でも批判を受けるとすれば、中庸的な「実践主義的な裁判所」を目指すべきなのだろうか。
ICC所長である赤根智子裁判官は、自著『戦争犯罪と闘う』(25年)で、第1次トランプ政権の制裁の理由となったアフガニスタンについての捜査開始許可決定に触れている。赤根裁判官が入った予審第2部は、検察官からの捜査開始許可申請に対し、正当な法的利益がないとして不許可とした。相当前に起きた事件が多く、実際に捜査の対象にできそうな事件が少なかったこと、捜査に協力する国や団体がなく捜査の進展する見込みがない、といったことがこの決定の理由である。他方で、上訴審ではこの決定は覆されて捜査は開始され、米国によりベンソーダ主任検察官らが制裁対象とされた。予審部の決定が大国に配慮したものであるという証拠はないが、他方で、捜査・訴追の実践的な実現可能性という観点から、政治的状況を分析した実践主義的な判断であったといえるだろう。
他方で、本稿執筆時点で継続中の国際的武力紛争であるロシア・ウクライナ戦争やイスラエル・ガザ紛争はどうであろうか。ロシアは、自国の大統領と側近らに逮捕状を出した赤根裁判官と主任検察官らを指名手配した。米国は、同盟国であるイスラエルの首相らに逮捕状を出した裁判官らと主任検察官に制裁を課した。このような状況下では、関係国からの有効な協力が得られないため、逮捕状を出したとしても実践的ではない、と論じることは可能であろう。
しかし、この間の活動が示すのは、ICCの役割は、被疑者を訴追し個人責任を追及する、という基本的な刑事裁判だけではないことである。国際社会がウクライナから連れ去られた子どもたちを案じ、その奪われた時間や人格についての被害への責任を、これから先、被疑者らが死去するまで追及することが約束されているのは、ICCの逮捕状発付という、制度のスタートボタンが押されたからである。ガザで食料や水を奪われ、戦争の道具として命をもてあそばれた人々への償いを、この先の未来において、忘れることなく、責任ある人たちに問うていくというレジームを発動させたのも、ICCの逮捕状の発付である。
実践が伴わない刑事訴追には、その効果を上回る弊害があるかもしれない。ただしそれは短期的に見た結論であり、法の強みは、一個人の人生をも軽く超えて、未来において執行されることが予定されるところにある。その意味では、政治性という議論を超えたところに、国際刑事司法は鎮座しているのかもしれない。狐の知恵や狼の牙におびえて、被害者の羊に辛酸をなめさせるような世界は、終わりへ向かっているように思える。
立命館大学国際関係研究科 准教授 越智萌(おち・めぐみ) 大阪大学(学士(言語・文化)、修士(国際公共政策)、博士(法学))、ライデン大学(オランダ)(法学修士)。京都大学白眉プロジェクト特定助教、2020年から現職。著書に「国際刑事手続法の原理―国際協働におけるプレミスの特定」(信山社、2022)、「国際刑事手続法の体系―『プレミス理論』と一事不再理原則」(信山社、2020)、「だれが戦争の後片付けをするのか—戦争後の法と正義」(筑摩書房、2025年)
(Kyodo Weekly 2025年7月28日号より転載)
編集部からのお知らせ
新着情報
あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター