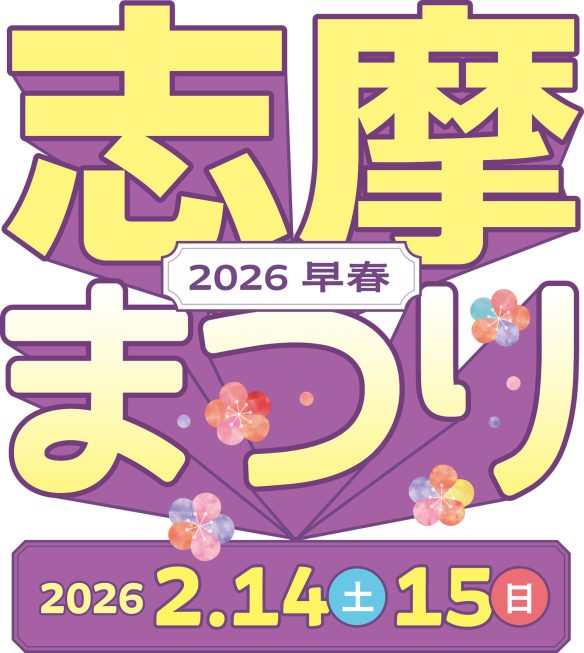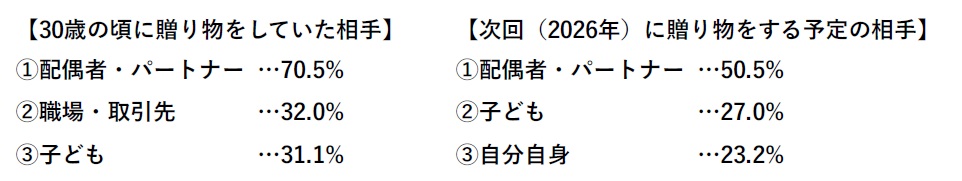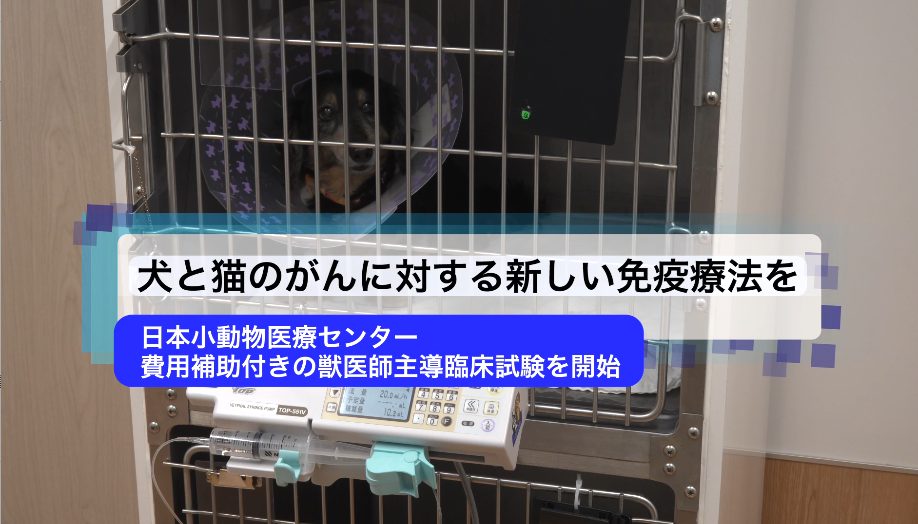「特集」ゲームチェンジの行方 異次元のトランプ2.0政権 ~ポスト・パックス・アメリカーナを見据えて日本に求められる対応~

簑原俊洋
インド太平洋問題研究所理事長
将来の歴史家は、ドナルド・トランプ大統領がホワイトハウスに返り咲いて2期目の就任日となった2025年1月20日を、どのように記憶するのであろうか。いずれこの日は、米国の衰退が決定的となり、パックス・アメリカーナ(米国の力による平和)の終焉((しゅうえん)が一気に加速した原点として位置付けられているかもしれない。
このような懸念に基づき、昨年の選挙戦の火蓋(ひぶた)が切られた直後からことあるごとに、筆者は「トランプ2・0は1・0と比較にならないほど国際政治に波乱をもたらし、日本を含む価値を共有する国家に対して幾多の苦難をもたらすであろう」との警告を発した。さらに、事前の備えは焦眉の急で、「価値を共有するEU(欧州連合)諸国、韓国、カナダ、オーストラリアなどと密接に連携し、国ごとのちぐはぐな対応ではなく、各国が足並みを揃(そろ)えて面として米国に対応できるような体制を整えることで国益を担保できる」という考えのもとに、日本による俊敏かつ能動的な対応も訴えた。しかしながら、当時の日本ではこうした危機感を持つ者は少数で、未知数のカマラ・ハリス氏よりも、すでに1期を経験して「手の内を熟知している」トランプ氏の方が望ましいという意見が支配していた。
この見解に対して、過去の成功体験に基づく根拠なき楽観論は必ず挫折すると筆者が反論しても、ハリス氏はマイノリティーの女性候補であるがゆえに、ジョー・バイデン氏よりさらに踏み込んでLGBTQなど性的少数者や同性婚の問題で日本に圧力を加えてくるのは必至だから、日本にとってはトランプ氏の方がはるかにマシだと悉(ことごと)くはねのけられた。
しかし、「手の内を熟知しているから問題ない」との見解が誤謬(ごびゅう)でしかなかったのは、トランプ氏の2期目の就任初日から一目瞭然となった。1期目での経験のみならず、下野していた4年間に研ぎ澄まされた目的意識を有した政策集団で周囲を固めたトランプ大統領は、目を見張るスピードで果敢に動いた。それは8年前とは似ても似つかぬ様相で、政権発足から半年経ってもまだ埋まらないポストが多数あった1期目とは打って変わり、このたびは主要閣僚ポストの人選は出だしからほとんど固まっていた。しかも、その陣容は明らかに〝能力〟よりも〝忠誠心〟に重きを置いた登用であった。
米国史上で過去に1回しか例がない非連続の2期目という形をもって権力の座を奪取したトランプ氏は、この勝利によって自らの正当性が立証されたと確信するとともに、トップ・リーダーとして彼の自信もはるかに増大した。これこそが、米国を自らが理想とする国家を一気につくり直そうとするトランプ氏の原動力の淵源だ。
実際、彼は初日だけで40前後の行政命令と200を超す行政人事令に署名し、さらに就任からわずか100日間で国家非常事態法を8回も発令した(通常は8年で10回前後)。ここまで短期間で米国を一変させた大統領は、大恐慌真っただ中に就任したフランクリン・ルーズべルト氏以来である。このように、2期目のトランプ政権は1期目とは全く別物として見なされるべきであり、行政府が立法府を牛耳っているートランプ氏の政策の目玉であった「大きくて美しい法案」が難なく連邦議会を通過したことからもこれは明白であるー現実を踏まえれば、少なくとも中間選挙までは彼はさして抵抗に遭遇することもなく、思いのままに政策を実現できる状況にある。さらに、従来の慣行を無視して、彼が司法省及びその下部組織の連邦捜査局(FBI)を完全に掌握して自らの意のままに動く組織としている事実を加味すれば、とてつもない政治力を手に入れたことが分かる。
トランプ氏はもはや完全に政治的エスタブリッシュメント(既存の支配層)としての地位を確立したため、かつての政敵の多くが転向し、彼の側近として政権を支えている。この好例が、J・D・バンス副大統領やマルコ・ルビオ国務長官である。その他の側近と同様に、彼らは大統領の号令に合わせて躊躇(ちゅうちょ)なくアクセルを踏む。他方、1期目のジェームズ・マティス国防長官やレックス・ティラーソン国務長官のようにブレーキ役を果たす者の存在は、政権2期目では皆無だ。
この事実は、トランプ氏が1期目から希求していた軍事パレードが6月14日、ついに実現したことからも明らかである。米国においてあまりなじみのない軍事パレードが、米陸軍創設250周年記念と銘打って、大統領の79歳の誕生日と同日に首都ワシントンで行われた。ただし、軍楽隊が大統領に対して「ハッピーバースデー」を演奏したことからも、パレードの目的がトランプ氏の要求に応えるものであったのは間違いない。
2期目のトランプ大統領の特徴として、彼の元来の仕事が不動産業だったためか、異様なまでに米国領土の拡大に情熱を注いでいることが挙げられる。彼は、米国にとっての戦略的重要性を根拠に、パナマ運河とグリーンランドの支配、さらには隣国カナダを51番目の州として併合することを度々言及している。このように、今までの常識と規範を悉く打ち砕き、相手が価値を共有する国家であったとしても全く容赦しないトランプ氏の強硬な姿勢は、今までの米国の行動規範から大きく逸脱している。もっとも、彼の領土拡張政策は進展しておらず、いまだに口にはするものの、力ずくで実行する気配は今のところない。
とはいえ、こうした異次元の対応は、米国の対日政策でも顕著に現れている。安全保障の観点からは、対GDP(国内総生産)比で5%の日本の防衛支出の大幅な増加を求め、要求に応じない場合は日本の防衛に尽力できないかもしれないとの態度を平然と示す。他方、通商の観点からは、トランプ氏が7月7日、貿易相手国・地域別に課す「相互関税」について、8月1日から日本には25%をかける方針を示した。4月発表当初の24%を1%分上回る。相互関税の上乗せ分の停止期限を7月9日から8月1日に延長する大統領令にも署名した。トランプ氏は日本の市場開放を要求し、応じれば関税率変更を検討するとして、新たな期限までの譲歩を迫るなど「脅しのディール」をほのめかす。
トランプ政権の政策の特に厄介なところは、各国に課す関税率に違いを設けることで、国家同士の結束の防止を図り、分断を促すための道具として活用していることだ。その背景には、トランプ大統領と彼の取り巻きは、世界においてカオスが生じることで米国はより多くの利益を甘受できるとの考えがある。そのため、世界を混乱させる政策を矢継ぎ早に打ち出すのみならず、先進国に対してはポピュリスト的な愛国主義右派勢力の伸長を後押しすることで、トランプ政権とより親和性の高い政府の出現を促すだけでなく、民主主義自体の後退さえも企(たくら)んでいるように見える。
こうした同盟国に対するなりふり構わぬ姿勢は、中国に千載一遇の好機をもたらすことになる。つまり、中国は同盟が揺らいでいる隙を狙って西側諸国に接近することで、それぞれの国家の対中経済依存を一気に拡大できる。当然、日本も標的であり、中国はすでに通商面で対日融和姿勢を取り、東京電力福島第1原発の処理水放出を理由に一昨年の8月から全面停止していた日本産水産物の輸入を先月末に一部再開に踏み切った(ただし、福島、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、長野、新潟の10都県の水産物は対象外)。また、日本のメディア関係者に聞いたところによれば、中国当局の接し方は以前と打って変わって友好的になったという。とはいえ、したたかな中国であるだけに、日中の経済連携の強化を建前に日米同盟の弱体化を目指していると考えるのが合理的だ。事実、安全保障の領域では、日本に対する融和的な姿勢はなく、同国のヘリコプターが尖閣諸島の上空を領過し、さらに先日は空母2隻が太平洋にまで出没して軍事演習を行って日本を威嚇している。
確かに米国国内は政治的に分断されているが、厳しい対中姿勢は超党派的であり、多くの米国民は中国に対して強い警戒心を抱いている。それゆえ、将来的には米中関係がさらに悪化し、相互の報復合戦になる可能性は否定できない。加えて、中国の習近平国家主席も米国に屈服したという印象を持たれないようにする必要があるため、米中対立の回避は至極困難となる。そして、両国関係が緊張していく過程で、米国が中国のサプライチェーン(供給網)から同盟国を引き離す圧力を増していく可能性は十分に想定できよう。そうなれば、伝統的安全保障は米国に頼りつつも、経済安全保障では中国に依存している日本のような国家は、苦境に立たされるのはいうまでもない。このように米国の行動が今までの規範から大きく逸脱して〝変数〟となった時代において、日本はいかにして生存を担保するのか。
筆者の考えでは、まず急いで構築する必要があるのは、米国以外の国々との安保枠組みである。主対象となるのは価値を共有する国家だが、その中でもEU諸国と海洋ASEAN諸国(海洋域での利権を有し、中国を脅威として見なしている東南アジアの国家)との連携強化は特に重要である。さらに、Quad(クアッド:日米豪印)の安全保障に特化した枠組みであるSquad(スクアッド:インドの代わりにフィリピンが参画)も増強したい。必然的に、日本から最も近い韓国と台湾との連携も求められるが、政治的な理由でこちらのハードルは高くなる。同様に、北大西洋条約機構(NATO)との防衛交流もIP4(日韓豪ニュージーランド)に固執することなく、準同盟関係にある豪州と共に、あるいは日本単独でもさらに活性化させなければならない。
このように、今後の動乱期において日本の生存のために安保枠組みの多角化は必須であるものの、これだけでは心もとない。どうしても最後の後ろ盾として米国が必要だ。では、いかにして米国を日本につなぎとめておくのか。それは、現在の日米同盟を双務的な形に改めることが鍵となる。米国を防衛する義務を日本が持つようになれば、日米安全保障条約は大幅に強化される。結局のところ、同盟の強さを決めるのは信頼である。すなわち、片務的な同盟関係よりも双務的な同盟関係の方が、相互信頼は飛躍的に拡大する。さらに、安全保障に対する日本の本気度をトランプ政権に強く印象づけることになり、その結果、関税問題での譲歩も期待できる。
いずれにせよ、米国がMAGA(米国を再び偉大に)の掛け声の下で自らの狭い国益の追求のみに邁進(まいしん)するのであれば、日本に対する他の自由主義陣営の期待は自ずと高まる。これに応えるべく、日本が外交と安全保障政策を能動的に展開させ、米中のような超大国ではないにせよ、大国としてふさわしいリーダーシップを発揮していくことこそがポスト・パックス・アメリカーナの時代を乗り切るために必要な覚悟と気概ではなかろうか。
インド太平洋問題研究所理事長 簑原俊洋(みのはら・としひろ)1971年生まれ。米カリフォルニア州出身。カリフォルニア大デイビス校卒。神戸大大学院博士課程修了。政治学博士。インド太平洋問題研究所理事長、神戸大大学院法学研究科教授。専門は日米関係、国際政治、安全保障。『アメリカの排日運動と日米関係-「排日移民法」はなぜ成立したか』(朝日新聞出版、2016年)、『大統領から読むアメリカ史』(第三文明社、2023年)などの著書がある。
(Kyodo Weekly 2025年7月21日号より転載)
編集部からのお知らせ
新着情報
あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター