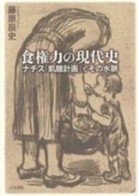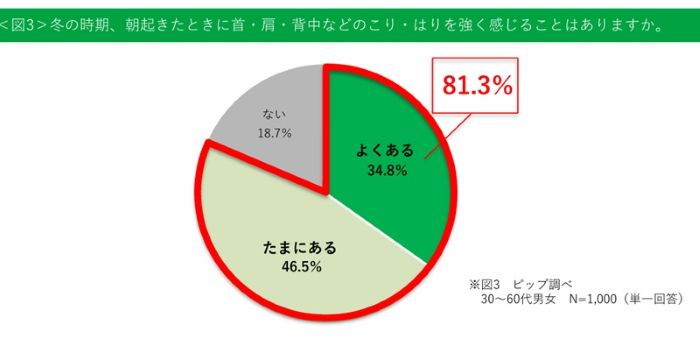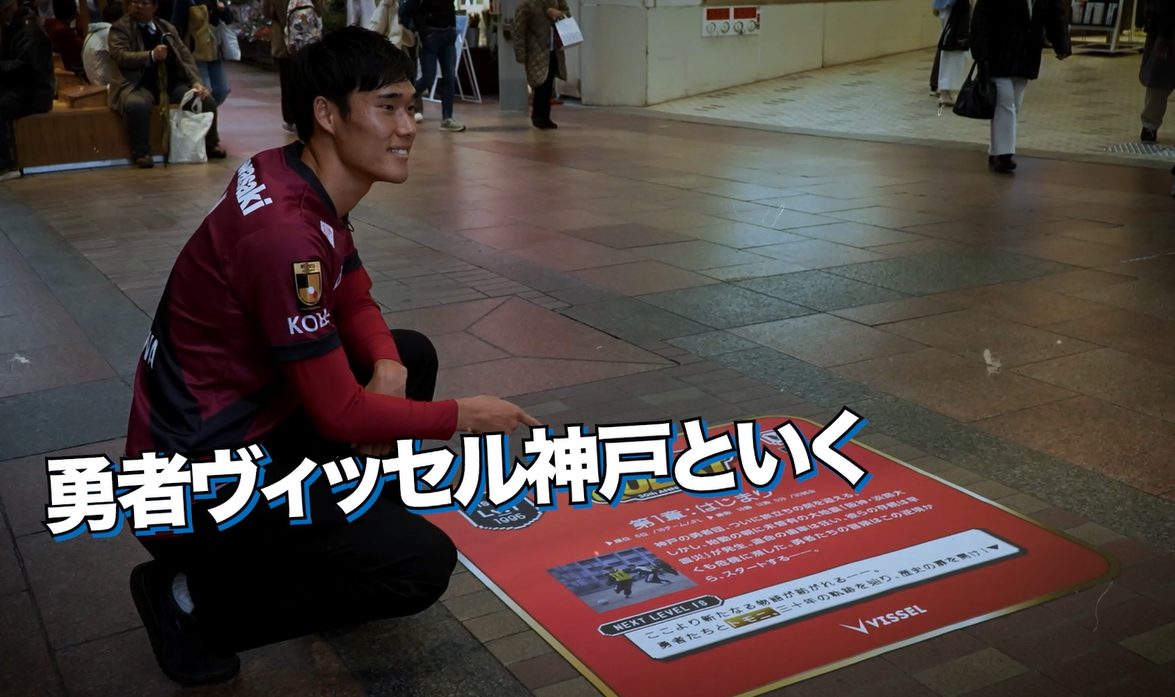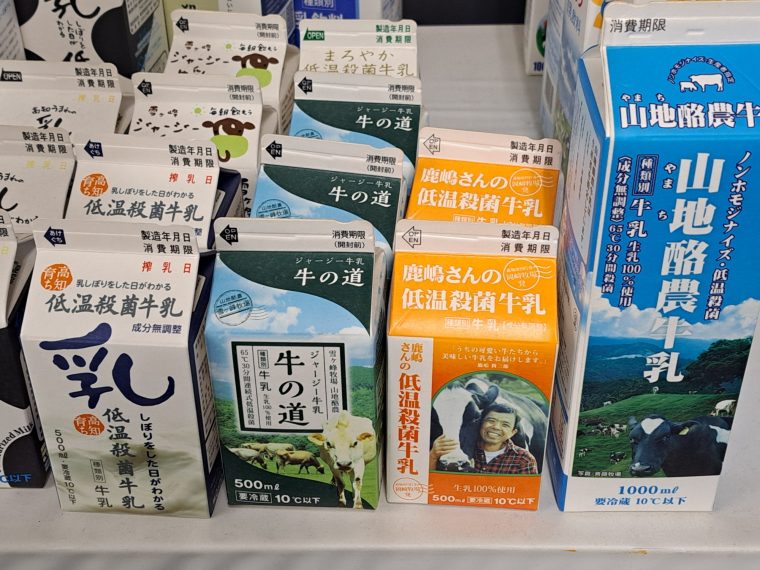軸足定まらぬ農業政策 高市内閣が発足 アグリラボ編集長コラム
高市早苗内閣が発足した。初の女性首相として「画期的」(米ニューヨークタイムズ紙)と内外で期待が高まっている。ただ、少数与党であることに変わりはなく、日本維新の会による閣外協力に支えられた不安定な政権だ。石破茂前首相が9月7日の退陣表明で「強い思い」と強調した「増産への転換」の軸足は定まらず、農政が迷走する恐れもある。
農相には、農水官僚出身の鈴木憲和復興副大臣が就任した。東大法学部を卒業、2005年に入省、消費・安全局総務課総括係長だった12年に退官。同年12月の衆院選に山形2区から出馬し、環太平洋連携協定(TPP)交渉への参加反対を公約に掲げて初当選した。
党農林部会長代理だった16年11月10日には、TPP承認案・関連法案の衆院本会議採決で投票を棄権、賛成票を投じる党議拘束に造反したこともある。地盤とする米どころの山形県では「筋を通した」と評価され、当選5回。自民党の若手議員の登竜門である青年局長なども歴任している。趣味は「うまい米探し」というほど米政策に通じている。
早速、22日の就任会見で「需要に応じた(米の)生産が原理原則」と述べ、小泉進次郎前農相が「過剰局面をつくらなければ(米価は)安定しない」と展開してきた「ジャブジャブ路線」を軌道修正する姿勢を明らかにし、「米議員」の本領を発揮した。
一方、連立を組む日本維新が先の参院選で示した公約「維新八策2025」の政策は、自民党農林議員との主張とは、まったく相いれない。例えば、米価を下げるためミニマムアクセス(最低輸入量)を超える輸入に課せられている高率関税の大幅引き下げや、株式会社による農業分野への参入促進、地域で総合事業を営んでいる農業協同組合(JA)からの金融事業の分離などの規制改革が含まれている。
ただ、この維新の公約は、政権発足前に自民党と合意した政策協議にはまったく反映されていない。12項目の施策の7番目に「食料安全保障・国土政策」とあり、植物工場や陸上養殖など施設型食料生産設備に対する大型投資の促進などが盛り込まれているが、明らかに農政の優先度は低く、直接支払などの本筋には言及がない。要するに空っぽだ。
これは、調整が難しい農業政策を棚上げにすることで両党の思惑が一致した結果だ。鈴木農相の起用の本質は、「農業政策が維新の主張に傾くかもしれない」という農林議員の懸念を押さえ込み、次の衆院選で農村部の離反を回避するためのバランス人事だ。
官邸、党(自民党農林議員)、維新、それぞれの農政の方向性はばらばらだ。高市政権が本気で石破政権の「増産路線」を転換するのかも疑わしい。米価の高騰が続けば、場当たり的な対策が検討されるかもしれないが、次の選挙まで農業政策が正面から論じられることはないだろう。その後も不安定な政権が続けば、農政は迷走する恐れさえある。
(共同通信アグリラボ編集長 石井勇人)