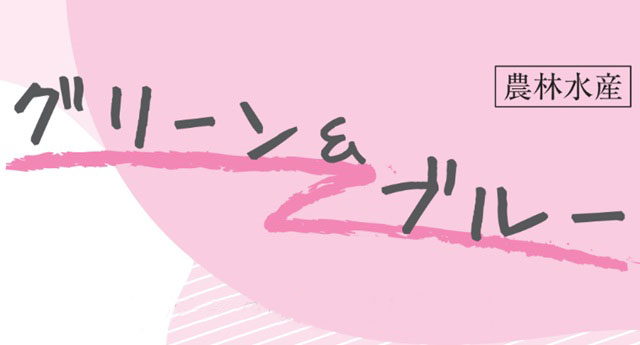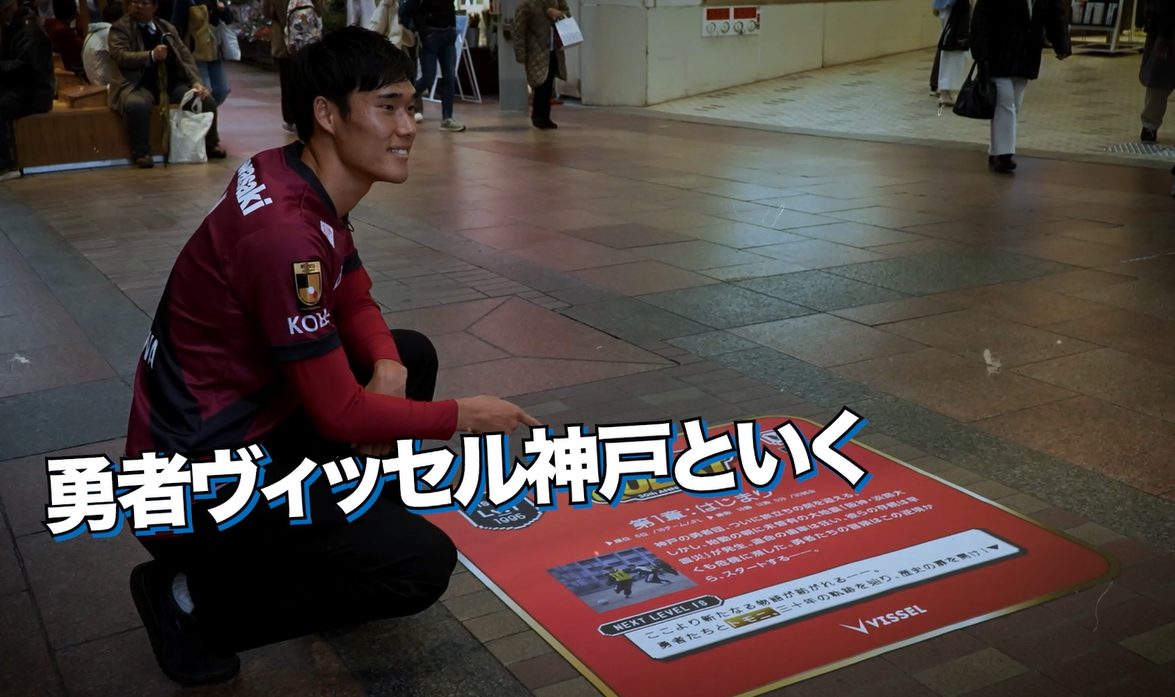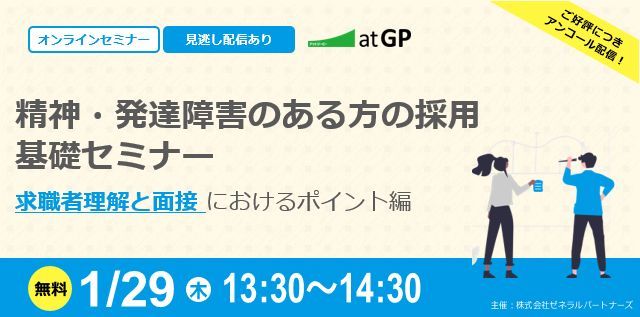バーナード・マクマホン監督「この映画はレッド・ツェッペリンのファンのために作ったというよりも、100年後の人たちが見ても楽しめるかどうかというのがとても大切な要素でした」『レッド・ツェッペリン:ビカミング』【インタビュー】
この映画では、彼らのデビューから世界で一番ビッグなグループになっていくまでの過程を見ていただくわけですが、デビュー当時は、メディアに嫌われ、自分の国ではあまり受け入れられず、レコード契約のためにわざわざ遠く離れたアメリカまで行かなければならなかった彼らが、どれだけ偉大なグループになっていったのかを見ることによって、映画館から出ていく時には、彼らに共感したり、これから自分は何をする必要があるのか、どう生きていけばいいのかを学ぶヒントが得られると思います。そして、この映画では7分間の曲もノーカットで流れます。アメリカの観客が初めて彼らのパフォーマンスを見た時に、驚きと共にすごい拍手で迎えたわけですが、その感覚を皆さんにも味わってほしいと思いました。
-この映画は、音と映像の再現というか修復が見事でしたが、デジタルではなく割と原始的な方法で修復したと聞きましたが。
そこに気付いてくださってありがとうございます。過去にさかのぼる旅をするような気分で見ていただきたいと思ったのがその理由です。つまり、それはエフェクトなどがあまり使われていないモノラルの世界から始まります。例えば、当時のスタジオの中で録られた音は、今では聞きたくても聞けません。それを最高のプレイバックの状態で観客に提示したいと思いました。レッド・ツェッペリンが最初のアルバムを作った68年はまだモノラルだったものが、2枚目の時にはステレオになり、それがさらに進むと、より広がりのあるステレオサウンドになっていく。モノラルからステレオ、そして映像もモノクロからカラーへという時代の変遷を経ているわけです。また、実際にレッド・ツェッペリンのファンでなくても楽しめるという意味では、音の面白さがあります。例えば、レッド・ツェッペリンのファンの方がレッド・ツェッペリンを知らない奥さんをこの映画に連れて行ったとしても、奥さんが「あなたが何で好きだったのか何となく分かるわ」とか、「私も好きになったわ」というような反応をしてもらえると信じています。
-確かに昔自分が聞いたレコードの音を思い出しました。
そうした音の違いに気付いてくださってありがとうございます。そもそもレッド・ツェッペリンの音楽を知らない人たちにも彼らのオリジナルの音を感じてもらうことを目的に作ったので本当にうれしく思います。
-日本のファンに向けて一言お願いします。
ジョン・ボーナムが詳細な説明をしている生前のインタビューは、オーストラリアと初めて日本にツアーをした時のものが収録されています。これは大変貴重なものです。それから日本の皆さんにお伝えしたいのが感謝の言葉です。僕らの映画の作り方を理解してくれたのは日本の映画会社だけでした。ほかの多くの映画会社は、例えばドラッグなど、もっと下世話なところにフォーカスを当ててほしいというような感覚だったので、日本の映画会社の支えがなかったら、この映画を私たちの撮りたい方法で撮ることはできなかったと思います。ですから本当にとても感謝しています。
(取材・文/田中雄二)

(左から)バーナード・マクマホン監督、プロデューサーのアリソン・マクガーティ