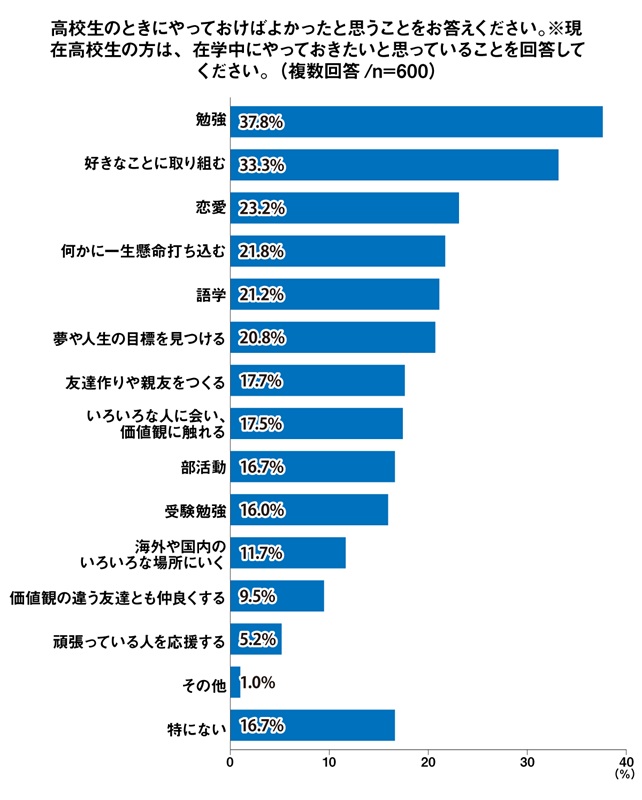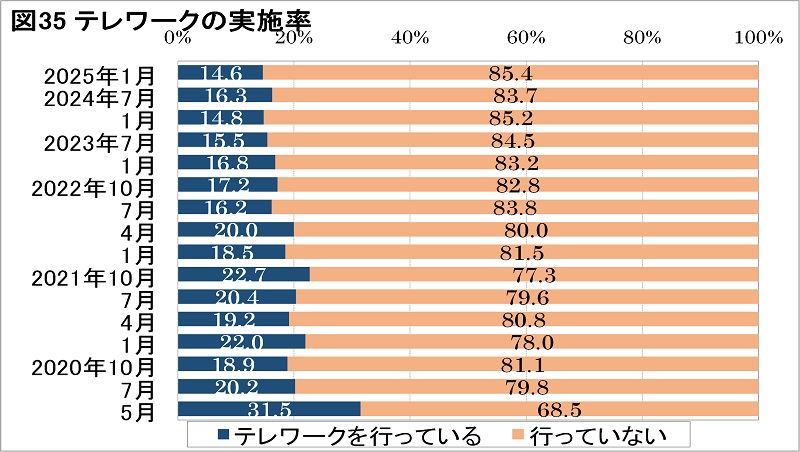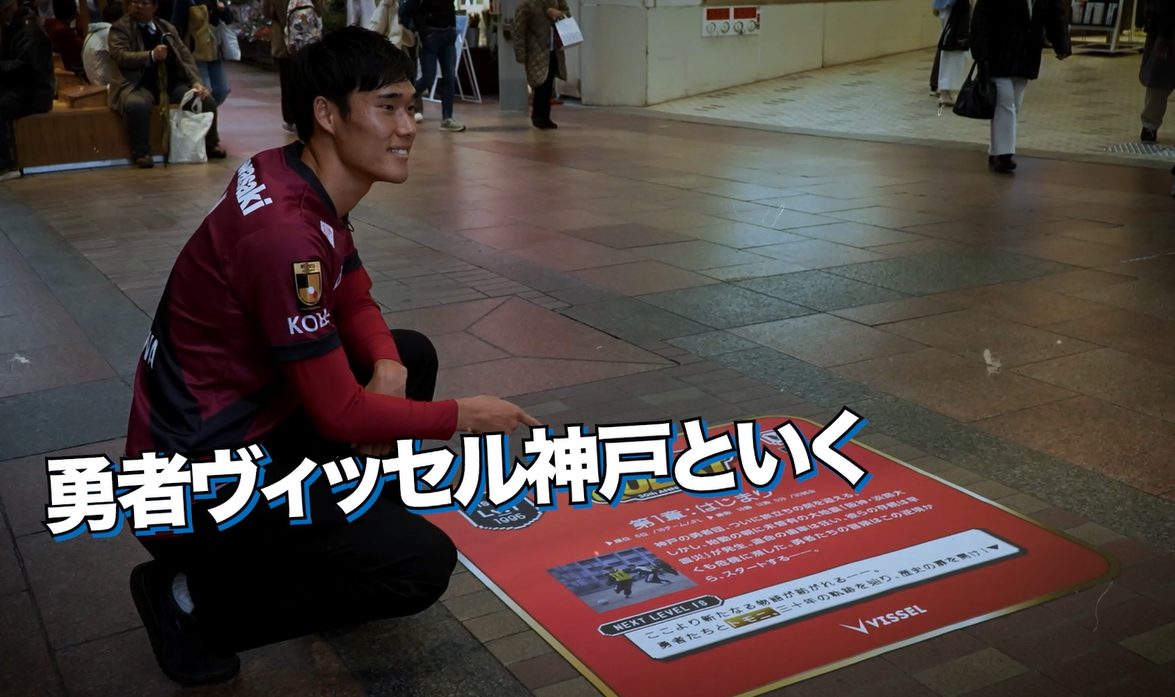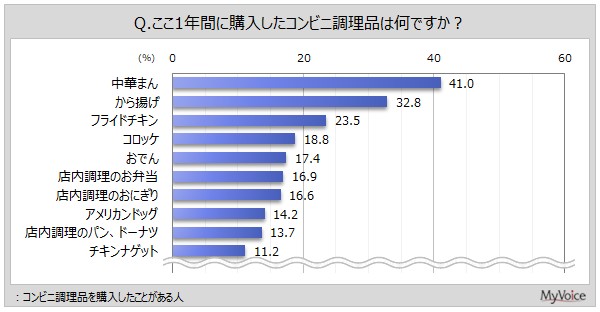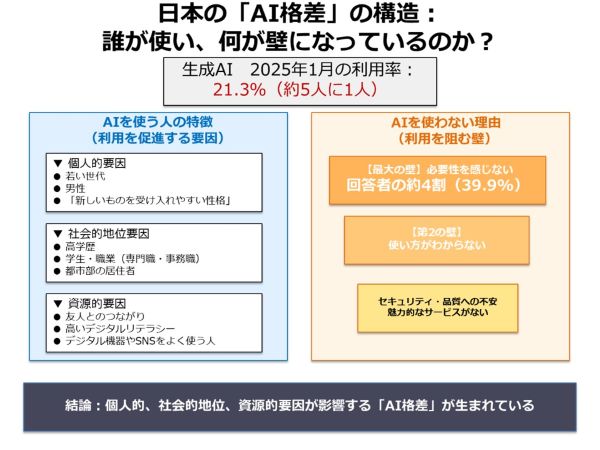「特集」ゲームチェンジの行方 〝なぜか働き続けてほしい人〟を解き明かす「定年がなくなる時代のシニア雇用の設計図」から考える「特集」
高年齢者雇用安定法の改正に伴い、2025年4月からは、すべての企業に65歳までの雇用確保が義務付けられた。すでに、70歳までの雇用についても努力義務となっている。
しかし、現場で働くミドル・シニア(40〜60歳超)に目を向けると、モチベーションが低い、活躍してもらうための仕事が見つからないなど、多くの問題が顕在化している。実際、一人一人は高いポテンシャルを持ちながらも、自身の能力を自覚、さらに表現ができておらず、社内外問わず能力を活用する機会を獲得できていない方があまりにも多い現状がある。
社外から声がかかる人とそうではない人がいるように、社内においても、働き続けてほしいと思われる人とそうではない人がいる。その違いは断片的な要素は思い浮かぶが、よくよく考えてみる機会は少ないのではないか。また、ミドル・シニア自身もなぜ自分が必要とされているのか、そうではないのかを理解することは難しいだろう。実際、現場ではどのような人材が求められているのか。今後も活躍し続けたいと願うミドル・シニア自身の気づきにつながるよう、本稿では「定年がなくなる時代のシニア雇用の設計図」(日経BP 日本経済新聞出版/宮島忠文・小島明子)より〝なぜか働き続けてほしい人〟の10の理由のうち、二つを紹介したい。
大切なのは経験を「きちん」と活かすこと
〝なぜか働き続けてほしい人〟の10の理由の一つ目が「経験を『きちん』と活(い)かす」人である。ミドル・シニアの価値は「経験」にある。
その経験というのは、やはり実践の場面で培った体験的な知見、すなわちどういう場合にはどうなるのかの先読みができる、実体験からもたらされる実践的な知見であり、抽象化された知見ではない。これは若者にはない最大の魅力である。
しかし正確に言えばミドル・シニアの価値は「経験」そのものではなく「経験に基づく価値の創出」である。「活かす」とは結果的には価値を創出することであり、文字通り「活用する」ことである。
経験を「きちん」と活かしている人と、経験を「きちん」と活かすことができていない人の分かれ道は「キャリアのマネジメント(仕事を通じてありたい自分を実現させていく行動)をしているか否か」である。
残念ながら多くの人たちはキャリアマネジメントの重要性を理解していないと言える。
時間は有限・不可逆的であるため、どのように資源配分するかは戦略がなければならない。個人ではこの戦略がキャリアマネジメントである。
たとえば、難易度の高い資格の取得は時間が必要である。さらに実務経験はいくら本を読んでも得られないため、意図的に「知識を得られる場」に入る必要があり長期的な戦略が必要である。そのためには偶発性を念頭に置きながら必要な経験・知識を着実に獲得し、能力の向上を図る必要がある。
自分の経験を「きちんと理解すること」
より具体的に必要な事項は「自身が何のプロなのかを定義できること」である。プロフェッショナルとして何を研ぎ澄ませていくのかを考えることである。すなわち、自分のプロフェッショナルとしての領域(ドメイン)をミドル・シニアの場合はこれまでの経験によるスキル活用も考えつつ設定することである。
そのためには自分の経験を「きちんと理解」することが必要である。キャリア研修などで「棚卸し」という言葉もあるが、実務的には棚卸しレベルでは十分ではないと感じている。
単に「○○という仕事を経験してきました」ではなく、どのように貢献してきたのかを具体的に語れる必要がある。
自分の経験を理解したところで次にどのように社内で、あるいは社外で活躍をするのか市場性を読みながら自身のプロフェッショナルとしての領域(ドメイン)を定義することである。
もっともこれも流動的なものである。「まずは設定する」ことが必要であり、行動した後から補正すればよいことである。精緻に考えるよりも外部環境に合わせて、行動して補正するほうが実践的である。
そして学び続け、スキルを使い続けることである。使わなくなった刃は錆(さ)びてしまう。
現時点で現場から少し遠いところにいたとしても、少しでもいいので現場のメンバーと話し、最新の知見を入れていくということが必要である。
学んでいないうちに環境はどんどん変化してしまう。これも予測困難なところであるため、環境に合わせてどんどんインプットしていくことが必要である。常にアップデートをしていくということが必要である。
環境変化に対し自身のスキルの再現可能性を意識して、スキルを整理しておくことである。
これらを実行することで「年齢に見合った経験値」を獲得し「きちんと活用」できるようにする必要がある。
「年齢を重ねることで有利になる力を活かす」こと
〝なぜか働き続けてほしい人〟の10の理由の二つ目が「年齢を重ねることで有利になる力を活かしている」人である。すなわち年をとることで有利になる力を活かし、高いパフォーマンスを発揮できる人である。
人は誰でも年を経ることで体力・気力といった能力がどうしても劣ってくる。これは避けられないことではあるが、年を経ても劣らない身体的な能力や、経験値などの蓄積できる能力がある。
求められる人とはこの能力をうまく活用し、年齢にとらわれない活躍ができるようになっている人である。
役職のついていた方でも多くの方は、いずれは役職を離れ、プレーヤーとして活動することになるが、再び若い時のように働くことは難しいと言える。
そもそも若者と同じ仕事の仕方をしなければならないわけではない。今までの経験値などを活用して、より高度な業務に対応することが可能である。
有利な三つの力
では年をとることで有利になる力とは具体的に何だろうか。
一つ目として、知識の量と質が挙げられる。
記憶力は落ちても、知識の量は向上すると言われている。加えて、知識の質は実務における体験から得ているものであるため、陳腐化に気を付ける必要はあるが、年をとることで獲得できている実践的な知的資本と言える。
二つ目は、見た目の重厚感や落ち着きという特性が挙げられる。
ベンチャー企業の若手社長と話していて話題に上がるのが若手ならではの苦労である。
営業に行くときなど、どうしてもクライアントから見て説得力に欠けてしまうということである。もちろん作法などもあるが、若手が一見経験値が低く見える外見は否定できないところである。
三つ目は、社会的なルールを認知しているという特性も挙げられる。合理性から言えば社会的なルール・作法など関係ないと思われる方もいるかもしれない。
しかし、社会で構築されてきた作法には意味がある。そのルール・作法を知っているか否かは対話をする相手にとっては信頼を醸成する基盤となる。
その点、年を経るごとに相手をつぶさに観察し、過去の知見も含め、どのように対応すべきかの判断力が磨かれているため、相手の信頼を獲得しやすい。それも大きな能力といえるだろう。
最後に、非公式組織も含めた企業内での存在感という特性が挙げられる。非公式組織とは自然発生的に形成される人間関係・立ち位置である。
年を経ればその組織での影響力は大きくなり、役職にかかわらず、役職者が役職を離れた後も容易に消えるものではない。この存在感は良くも悪くも作用するが、うまく活用することで組織をリードすることが可能である。
では「年をとることで有利になる力」をさらに伸ばすことは可能なのか。
そのために必要なことは、「日々の仕事の中でプロフェッショナルとしてのノウハウを蓄積していく」ことに尽きる。すなわち記憶の量・質を上げていくことである。記憶の質を上げていくには日々の業務で「きちんと」ノウハウを獲得し、さらにアップスキリング・リスキリング(学び直し)も含めて最新のものにしていく必要がある。
将来にわたる自身の加齢も考慮し日々鍛錬してきたかに尽きる。経験値なので後になって身に付けられるものではない。
すなわち根底にあるのは自身のキャリアマネジメントを行ってきたかどうかである。将来の第一線で活躍する自身の姿を、自身の得意領域や会社の方向性も見極めて作り上げることである。
少子化により若手も減り、ミドル・シニアがさらに第一線で活躍する必要がある。一方で、若手と一緒に仕事をしていくことも必要である。その中での貢献の仕方をより具体的にイメージする必要がある。
その具体的なイメージに向かって、日々の仕事を通して自分の経験値・実績を積み上げていくことがより必要とされているのである。
シニアは企業にとって「雇ってあげる」から「稼いでもらう」存在に
少子高齢化が進む日本社会では、ミドル・シニア人材に対して、法律で決まっているから「雇ってあげる」ではなく「稼いでもらう」という姿勢が企業に求められている。本書は、個人、企業、社会、それぞれの視点からミドル・シニアの活躍を実現していくためのヒントを示した1冊である。
ミドル・シニアの施策を検討する企業の担当者はもちろん、今後も活躍したいと考える個人の方にもぜひご一読いただけると幸いである。
社会人材コミュニケーションズ代表取締役社長 宮島忠文(みやじま・ただふみ) 総合電機メーカーにてエンジニアとしてキャリアをスタート。その後、以前から問題意識を有していた教育事業において教務責任者・執行役員として従事。同時に中小企業診断士として事業再生・新規事業の立ち上げなどを行う。2013年にはビジネスパーソンの能力を最大限発揮できる教育・研修を実現させるため、社会人材学舎を創立。以来「知命塾」でのミドル・シニアの活躍支援を起点として、そのノウハウを活用したすべての世代の実践的キャリア構築のための支援・研修をミッションとして活動を続けている。

宮島忠文
日本総合研究所創発戦略センター・スペシャリスト 小島明子(こじま・あきこ) 民間金融機関を経て、2001年、日本総合研究所入社。ミドル・シニアのキャリアや協同労働に関する調査研究に従事。東京都公益認定等審議会委員、東京都地方独立行政法人評価委員会公立大学分科会委員、厚生労働省労働者協同組合促進モデル事業企画書等検討・評価委員会委員。著書に「中高年男性の働き方の未来」「女性と定年」(ともに金融財政事情研究会)「協同労働入門」(共著、経営書院)など。

小島明子
(Kyodo Weekly 2025年10月13日号より転載)