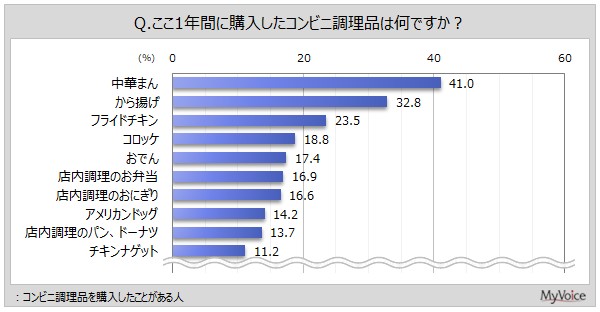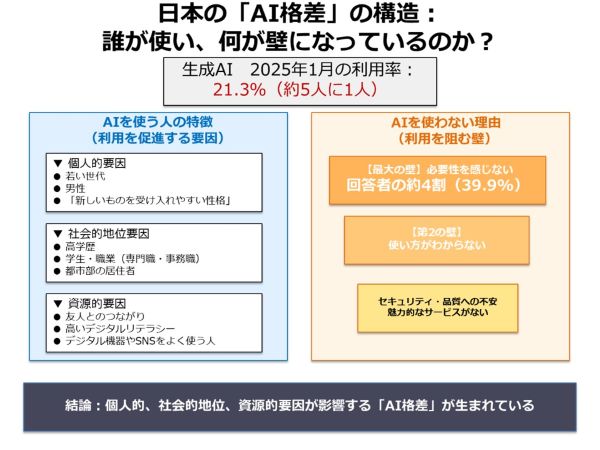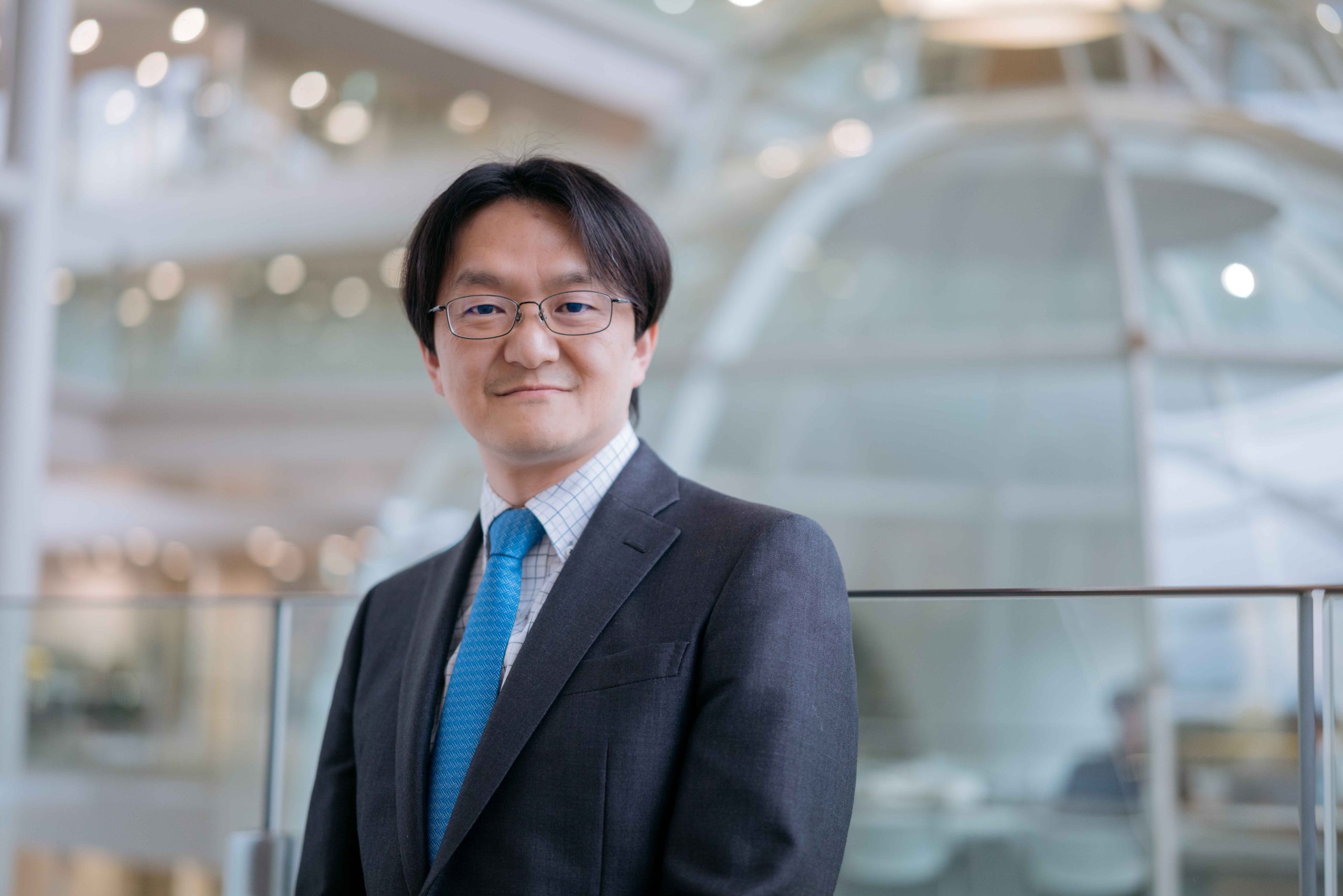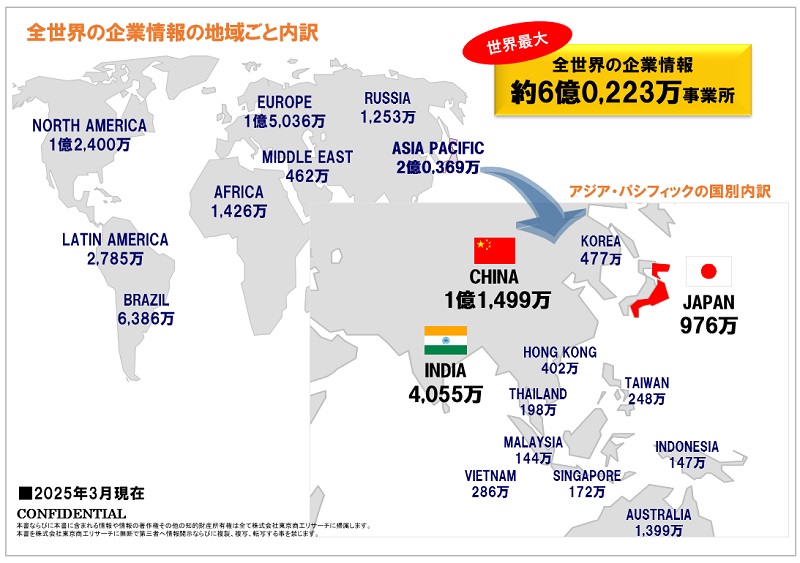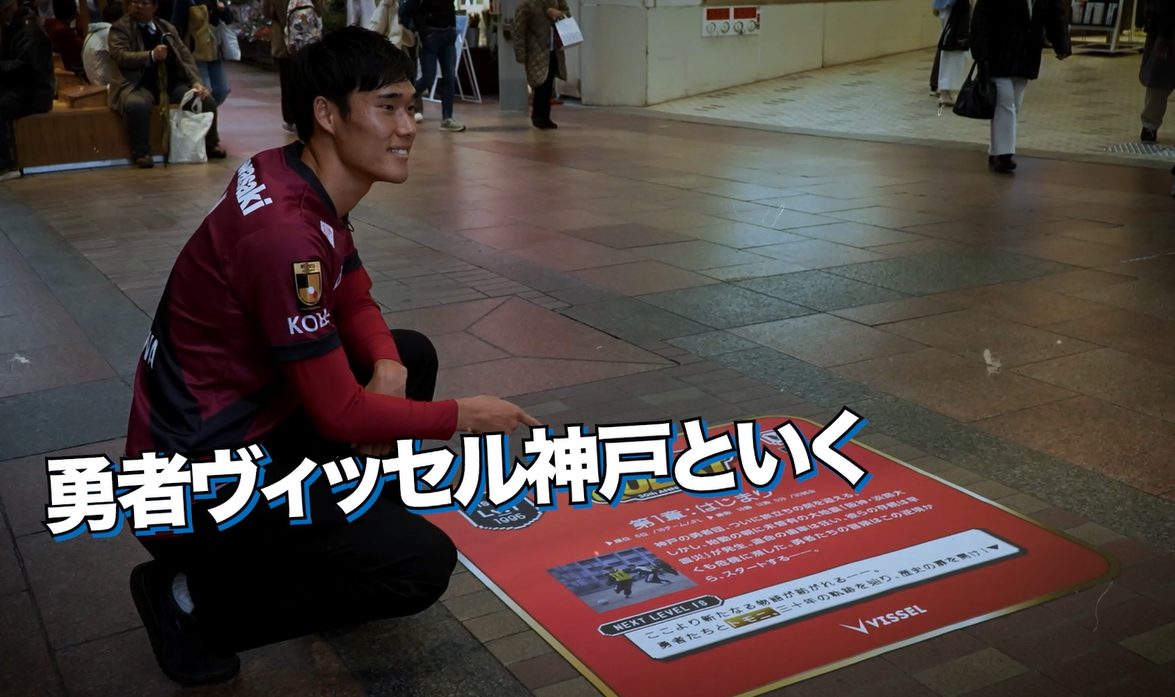「特集」 ゲームチェンジの行方 アメリカ・イスラエルによるイラン攻撃の余波と日本への影響

中川浩一
日本国際問題研究所客員研究員
6月13日に始まったイスラエル軍によるイラン攻撃では、イランの核施設、石油施設、発電所、国際空港、国営テレビ、各政府機関などが対象となった。その後イラン政府の報道官は、この攻撃でイラン側の死者が1062人に上ったと述べたが、大半は軍事関係者で国家への被害が甚大であることが明らかになった。一方、イランもイスラエル全土に報復攻撃を行い、イスラエル人も30人が死亡した。
6月22日のアメリカによる史上初のイラン核施設の攻撃もあり、6月24日にはイスラエル、イランの間で停戦合意が実現し、いわゆる「12日間戦争」は、いったん終了、現在(8月7日)まで、表面上は停戦が維持されている。しかし、イスラエルはイランが核開発を継続すれば再攻撃も辞さない構えをすでに見せており、危機は去っていないのが現状だ。中東に95%以上の原油の輸入を依存する日本にとっても緊急事態となっている。本稿では、〈1〉対立の背景、〈2〉当事者(アメリカ、イスラエル、イラン、アラブ諸国)の思惑、〈3〉日本への影響と取るべき対応、〈4〉今後の見通しと留意点―について考察する。
〈1〉対立の背景
イスラエルとイランの直接対立は、昨年4月と10月にも発生した。23年10月のハマスによる急襲を受け、多くのイスラエル人人質を取られたイスラエル・ネタニヤフ首相は「大失態」を犯したとして、イスラエル国民から厳しい批判にさらされたが、同首相はこの戦争を1948年のイスラエル独立戦争に続く第2次独立戦争と表現し、イスラエルをせん滅しようとする周辺勢力(イランおよびその代理勢力とされるレバノンのヒズボラ、イエメンの親イラン武装組織フーシ派)に攻撃を仕掛け、自ら政治的成果を得ようとしていた。
今回の対イラン先制攻撃もその一環と捉えることが妥当である。昨年の2回の攻撃は、いずれもイランからの攻撃への報復という形であったが今回はイスラエルからの先制攻撃であるという点で大きく局面が異なる。イスラエルはイランの体制転換も排除しない形で、徹底的にイランを攻撃する覚悟である。
〈2〉当事者の思惑
① アメリカ
今年1月20日のトランプ2・0発足以降、4月12日にはアメリカとイランの間で直接交渉が開始され、5月23日までに5回の交渉が行われていた。トランプ米大統領は、イランを脅せば、イランの核開発を止めることができると過信し、ディール(取引)を持ちかけたが、イランに核開発のためのウラン濃縮の権利を認めない、イラン制裁は解除しないというアメリカの従来の立場に変更はなく、ディールが成立する見込みは当初からほぼなかったと言えよう。案の定、イランは核開発のためのウラン濃縮の権利を決して放棄しようとはしなかった。
それにもかかわらず、6月13日のイスラエルによるイラン空爆後、トランプ大統領は、米ABCテレビのインタビューで、イスラエルによるイラン核施設への攻撃で核協議進展が困難になる可能性を問われ「むしろ逆だろう。今後真剣に(アメリカと)交渉するかもしれない」と期待を示していたが、仲介役のオマーンのバドル外相は14日、15日に同国の首都マスカットで予定されていたアメリカとイランのイラン核問題を巡る第6回の高官協議の中止を発表した。
一方、トランプ大統領は、6月15日のFOXテレビとのインタビューでは イスラエルとイランの衝突に「関与する可能性がある」と初めて認めた。13日のイスラエルのイラン空爆時点ではアメリカは関わっていないと強調していたが、イランの弱体化が明らかになる中で、22日、トランプ大統領はイランの核施設3カ所を攻撃し、成功したと発表した。6月24日の停戦合意以降は、トランプ大統領は、対話に応じれば対イラン制裁解除を示唆するなどイランにさざなみを送る一方で、イランとの対話を急がないと述べるなど、対イラン政策の一貫性は見られない。また、米政府内のイラン核施設の破壊の程度の評価も割れている。トランプ大統領自身は、核施設をすべて破壊したとの評価であるが、7月18日の米紙ワシントン・ポスト(電子版)は、フォルドゥの核施設には打撃を与えたが、ナタンズとイスファハンの2施設の損傷は壊滅的とはいえない、と米政府が暫定評価していると報じている。
② イスラエル
イスラエルのネタニヤフ首相としては、トランプ2・0発足後、前述〈1〉の背景から、ただちにでもイランを攻撃したかったが、当面はトランプ大統領のイランとのディールの意向を尊重することとした。しかし、交渉の行き詰まりが明確になり、イランが核開発をさらに進める前に、満を持して、作戦を敢行した。
また、ネタニヤフ首相個人の置かれた立場からは、ガザのイスラエル人人質が取り戻せない中、国内で選挙になると敗北は確実であり、それを回避するためにも戦時内閣を継続する必要があった。イランをはじめ多方面に戦線を拡大することが唯一の生き残り策でもあった。この点、ネタニヤフ首相は6月15日の米FOXテレビのインタビューでイランの体制転覆が軍事行動の目標のひとつかとの質問に「その結果であることは間違いない」と答えた。ネタニヤフ首相がイランの体制転覆に異を唱えなかったのは初めてのことで、今回のイスラエル・イラン戦争は、軍事的な応酬にとどまらない長期化の可能性が出てきたと思われる。6月24日の停戦合意後も、イスラエルのカッツ国防相は、イランへの再攻撃の計画を策定中である旨、イランへの新たな軍事作戦が実施される可能性があると言及しており、対イラン強硬姿勢には微塵(みじん)の変化も見られない。
③ イラン
イランの最高指導者ハメネイ師は、イスラエルによる空爆後の6月13日の声明で「イスラエルは必ず報いを受ける」と述べ、報復する姿勢を示した。その後、イスラエル全土に多数のミサイルを発射し、イスラエル側にも被害が出たことは一定の成果となった。当初、イランとしては、トランプ大統領がディールを持ちかけてくるのは「渡りに船」であった。
24年の2回のイスラエルによる攻撃で、イランの防衛体制は弱体化しており、また、レバノンのヒズボラは指導者だったナスララ師の暗殺もあり弱体化。イエメンのフーシ派も米英、イスラエルによる激しい空爆で弱体化、またシリアでもアサド政権の崩壊により影響力を失いつつあった。地域全体のイラン支持体制を復活させるためにも、時間が必要であったが、前述ネタニヤフ首相をめぐる状況はそれを許さなかったといえる。6月24日の停戦合意後、イラン側は、アメリカとの早期交渉の再開の可能性を否定するとともに、IAEA(国際原子力機関)との協力停止を決定するなど、強硬姿勢に変更は見られない。また、イランの代理勢力であるイエメンのフーシ派の対イスラエルへの活動が活発化していることも懸念される。
④ アラブ諸国
一方、アラブ諸国は今のところ、このイスラエル・イランの直接対峙(たいじ)に関与していない。鍵を握るのは、アラブの大国サウジアラビアだろう。サウジアラビアは、23年3月にイランと国交回復し、地域の安定という戦略的利益を共有している。すでに、イランはサウジアラビア、オマーンなどを通じて、トランプ大統領に事態の鎮静化の働きかけを依頼している。サウジアラビアにとっても、自国の経済発展、国家成長戦略ビジョン2030の実現が最優先課題であり、地域の不安定化はぜひとも回避したい思惑があるが、22日のアメリカの参戦により、米軍基地を有する湾岸諸国は、イランとの関係でも、今後難しいかじ取りを迫られることとなった。
〈3〉日本への影響と取るべき対応
中東に原油の95%以上を依存している日本にとって、中東の安定は日本人の生活に直結する国益そのものである。今回、アメリカの参戦により追い込まれたイランがホルムズ海峡を封鎖する可能性も現実味を帯びている。日本は、戦争の当事者であるイスラエル、イラン双方にパイプを有しているところ、外相のみならず首脳レベルも含めた多層的なチャネルで働きかけを強化すべきであろう。
またG7(先進7カ国)などマルチの枠組みでも取り組みが必須となるが、6月16、17日に開催されたカナダにおけるG7共同声明は、「われわれはイスラエルに自国を防衛する権利があることを確認する。イスラエルの安全保障に対する支持を改めて表明する」とする一方、「イランは地域の不安定な情勢とテロの根源で、(G7は)イランが決して核兵器を持てないことを明確にする」というイランに厳しい内容となった。アメリカの参戦により、対イランへの圧力強化が一層要請される可能性も出てくる中、日本は中東外交の選択肢を狭めないよう、石油を依存する湾岸諸国も含め、当事者への働きかけをバランスよくかつ一層緊密にするべきであろう。
〈4〉今後の見通しと留意点
6月24日の停戦合意は、8月7日現在、表面上は維持されているが、イスラエル、イランとも、「12日間戦争」を受けて、自らの立場を変更することは全くなく、強硬な姿勢を崩していない。
今回のアメリカの参戦は、この応酬を新たなレベルに引き上げたと言えるだろう。03年のイラク戦争後、一貫してきたアメリカの中東からの漸次撤退戦略は、今回のイランへの直接攻撃で時計の針を逆戻りさせることになった。中東の「パンドラの箱」を再度開けたと言えよう。
イスラエルによるイラン再攻撃は時間の問題と思われ、今後、追い込まれたイランの打ち手として、①核開発の進行、完遂(ただし、イスラエルおよびアメリカによる核施設の攻撃のため困難になる可能性が高い)、②ホルムズ海峡の封鎖による世界エネルギー情勢の混乱醸成、③アメリカへの報復としての中東地域の米軍施設への攻撃(カタールには6月23日にすでに実施)などが考えられる。ハメネイ師はすでに自らの暗殺も想定して後継者選びに着手した。いずれのシナリオももはや想定の範囲内であり、中東はかつて経験したことのない未曽有の時代に突入したと言えよう。
日本国際問題研究所客員研究員 中川浩一(なかがわ・こういち) 1969年京都府生まれ。94年外務省入省。エジプトでアラビア語研修後、対パレスチナ日本政府代表事務所(ガザ)、イスラエル、米国、エジプトの日本大使館などで勤務。天皇陛下、首相のアラビア語通訳を務める。2020年外務省退職。著書に「総理通訳の外国語勉強法」(講談社)、「ガザ」(幻冬舎)、「『新しい中東』が世界を動かす」(NHK出版)など。
(Kyodo Weekly 2025年8月25日号より転載)