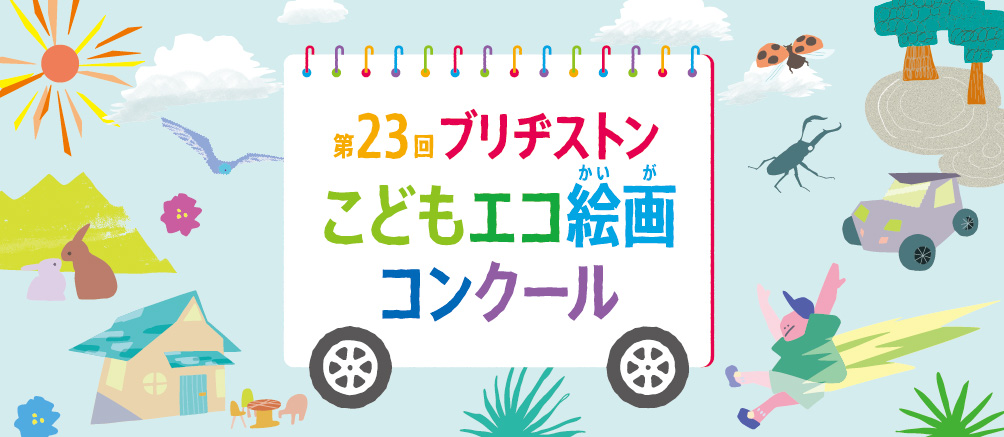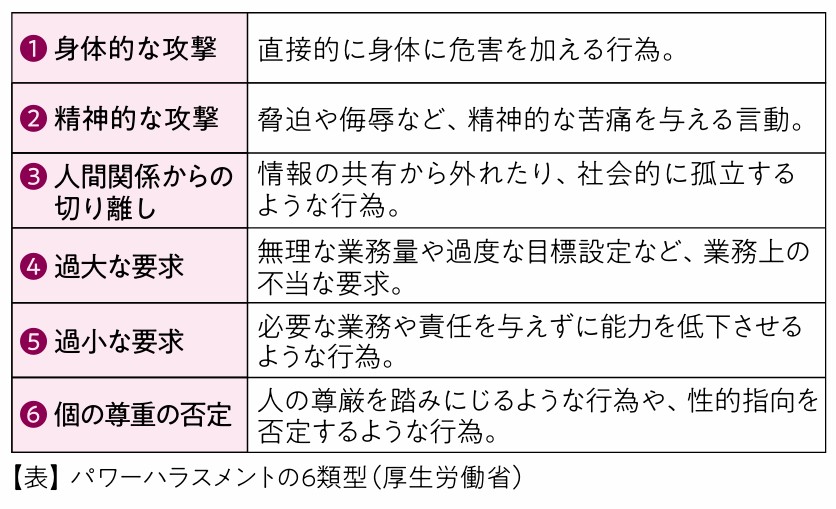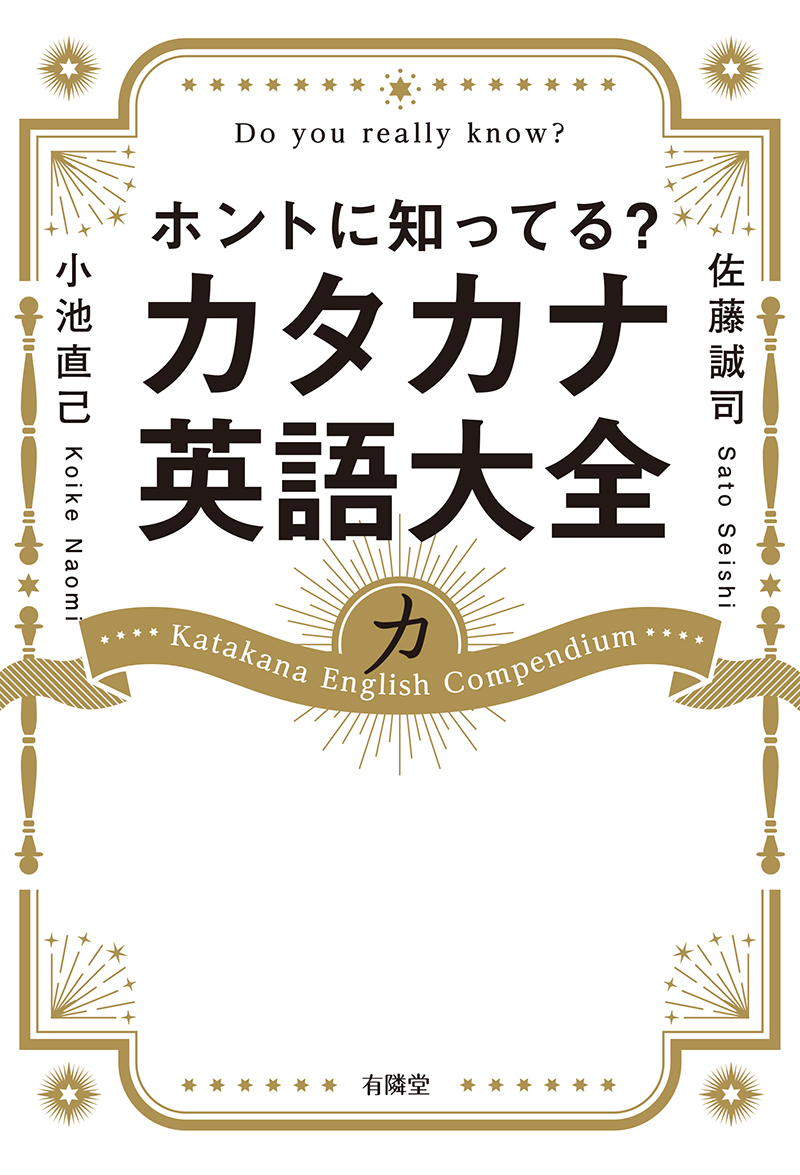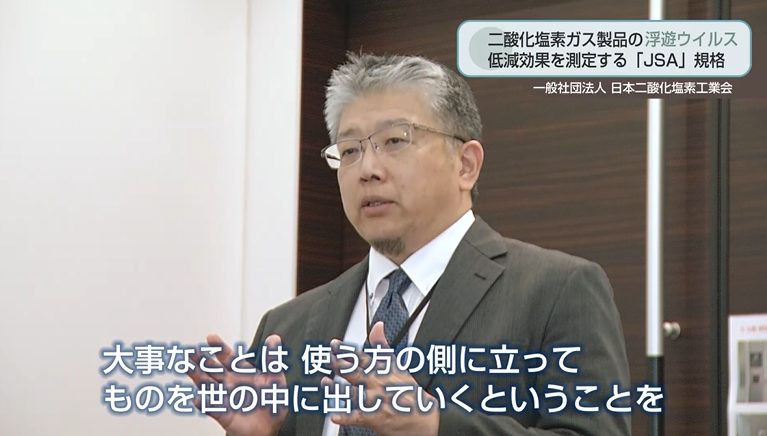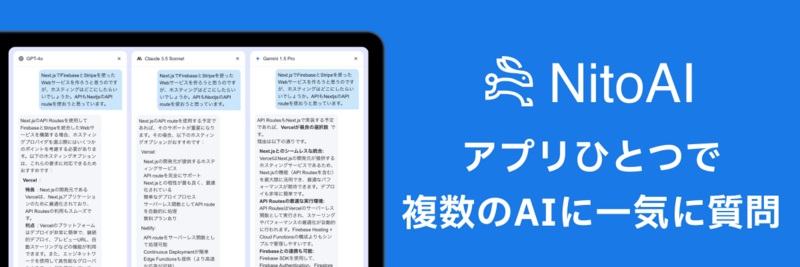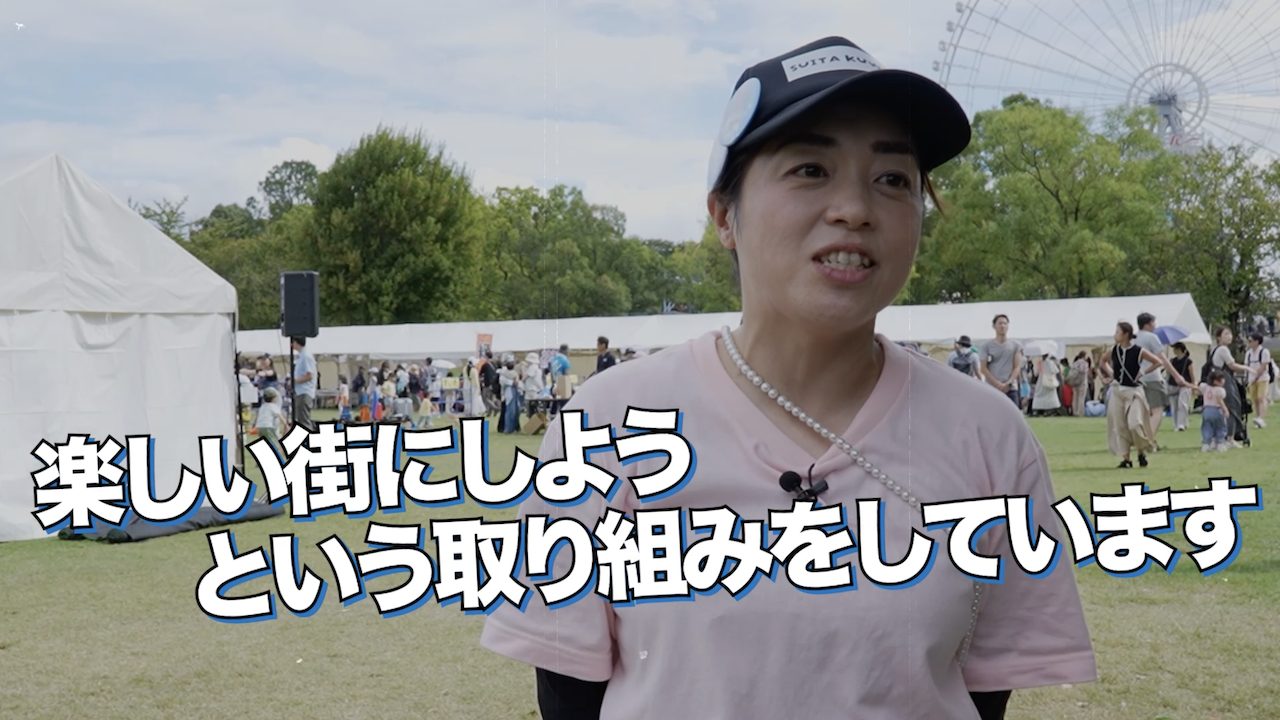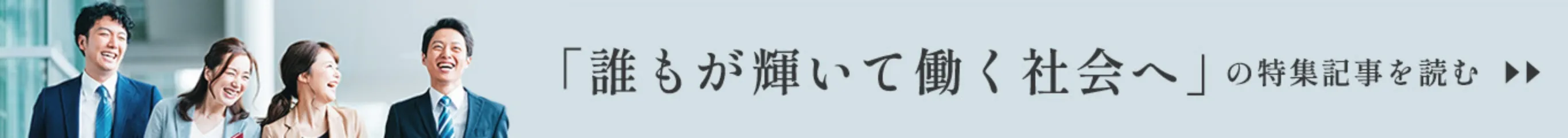「特集」ハリス、トランプ五分五分の戦いどうなる対日外交 両方への備えを

渡部 恒雄
笹川平和財団上席フェロー
米国の大統領選挙は、史上稀(まれ)な接戦状況にある。7月21日にバイデン大統領は選挙からの撤退を表明し、カマラ・ハリス副大統領を後継に指名したことで流れが変わり、トランプ氏優勢の状況から、勝負を互角に戻した。8月5日の全米の支持率でハリス氏が47・0%対46・8%とトランプ氏を逆転して以降、全米の世論調査ではハリス氏がトランプ氏をやや上回る展開となっている。ただし全米の支持率でハリス氏がトランプ氏に勝っているからといって、それがそのまま選挙結果に繋(つな)がるわけではない。七つの接戦州の支持率では、トランプ氏対ハリス氏の差は全て2ポイント以下で、ペンシルベニア州では支持率が同じという接戦であり、両者互角の状況が続いている。
伸び悩むハリス氏
特筆すべきは、9月10日の初のトランプ氏対ハリス氏のテレビ討論で、CNNの調査によると63%がハリス氏の勝利、37%がトランプ氏の勝利という結果になったにもかかわらず、それ以後、ハリス氏の支持が伸びていない点だ。
ハリス氏にとっての逆風は、現職のバイデン政権に対する経済、特に物価高への不満がある。またガザやレバノンでのイスラエルの軍事攻撃の拡大を止めることができないバイデン政権への不満もある。バイデン政権はイスラエル支持を継続しているが、これに対して民主党のリベラル派は4万1千人を超えるガザでの死者に憤り反発している。イスラエル支持でまとまっているトランプ陣営に比べ、ハリス陣営は分裂のリスクを抱えている。
もし直近でイスラエルが、イランの製油施設などを狙った軍事攻撃を行えば、原油価格の高騰を招き、それでなくとも物価高に不満を持つ有権者が、ガソリン価格の高騰により、現職副大統領のハリス氏に反旗を翻すことになり、ハリス陣営にとって逆風の種は尽きない。
情報の二極分化
ハリス氏とトランプ氏との接戦が継続するもう一つの理由は、メディアやネット情報の二極分化である。米国のメディアやネット情報は、保守とリベラルで、全く異なる情報を提供しており、有権者は客観的な情報で候補者を判断していない。米国の有権者は大統領としての能力を判断するというよりは、自分の政治信条に近い候補に投票する傾向が強まっている。テレビ討論でのハリス氏勝利が支持率向上に繋(つな)がらなかった理由の一つといえるだろう。
歴史的にみれば、10月には大統領選挙結果に決定的に影響する「オクトーバーサプライズ」という現象が起こる、あるいは意図的に起こされる。ただし今回の選挙では、有権者の投票を決定的に変えるというよりは、接戦州における少数の有権者の動向に影響を与える「マージナル」なレベルになるのではないか。
現時点で考えられるオクトーバーサプライズは、先に指摘した中東情勢に加えて、ハリケーンの被害とバイデン政権の対応だ。ハリケーン「へリーン」はジョージア州やノースカロライナ州を直撃し、特にトランプ支持が強い地域が被害を受けているため、トランプ氏への投票が減少する可能性が指摘されている。一方で、バイデン政権の対応について批判が高まればハリス氏の支持にマイナスとなる。
この点でも分極化したメディアとネットの影響を排除できない。バイデン政権は、災害救援に真摯(しんし)な対応をしているようだが、トランプ氏は「バイデン大統領が対策をせずに週末は自宅で寝ていた」「民主党のノースカロライナ州知事は、共和党支持が強い地域への救助を意図的に行っていない」というような偽情報を発信している。
鍵は接戦州の少数票
情報が均質に伝わるような社会であれば、トランプ陣営の偽情報は不利になりかねない。しかしメディアの分極化により、トランプ支持者や保守系の有権者は自陣営の偽情報の方を信じ、ハリス支持者とリベラルな有権者はトランプ氏にさらなる不信を深めることになり、これにより支持は動かなさそうだ。
ハリケーンに加えて、ジャーナリストの重鎮的存在のボブ・ウッドワード氏の著作「War」(戦争)(10月14日の週に発売予定)の内容の一部が、リベラル系のニューヨーク・タイムズ紙で報道された。本には、トランプ氏が大統領時代にロシアのプーチン大統領に対し、当時は貴重な新型コロナウイルスの検出機器を秘密裏に送ったという内容が含まれているという。かつての米国社会であれば、トランプ氏に決定的なダメージとなる内容だが、分極化した有権者の投票にどこまで影響するかはわからない。
結局のところ、11月5日の選挙では世論調査では把握しきれない接戦州におけるマージナルな少数の票の動きが、大統領選挙の結果を左右することになるだろう。前述したオクトーバーサプライズ的な各要素は、それぞれ見えないレベルで静かに接戦州の有権者の投票に影響を与えている状況だと考えられる。
トランプ2・0の対日外交
次の米国政権がトランプ政権かハリス政権になる可能性は五分五分と考えらえるため、日本は両政権の対日姿勢を考えておく必要がある。
まずトランプ政権2・0だが、2017年からのトランプ政権が参考になる。ただし政治経験が全くなく「初心者」だったトランプ政権1・0に比べて、4年の経験を経たトランプ政権2・0は、トランプ氏の進める「米国第一」と個人的な影響が強まると想定される。トランプ政権1・0には、伝統的な米国の国益を尊重するジョン・ケリー首席補佐官などが「米国第一」政策を抑制した。トランプ政権2・0では、当初からトランプ氏へのイエスマンが中心となるため、「米国第一」がより強くなるだろう。
トランプ氏は企業の最高経営責任者(CEO)の発想で米国の貿易赤字を黒字化しようとするはずで、すでに中国に対して60%の関税と、同盟国も含む他国にも一律10%の関税をかける方針を示している。日本はトランプ政権1・0で二国間の通商協議を妥結しており、トランプ氏にとって欧州連合(EU)や韓国に対してよりは、通商協議の再交渉の優先順位は低いと思われる。ただし世界の自由貿易体制が弱まり、米国の保護主義に失望するグローバルサウスの離反が進み、国際秩序の弱体化という悪影響を日本も被ることになる。
トランプ氏は同盟国を、米国にただ乗りする存在としか見ておらず、米国の同盟ネットワークが中国やロシアとの競争に有利になるという発想はゼロだ。そもそも、プーチン大統領や北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党総書記などの独裁者に親近感と憧れを持っており、同盟国を犠牲にしてでも、ロシアや北朝鮮の意向に沿う政策を取る可能性もある。特に、トランプ政権1・0で決定したNATO(北大西洋条約機構)からの米軍の一部撤退を再度行い、在韓米軍の撤退も視野に入れ、ロシアや北朝鮮と交渉を行う可能性がある。在日米軍はライバルの中国への圧力形成に有用なので撤退まではいかないだろうが、日本側により大きな財政負担を求めてくることは間違いない。岸田文雄前首相は、2027年度に日本の防衛費をGDP(国内総生産)比2%に引き上げる決定をしているが、トランプ氏に近い専門家の発言を考えれば、GDP比3%以上を求め、また在日米軍の費用負担も100%以上の負担を求めてきてもおかしくない。100%以上というのは、米国は日本を守っているのだから、費用負担以上に米国側に金を払うべきだという日本の暴力団の「みかじめ料」的な発想のことだ。
トランプ政権2・0でも、NATOや米韓同盟に比較すれば、日米同盟への直接のダメージは少ないだろう。だが米国の同盟ネットワークが弱体化して、世界はさらに荒れる可能性が高く、日本はトランプ氏の意向とは関係なく、自らの防衛費を拡充して東アジアの安定を図る必要に迫られるのではないだろうか。
ハリス政権なら
ハリス政権の外交・安全保障政策は現在のバイデン政権の政策の延長となるだろう。ただし、かつての安倍晋三・トランプ関係や岸田・バイデン関係のような強い関係が形成されるかどうかは、石破茂・ハリスの相性と、ハリス政権に入る外交・安保専門家の方向性にもよるだろう。特に、現在のハリス副大統領のフィル・ゴードン国家安全保障問題担当補佐官は、ハリス大統領でも担当補佐官となる可能性は十分にあるが(バイデン大統領のサリバン国家安全保障問題担当補佐官は副大統領時代の担当補佐官)、彼は欧州専門家であり中東の経験も豊富だが、アジアでの経験はほとんどない。その場合、サリバン現補佐官が、アジア専門家のキャンベル現国務副長官を、直属のインド太平洋調整官に起用したような人事が行われるかどうかが注目される。
ハリス政権でも対中競争政策は安全保障戦略の最優先課題として残るため、日米同盟とインド太平洋重視は継続するだろう。ハリス氏はインド系の血を引いていることもあり、副大統領時代に大統領の代理としてアジア外交に関与しており、インド太平洋戦略の重要性は理解していると思われる。しかもハリス氏とも関係があり、バイデン政権の国防長官候補の一人であり、女性初の国防長官として入閣が期待されているミシェル・フローノイ元国防次官は、日米同盟やアジアの安全保障にも造詣の深い専門家だ。彼女はキャンベル国務副長官とシンクタンク「新米国安全保障センター」(CNAS)を立ち上げた盟友であり、日本にとっては心強いパートナーとなるはずだ。日本は、岸田前首相が敷いた日NATO協力を進める路線が、ハリス政権に対してより有効なツールとなると思われる。ハリス政権の日米同盟政策については、あまり懸念材料はない。
ただしハリス政権も、バイデン政権同様、民主党内の左派と中道の分断を抱え、軍事力行使について抑制的な左派の影響もあり、米国の求心力を回復するような強いアメリカの復活は期待できない。日本はトランプ政権2・0発足の場合と同様に、自国の防衛力の強化と東アジアの安定のための自助努力が必要となるだろう。
笹川平和財団上席フェロー 渡部 恒雄(わたなべ・つねお) 1963年福島県生まれ。東北大学歯学部卒。歯科医師となった後、米ニューヨークのニュースクール大学で政治学修士課程修了。米戦略国際問題研究所(CSIS)上級研究員、三井物産戦略研究所主任研究員などを経て、2017年に笹川平和財団上席研究員、24年から現職。CSIS非常勤研究員も務める。著書に「防衛外交とは何か」(共編著、勁草書房)、「2021年以後の世界秩序」(新潮社)など。
(Kyodo Weekly 2024年10月21日号より転載)