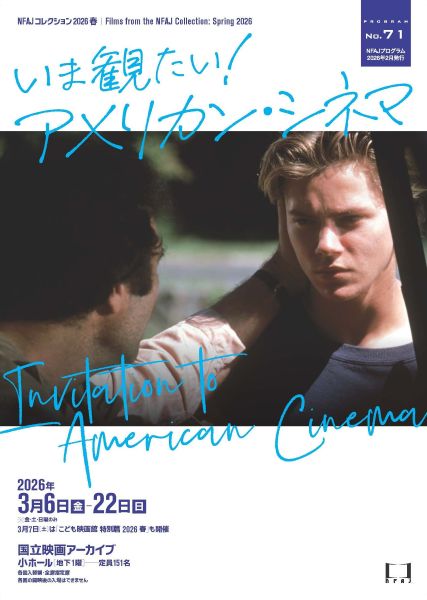「特集」高市早苗政権、〝薄氷〟の上を好発進

本田雅俊
政治行政アナリスト・金城大学客員教授
紆余曲折の末の新たな連立
大方の予想を覆した自民党総裁選から2週間半がたった10月21日、高市早苗政権がようやく発足した。今や諸外国では珍しくないものの、わが国初の女性首相の誕生である。「和製サッチャー」よろしく、高市氏本人は女性を〝売り〟にしてこなかったからか、ジェンダー平等を唱える一部の面々からの評判は芳しくないが、日本でもついに「ガラスの天井」が破られたことは歓迎すべきだ。
内閣支持率も極めて高い。共同通信社が21、22の両日に行った世論調査によれば、支持率は64・4%を記録した。ご祝儀相場や期待値も含まれているだろうが、初の女性首相であることに加え、経済最優先の姿勢や明確な政策目標が評価されているようだ。マーケットもすでに〝高市トレード〟に沸き立っている。「安倍晋三首相の再来」に気持ちを高揚させている保守層も多い。実際、高市首相も「安倍さんとイメージが重なるように意識している」(自民中堅)という。一連の首脳外交で、支持率はさらに上昇するかもしれない。
努めて前向きに、そして強い目力と笑顔で歯切れよく言葉を発する高市首相のキャラクターによるところも大きい。だが、彼女はまさに叩(たた)き上げで、落選も経験している。後に知事に転出したある国会議員はかつて「われわれ世襲議員は山の中腹までバスに乗ってきたが、高市さんや辻元(清美)さんなどは岩山を爪を立てて必死に登ってきた。根性が違う」と評したことがある。所信表明演説で口にした「絶対に諦めない気持ち」は、自分自身への叱咤(しった)でもあったといえる。
高市政権は大変な〝難産〟で誕生した。総裁に選出されるや否や、政治資金問題への取り組みの甘さを理由に公明党が連立から離脱したからだ。「下駄の雪だと思って舐めるなよ」との思いもあったのだろうし、失われた約300万票の責任を自民党に転嫁するきっかけを探していたのかもしれないが、「単にウルトラ保守の高市さんが嫌いだっただけ」(自民ベテラン秘書)といった見方もある。高市氏自身、「総理になれないかもしれないかわいそうな女」などの自虐ネタを使うほど、一時期は悲嘆に暮れた。
だが、捨てる神あれば拾う神あり、救いの手を差し伸べたのは日本維新の会であった。両党はともに保守政党であるし、「高市総裁とは関西人同士で馬が合い、至って真摯(しんし)な協議が重ねられた」(自民国対)という。たとえ連立を組んでもまだ両院で過半数に達しないが、これによって温められてきた野党連携の話はいとも簡単に吹き飛んだ。もっとも、維新執行部には弁護士もいれば、体育会系や人情派もおり、自民党が侮ると手痛いしっぺ返しをくらうことになる。
そもそも維新のハードルは決して低くはない。最初の関門は国会議員定数の1割削減だが、自民党がこの合意事項を過小評価するだけでも、下手をすれば連立解消となる。逆に、比例区の定数を大幅に削減すれば、自民党はルビコン川を渡ることになり、公明党との関係は不可逆的に悪化する。医療費の削減や社会保険料の引き下げも、自民党にとっては大きな試練だ。
維新が閣僚を送り込まない閣外協力にとどまったのは、自民党の本気度と覚悟を見極めるためだろう。〝吊(つ)り橋〟のケーブルが切れるのか、それとも〝鉄橋〟になるのかは、これからの数カ月で見えてくる。そしてこの難解な〝連立方程式〟に最前線で取り組むのが自民党の梶山弘志、維新の遠藤敬の両国対委員長にほかならない。
垣間見られる「したたか人事」
一昔前の自民党では「勝てば官軍」のことわざ通り、主流派偏重の人事は当たり前であったものの、やがて各派閥に配慮する人事が一般化した。だが、高市氏が新総裁に選出されると、支援をしてくれた麻生太郎元首相を副総裁に、その義弟の鈴木俊一氏を幹事長に、さらに子飼いの有村治子氏を総務会長に就ける一方、〝賊軍〟からは起用せず、「第2次麻生政権」「論功行賞人事」などと皮肉られた。
閣僚人事も主流派偏重で行うのかと思いきや、適度にバランスがとられた。旧茂木派がやや目立つものの、旧岸田派や旧森山派からもくまなく登用され、石破茂前首相に近い赤沢亮正氏も経済産業相に横滑りとなった。政権全体の人事を見る限り、タカ派もハト派も、またベテランも若手も分け隔てがなく、まさに高市氏が掲げる「全世代総力結集型」になっている。
しかし、よくよく見てみると、したたかな工夫が凝らされている。積極財政と右派的な政策を推し進めるため、木原稔官房長官や片山さつき財務相、城内実経済財政担当相、小野田紀美経済安保担当相など、高市首相の考えに近い議員たちが要所要所に配置されている。政調会長に起用された小林鷹之氏も、広い意味での〝チーム高市〟の一員だ。税調会長も実質的に差し替えられ、小野寺五典氏が充てられた。
ライバルの扱いでも、工夫が見られる。とりわけ2年後の総裁選で再び高市氏の強力な対抗馬になりそうな林芳正氏と小泉進次郎氏の処遇だ。政権外に置いて完全に干すのも選択肢だったはずだが、高市氏はあえて両名を閣内に取り込んだ。挙党体制といえば聞こえはいいが、自らの監視下に置いて反主流派を台頭させないだけでなく、政権の共同責任も負わせる手法は絶妙だ。
林氏は「地方回りができる役職ならば受ける」とのことで総務相に起用されたが、このポストは高市首相が計4年近くも務めたことがあり、今も役所には強い影響力が残る。さらに、党三役の一角を担わせなかったのもミソだろう。林氏は実に9回目の入閣で、〝超〟が付くベテラン議員だが、党三役の経験は皆無だ。過去に幹事長などを経ずに総理総裁になった例は少ない。
総裁選の決選投票を争った小泉氏も防衛相に起用され、一見、活躍の場が与えられた。だが、防衛費増額の前倒しや安保関連3文書の改定などで矢面に立たされることは必至だ。ちぐはぐな説明や答弁を行えば、小泉氏への期待はさらに萎(しぼ)む。しばらく前までは「最年少閣僚」で大目に見られていたが、鈴木憲和農水相や小野田経済安保担当相は小泉氏より年下だ。小林政調会長とも比較されよう。小泉氏の〝モラトリアム期間〟はとっくに過ぎている。
いわゆる裏金議員の扱いも巧みだ。さすがに入閣はさせなかったものの、萩生田光一氏は幹事長代行に、また7人を副大臣や政務官に起用し、世論の反応を見ている。〝うちわ〟で有名になった松島みどり元法相も閣僚ではなく、首相補佐官に充てられた。今後、国会での追及や新たなスキャンダル報道もあるだろうが、大きく〝炎上〟しなければ、次の内閣改造あたりで裏金議員たちは「完全復権」するのではないか。
高市首相の大きな賭け
安倍元首相の信任が厚かったとはいえ、自民党内における高市首相の政権基盤は強固ではない。維新の協力が得られ、高支持率で発進したものの、至るところに〝地雷〟もある。顧みれば、第2次橋本龍太郎政権で社民党と新党さきがけは閣外協力の立場をとり、ほどなく野党に戻った。鳩山由紀夫政権の発足時の支持率は7割を超えたが、半年後には半減した。歴史を紐(ひも)解くまでもなく、政界はまさに一寸先は闇で、政権運営は容易でない。
今国会の最大の関心事の一つは「高市首相が賭けに勝つかどうか」(閣僚経験者)だ。高市氏は企業・団体献金をめぐる公明党の要求をはねつけたし、裏金議員を要職に起用した。所信表明演説でも政治資金問題について何ら言及しなかった。つまり、高市首相は、国民は内心、政治とカネの問題に飽き飽きしている、むしろ物価高対策と経済成長を求める声のほうが圧倒的に高まっていると判断したのだろう。そしてそちらに賭けたのだ。
一方、野党は物価高対策を唱えながらも、政治とカネの問題を厳しく追及し続ける。とりわけ立憲民主党の野田佳彦代表は正論で高市首相を責め、自民党政治の裏の裏まで熟知する安住淳幹事長は、あの手この手で連立与党に揺さぶりをかけてくる。
だが、直近の世論調査では、最優先課題に物価高対策を求める者は政治資金問題を挙げる者より5倍近くも多い。だからだろう、公明党を含めた野党各党の支持率は軒並み下がっている。現時点では、高市首相の〝読み〟はあながち間違っていないようだ。
しかし、賭けに勝つには、まずは力強い経済対策によって早期に成果を示す必要がある。高市首相は「暮らしの安心を確実かつ迅速に届ける」と言い切り、ガソリン税の暫定税率廃止や電気・ガス代の補助などを挙げているが、それらだけで国民が納得するかは不明だ。「年収の壁」の引き上げや所得税の「基礎控除」の見直し、「給付付き税額控除」についても実施するというが、国民がお手並み拝見で政権を見守る〝賞味期限〟はそれほど長くはない。
一つのバロメーターは年末の内閣支持率だ。国民の期待と実際の成果との間に大きな乖離(かいり)が生じれば、支持率は一気に低下しかねない。高市首相が憂いなく来年正月の伊勢参拝を果たすには、議員定数の削減と効果的な物価高対策による高支持率の維持が不可欠なのだ。そしてもしも4、5割以上の支持率で新年を迎えられそうになれば、早期の衆院解散が頭をよぎっても不思議ではない。高市氏は以前、「身を屈して分を守り、天の時を待つ」との『三国志』の一節を引用したことがある。首相になった今も、発想は同じかもしれない。
来年の事を言えば鬼が笑うというが、すでに今年も残すところ2カ月を切っている。高市首相は自民党内はもとより、維新との関係、そして野党との関係で微妙なバランスをとりながらの政権運営を強いられている。いわば〝やじろべえ政権〟だ。だが、「難産の子は健やかに育つ」ともいう。維新との二人三脚が奏功すれば、本格政権への道が開かれるとともに、新たな政界再編の可能性も芽生えるかもしれない。それらを含め、年末には来年の政治の光景がおぼろげながら見えてくるはずだ。
政治行政アナリスト・金城大学客員教授 本田雅俊(ほんだ・まさとし) 1967年富山県生まれ。内閣官房副長官秘書などを経て、慶大院修了(法学博士)。武蔵野女子大助教授、米ジョージタウン大客員准教授、政策研究大学院大准教授などを経て現職。主な著書に「総理の辞め方」「元総理の晩節」「現代日本の政治と行政」など。
(Kyodo Weekly 2025年11月10日号より転載)
編集部からのお知らせ
新着情報
あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター