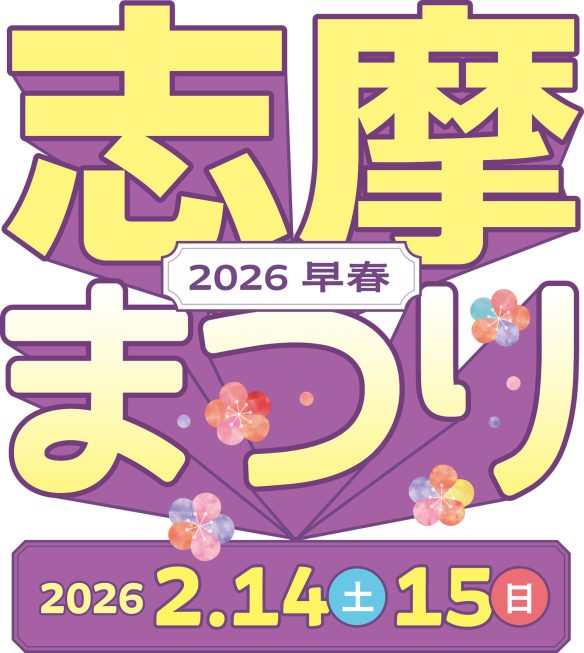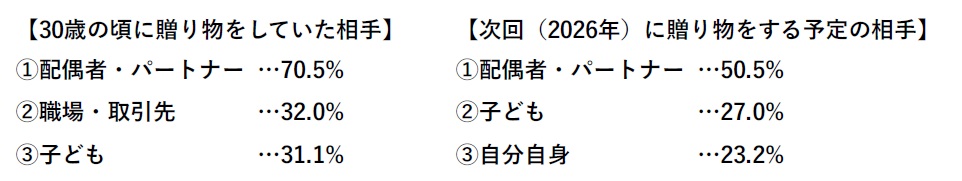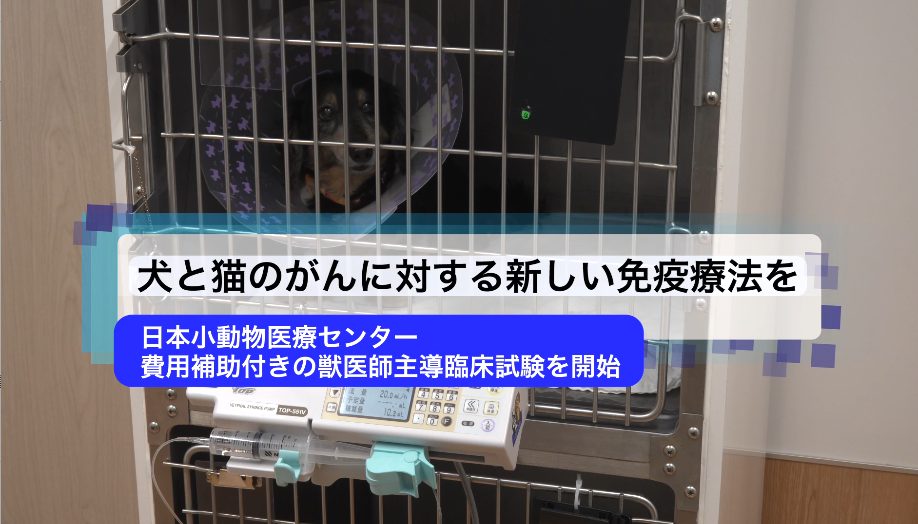「特集」ゲームチェンジの行方 日本はパレスチナを国家承認すべきか?

中川浩一
日本国際問題研究所客員研究員
パレスチナ国家承認に向けた新たな動き
2025年9月22日、米ニューヨークの国連本部で開催された、フランスとサウジアラビアが共催したパレスチナ和平会議で、フランスのマクロン大統領はパレスチナを正式に国家承認すると表明した。マクロン大統領は「パレスチナ自治区ガザの爆撃と虐殺を止める時が来た」と述べ、イスラエルにガザ攻撃停止を強く要請した。英国やカナダもこの日までに承認済みで、パレスチナを国家承認した国は150カ国を超えた。一方、米国や日本、イタリアは承認を見送り、先進7カ国(G7)の足並みが乱れることになった。
イスラエルのネタニヤフ首相は9月26日、国連総会の一般討論演説でパレスチナ国家承認は「全くの狂気だ」と訴え、国家承認に踏み切った英仏などを痛烈に批判した。ネタニヤフ首相は国家承認がパレスチナに「ユダヤ人殺害は報われるとのメッセージを送った」と主張、イスラエルが他の西側諸国に代わってイスラム組織ハマスというテロ集団と戦っていると繰り返し、パレスチナ自治区ガザでの軍事作戦に改めて理解を求めた。
また、イスラエルとパレスチナが国家として共存する「2国家解決」は不可能だとの考えを示した。
本稿では、2023年10月7日のハマスによるイスラエル奇襲およびその後のイスラエル軍によるガザ地上侵攻から2年が経過した現在における、パレスチナ問題の現状をまとめながら、パレスチナ国家承認問題の本質とは何か、日本はパレスチナを国家として承認すべきかについて考察したい。
また、トランプ米大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が9月29日に公表した新たな提案である「ガザ紛争終結に向けた包括計画」20項目、その後の第1段階の停戦合意発効(10月10日)、トランプ大統領の中東訪問など、パレスチナをめぐる最新の動きもあわせ解説する。
パレスチナ問題の本質とは?
まず、パレスチナ問題とは一体何なのか、またどういう歴史的経緯で今に至っているのかにつき簡潔に触れておきたい。これらを知らずに、トランプ大統領の新たな提案の実現性を理解することは困難だからである。
イスラエルは1948年の第1次中東戦争に勝利し、パレスチナの地に、ユダヤ人の国を建設、また、1967年の第3次中東戦争でさらにヨルダン川西岸やガザ地区などを占領した。これに対し、同年、国連安全保障理事会はすべての占領地からのイスラエル軍の撤退を求める決議242号を採択したが、その後この問題の進展は長く見られなかった。
同問題に大きな変化をもたらしたのは、1989年の東西冷戦終結、1991年の湾岸戦争を経て、アメリカが「世界の警察官」となってからであった。
1993年9月には当時のクリントン米大統領の仲介のもと、イスラエルとパレスチナ解放機構(PLO)が相互に承認するオスロ合意が締結され、将来のパレスチナ国家樹立への第一歩と期待された。
しかし、オスロ合意に基づく交渉の進展が遅れ、期限が切れる1999年5月には、パレスチナは一方的に国家樹立を宣言する動きも見られた。
また、2000年7月には翌年で任期を終えるクリントン大統領のイニシアチブで、キャンプデービッド和平会談が開催されたが、15日間に及ぶ交渉も、結局、パレスチナ問題の根幹である、パレスチナ国家の首都はどこか(イスラエルもパレスチナもエルサレムが首都であるとして譲歩せず=エルサレム問題)、ガザなどのパレスチナ難民が、故郷であるイスラエル本土に帰還することができるかの問題(難民問題)が解決せず、またその後、パレスチナの雄、アラファトPLO議長の逝去(2004年)もあり、パレスチナ内部の連帯が急速に弱まった。2006年に実施された選挙ではハマスが勝利し、ガザを実効支配して、ヨルダン川西岸の自治政府と、事実上、分裂統治となってしまった。
一方で、イスラエル側は、右派のネタニヤフ政権が一時期(2021年)を除いて継続しており、双方から和平への機運は急速に失われることになった。トランプ第1期政権(2017年〜2020年)では、オスロ合意の仲介者であったアメリカ自身が、イスラエルの首都をエルサレムであると認定して、大使館もエルサレムに移転(2018年)させるという、パレスチナ問題の解決にとっては暴挙ともいえる決定を下したのである。
オスロ合意の精神であった、イスラエルとパレスチナの直接交渉も、2014年を最後に行われていない。そのような中、2023年10月のハマスによるイスラエル奇襲とイスラエル軍によるガザ地上侵攻により、ガザにおける死者はすでに6万人を突破している。
トランプ和平提案20項目とは?
このような状況下で、2025年9月29日に新たに示されたトランプ和平提案20項目にはいかなる意義があるのだろうか。ポイントは以下のとおり。
▽ガザは過激主義が排除されたテロのない地域となり、近隣諸国に脅威を与えない。
▽ガザはすでに十分な苦しみを受けたガザの人民の利益のために再開発される。
▽双方がこの提案に同意すれば、戦争は直ちに終結する。イスラエル軍は人質解放に備えて合意された境界線まで撤退する。この期間中、空爆や砲撃を含むすべての軍事行動は停止され、戦線は完全撤退の条件が整うまで凍結される。
▽イスラエルがこの合意を公式に受け入れてから72時間以内に、生存者と遺体を含むすべての人質が返還される。
ここまでが第1段階であり、13日には生存人質全員が解放された。以下は、第2段階の提案内容となる。
▽ガザは暫定的に、実務官僚による非政治的なパレスチナ人委員会の統治下に置かれ、日常的な行政や公共サービスを担う。この委員会は有能なパレスチナ人と国際的な専門家で構成され、新設される国際機関「平和評議会」によって監督される。評議会はトランプ大統領が議長を務め、トニー・ブレア英元首相を含む他の首脳も参画を予定する。
▽トランプ政権は、ガザの再建と活性化を図る経済開発計画を策定するため、中東で繁栄を見ている奇跡的な現代都市群の創設に関わった専門家らによるパネルを招集する。
▽ハマス及びその他の派閥は、ガザの統治において直接的、間接的、あるいはいかなる形態でも、一切の役割を担わないことに合意する。トンネルや武器製造施設を含む、すべての軍事・テロ・攻撃用インフラは破壊され、再建されない。独立監視団の監督下でガザの非軍事化プロセスを実施する。
▽中東パートナーは、ハマス及びその派閥が義務を順守し、新たなガザが近隣諸国や住民に脅威を与えないことを保障する。
▽米国はアラブ諸国や国際パートナーと連携し、ガザに即時展開する暫定的な国際安定化部隊(ISF)を設置する。
▽ガザ再開発が進み、パレスチナ自治政府の改革プログラムが忠実に実施されるにつれ、パレスチナ人民の願望であるパレスチナの自己決定権と国家樹立への信頼できる道筋が、ついに整う可能性がある。
▽米国は、平和で繁栄した共存という政治的展望に賛同し、イスラエルとパレスチナ間の対話を構築する。
今回のトランプ和平提案20項目は、2014年以降、イスラエル・パレスチナ間の直接交渉が途絶え、2023年10月から始まったイスラエルによるガザ地上侵攻の現実から考えると、第1段階のハマスによるイスラエル人人質の解放以外は、おそろしく非現実的であると言わざるを得ない。生存人質解放は10月13日に実現し、同日イスラエルを訪問中のトランプ大統領が人質を出迎えた。
しかし、一方で、ここまでパレスチナ問題を解決する基盤が大胆に提案されたことも初めてである。特筆すべきは、新設される国際機関「平和評議会」とそれを欧米、アラブ諸国が監視する枠組みである。トランプ大統領が同機関のトップを務めることで、イスラエルによる〝ガザの支配〟を終結することができる唯一の解決策となる可能性はある。
ただし、ハマスが武装解除して、ガザの統治から完全に手を引く可能性は極めて低く、第2段階以降の実現は困難だと言わざるを得ない。
日本はパレスチナを国家承認すべきか?
このようなパレスチナをめぐる現状の中で、日本はパレスチナを国家として承認すべきなのであろうか。
岩屋毅外相は冒頭のパレスチナ和平会議で、フランスや英国などパレスチナを国家承認する動きに追随せず、日本は独自の立場でイスラエル、パレスチナ双方と対話を続ける考えを説明、パレスチナの国家承認は「『するか否か』ではなく『いつするか』だ」と述べた。イスラエルとパレスチナが共存する「2国家解決」を実現する上で、今は最善のタイミング、選択肢ではないと判断したということだ。
筆者は、日本政府の対外説明はともかく、今回の日本のパレスチナ国家承認の見送りには賛成の立場である。これまで説明してきたとおり、整備された統治機構も、統一された領土も、首都もないパレスチナはおよそ国家としての体をなしていない中で、国家承認はまったくの政治的カードに過ぎないからである。
今、必要なのは、政治的なパフォーマンスではなく、パレスチナ問題の解決を再起動させるための効果的な外交である。2000年のキャンプデービッド和平会談で、アメリカ大統領が問題解決に15日間を費やしたにもかかわらず、解決できなかったパレスチナ問題。その後、イスラエルは右翼化し、パレスチナは分裂した。2国家解決への道のりははてしなく遠いと言わざるを得ない。
しかし、今回の新たなトランプ和平提案で、パレスチナの統治機構が整備され、イスラエルとの2国家解決を前提としたイスラエル・統一されたパレスチナの間の交渉が再開されるならば、今度こそ、その交渉を、スタート地点から後押しする意味でも、まだ国家承認のカードを切っていない日本が、パレスチナを国家承認すべきタイミングではないかと著者は考えている。
その交渉再開までの道のりも険しいが、今回のトランプ大統領の野心的な提案を日本は知恵を出しながら後押しすべきであろう。
日本は、約95%の原油輸入を中東に依存し、中東の安定は日本の死活的国益である。日本人にとって、パレスチナ問題は対岸の火事ではないのである。
日本国際問題研究所客員研究員 中川浩一(なかがわ・こういち) 1969年京都府生まれ。94年外務省入省。エジプトでアラビア語研修後、対パレスチナ日本政府代表事務所(ガザ)、イスラエル、米国、エジプトの日本大使館などで勤務。天皇陛下、首相のアラビア語通訳を務める。2020年外務省退職。著書に「総理通訳の外国語勉強法」(講談社)、「ガザ」(幻冬舎)、「『新しい中東』が世界を動かす」(NHK出版)など。
(Kyodo Weekly 2025年10月27日号より転載)
編集部からのお知らせ
新着情報
あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター