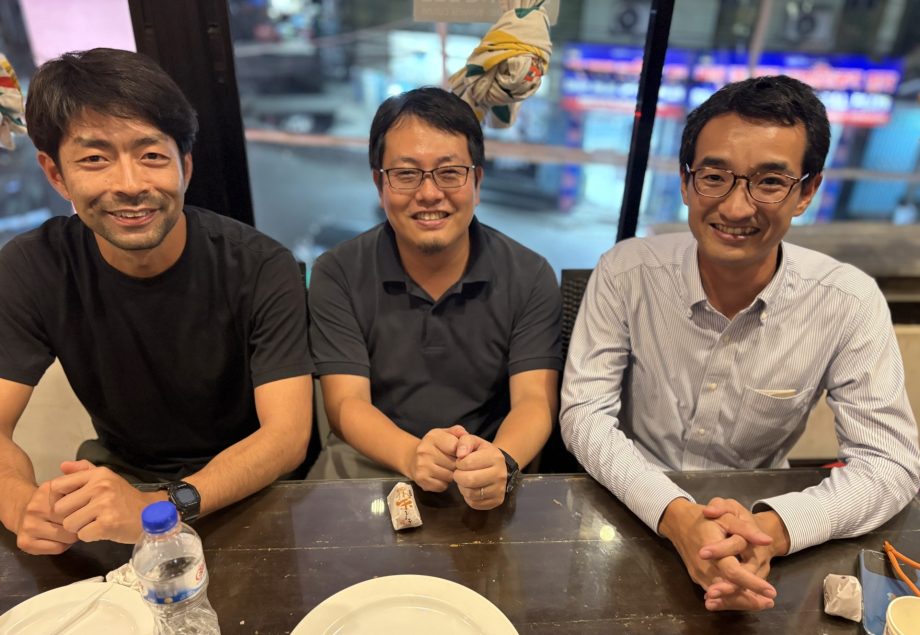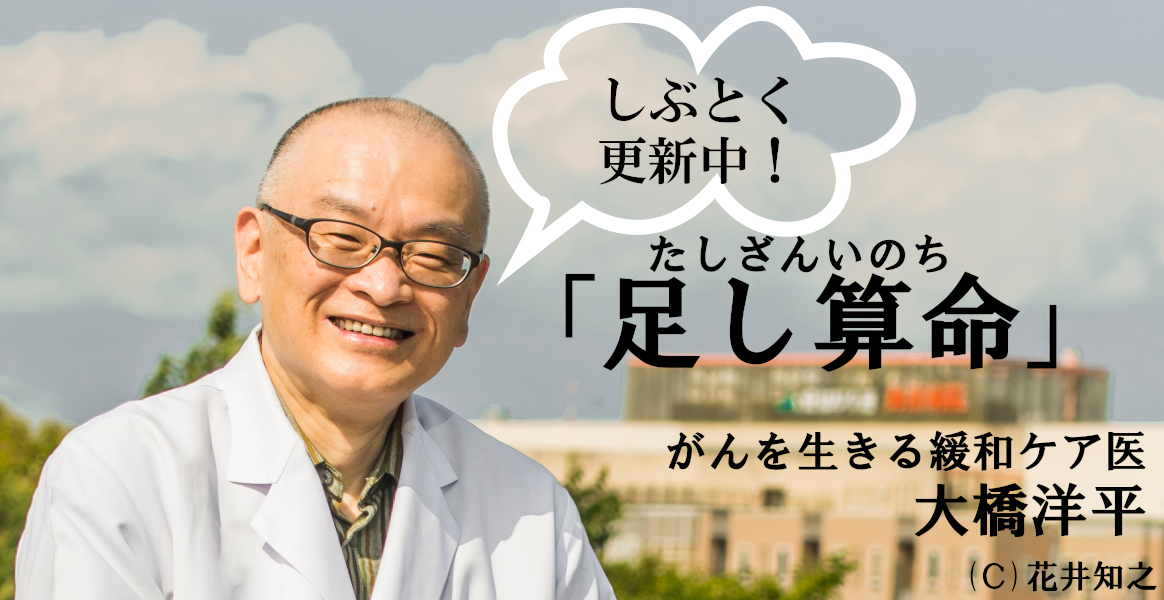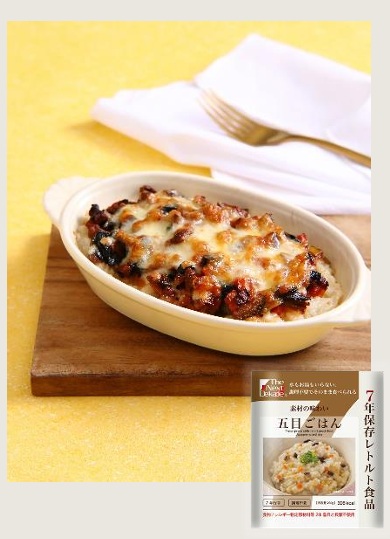「特集」世界で異常気象、災害頻発 温暖化と相互作用、負の連鎖 森林焼失増、極北で顕著 CO2削減、対策強化を

串田圭司
日本大学教授
2015年の国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議(COP21)で採択されたパリ協定では、世界の平均気温上昇を産業革命以前(1850~1900年)に比べて2度より十分低く保ち、1.5度以内に抑える努力を追求している。ところが、2024年は世界各地で高温が数日以上続く熱波が猛威を振るい、世界の年間平均気温は過去最高の15.1度となって産業革命前の水準を1.6度上回った。ある年に目標の温度に抑えられなかったとしても、それ以降も達成できないことを意味しないが、世界の地球温暖化対策は危機にある。
温度上昇は、地球温暖化と自然変動に分けて考えることができる。地球温暖化とは、産業革命以降の人為起源の温室効果ガスの放出により、大気中の温室効果ガスが増加し、継続的に温度上昇することである。自然変動とは、産業革命以前の遥(はる)か昔からある気候や気温の年ごとの変動である。昔から暑い年もあれば寒い年もある。気候変動とは、地球温暖化と自然変動の二つを合わせたものである。地球温暖化により気温のベースラインが年々上がるため、自然変動による高温が重なった年には、これまでにない高温をもたらす。24年について、世界の年間平均気温、極域を除く平均海面水温、大気中の水蒸気の総量は、全て過去最高となり、1991〜2020年の平均より、それぞれ0.72度、0.51度、5%高かった。異常気象と災害は今後どうなるのか?
世界の猛暑と洪水
24年は米国西部ネバダ州ラスベガスでは過去最高気温48.9度を記録した。インドのニューデリーでは5月中旬から1カ月以上の間40度以上の気温が続いた。このインドの熱波により100人以上が死亡した。ヨーロッパでもギリシャなど地中海を中心に熱波が生じた。ギリシャでは少なくとも6人の観光客がハイキング中に死亡した。10月には、スペイン東部バレンシアの西で24時間降水量618ミリ、スペイン過去最大の1時間降水量179ミリの豪雨があった。河川氾濫が発生し、200人以上が死亡した。4月下旬からのブラジル南部の豪雨では170人以上が死亡した。東アフリカ北部から西アフリカでは、3~9月の豪雨により2900人以上が死亡した。サハラ砂漠の南の乾燥地に位置するチャドでは、豪雨と洪水により570人以上が死亡し、190万人が家を失った。9月に南シナ海で急速に発達した台風は猛烈な台風となった。ベトナムでは土砂災害や洪水で100人以上が死亡した。中国南部とフィリピンでは少なくとも24人が死亡した。9月に米南部フロリダ州に上陸したハリケーンは、24時間雨量が300ミリを超えた。洪水や高潮が起こり230人以上が死亡した。10月にフロリダ州に上陸したハリケーンは、多くの竜巻を発生させ、少なくとも16人が死亡した。
日本の猛暑と洪水
24年夏に福岡県太宰府市では40日連続で最高気温が35度以上の猛暑日となり、国内最長記録を更新した。日本の4分の1ほどの観測地点で猛暑日連続日数が過去最長となり、熱中症による救急搬送が相次ぎ、死者も出た。
7月には梅雨前線の影響で山陰地方を中心に大雨があり、愛媛県の松山城の斜面の土砂崩れで3人が死亡した。山形県では大雨特別警報が1日に2度発表された。8月中旬に岩手県大船渡市付近に上陸した台風は、東北地方を横断した。8月下旬、鹿児島県薩摩川内市付近に台風が上陸し8人が亡くなった。
能登半島地震の被災地では、復旧が進行中の9月下旬に記録的大雨が降り、死者16人、負傷者47人の被害があった。48時間雨量が輪島市499ミリ、珠洲市394ミリと過去最大であった。平年の9月の雨量の2倍ほどの雨が2日間で降った。10月には宮崎県で記録的大雨により2人が亡くなった。
地球温暖化が進むと…
地球温暖化が進むと、世界全体で見て、極端な猛暑、極端な乾燥、極端な大雨は、どれも強度、頻度ともに増す。地域的に見た場合、例外的にそう言えない場所があるものの、多くの場所でそうなると予想されている。気温が上がると空気中に含むことのできる水蒸気の量が多くなるため、地面や草木の水分が蒸発しやすくなる。空気中に含むことのできる水蒸気の量は、気温が1度上がるごとに5〜7%ずつ増える。このため、気温上昇に伴って、これまで以上の乾燥が起こりやすくなり、極端な乾燥につながることがある。蒸発によって空気中に増えた水蒸気は、冷やされると水滴となり、雨を降らせる。同じ温度だけ冷やされても、暖かく水蒸気を多く含む空気の方が大雨につながる。このため、極端な大雨が起こりやすくなる。今後地球温暖化が進むと、24年のような高温、熱波、豪雨は、より起こりやすくなる。特にそれらは、自然変動による高温と重なった年に激化する。
山火事と干ばつ
米西部ロサンゼルス周辺で今年1月7日に発生した山火事は、1月31日に鎮圧するまで、高級住宅街パシフィックパリセーズとアルタデナで150平方キロを焼き、29人が死亡し、少なくとも14人が行方不明であり、住宅など1万8千棟以上が損壊した。大船渡市で2月26日に発生した山火事は出火から12日目の3月9日にようやく鎮圧となった。1990年代以降の国内最大である29平方キロを焼失、1人が死亡し、住宅など210棟が被害を受けた。
2024年を振り返ると、世界では大規模な干ばつと山火事が起こった。アフリカ南部では雨期の2月に過去100年以上で最小の降水量を記録し、深刻な干ばつが起こった。熱波が、乾燥帯やその他の気候帯の乾燥した季節において起こると、山火事が増大する。長期の高温が蒸発を促進し、草木や土が極端に乾燥するためである。山火事の直接的な原因は、北米を除いた地域では、火の不始末などの人為的なものがほとんどを占める。北米では火災面積ベースでは、多くが落雷による。山火事が広く拡大するかどうかは、乾燥や強風といった気象要因が大きく関わる。火災が大きく広がると、消火活動が追いつかなくなり、鎮火にはまとまった降水が必要になる。
南米では24年に高温乾燥下で、日本の国土面積の2.3倍である86万平方キロの草原や森林、湿原が燃えた。人工衛星による観測が開始された1998年以降で最大の火災面積であった。干ばつにより、アマゾンの河川の水位は過去最低の水準となり、南米では水不足が深刻化した。ロシアのシベリアでは6月から8月に8万8千平方キロが燃えた。ポルトガルでは9月に1350平方キロが燃焼し、少なくとも9人が死亡した。山火事は極端な乾燥の時に大規模になる。地球温暖化により、世界の多くの地域で山火事のリスクが高まる。シベリア、カナダ、アラスカなど北方森林では、地球温暖化により雪解けが早まり初雪が遅れると、土地が乾いている季節が長くなり、山火事が起こりやすくなる。
山火事は猛暑、豪雨とは違った特徴を持つ。近年の山火事の増加は地球温暖化を増大させる。通常の場合、森林は火災の直後から植生回復を始める。最初は草が生えて、次第に低木が混ざり、ついには元通りの森林に回復する。しかし近年は、元通りの森林に回復しない場合が生じてきた。元通りに回復する前に、再び火災が起きるのである。このような事態では、森林が元より小さい状態が続くことになり、森林の劣化をもたらし、森林が小さくなった分の二酸化炭素(CO2)の大気への放出を意味する。
過去20年間で世界の火災による森林消失面積は増加傾向にある。特に北方森林で顕著である。地球温暖化→極端な乾燥の増大→森林火災の増大→大気中のCO2濃度の上昇→地球温暖化という、正のフィードバック効果により加速度的に地球温暖化を進める構造がある。猛暑、豪雨については、現在のところ明確ではないが、地球温暖化が進むと、猛暑や豪雨が、樹木の枯死や病害虫の蔓延(まんえん)や栄養分を含む土壌の流亡を引き起こし、世界の森林劣化をもたらす可能性も考えられる。
豪雪
日本海側は世界でも有数の豪雪地帯である。24年から25年の冬は、平年より降雪量が多く、青森市、会津若松市、敦賀市、松江市は平年の1.3〜1.4倍であった。この豪雪は日本近海の海面水温が高かったことに起因している。24年12月から25年1月には、日本海の海面水温は高いところで平年より3度高く、東北地方太平洋沖の海面水温は高いところで平年より6度高かった。冬に大陸から張り出す上空での寒波の下で、大陸からの冷たく乾いた北西からの季節風は、周囲より特に温かい日本海水の蒸発と暖められた空気の上昇気流により大量の雪雲を発生させ、日本海側に豪雪をもたらした。
日本近海の海面水温上昇は過去100年間でプラス1.3度であり、世界の海域の中でも特に大きい。地球温暖化によって海面水温は上昇するため、日本海側の雪雲は増大する。一方で、温度上昇により、これまで雪だったものが雨として降る場合が増える。このため、地球温暖化の進行により、日本海側の降雪量は全般的に減る。ただし、日本海側の山間部や北海道の内陸部では、10年に1度の頻度で起こるような豪雪時には、降雪量は増える可能性が指摘されている。海面水温が27度以上で高いと台風の発達を促す。日本近海の海面水温上昇は台風の強大化にもつながる。
異常気象と災害
先述の通り、24年は地球温暖化と自然変動とを合わせた世界の年間平均気温上昇が、産業革命前の水準を1.6度上回り過去最高となった。2023年春から24年春のエルニーニョ現象が熱帯の温度を上げたことなど、24年の気象や自然災害は、自然変動による地域ごとの気候の変動の影響を含んでいる。24年は、自然変動が世界の平均温度を上昇させた側面もあるが、世界の平均気温が過去最高となったことから、世界各地で今後地球温暖化が進んで常態化する気象や自然災害の傾向を示唆している。
高温、熱波、豪雨、干ばつ、山火事のそれぞれのリスクが高まることから、今後はこれらが複合して起こる災害にも注視しなければならない。山火事の後の豪雨は、栄養分を含んだ土壌の流亡により、植生回復を妨げる。台風の後の山火事は、台風による倒木や落ちた樹枝が「燃料」となり、山火事の燃焼を増大する。大船渡市での24年8月の台風被害の後の25年2月からの山火事が、1990年代以降の国内最大規模となったことにも注目しなければならない。CO2などの温室効果ガス削減に取り組むとともに、高温、熱波、豪雨、干ばつ、山火事への適応策、被害軽減策の強化が求められる。
日本大学教授 串田 圭司(くしだ・けいじ) 1968年香川県生まれ。東京大学農学部卒。東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了、博士(農学)。現在、日本大学生物資源科学部教授。北海道大学低温科学研究所助教、富山大学極東地域研究センター准教授などを経て、2016年4月から現職。専門は、地球環境学。米国アラスカ州やシベリア、インドネシアなどで森林火災の研究を進める。
(Kyodo Weekly 2025年3月24日号より転載)
編集部からのお知らせ
新着情報
あわせて読みたい

自動車リサイクル促進センター